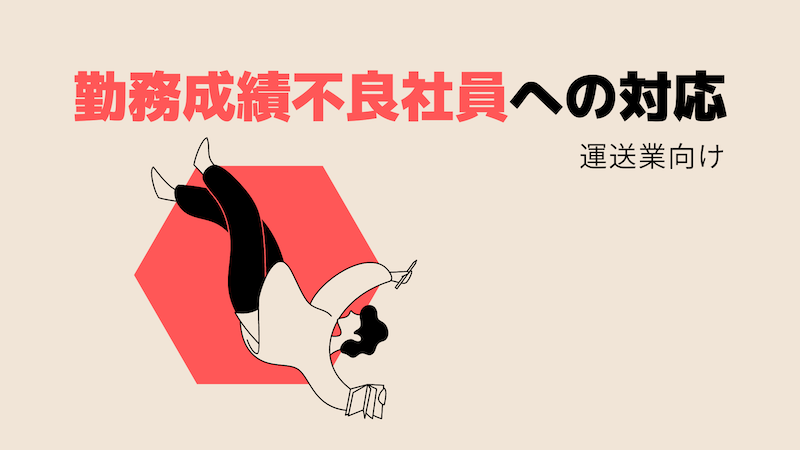はじめに
就業規則は、常時10人以上の従業員を使用する事業者に作成・届出が義務付けられている、いわば「会社の法律」です。しかし、多くの運送事業者が、その重要性を十分に認識せず、インターネットでダウンロードした雛形をそのまま流用したり、何年も前の古い規則を放置したりしているのが実情ではないでしょうか。
それは、非常な危険な状態です。運送業は、2024年問題に代表される複雑な労働時間管理、歩合給や固定残業代といった特殊な賃金体系、そして何より交通事故や貨物事故といった特有のリスクを常に抱えています。汎用的な雛形では、これらの業界特有のリスクに全く対応できません。
就業規則は、単に法律上の義務を果たすための書類ではなく、労使間の無用なトラブルを防ぎ、万が一の際に会社と誠実な従業員を守るための最も強力な「盾」です。本稿では、一般的な雛形を参考にしつつも、それを運送業の実態に合わせてどうカスタマイズし、真に「使える」就業規則を作成すべきか、その具体的なポイントを解説します。
Q&A
就業規則に関するよくある質問
Q1. 従業員が10人未満の小さな会社ですが、就業規則は作ったほうがよいですか?
法律上の作成義務はありませんが、強く作成をお勧めします。従業員が1人でもいれば、労働時間、賃金、解雇といったトラブルが発生する可能性はゼロではありません。トラブルが発生した際に、拠り所となるルールがなければ、感情的な対立に発展しやすくなります。就業規則を整備しておくことで、採用時に労働条件を明確に提示でき、従業員の安心感にも繋がります。会社の規模に関わらず、就業規則は健全な労使関係の土台となります。
Q2. 就業規則で、ドライバーが起こした事故の修理代を、本人の給料から天引きする(相殺する)と定めることはできますか?
「給料から一方的に天引きする」という定めは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反するため、原則として無効です。会社がドライバーに対して損害賠償を請求する権利を持つことと、給料から一方的に天引きすることは、全く別の問題です。判例上も、労働者の責任は様々な要素を考慮して制限されることが多く、全額の賠償が認められるケースは稀です。給料との相殺は、本人がその内容を真に自由な意思で同意した場合などに限定的に認められるに過ぎず、極めて慎重な対応が求められます。
Q3. 服務規律の条項には、運送業としてどのようなことを具体的に書けばよいですか?
服務規律は、運送業の安全と信頼を守るための根幹です。一般的な内容に加え、①出勤・退勤時の対面(またはそれに準ずる方法での)点呼の確実な実施、②乗務前後のアルコール検知器によるチェックの絶対遵守、③デジタルタコグラフ等の運行記録計の適正な使用、④車両の日常点検の実施義務、⑤制限速度の遵守と安全運転の徹底、⑥走行中の携帯電話・スマートフォンの使用禁止、⑦交通事故・貨物事故発生時の会社への即時報告義務、といった運送業に特有の義務を、具体的に、かつ網羅的に記載することが不可欠です。
解説
就業規則の基本構造と作成手続き
就業規則に記載すべき事項は、労働基準法第89条で「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」に分けられています。
絶対的必要記載事項(必ず記載が必要)
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務に関する事項
- 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要記載事項(制度として設ける場合に記載が必要)
退職手当、賞与、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰及び制裁(懲戒)に関する事項など
運送業の就業規則では、特に「安全衛生」や「懲戒」に関する規定を、いかに自社の実情に合わせて具体化できるかが、リスク管理上の鍵となります。
また、内容が法的に有効となるためには、厳格な手続きの遵守が不可欠です。
- 意見聴取義務
労働者の過半数を代表する者の意見を聴取することが義務付けられています。この手続きを怠ると就業規則は無効となります。 - 労働基準監督署への届出
作成・変更した就業規則は、所轄の労働基準監督署長へ届け出なければなりません。 - 周知義務
全従業員に周知されなければ効力を生じません。いつでも確認できる状態に置くことが求められます。
【運送業特化】就業規則カスタマイズの9つの急所
市販の雛形に、以下の運送業特有の視点を加えてカスタマイズすることで、就業規則は「生きたルール」に生まれ変わります。
労働時間・休憩・休日
2024年問題への対応として、改正された「改善基準告示」の内容を就業規則に明記します。具体的には、1日の拘束時間は原則13時間・上限15時間、休息期間は継続11時間を基本とし最低9時間、1か月の拘束時間は原則284時間といった具体的な数値を条文として組み込みます。これにより、国のガイドラインを自社の正式な命令へと転換し、運行管理者や配車担当者が法令遵守を徹底するための明確な権限と根拠を与えます。
懲戒規定
懲戒処分の有効性は、根拠規定の具体性にかかっています。運送業特有の重大な違反行為を網羅的に列挙します。
- 飲酒運転
「業務の内外を問わず」行った一切の飲酒運転を懲戒解雇事由と明記します。 - 不正行為
アルコールチェックの拒否や不正行為、運行記録の改ざんを明確な懲戒事由とします。 - 報告義務違反
交通事故、貨物事故、交通違反の事実を会社に即時報告することを義務付け、その懈怠自体を独立した懲戒事由として規定します。
これらの行為と、譴責、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇といった処分の種類を段階的に紐づけておくことで、処分の相当性が確保されます。
安全衛生・健康管理
定期健康診断の受診義務に加え、深夜業に従事するドライバーには年2回の健康診断受診義務があることを明記します。さらに、会社が安全運行確保のために必要と判断した場合に命じるSAS(睡眠時無呼吸症候群)スクリーニング検査や脳ドック等の受診に、従業員が協力する義務がある旨を定めます。
事故・違反報告
事故発生時の対応フロー(負傷者救護→警察への届出→会社への報告)を具体的に規定します。会社への報告を怠った場合には、懲戒処分の対象となることを明記し、迅速な情報収集と損害拡大の防止を図ります。
損害賠償
従業員の故意または重大な過失により会社に損害が生じた場合、会社がその賠償を請求できる権利を持つことを規定します。ただし、前述の通り、全額賠償を義務付けるような条項は無効となる可能性が高いため、「会社の被った損害の全部または一部を賠償させることがある」といった表現にとどめ、具体的な金額は協議の上で決定する、という姿勢を示すことが現実的です。
賃金規定
運送業で最もトラブルになりやすい部分です。固定残業代制度や歩合給(出来高払制)を導入している場合、その名称、計算方法、対象となる時間、通常の賃金との区分などを、誰が読んでも一義的に理解できるよう、詳細に規定します。
車両管理
車両の私的利用の禁止、日常点検の実施義務、免許証の常時携帯義務、免許の停止・取消処分を受けた場合の即時報告義務などを定めます。特に免許関連の報告義務違反は、無免許運転という最悪の事態を招きかねないため、厳格な懲戒処分と結びつける必要があります。
服務規律
Q&Aで触れた事項に加え、会社の制服着用義務、身だしなみ、荷主先での丁寧な応対、車両の清潔保持などを具体的に定めます。これらは企業の信頼性を維持するための重要な行動規範です。
教育・研修
会社が実施する安全教育や研修(初任運転者教育、適性診断など)への参加を従業員の義務として明確に規定します。
雛形流用の見過ごされがちなリスク
雛形をそのまま使うと、必要な条項が漏れているだけでなく、自社の実態に合わない条項によって、かえって経営の首を絞めることにもなりかねません。例えば、「賞与は原則として業績に応じて支給する」という雛形の条文をそのまま使っていると、過去に支給実績があれば、従業員は「今年ももらえるはずだ」と期待し、不支給の場合にトラブルになる可能性があります。自社に賞与制度がないなら、賞与に関する条項は記載すべきではありません。
就業規則は、会社の労働条件の最低基準を定めるものです。一度定めた内容は、従業員の同意なく不利益に変更することは原則としてできません。だからこそ、作成・変更の段階で、専門家と共に自社の実態を慎重に吟味し、将来を見据えた設計をすることが何よりも重要なのです。
まとめ
就業規則は、会社の姿勢を映す「鏡」であり、経営を守る「鎧」です。運送業を取り巻く環境が激変する今、雛形という名の「借り物の服」を着ていては、業界の荒波を乗り切ることはできません。自社の体格にぴったりと合い、かつ最新の法改正や裁判例を踏まえたオーダーメイドの鎧(就業規則)を身に着けることが、これからの運送事業者には不可欠です。自社の就業規則が、今のままで本当に会社を守れるのか、少しでも不安を感じたら、専門家への相談をご検討ください。
長瀬総合の運送業専門サイト
2024年4月1日からの働き方改革関連法施行により、物流業界での働き方が今までと大きく異なっていきます。
違反してしまうと刑事罰の対象になってしまうので、運送・物流業を営む方の対策は必須です。
「どうしたら良いかわからない」という方は当事務所までご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス