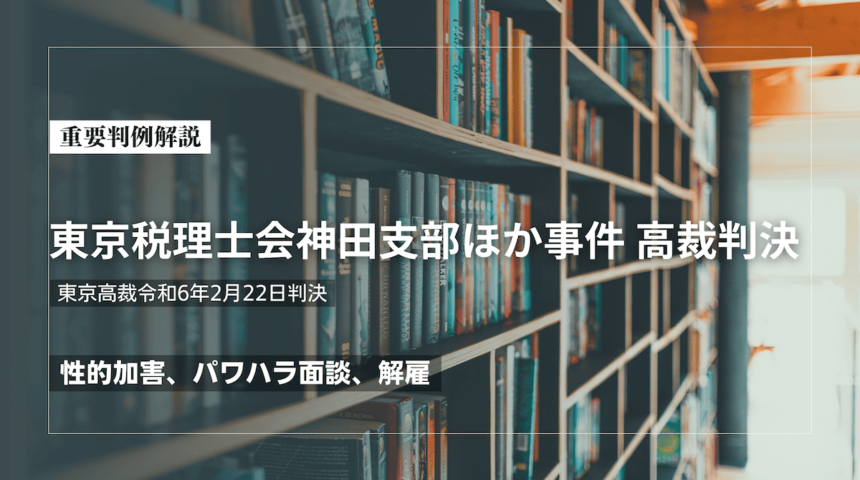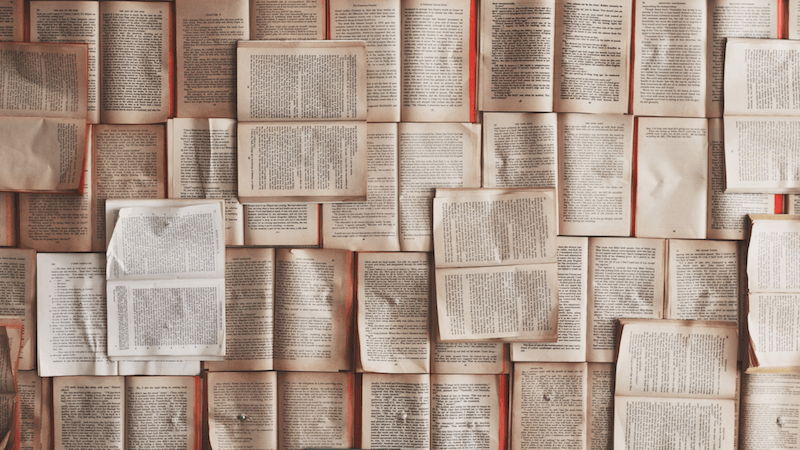はじめに
職場におけるハラスメント問題は、単に加害者個人の責任に留まらず、その後の会社の対応次第で問題がより複雑化し、深刻な二次被害を生むことがあります。また、被害者である従業員の労務提供義務や、会社側の解雇権の行使といった、労働契約の根幹に関わる問題に発展することも少なくありません。
この度、税理士会の事務局職員が支部の部長から性的加害を受けたと申告したことを発端に、その後の復職面談におけるハラスメント、復職命令拒否を理由とする解雇の有効性、さらには加害者とされる側から被害申告者に対する名誉毀損の反訴までが争われるという、極めて複雑な事案について高等裁判所の判決が下されました(東京高裁令和6年2月22日判決)。
一審判決が性的加害の事実を認めなかったのに対し、高裁がこれを覆して性的加害を認定する一方、解雇の有効性については一審同様に認めるなど、争点ごとに緻密な判断がなされています。本稿では、この「東京税理士会神田支部ほか事件」について、判断のポイントを整理し、企業が同様の事態に直面した際にいかに対応すべきか、実務的な観点から詳説します。
本件のポイント
性的加害行為の事実を認定(一審判断を破棄)
一審とは対照的に、高裁は性的行為に至る経緯や当事者間の関係性を踏まえ、「同意のない性的行為であった」と評価し、加害者個人の不法行為責任を認めました。
使用者(税理士会支部)の使用者責任は否定
性的加害は、業務とは無関係の私的な飲食後に、加害者の事務所で行われたものであり、「事業の執行について行われたもの」とはいえないとして、使用者責任や安全配慮義務違反は認められませんでした。
復職面談がハラスメントにあたると認定
被害を申告し休職していた職員に対し、復職の可否を判断する面談において、1対8という状況設定や、支部役員らによる否定的な感情の吐露や不適切な発言は、それ自体がハラスメントにあたり人格権侵害であるとして、支部側の不法行為責任を認めました。
解雇は有効と判断
復職面談がハラスメントにあたると認定されたものの、職員が合理的な理由なく約3週間にわたり復職命令に応じなかったことは、就業規則上の解雇事由に該当し、業務に著しい支障を生じさせたとして、解雇は客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であると判断されました。
名誉毀損の反訴は棄却
職員が提訴に際して記者会見を開いた行為について、高裁は性的加害の事実が真実であると認定したことから、名誉毀損の違法性は阻却されるとして、加害者側からの反訴請求を退けました。
事案の概要
当事者
- 原告(控訴人)
東京税理士会神田支部(被告支部)の事務局職員であった女性X。 - 被告(被控訴人)
神田支部のC部長であった税理士Y2、および使用者である神田支部Y1。
事実経緯
- 性的加害の発生
令和元年8月、Y2はXと業務外で飲食した後、自身の事務所にXを誘い、そこで同意のない性的行為(以下「本件性的暴行」)に及びました。 - 被害申告と休職
Xは直後に支部の別の役員に被害を相談。その後、PTSDと診断され、同年10月から休職に入りました。 - 復職面談
令和2年4月、Xの復職の可否を判断するため、X1名に対し、支部長や副支部長ら合計8名が出席する面談(以下「本件面談」)が実施されました。 - 復職命令と解雇
同年5月、支部はXに対し復職を命令しましたが、Xは復職後のハラスメント防止措置が不十分であることなどを理由に復職しませんでした。これを受け、支部は同年6月、復職命令に応じなかったことなどを理由にXを解雇しました(以下「本件解雇」)。 - 提訴と反訴
Xは、Y2個人と支部に対し損害賠償等を、支部に対し解雇無効と地位確認等を求めて提訴。提訴に際し、記者会見を開きました。これに対し、Y2は、記者会見により名誉を毀損されたとして、Xを相手取り損害賠償等を求める反訴を提起しました。
一審の判断
東京地裁は、本件性的暴行の事実を認めず、Xの本訴請求を全て棄却。本件解雇は有効と判断しました。一方、Y2の反訴請求も、記者会見は公益目的であり違法性が阻却されるとして棄却しました。これを不服として、XとY2がそれぞれ控訴しました。
主な争点
本件における法的な争点は、以下の5つに大別されます。
- 本件性的暴行の存否と、Y2個人の不法行為責任の有無
- 支部Y1の使用者責任、または安全配慮義務違反の有無
- 本件面談における支部側の言動の違法性(ハラスメント該当性)
- 本件解雇の有効性
- 記者会見による名誉毀損の成否(Y2からXへの反訴)
裁判所の判断理由
高等裁判所は、これらの複雑に絡み合った争点に対し、一つ一つ切り分けながら緻密な判断を下しました。
性的加害行為の認定(一審判断との相違点)
高裁は、一審とは異なり、本件性的暴行の事実を認定しました。その理由として、Xが一貫して被害を訴えていること、事件直後にPTSDと診断されていること、一方でY2の供述には不自然な点があることなどを指摘しました。特に、「支部役員である税理士と支部事務局の職員という関係を意識して、あからさまに拒絶的な態度をとることを当初控えていた」というX側の状況を考慮し、「全体として、同意のない性的行為であったとの評価を免れない」と結論付け、Y2個人の不法行為責任を認めました。
使用者責任・安全配慮義務違反の否定
一方で、支部Y1の責任については否定しました。本件性的暴行は、業務とは全く関係のない私的な会食の後、Y2の個人事務所という私的な空間で行われたものです。そのため、「事業の執行について行われたものであるとは認められない」とし、民法715条の使用者責任は成立しないと判断しました。また、使用者が安全配慮義務を負うべき場面でもなかったとして、債務不履行責任も否定しました。
復職面談におけるハラスメントの認定
しかし、支部Y1の責任が全く問われなかったわけではありません。高裁は、本件面談における支部側の対応を違法なハラスメントと認定しました。
その理由として、①休職中の被害者1名に対し、支部長ら8名が出席するという状況設定自体が強い精神的圧迫を与えるものであること、②面談の目的が復職の可否判断であるにもかかわらず、実際には「なぜ訴えたのか」といった否定的な感情を吐露する場となっていたこと、③「魅力的だからまた誘われてしまうかも」といった二次加害にあたる発言があったこと、などを挙げました。これらの言動は、Xに対する人格権侵害にあたるとして、支部Y1に不法行為責任を認めました。
解雇の有効性の肯定
本件の判断で最も注目すべき点の一つが、支部によるハラスメントを認定しつつも、解雇は有効と判断した点です。高裁は、Xが本件復職命令に従わなかったことについて、Xが主張する復職拒否の理由(座席配置など)は、復職を拒む「合理的な理由」とはいえないと判断しました。そして、「約3週間にわたり、合理的な理由なく出勤しなかったことは、…実質的に、支部の業務について、著しい支障を生じさせた」と認め、本件解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないとはいえない、と結論付けました。
名誉毀損(反訴)の否定
Y2からの反訴について、高裁は、Xが行った記者会見での発表はY2の社会的評価を低下させるもので名誉毀損にあたりうることは認めました。しかし、その上で、本件性的暴行は真実であると認定したことから、刑法230条の2の違法性阻却事由(公共性・公益性・真実性)が認められ、不法行為は成立しないとして、Y2の反訴請求を棄却しました。
裁判所の判断内容(結論)
以上の判断に基づき、高等裁判所は一審判決を一部変更し、以下の通り結論付けました。
- Y2個人に対し、本件性的暴行に関する不法行為責任を認め、慰謝料等約357万円の支払いを命じる。
- 支部Y1に対し、本件面談におけるハラスメントに関する不法行為責任を認め、慰謝料50万円の支払いを命じる。
- 支部Y1による解雇は有効とし、Xの地位確認請求等は棄却する。
- Y2からXに対する名誉毀損を理由とする反訴請求は棄却する。
実務に与える影響
本判決は、ハラスメント事案への対応に苦慮する多くの企業にとって、重要な教訓を含んでいます。
ハラスメント申告への対応は慎重に(二次加害の防止)
本件で支部が賠償責任を負ったのは、性的加害そのものではなく、その後の面談での不適切な対応でした。ハラスメントの申告があった場合、たとえ会社に直接の法的責任がないと思われる事案であっても、その後の対応、特に被害を訴える従業員との面談の進め方には細心の注意が必要です。多人数で一人を問い詰めるような形式は避け、プライバシーに配慮した中立的な担当者が、傾聴の姿勢で臨むべきです。不適切な対応は、それ自体が新たなハラスメント(二次加害)となり、企業の法的責任を生じさせるリスクがあることを本件は明確に示しました。
ハラスメント問題と労務問題を切り分けて対応する
本判決は、従業員がハラスメント被害者であるという側面と、一人の労働者として労務提供義務を負うという側面を、明確に切り分けて判断しました。会社側によるハラスメントがあったからといって、労働者が無条件に労務提供を拒否できるわけではありません。逆に、労働者に労務提供上の問題があったとしても、それをもってハラスメントの訴えを軽視することは許されません。企業としては、それぞれの問題に対し、就業規則や法に基づき、独立した事柄として適切に対処していく冷静な姿勢が求められます。
職務関連性の範囲を再認識する
使用者が責任を負うのは、あくまで「事業の執行について」行われた加害行為です。業務時間外や事業場外での私的な会食等がきっかけとなる事案では、使用者責任が否定される可能性があることを本件は示しています。しかし、だからといって企業が何もしなくてよいわけではありません。日頃から研修等を通じて、役職員に対し、職務上の関係性を私的な関係に持ち込まないよう注意喚起し、ハラスメント防止意識を高めておくことが、紛争の未然防止に繋がります。
本件は、一つの出来事をきっかけに、複数の法的問題が連鎖的に発生しうる現代のハラスメント事案の複雑さを象徴しています。企業は本判決を他山の石とし、自社のハラスメント相談体制や、申告後の対応フロー、そして管理職の面談スキルなどを今一度見直す必要があるでしょう。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、様々な分野の法的問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。ご興味をお持ちの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
長瀬総合法律事務所は、お住まいの地域を気にせず、オンラインでのご相談が可能です。あらゆる問題を解決してきた少数精鋭の所属弁護士とスタッフが、誠意を持って対応いたします。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
企業が法的紛争に直面する前に予防策を講じ、企業の発展を支援するためのサポートを提供します。
複数の費用体系をご用意。貴社のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたします。