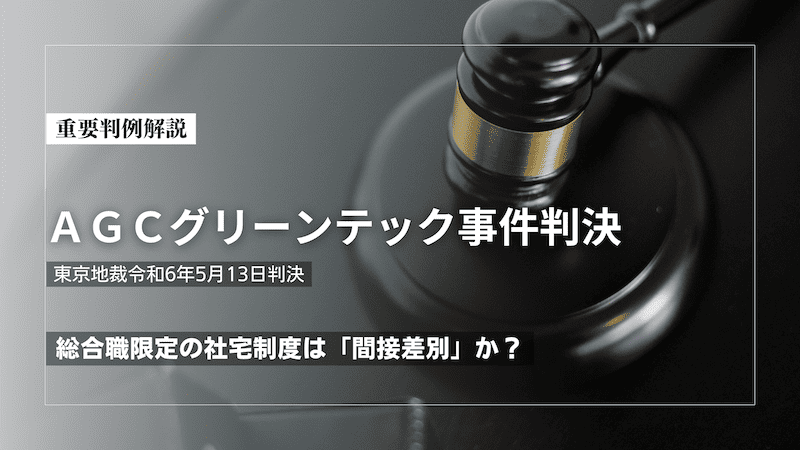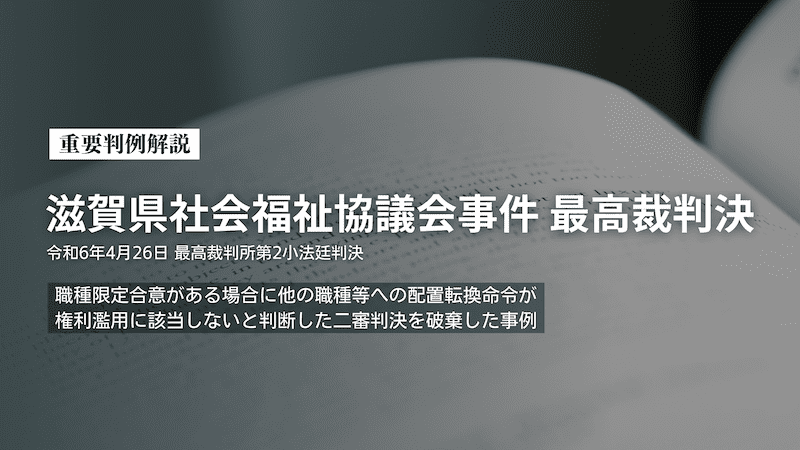はじめに
企業の福利厚生制度が、意図せず男女間の格差を生んでいると指摘されるケースがあります。職務内容や転勤の有無などに応じて従業員の区分を設け、それぞれに異なる待遇を定める「コース別人事制度」を導入している企業は少なくありません。しかし、その制度設計や運用によっては、男女雇用機会均等法(以下「均等法」)の趣旨に反するとして、法的な問題に発展するリスクを孕んでいます。
この度、総合職の従業員にのみ社宅制度の利用を認め、その総合職のほとんどが男性、利用が認められない一般職のほとんどが女性で構成されていたという事案において、裁判所が均等法の趣旨に照らして「間接差別」に該当し違法であると判断した注目すべき判決が出されました(東京地裁令和6年5月13日判決・AGCグリーンテック事件)。
本稿では、この裁判例の概要と判断のポイントを整理し、企業実務に与える影響について弁護士の視点から解説します。
本件のポイント
- 総合職限定の社宅制度が「間接差別」に該当
総合職の大部分が男性、一般職の大部分が女性である状況下で、総合職にのみ社宅利用を認める措置は、性別以外の事由(職務区分)を要件としつつも、実質的に女性従業員に相当程度の不利益を与えるものであり、合理的な理由がないため「間接差別」に該当すると判断されました。 - 均等法施行規則にない措置も「間接差別」の対象に
均等法が直接規制する間接差別の類型(均等法施行規則第2条)として「住宅の貸与」は明記されていません。しかし、裁判所は、規則に挙げられていない措置であっても、民法等の一般法理に照らして間接差別として違法と判断される場合があるとの判断枠組みを示しました。 - 制度の運用実態を重視
社宅制度が「転勤の可能性がある総合職」を対象とするという建前があったとしても、実際には転勤の有無や可能性にかかわらず、総合職であれば自己都合の転居でも利用が認められていた運用実態を重視し、制度の合理性を否定しました。 - 不法行為責任を認め、損害賠償を命令
違法な間接差別状態を是正せず、漫然と継続した会社の行為は不法行為にあたるとして、原告が社宅制度を利用した場合に会社が負担したであろう家賃相当額と、実際に支払われた住宅手当との差額、および慰謝料の支払いを命じました。
事案の概要
当事者
- 原告X
被告Y社に一般職として勤務する独身の女性従業員。 - 被告Y社
農業用製品の販売事業を営む株式会社。本社(東京)のほか、3つの営業所を有する。
背景
Y社では、正社員を「総合職」と「一般職」に区分していました。
- 総合職
「会社の命ずる任地に赴任することが可能」な従業員と定義され、その多くが営業職であり、男性が大多数を占めていました。 - 一般職
「一般事務等の定型的、補助的な業務に従事」し、「就業場所に異動がない」従業員と定義され、その多くが女性でした。
問題となった社宅制度
Y社は、総合職の従業員を対象とした社宅制度(借上社宅制度)を設けていました。当初は転勤者を対象としていましたが、平成23年7月以降、運用が拡大され、親元からの独立や結婚といった自己都合による転居の場合でも利用が認められるようになりました。その結果、通勤圏内に自宅を所有しない総合職であれば、転勤の有無にかかわらず社宅制度の恩恵を受けることができ、その利用者のほとんどが男性でした。
一方、一般職である原告Xには社宅制度の利用は認められず、少額の住宅手当が支給されるのみでした。社宅を利用する総合職が受ける経済的利益(家賃の8割等を会社が負担)と、原告が受ける住宅手当との間には、著しい経済的格差が存在していました。
そこで原告Xは、Y社が一般職である自身に社宅制度の利用を認めないのは、性別を理由とする直接差別、または間接差別に該当し違法であるとして、Y社に対し、損害賠償等を求めて提訴しました。
主な争点
本件の主要な争点は、「Y社が社宅制度の利用を総合職に限定し、一般職である原告Xに認めなかった措置が、直接差別または間接差別に該当し、違法といえるか」という点でした。
その他、男性一般職との賃金格差の違法性や、業務外し・不当査定の有無なども争われましたが、本稿では主要な争点である社宅制度の問題に絞って解説します。
裁判所の判断理由
裁判所は、Y社の措置について直接差別と間接差別の両面から検討し、以下の理由で「間接差別」に該当すると結論付けました。
1. 直接差別には該当しない
まず、裁判所は、Y社の措置が「男女の性別を直接の理由とするもの」とは認められないとして、直接差別(均等法第6条違反)にはあたらないと判断しました。
その理由として、社宅制度の適用対象である総合職のほとんどが男性であったのは、総合職の多くを占める営業職に女性からの応募が少なかったことが原因であり、Y社が意図して性別により取扱いを分けていたとは推認できない、としました。制度設計の背景に、男女間で格差を生じさせる趣旨があったと認めるに足りる事情はないと判断されたのです。
2. 間接差別に該当する
次に、裁判所は、本件措置が間接差別に該当するかを検討しました。
(1) 判断の枠組み
まず、均等法第7条および同法施行規則第2条が間接差別として禁止する類型に「住宅の貸与」が明記されていない点に触れつつも、「間接差別は、均等法施行規則に規定するもの以外にも存在し得るのであって、均等法7条には抵触しないとしても、民法等の一般法理に照らし違法とされるべき場合は想定される」との重要な判断枠組みを示しました。
その上で、①措置の要件を満たす男女の比率、②措置の具体的な内容(経済的格差の程度)、③業務遂行上や雇用管理上の必要性(合理的な理由の有無)といった観点から、Y社の措置が間接差別に該当するかを検討しました。
(2) 間接差別に該当する具体的理由
上記の枠組みに本件を当てはめ、裁判所は以下の点を指摘しました。
- 運用実態
社宅制度は、転勤の有無やその現実的可能性を問わず、総合職でありさえすれば通勤圏内に自宅がない限り希望者全員に適用されており、その恩恵を受けていたのは(1名を除き)全て男性であった。 - 経済的格差の大きさ
社宅利用者が受ける経済的恩恵(家賃負担額)は、一般職に支給される住宅手当を大幅に上回っており、格差はかなり大きい。 - 合理的な理由の欠如
Y社は、制度の目的を「①営業職のキャリア形成(転勤の必要性)」「②営業職の採用競争における優位性確保」「③労働の対価」と主張した。しかし裁判所は、- ①について、実際には転勤が定期的に行われておらず、転勤経験のない総合職も多数利用しており、キャリア形成の観点から説明できない。
- ②について、採用戦略上の重要性が高いとは認められず、営業職以外の総合職(管理部門)にも適用していることを合理的に説明できない。
- ③について、制度の内容は実質的に住宅費用を補助する福利厚生であり、労働の対価とはいえない。
と、Y社の主張をいずれも退け、総合職に限定する合理的な理由はないと判断しました。
(3) 結論
以上のことから、裁判所は「被告が…社宅制度の利用を、…総合職に限って認め、一般職に対して認めていないことにより、事実上男性従業員のみに適用される福利厚生の措置として社宅制度の運用を続け、女性従業員に相当程度の不利益を与えていることについて、合理的理由は認められない」とし、この措置は均等法の趣旨に照らし「間接差別に該当する」と結論付けました。
裁判所の判断内容(結論)
以上の判断に基づき、裁判所は以下の通り結論を示しました。
- 不法行為の成立
均等法の趣旨に照らし間接差別に該当する違法な状態を是正することなく、漫然と継続したY社の行為は、少なくとも過失があり違法であるとして、不法行為の成立を認めました。 - 損害賠償命令
Y社に対し、原告Xが被った損害として、社宅管理規程が適用された場合にY社が負担すべきであった家賃額と、実際に支払われた住宅手当との差額である約323万円、および慰謝料50万円と弁護士費用を合わせた合計約378万円の支払いを命じました。 - その他の請求
一方で、社宅管理規程の「総合職」という文言自体が公序良俗に反して無効とまではいえないとして、原告が社宅制度の適用を受ける地位にあることの確認請求は棄却しました。
実務に与える影響
本判決は、企業の人事労務管理、特にコース別人事制度を導入している企業にとって、極めて重要な示唆を与えるものです。
1. 福利厚生制度における「間接差別」リスクの顕在化
本判決の最大の意義は、均等法施行規則に明記されていない「住宅の貸与」という福利厚生措置について、初めて「間接差別」にあたると司法判断を下した点です。これにより、社宅制度だけでなく、社内貸付、財形貯蓄、あるいは各種手当など、従業員の区分によって差を設けているあらゆる福利厚生制度について、間接差別と評価されるリスクがあることが明確になりました。
2. 制度の「建前」ではなく「運用実態」が問われる
「転勤可能性があるから」といった制度上の建前だけでは、合理的な理由として不十分であり、実際の運用実態が厳しく問われることが示されました。自社の制度について、「本当にその目的通りに運用されているか」「目的と無関係な従業員が利益を得ていないか」といった観点からの検証が不可欠です。
3. 企業が取るべき対策
コース別人事制度を導入している企業は、以下の点について速やかに点検・見直しを行うべきでしょう。
- 従業員の男女構成比の把握
総合職・一般職といったコースごとの男女比率に著しい偏りがないかを確認する。 - 待遇差の合理性検証
コース間で設けている待遇差(給与、手当、福利厚生など)の一つひとつについて、その差異を設ける目的は何か、その目的は正当か、そして目的達成のためにその差異は本当に必要かつ合理的な手段かを客観的に説明できるか、再検証する。 - 運用実態の確認
制度の目的と実際の運用に乖離がないかを確認する。形骸化した制度は大きなリスクとなります。
本判決は、形式的な平等だけでなく、実質的な平等を確保することの重要性を企業に改めて突きつけるものです。自社の人事制度が、意図せず特定の性に不利益を与える構造になっていないか、この機会に深く点検することが求められます。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、様々な分野の法的問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。ご興味をお持ちの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
長瀬総合法律事務所は、お住まいの地域を気にせず、オンラインでのご相談が可能です。あらゆる問題を解決してきた少数精鋭の所属弁護士とスタッフが、誠意を持って対応いたします。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
企業が法的紛争に直面する前に予防策を講じ、企業の発展を支援するためのサポートを提供します。
複数の費用体系をご用意。貴社のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたします。