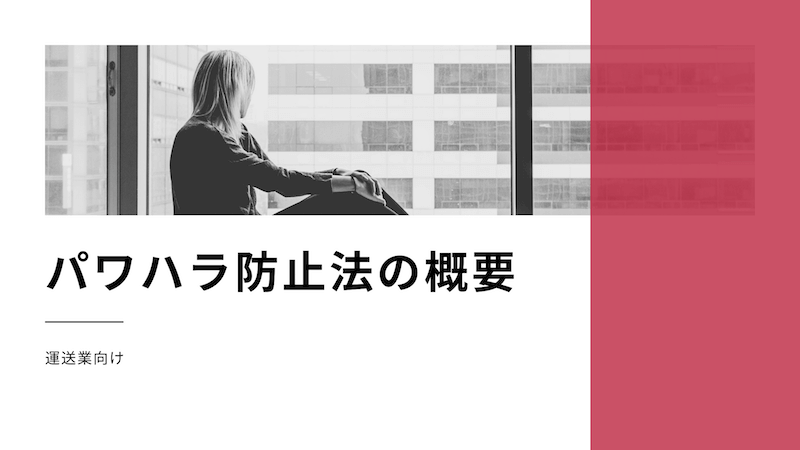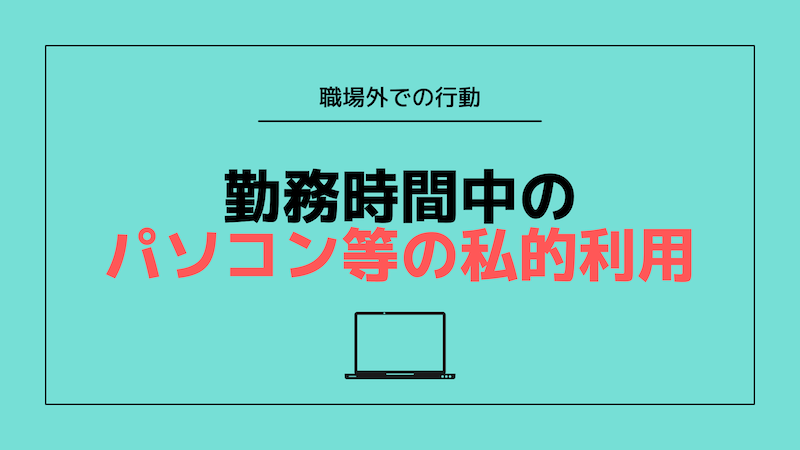はじめに:法的リスク管理のポイント
安全運転を徹底し、万全の管理体制を敷いていても、事業用トラックが公道を走る以上、交通事故のリスクを完全にゼロにすることはできません。そして、ひとたび事故が発生した時、その直後のわずか数時間の「初動対応」の質が、その後の会社の民事・刑事・行政上の責任を決定づけます。
パニックに陥ったドライバーへの不適切な指示、法律上の義務の懈怠、現場での安易な約束。これら初動対応の失敗は、被害者感情を著しく悪化させ、示談交渉を困難にするだけでなく、救護義務違反(ひき逃げ)といった本来負う必要のない重大な刑事責任を会社とドライバーに付加し、行政処分を招き、経営に深刻なダメージを与えかねません。
逆に、マニュアルに基づいた冷静な初動対応は、被害の拡大を防ぎ、被害者からの信頼を得て、会社の損害を最小限に食い止めるための効果的なリスクマネジメントです。本稿では、いつ起こるとも知れない「その時」に備え、運送会社の経営者様、運行管理者様が、ドライバーと会社自身、双方の視点から何をすべきか、そして何をすべきでないかを、具体的なポイントについて解説します。
ドライバーの義務:現場で必ず実行すべきアクション
会社は、以下の4つのアクションを、ドライバーが実行できるよう、日頃から教育・訓練しておく法的・社会的な責任があります。これらは、単なる推奨事項ではなく、法律で定められた義務です。
アクション1:直ちに運転を停止し、負傷者を救護する(道路交通法第72条第1項前段 – 救護義務)
事故を起こした場合、まず車両を直ちに停止させ、負傷者の有無を確認することが最優先です。負傷者がいる場合は、ためらわずに119番通報を行い、救急車の到着まで可能な範囲で止血などの応急手当を行います。これを怠ることは「救護義務違反(ひき逃げ)」という極めて悪質な犯罪となり、会社の存続を揺るがす事態に発展します。
アクション2:二次的危険を防止する(道路交通法第72条第1項前段 – 危険防止措置義務)
後続車による追突など、二次的な事故を防ぐための措置を講じる義務があります。ハザードランプを点灯させ、車両を安全な場所に移動させます(移動が困難な場合はそのままで構いません)。さらに、発炎筒や停止表示器材(三角表示板)を、車両の後方に十分な距離をとって設置し、後続車に危険を知らせる必要があります 3。この措置は、自社と他者の安全を守るだけでなく、会社が安全配慮義務を尽くしていることを示す重要な行動です。
アクション3:警察へ必ず報告する(道路交通法第72条第1項後段 – 報告義務)
人身事故・物損事故を問わず、どんなに些細な事故であっても、必ず110番通報し、警察に報告しなければなりません 4。警察官には、発生日時、場所、死傷者の数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故後に講じた措置などを、落ち着いて報告します。相手方から「警察を呼ばずに示談で」と持ちかけられても、絶対に応じてはいけません。警察への届出がなければ、保険金の請求に必要となる「交通事故証明書」が発行されず、保険が使えないという致命的な事態に陥ります 5。
アクション4:証拠の保全と情報交換を行う
警察の到着を待つ間、安全を確保した上で、事故状況の証拠を保全します。スマートフォンのカメラで、車両の損傷箇所、スリップ痕、周辺の道路標識や信号、事故現場全体の状況などを、様々な角度から撮影しておきます。また、相手方とは感情的にならず、丁寧な言葉遣いで、氏名、住所、連絡先、勤務先、車両の登録番号、自賠責保険・任意保険の会社名と証明書番号などを確認し、メモを取ります。この際、「全面的にこちらが悪いです」といった過失を認める発言は、法的な判断がなされる前に行うべきではありません。
会社・運行管理者の責務:「7ステップ」指令センタープロトコル
ドライバーからの第一報を受けたら、運行管理者はパニックに陥ることなく、以下の手順で冷静に対応します。管理者の役割は、単なる情報収集に留まらず、ドライバーを法的に保護し、会社の損失を最小化するための指令センターとして機能することです。
- ドライバーの安否確認と義務履行の徹底指示
まず「ケガはないか?落ち着いて」と声をかけ、ドライバーの精神状態を安定させます。その上で、最優先事項として「119番と110番への通報は済んだか?」を確認し、もし実行されていなければ、即座に実行するよう強く指示します。管理者のこの確認行為が、会社のコンプライアンス体制の根幹をなします。 - 状況の正確な把握
5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)に沿って、事故の概要を簡潔に聴き取ります。人身事故か物損事故か、被害の程度はどのくらいか、といった核心情報を把握します。 - 現場への急行判断
人身事故、大きな物損事故、交通に著しい影響を与えている事故の場合は、可能な限り運行管理者が現場に急行すべきです。現場では、ドライバーの精神的サポート、被害者へのお見舞いと謝罪、警察の実況見分への立ち会い補助、証拠保全など、会社としての誠実な対応姿勢を示します。 - 保険会社への事故第一報
契約している任意保険会社へ、事故の第一報を入れます。事故日時、場所、概要などを正確に伝え、今後の対応について指示を受けます。 - 荷主・関係先への連絡
積荷に損傷がある場合や、配送の大幅な遅延が見込まれる場合は、契約内容に従い、速やかに荷主へ報告し、指示を仰ぎます。誠実かつ迅速な報告が、信頼関係の維持に繋がります。 - 代替輸送の手配
運行を継続する必要がある場合、速やかに代替車両や交代ドライバーを手配し、事業への影響を最小限に抑えます。 - 社内での記録・情報共有
ドライバーからの聴取内容や、現場での対応状況などを時系列で正確に記録し、「事故報告書」を作成します。経営層を含め、関係者間で正確な情報を共有し、会社としての方針を決定します。
絶対的禁止事項:会社の未来を危険に晒す行動
以下の行動は、その場の雰囲気に流されて行いがちですが、後々、会社に計り知れない不利益をもたらすため、絶対に禁止しなければなりません。
- その場での示談や念書の作成
過失割合や損害額が全く不明な段階での金銭的な約束や、「修理代は全額持ちます」といった念書への署名は絶対に行いません。「すべて保険会社に任せておりますので」と伝え、専門家の判断に委ねる姿勢を貫きます。 - 安易な過失の承認
丁寧なお見舞いの言葉は必要ですが、「100%私が悪かったです」などと、法的な責任(過失)を全面的に認める発言は厳禁です。過失割合は、客観的な証拠に基づき、保険会社や弁護士が判断するものです。
まとめ
交通事故の初動対応は、企業の危機管理能力そのものが問われる場面です。その成否は、日頃からの準備と教育にかかっています。「事故対応マニュアル」を整備し、その内容を全ドライバーに周知徹底すること。そして、緊急連絡体制を確立し、定期的に訓練を行うこと。こうした地道な取り組みこそが、万が一の際にパニックを防ぎ、ドライバーと会社を守る最大の防御策となります。事故は起きてほしくないものですが、起きてしまった時にどう動くかで、その後の結果は天と地ほど変わります。
長瀬総合の運送業専門サイト
2024年4月1日からの働き方改革関連法施行により、物流業界での働き方が今までと大きく異なっていきます。
違反してしまうと刑事罰の対象になってしまうので、運送・物流業を営む方の対策は必須です。
「どうしたら良いかわからない」という方は当事務所までご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス