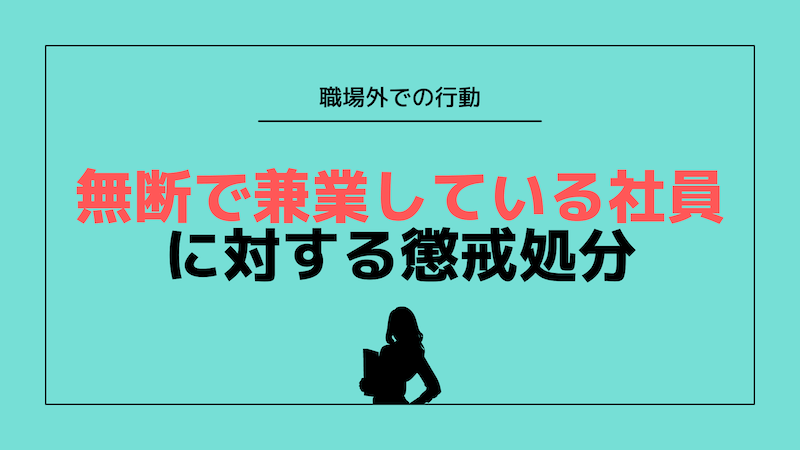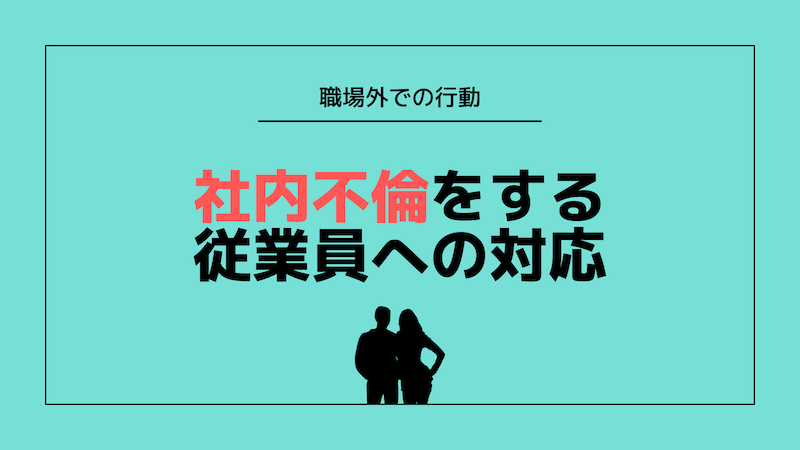はじめに
2019年4月から、すべての企業において「年10日以上の年次有給休暇(以下、有給休暇)が付与される労働者に対し、そのうち年5日については、会社が時季を指定して取得させなければならない」ことが義務化されました。このルールは、もちろん運送業も例外ではありません。
しかし、運送業界では、「ドライバーが休むと代わりがいない」「配車が回らなくなる」といった理由から、有給休暇の取得が進みにくいという現実があります。ドライバー自身も、同僚への気兼ねや、歩合給が減ることへの懸念から、取得をためらうケースが少なくありません。
だからといって、年5日の取得義務を果たさなければ、会社は労働基準法違反として、従業員一人あたり最大30万円の罰金を科される可能性があります。また、有給休暇を取得しにくい職場環境は、従業員の心身の疲労を蓄積させ、安全運行を脅かすだけでなく、人材の定着を妨げる大きな要因となります。
※ 本記事では、この有給休暇の年5日取得義務を確実に遵守しつつ、事業への影響を最小限に抑えるための賢い管理方法、特に「計画的付与制度」の活用法について法的なポイントを交えて解説します。
Q&A
Q1. ドライバーが「有給休暇はいらないから、その分給料を上乗せしてほしい」と言っています。本人が納得していれば、有給休暇を与えなくても問題ないでしょうか?
問題があります。年5日の有給休暇取得義務は、労働基準法で定められた会社の「義務」であり、たとえ労働者本人が同意していても、免除されることはありません。有給休暇の目的は、労働者の心身のリフレッシュを図ることにあり、会社が休暇を与えずに金銭で買い上げる(特に、法定の5日分について)ことは、原則として認められていません。そのような対応は明確な法令違反となります。
Q2. 繁忙期にドライバーから有給休暇の申請がありました。どうしても人手が足りない場合、会社は取得日を変更してもらうことはできますか?
はい、可能です。会社には「時季変更権」という権利が認められています。これは、労働者が指定した時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、他の時季に休暇日を変更できるというものです。ただし、この権利の行使は厳格に解釈されます。単に「忙しいから」「代わりの人がいないから」という理由だけでは不十分で、代替要員の確保など、会社として最大限の努力をしてもなお、事業運営に客観的に重大な支障が生じる場合に限定されます。
Q3. 会社が休みの日(夏季休暇など)を、有給休暇として処理することはできますか?
「計画的付与制度」を導入すれば可能です。この制度は、労使協定を結ぶことを条件に、会社が計画的に従業員の有給休暇の取得日を割り振ることができる制度です。例えば、夏季やお盆の時期に、会社全体で3日間の一斉休業日を設け、その日を従業員の有給休暇取得日として処理することができます。これにより、会社は計画的に取得義務を消化させることができ、ドライバーも気兼ねなく休むことができます。
解説
必ず守るべきルール!「年5日」の有給休暇取得義務
まずは、法律で定められた義務の基本を正確に理解しましょう。
対象者: 法律上の労働者で、年10日以上の有給休暇を付与される者。
正社員だけでなく、パートやアルバイトも、勤続年数や所定労働日数に応じて年10日以上の権利が発生すれば対象となります。管理監督者も対象です。
義務の内容
有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、そのうち5日間について、会社が時季を指定して取得させる必要があります。
カウント方法
労働者自らが請求して取得した有給休暇の日数は、5日から差し引くことができます。
- 後述する「計画的付与」によって取得した日数も、もちろんカウントできます。
- 例えば、労働者が自ら3日取得した場合、会社は残り2日について時季を指定して取得させれば、義務を果たしたことになります。
罰則
義務を果たせなかった場合、労働基準法第120条に基づき、対象となる労働者1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。
運送業における有給休暇管理の課題
運送業で有給休暇の取得が進まない背景には、特有の課題があります。
- 代替要員の不足
特定のコースや荷主を担当するドライバーが休むと、代わりを務められる人材がいない。 - 配車計画の複雑化
属人的な配車を行っている場合、一人が休むことで全体の計画が崩れてしまう。 - 歩合給・出来高払制の影響
休むと売上や走行距離が減り、歩合給部分が減少するため、ドライバー自身が取得をためらう。 - 同僚への気兼ね
自分が休むと同僚に迷惑がかかるという、職場風土の問題。
これらの課題を放置したまま、「自由に取っていいよ」と言うだけでは、取得率は上がりません。会社が主導して、計画的に休暇を取得できる仕組みを作ることが不可欠です。
課題解決のポイント 「年次有給休暇の計画的付与制度」
計画的付与制度は、これらの課題を解決するための有効な手段です。
- 制度の仕組み
従業員が保有する有給休暇の日数のうち、5日を超える部分について、労使協定を締結すれば、会社が計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。(5日間は、従業員が病気などのために自由に取得できるよう、必ず残しておく必要があります。) - 導入のメリット
会社側: 計画的に休暇を消化させられるため、年5日の取得義務を確実にクリアできる。あらかじめ休みの日が分かるため、配車計画が立てやすくなる。 - 従業員側
会社が指定してくれるため、同僚への気兼ねなく堂々と休むことができる。長期休暇も取得しやすくなる。 - 導入の方法(労使協定の締結)
この制度を導入するには、必ず**労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)との間で、書面による協定(労使協定)**を締結する必要があります。就業規則に記載するだけでは導入できません。 - 計画的付与の主な方式
一斉付与方式: 全従業員に対して、同じ日に有給休暇を付与する方式。(例:お盆の時期の〇月〇日~〇日、年末年始の〇月〇日~〇日を、全社一斉の有給休暇取得日とする) - 班・グループ別の交替制付与方式
営業所やチームごとに、交替で休暇日を設定する方式。運送業のように、事業全体を一度に止めるのが難しい場合に有効です。(例:Aチームは〇月の第2月・火、Bチームは第3月・火を計画的付与日とする) - 個人別の付与方式
個人ごとに、有給休暇の取得計画表を作成させ、会社がその計画に基づいて時季を指定する方式。個人の希望を反映しやすいですが、管理が煩雑になる側面もあります。
確実な義務履行のための管理体制
計画的付与制度を導入するとともに、以下の管理体制を整備することが重要です。
- 年次有給休暇管理簿の作成と保存
会社は、従業員ごとに、「基準日」「付与日数」「取得時季」「残日数」を記録した管理簿を作成し、3年間保存する義務があります。これは、取得義務を果たしていることを証明するための重要な証拠となります。 - 取得状況のモニタリング
管理簿に基づき、従業員ごとの取得状況を定期的に確認します。基準日から半年が経過した時点などで取得日数が少ない従業員に対しては、上長から取得を促すなどの声かけを行います。 - 時季指定の方法
労働者が自ら取得した日数と計画的付与日数を合わせても5日に満たない場合、会社は労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めながら、残りの日数について時季を指定します。「来月の〇日に休んでください」と、具体的な日付を明確に伝える必要があります。
弁護士に相談するメリット
有給休暇の管理は、法律の要件と、事業運営の現実を両立させる必要があり、専門的な知見が求められます。
- 計画的付与制度導入のトータルサポート
貴社の事業実態に合った付与方式(一斉付与、グループ別など)を提案し、法的に有効な労使協定書の作成を支援します。就業規則への規定方法についても、的確にアドバイスします。 - 時季変更権の行使に関する助言
ドライバーから繁忙期に有給休暇の申請があった場合に、時季変更権の行使が法的に認められるケースかどうか、具体的な状況に基づき判断します。不当な時季変更権の行使によるトラブルを未然に防ぎます。 - 年次有給休暇管理簿の整備支援
法令の要件を満たした、実用的な管理簿のフォーマット提供や、管理方法に関するアドバイスを行います。勤怠管理システムとの連携についても助言できます。 - 労働基準監督署の調査対応
万が一、年5日の取得義務違反で調査が入った場合にも、会社の状況を的確に説明し、是正勧告等への対応をサポートします。
まとめ
有給休暇の年5日取得義務は、会社にとって負担に感じられるかもしれません。しかし、見方を変えれば、これはドライバーに計画的にリフレッシュの機会を与え、心身の健康を維持し、安全運行を確保するための絶好の機会です。そして何より、従業員満足度を高め、「働きやすい会社」として人材を確保・定着させるための重要な一手となります。
「うちは忙しいから無理」と諦めるのではなく、「どうすれば計画的に休ませられるか」という視点に立ち、計画的付与制度などの仕組みを賢く活用することが、これからの運送事業者には求められます。
制度の導入や運用方法に迷ったら、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。貴社が法令を遵守し、従業員がいきいきと働ける職場環境を構築するため、法務の専門家として最適なソリューションを提供いたします。
長瀬総合の運送業専門サイト
2024年4月1日からの働き方改革関連法施行により、物流業界での働き方が今までと大きく異なっていきます。
違反してしまうと刑事罰の対象になってしまうので、運送・物流業を営む方の対策は必須です。
「どうしたら良いかわからない」という方は当事務所までご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス