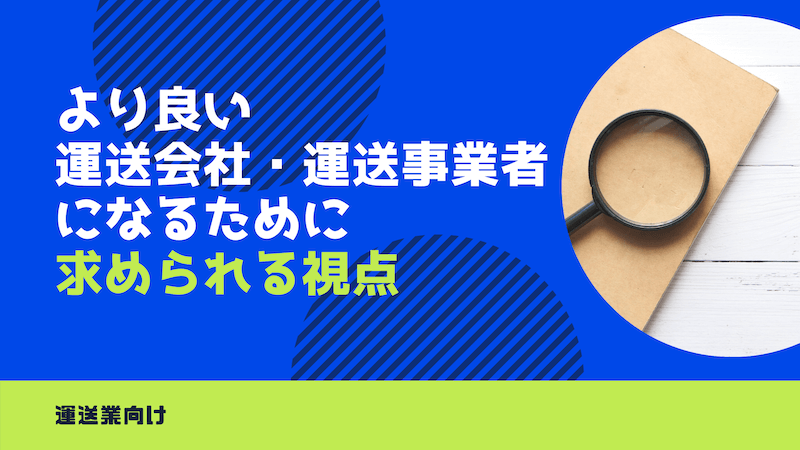はじめに
「約束の時間に到着したのに、荷主の都合で2時間も待たされた」「契約にないはずの荷物の仕分け作業までやらされた」。このような「荷待ち」や「荷役」に伴う長時間労働は、多くのトラックドライバーが経験する深刻な問題であり、2024年問題の根幹をなす課題の一つです。
この状況を改善するため、2024年4月1日から、運送事業者には、ドライバーが荷主の事業場で行った荷待ち・荷役の時間や作業内容を記録することが「義務」となりました。これは、貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正によるものです。
この法改正を、単に「また記録する手間が増えた」と捉えるのは、非常にもったいないことです。むしろ、これはこれまで曖昧にされてきた荷主の責任を明確化し、不当な長時間待機や無償の付帯作業に対して、運送事業者が正当な声を上げるための強力な「法的ツール」を手に入れたことを意味します。
本記事では、この記録義務化の具体的な内容、違反しないための管理方法、そして記録したデータを武器として荷主との改善交渉や料金交渉を有利に進めるための法的ポイントを、弁護士が解説します。
Q&A
Q1. 具体的に何を、どのような方法で記録すればよいのでしょうか?
貨物自動車運送事業輸送安全規則では、①荷主の氏名・名称、②集貨・配達地点、③荷待ちの開始・終了日時、④積込み(荷役)の開始・終了日時、⑤取卸し(荷役)の開始・終了日時などを記録することが求められています。運転日報への追記や、専用のスマートフォンアプリ、勤怠管理システムなどのデジタルツールを活用する方法があります。重要なのは、後から客観的に確認できる形で、1年間保存しておくことです。
Q2. 記録した内容は、必ず荷主に渡したり、見せたりしなければならないのですか?
法律上、記録した内容を荷主に提出する義務はありません。この記録は、まず運送事業者自身がドライバーの労働実態を把握し、改善に役立てるためのものです。しかし、荷主に対して待機時間の削減を要請したり、待機料金を請求したりする際には、この客観的な記録が極めて有力な「証拠」となります。「当社の記録によれば、貴社では平均〇時間の荷待ちが発生しています」と具体的なデータを示すことで、交渉に説得力を持たせることができます。
Q3. 記録を元に荷主に追加料金を請求したら、取引を打ち切られないか心配です…
そのような懸念を持たれるのは当然です。しかし、泣き寝入りを続けていては、ドライバーの負担は増え、会社の経営は立ち行かなくなります。重要なのは、感情的にならず、法的な根拠に基づいて交渉することです。国土交通省が告示した「標準的な運賃」には待機時間料なども含まれており、これを根拠に「法令遵守と安全運行の維持のため」と説明します。もし、荷主がその優越的な地位を利用して一方的に取引を打ち切るような行為に出た場合、それは独占禁止法が禁じる「優越的地位の濫用」にあたる可能性があります。そのような場合は、弁護士にご相談することもご検討ください。
解説
法改正の背景と目的 – なぜ記録が義務化されたのか
トラックドライバーの長時間労働は、個々の運送事業者だけの問題ではなく、荷主の慣行にも大きな原因がありました。特に、以下のような問題が指摘されてきました。
- 長時間にわたる荷待ち
荷主側の生産・出荷体制の都合で、トラックが到着してもすぐに荷物の積卸しができず、長時間待機させられる。 - 契約外の付帯作業
運送契約に含まれていないはずの、荷物の検品、仕分け、ラベル貼りといった作業を、サービスとして無償で強要される。
これらの時間は、ドライバーにとっては紛れもない「労働時間(手待ち時間)」であり、拘束時間を延ばす元凶です。しかし、これまではその実態が客観的なデータとして示されることが少なく、運送事業者が荷主に改善を求めにくい状況がありました。
今回の記録義務化は、この荷待ち・荷役という「ブラックボックス」を「見える化」し、その負担を明確にすることで、
- 運送事業者自身が労働時間管理を徹底する
- 荷主に対して、長時間労働の是正に向けた協力を促す
- 荷待ち・荷役を運送の対価として適正に評価し、料金に転嫁する土壌を作る
ことを目的としています。これは、荷主にもサプライチェーン全体で労働環境改善の責任があることを、国が公式に示したものと言えます。
記録義務の具体的な内容
改正された貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第2項では、一般貨物自動車運送事業者(緑ナンバーの事業者)に対し、乗務等の記録(運転日報)に以下の事項を記録させることを義務付けています。
記録が必要な行為
ドライバーが、荷主の事業場等に到着してから、以下の行為を行った場合。
- 集貨のための待機(荷待ち)
- 貨物の積込み(荷役)
- 配達のための待機
- 貨物の取卸し(荷役)
記録すべき事項
- その行為を開始及び終了した地点(荷主の事業場名、倉庫名など)
- その行為を開始及び終了した日時
- その行為の内容(例:「〇〇倉庫にてパレット積込み」「△△センターにて納品待ち」など)
- その他、参考となる事項
記録方法と保存期間
- 媒体
運転日報への追記、PC、スマートフォンのアプリ・システムなど、媒体は問われない。 - 保存
作成した記録は、1年間保存しなければなりません。
この義務に違反した場合、直接的な罰則はありませんが、運輸局の監査において指摘を受け、是正指導や行政処分の対象となる可能性があります。
記録データを「武器」にする!荷主交渉への活用法
記録は、ただ義務だから行うのではありません。経営を改善するための「データ」として積極的に活用することが重要です。
Step1: 現状分析と課題の特定
収集したデータを荷主別、月別、曜日別などに集計・分析します。これにより、「どの荷主の、どの時間帯に、どれくらいの荷待ち・荷役が発生しているか」という課題が客観的な数値として浮かび上がります。
Step2: 具体的な改善要請
分析結果をグラフなどで分かりやすく資料化し、荷主に提示します。「当社のドライバーは、貴社にて月平均〇〇時間の待機を強いられており、改善基準告示で定められた拘束時間の上限を圧迫しております。トラックバースの予約システム導入や、荷役作業員の増員といったご協力をお願いできないでしょうか」と、具体的な改善策をセットで提案します。
Step3: 適正な料金交渉
改善が見られない場合や、そもそも荷役作業が契約に含まれていない場合には、料金交渉に移ります。ここでも、「標準的な運賃」が強力な後ろ盾となります。
- 待機時間料
「標準的な運賃」で示されている待機時間(30分超)の料金を根拠に請求します。 - 荷役料
積込み・取卸しといった作業についても、「標準的な運賃」の料金表を参考に、作業内容に応じた料金を請求します。
「これは当社の勝手な要求ではなく、国が示した基準に基づき、法令を遵守するために必要なコストです」という論理で交渉を進めます。
荷主が協力しない場合の法的アプローチ
誠実な交渉にもかかわらず、荷主が改善の努力を見せなかったり、不当な要求を続けたりする場合には、法的手段を検討します。
荷主勧告制度
運送事業者の法令違反(過労運転など)の主な原因が荷主の行為にあると認められる場合、国土交通大臣が荷主に対して、再発防止策を講じるよう「勧告」することができます。荷待ち・荷役時間の記録は、この「荷主の行為」を証明する重要な証拠となります。
独占禁止法・下請法
- 優越的地位の濫用
荷主が取引上の優越的な地位を利用し、正当な理由なく付帯作業の対価を支払わなかったり、待機料金の支払いを拒否したりする行為は、独占禁止法違反となる可能性があります。 - トラックGメンへの通報
国土交通省に設置された「トラックGメン」は、荷主に関する不公正な取引の相談窓口です。具体的な状況を情報提供し、調査を促すことができます。
これらの法的手段の存在を交渉のカードとして持っておくことも、対等な関係を築く上で有効です。
弁護士に相談するメリット
荷主との交渉は、一歩間違えれば取引関係の悪化を招きかねない、デリケートな問題です。運送業に詳しい弁護士は、以下の点で貴社をサポートします。
- 交渉戦略の立案と法的根拠の整理
記録データを法的に分析し、荷主との交渉に向けた最も効果的な戦略を立案します。「標準的な運賃」や各種法令を引用した、説得力のある交渉資料の作成を支援します。 - 代理人としての交渉・通知書作成
貴社に代わって弁護士が代理人として交渉に臨んだり、弁護士名義で改善を求める通知書を送付したりすることで、荷主に対して事態の重大性を認識させ、真摯な対応を促します。 - 法的措置の実行支援
交渉が決裂した場合に、荷主勧告制度の活用や、公正取引委員会・中小企業庁への申告、トラックGメンへの通報といった具体的な法的アクションを、手続き面からサポートします。 - 契約書の見直しと作成
将来のトラブルを防ぐため、荷待ち・荷役に関するルールや料金体系を明確に定めた、貴社に有利な運送委託契約書を作成します。
まとめ
荷待ち・荷役時間の記録義務化は、運送事業者にとって、長年の課題であった荷主との不平等な関係を是正し、ドライバーの労働環境を抜本的に改善するためのチャンスです。
この法改正を負担と捉えるのではなく、自社の権利を主張するための「武器」と捉え、積極的に活用してください。客観的な記録に基づいた冷静な交渉は、荷主との間に、より健全で持続可能なパートナーシップを築くきっかけとなるはずです。
もし、荷主との交渉の進め方にお悩みでしたら、一人で抱え込まずに、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。我々は、法務の力で、貴社が正当な対価を勝ち取るためのお手伝いをいたします。
長瀬総合の運送業専門サイト
2024年4月1日からの働き方改革関連法施行により、物流業界での働き方が今までと大きく異なっていきます。
違反してしまうと刑事罰の対象になってしまうので、運送・物流業を営む方の対策は必須です。
「どうしたら良いかわからない」という方は当事務所までご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス