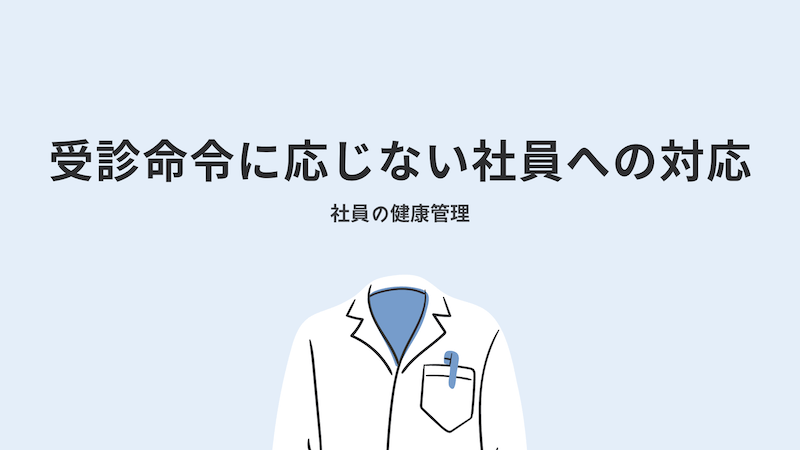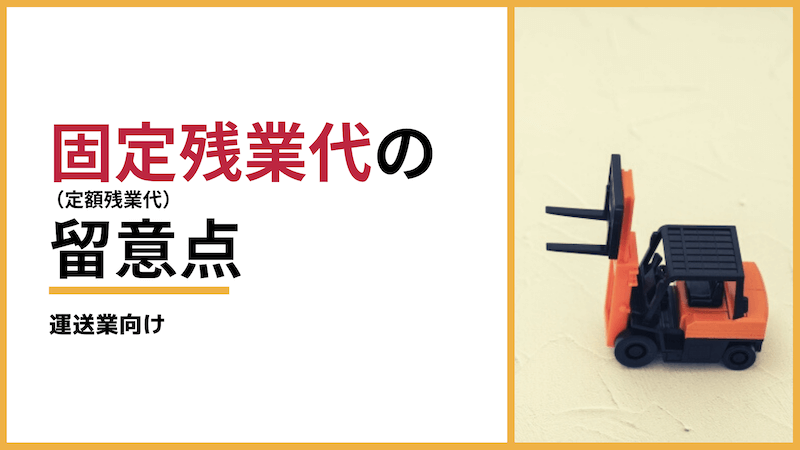はじめに
2024年問題への対応、すなわちドライバーの労働時間短縮と労働環境改善は、運送事業者にとって避けては通れない経営課題です。しかし、コンプライアンスを遵守すれば、人件費の増加や輸送効率の低下は避けられず、必然的にコストが増大します。この増加したコストを自社だけで吸収し続けることは、企業の体力を削り、いずれ立ち行かなくなることは明白です。
この構造的な課題を解決する唯一の道は、荷主に対して適正なコストを価格転嫁し、運賃を引き上げることです。しかし、長年の取引関係や力関係から、「荷主に運賃の値上げを言い出すのは難しい」と感じている経営者様が非常に多いのではないでしょうか。
そのような状況を打破するための強力な武器が、2020年の法改正で導入された「標準的な運賃」制度です。これは、国が「法令を遵守するためには、このくらいの運賃が参考になりますよ」と公式に示した、いわば交渉の「お墨付き」です。
本記事では、この「標準的な運賃」を法的な根拠として、荷主と対等な立場で運賃交渉を進めるための具体的なステップと、不当な要求を受けた場合の対抗策について解説します。
Q&A
Q1. 「標準的な運賃」に法的な拘束力はありますか?荷主はこの運賃に必ず応じなければならないのですか?
いいえ、「標準的な運賃」自体に、契約を強制するような法的な拘束力はありません。あくまで国が告示した「参考」となる運賃です。したがって、荷主がこの運賃での契約に必ず応じる義務はありません。しかし、これは「交渉の場で何の役にも立たない」という意味ではありません。この運賃は、2024年問題への対応など、法令遵守に必要なコストが算定根拠に含まれています。そのため、「法令を遵守し、安全で持続可能な輸送サービスを提供するためには、これだけのコストが必要です」という、極めて客観的で正当な交渉材料となるのです。単なる「値上げしてください」ではなく、「国の基準に基づくとこうなります」と説明することで、交渉に大きな説得力が生まれます。
Q2. 荷主から「他社はもっと安い運賃でやってくれる」と言われた場合、どう切り返せばよいですか?
これは交渉の場で頻繁に出てくる言葉です。この場合、感情的にならず、冷静に、しかし毅然と対応することが重要です。まず、「その運賃では、2024年4月から施行された改正労働基準法や改善基準告示を遵守することが、当社の試算では困難です」と伝えます。その上で、「法令を無視した運行は、重大な事故に繋がりかねず、結果として荷主様にご迷惑をおかけするリスクがあります。当社は、コンプライアンスを徹底し、安全・確実な輸送をお約束するために、適正な運賃でのご契約をお願いしております」と、安さの裏にあるリスクと、自社の安全への姿勢を訴えかけるのが有効です。
Q3. 交渉が決裂し、荷主から取引停止をちらつかされた場合、法的に問題はないのでしょうか?
ケースによりますが、法的に問題となる可能性があります。荷主がその取引における地位が運送事業者に対して優越している(例:取引依存度が高い、取引先の変更が困難など)ことを利用して、一方的に著しく不利益な条件を課したり、適正な運賃での取引を拒否して取引を打ち切ったりする行為は、独占禁止法が禁じる「優越的地位の濫用」や、下請法上の「買いたたき」に該当する可能性があります。泣き寝入りせず、弁護士にご相談ください。交渉の経緯を記録した議事録やメールなどの証拠を保全しておくことが重要です。
解説
「標準的な運賃」とは何か? – 交渉の強力な武器
「標準的な運賃」は、2020年4月に改正された貨物自動車運送事業法に基づき、国土交通大臣が告示したものです。これは、運送事業者が法令(労働関係法令、交通関係法令など)を遵守し、事業を継続的に運営していく上で「参考とすべき」運賃を示したもので、以下の特徴があります。
- コンプライアンスコストを反映
ドライバーの労働条件を改善し、2024年問題に対応するための人件費、社会保険料、安全対策費用などが原価として適切に算入されています。 - 具体的な算出基準
車両の大きさ(小型、中型、大型)、距離(距離制運賃)、時間(時間制運賃)など、具体的な算出モデルが示されており、自社の運賃体系と比較しやすくなっています。 - 付帯業務の料金も明記
待機時間料(荷待ち)、積込料・取卸料、検品料など、これまでサービス残業となりがちだった付帯業務についても、料金の参考例が示されています。
この制度の最大の意義は、これまで個々の運送会社が漠然と抱えていた「適正なコスト」を、国が公的な基準として可視化した点にあります。これにより、運賃交渉は単なる価格競争ではなく、「法令遵守と安全確保のためのコストを、サプライチェーン全体でどう負担していくか」という、建設的な議論の土台を得たといえます。
運賃交渉を成功させるための具体的な4ステップ
「標準的な運賃」という武器を手にしても、それを効果的に使うための戦略が必要です。以下の4つのステップで、交渉に臨みましょう。
Step1:「自社の原価計算」
交渉の第一歩は、敵を知る前に己を知ること、つまり自社のコスト構造を正確に把握することです。燃料費、人件費(残業代、社会保険料含む)、車両の減価償却費・リース料、修繕費、保険料、事務所経費など、全てのコストを洗い出し、1台・1時間あたり、あるいは1kmあたりの原価を算出します。この客観的な数字が、全ての交渉の出発点となります。
Step2:「交渉資料の準備」
口頭だけの説明では、荷主の理解を得ることは困難です。以下の資料を準備し、交渉のテーブルに臨みましょう。
-
- 「標準的な運賃」との比較表
自社の現行運賃と、「標準的な運賃」を並べて表示し、どれだけの乖離があるかを視覚的に示します。 - 自社の原価計算シート
Step1で算出した原価の内訳を示し、運賃が原価を割っている、あるいは適正な利益を確保できていない現状をデータで説明します。 - 2024年問題によるコスト増の試算
時間外労働規制や改善基準告示の改正に伴い、具体的にどれだけ人件費が増加するのか、あるいは輸送効率が低下するのかをシミュレーションした資料。 - 安全対策への投資実績
ドライブレコーダーやデジタコの導入、安全教育の実施など、安全確保のために投資しているコストをアピールします。
- 「標準的な運賃」との比較表
Step3:「交渉の実行」
交渉の場では、「苦しいから助けてほしい」といった感情論は避けましょう。あくまでビジネスパートナーとして、用意した資料に基づき、冷静かつ論理的に説明します。
-
- 交渉の目的を明確化
「目的は、法令を遵守し、今後も安定的かつ安全な輸送サービスを貴社に提供し続けることです」と伝えます。 - コスト増の要因を具体的に説明
「今回の法改正により、ドライバーの休息期間を11時間確保する必要があり、長距離輸送では中継輸送の導入やドライバーの増員が不可欠となります。そのためのコスト上昇分として、〇〇円のご負担をお願いするものです」と具体的に話します。
- 交渉の目的を明確化
Step4:合意内容の「契約書への反映」
交渉が妥結したら、それで終わりではありません。合意内容を書面に残すことが重要です。
-
- 運送委託契約書の締結・変更
改定後の運賃、待機時間や荷役作業といった付帯業務の料金体系を明記した契約書を新たに締結するか、覚書を取り交わします。 - 燃料サーチャージ条項の導入
燃料価格の変動分を運賃に自動的に反映させる「燃料サーチャージ条項」を盛り込むことで、将来の燃料価格高騰リスクに備えます。
- 運送委託契約書の締結・変更
荷主の不当な要求への法的対抗策
残念ながら、すべての荷主が建設的な交渉に応じてくれるとは限りません。中には、優越的な地位を背景に、不当な要求をしてくるケースもあります。そのような場合には、以下の法的制度を念頭に置き、対抗することも検討しましょう。
- 独占禁止法(優越的地位の濫用)
荷主が、取引上の地位が優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、「買いたたき(著しく低い対価での取引強要)」や「減額」、「取引の拒絶」などを行うことは、優越的地位の濫用として禁止されています。 - 下請法(下請代金支払遅延等防止法)
資本金規模などの条件を満たす場合、荷主(親事業者)には、下請事業者(運送会社)に対して、発注書面の交付義務、不当な返品の禁止、買いたたきや支払遅延の禁止といった、様々な義務が課せられています。 - 荷主勧告制度・トラックGメン
運送会社の過積載や過労運転といった法令違反の背景に、荷主からの無理な要求(到着時間の強要など)があると認められる場合、国土交通大臣が荷主に対して改善を求める「荷主勧告」を行うことがあります。また、国土交通省に設置された「トラックGメン」は、荷主との取引に関するトラブルの相談窓口として機能しており、違反が疑われる行為について調査を行います。
これらの制度を知っているだけでも、交渉における心理的なサポートになります。実際に問題が発生した際には、速やかに弁護士に相談し、どの法的手段が最も有効か検討することが重要です。
弁護士に相談するメリット
運賃交渉は、経営の根幹に関わる重要な業務です。弁護士は、単なる法律アドバイザーとしてだけでなく、交渉を成功に導く戦略パートナーとして貴社を支援します。
- 交渉戦略の策定と資料のリーガルチェック
貴社の状況と荷主との関係性を踏まえ、最も効果的な交渉戦略を共に立案します。準備した交渉資料に法的な抜け漏れがないか、相手に隙を与えない内容になっているかをチェックします。 - 交渉力の強化(通知書作成・交渉代理)
弁護士名で交渉を申し入れる内容証明郵便を作成したり、交渉を代理対応したりすることで、荷主に対して「本気で交渉に臨んでいる」という強いメッセージを伝え、安易な妥協を許さない状況を作り出します。 - 法的対抗措置の実行
交渉が決裂し、荷主による優越的地位の濫用や下請法違反が疑われる場合には、公正取引委員会や中小企業庁への申告手続きを代理し、貴社の正当な権利を守ります。 - 自社に有利な契約書の作成:
交渉で勝ち取った条件を、将来の紛争を防ぐ形で、法的に有効かつ自社に有利な運送委託契約書に落とし込みます。
まとめ
2024年問題に端を発する運賃への価格転嫁は、もはや「お願い」するものではなく、法令を遵守し、社会インフラである物流を維持するために、事業者として「当然の権利」として主張すべきものです。そして、その主張を支える最大の法的根拠が「標準的な運賃」です。
もちろん、交渉は一筋縄ではいかないでしょう。しかし、十分な準備と法的知識、そして毅然とした態度で臨めば、道は開けます。荷主は敵ではなく、共にサプライチェーンを支えるパートナーです。そのパートナーシップを、より健全で対等なものへと再構築する好機が、訪れています。
運賃交渉でお悩みの経営者様は、一人で抱え込まず、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。我々は、貴社が正当な対価を勝ち取り、持続可能な経営を実現するため、法務の力でバックアップいたします。
長瀬総合の運送業専門サイト
2024年4月1日からの働き方改革関連法施行により、物流業界での働き方が今までと大きく異なっていきます。
違反してしまうと刑事罰の対象になってしまうので、運送・物流業を営む方の対策は必須です。
「どうしたら良いかわからない」という方は当事務所までご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス