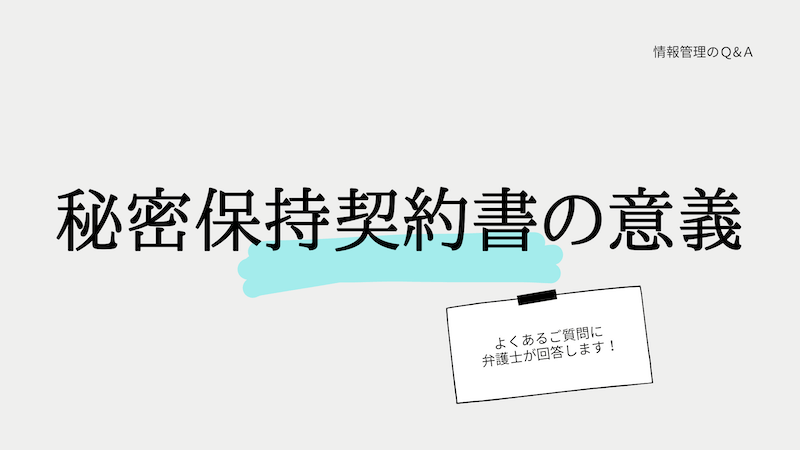はじめに
ある日突然、SNSや匿名掲示板で自分や自社に関する心ない書き込みを発見したとき、誰もが強い衝撃を受け、冷静ではいられなくなるものです。「どうしてこんなことを書かれるんだ」「すぐにでも反論したい」「早く消してほしい」と、怒りや不安で頭が真っ白になってしまうかもしれません。
しかし、このようなときこそ、感情に任せて行動するのではなく、冷静に、そして正しい手順で対応することが、その後の解決を大きく左右します。初動対応を誤ると、かえって事態を悪化させてしまったり、本来取れたはずの法的措置が取れなくなってしまったりする危険性があるのです。
この記事では、ネットで誹謗中傷の被害に遭った方が、パニックにならずに次の一手を打つための「初動対応の具体的なステップ」と、一人で抱え込まずに頼れる「相談窓口」について、弁護士が解説します。
Q&A
Q1. 誹謗中傷の書き込みを見つけ、怒りで我慢できません。すぐにでも「それは嘘だ!」と反論しても良いでしょうか?
お気持ちは察しますが、感情的に反論することは避けるべきです。加害者は、あなたの反応を見て楽しんでいる「荒らし」である可能性があり、反論することで相手を喜ばせ、さらなる攻撃を誘発しかねません。また、言い争いになれば、あなた自身も不用意な発言をしてしまい、相手に攻撃の口実を与えたり、話がこじれて炎上したりするリスクがあります。まずは冷静になり、直接反応するのではなく、後述する証拠保全を最優先してください。
Q2. 書き込みが多くの人に見られる前に、一刻も早く削除したいです。まずはサイト運営者に削除依頼をするのが一番ですか?
早く消したいというお気持ちは当然ですが、削除依頼の前に「証拠保全」を行ってください。投稿の削除や投稿者の特定といった法的手続きを進めるには、「いつ、どのサイトに、どのような内容の投稿があったか」を客観的に証明する証拠が必要です。証拠がない状態で投稿が削除されてしまうと、権利侵害の事実を証明できなくなり、その後のあらゆる法的措置が困難になってしまいます。まずは証拠を確保し、その上で削除依頼などの次のステップに進むのが有益です。
Q3. 警察と弁護士、どちらに先に相談すれば良いのか分かりません。
どちらに相談すべきかは、あなたの目的によって異なります。「殺すぞ」といった脅迫や、緊急の危険が迫っている場合は、迷わず警察に連絡してください。一方、「投稿を削除したい」「投稿者を特定して損害賠償を請求したい」といった、具体的な法的措置による解決を望む場合は、弁護士に相談するのが最適です。弁護士は、警察への刑事告訴のサポートも行えるため、民事・刑事両面での解決を目指す場合も、まずは弁護士に相談するとスムーズです。
解説
誹謗中傷の被害に遭ったとき、冷静さを失わずに以下の4つのステップを順番に実行することが、被害の拡大を防ぎ、将来的な法的措置の可能性を守る上で重要です。
【ステップ1】冷静になり、感情的な反応を避ける
誹謗中傷を発見した直後は、誰でも動揺し、怒りや不安に駆られます。しかし、ここで最もやってはいけないのが、感情に任せて投稿者に直接反論したり、言い争ったりすることです。
なぜ、直接反応してはいけないのか?
- 炎上のリスク
反論が新たな火種となり、第三者も巻き込んで「炎上」状態に発展することがあります。炎上すると、情報が爆発的に拡散され、収拾がつかなくなります。 - 相手を利するだけ
特に「荒らし」と呼ばれるタイプの加害者は、あなたの反応そのものを楽しんでいます。反応すればするほど相手の思う壺であり、攻撃がエスカレートする原因になります。 - 証拠隠滅の可能性
あなたが反応したことで、加害者が警戒し、アカウントを削除したり投稿を消したりして逃げてしまう可能性があります。 - 新たな攻撃材料の提供
言い争いの中で、あなた自身が不用意な発言をしてしまうと、それを捉えられてさらなる誹謗中傷のネタにされてしまう危険性があります。
まずは深呼吸をして、心を落ち着かせましょう。そして、相手の土俵には乗らず、次のステップである「証拠保全」に静かに着手することが、賢明な第一歩です。
【ステップ2】証拠を保全する(最重要)
初動対応の中で、重要なステップが「証拠保全」です。
ネット上の投稿は、加害者が任意に、あるいはサイト運営者の判断で、いつ削除されるか分かりません。投稿が消えてしまえば、そもそも権利侵害があったことを証明すること自体が困難になります。
削除請求、投稿者の特定(発信者情報開示請求)、損害賠償請求、刑事告訴など、あらゆる法的措置の出発点は、この「証拠」です。以下のポイントを押さえて、証拠を保存してください。
スクリーンショットを撮影する
必須項目
①誹謗中傷の投稿内容そのもの、②投稿された日時、③投稿ページのURL(アドレスバーの表示全体)、④サイト名やSNSのサービス名、⑤投稿者のアカウント名やID、などが一枚の画像に収まるように撮影します。
方法
PCの場合は、キーボードの「PrintScreen」キーを使い、画像編集ソフトに貼り付けて保存します。スマホの場合は、本体のスクリーンショット機能を使います。問題の箇所だけを切り取るのではなく、URLを含む画面全体を撮影してください。
動画の場合は画面を録画する
YouTubeなどの動画で誹謗中傷が行われている場合は、PCやスマホの画面録画機能を使って、動画全体とURLがわかるように録画・保存します。
印刷(プリントアウト)する
撮影したスクリーンショットやウェブページを紙に印刷しておくことも有効です。印刷することで、電子データが何らかの理由で破損・消失した場合のバックアップになります。印刷する際は、ヘッダーやフッターにURLや印刷日時が記録されるように設定すると、より証拠価値が高まります。
【ステップ3】投稿者の情報を記録する
誹謗中傷を行っている投稿者に関する情報も、できる限り記録しておきましょう。後の投稿者特定手続きの手がかりとなる可能性があります。
- アカウント情報
ユーザー名、アカウントID、プロフィールページのURLなどをスクリーンショットやテキストで保存します。 - 過去の投稿
他にどのような投稿をしているかを確認し、いくつか保存しておくと、投稿者の人物像や悪質性を判断する材料になることがあります。
【ステップ4】一人で抱え込まず、相談窓口に連絡する
証拠を確保したら、一人で問題を抱え込まずに、専門の相談窓口に連絡しましょう。客観的なアドバイスをもらうことで、冷静さを取り戻し、次に取るべき行動が明確になります。相談窓口には、無料で利用できる公的機関と、具体的な法的手続きを依頼できる弁護士があります。
無料で相談できる公的機関・団体
- 違法・有害情報相談センター
総務省の支援を受けて運営されている相談窓口です。ネット上の違法・有害情報に対し、どのように対応すればよいかアドバイスをもらえたり、サイト管理者への削除依頼の方法を教えてもらえたりします。相談内容によっては、センターからサイト管理者等へ削除を促す通知を行ってくれる場合もあります。 - 誹謗中傷ホットライン
セーファーインターネット協会(SIA)が運営する窓口です。インターネット上の誹謗中傷投稿について、国内外のプロバイダ等に利用規約に沿った削除等の対応を促す通知を行っています。 - 法務局(みんなの人権110番)
全国の法務局・地方法務局に設置されている人権相談窓口です。名誉毀損やプライバシー侵害といった人権侵害について、相談員が話を聞き、解決に向けたアドバイスをしてくれます。事案によっては、法務局がサイト管理者に対して削除要請を行うこともあります。 - 警察相談専用電話(#9110)
脅迫やストーカー行為など、犯罪の可能性がある場合は警察に相談します。「#9110」に電話すると、各都道府県警察の相談窓口につながり、状況に応じたアドバイスや、被害届の提出方法について教えてもらえます。
具体的な解決を依頼できる専門家
- 弁護士
上記のような公的機関は、あくまでアドバイスや削除の「要請」が中心であり、あなたの代理人として法的手続きを行うことはできません。サイト管理者が削除に応じない場合や、投稿者を特定して損害賠償を請求したい場合など、強制力のある法的な措置によって問題を解決したい場合は、弁護士への相談が唯一の選択肢となります。
弁護士に相談するメリット
誹謗中傷の被害に遭った際、弁護士に相談・依頼することには、他の相談窓口にはない以下のような大きなメリットがあります。
- 解決までの対応
弁護士は、被害者の代理人として、証拠保全のアドバイスから、サイト管理者への削除請求、裁判所を通じた発信者情報開示請求、特定した加害者との示談交渉や損害賠償請求訴訟、さらには刑事告訴まで、問題解決に必要なあらゆる法的措置を一貫して行うことができます。 - 被害状況に応じた最適な戦略の提案
「とにかく早く消したい」「損害賠償を求めたい」「二度と書かせないようにしたい」など、被害者の希望は様々です。弁護士は、被害内容や証拠の状況、被害者の希望を総合的に判断し、最も効果的でリスクの少ない解決策を提案します。 - 迅速かつ的確な手続きの実行
ネット誹謗中傷との闘いは、証拠(ログ)の保存期間や時効など、時間との勝負になる側面があります。法律と実務に精通した弁護士に依頼することで、複雑な手続きを迅速かつ的確に進め、「手遅れ」になる事態を防ぎます。 - 精神的負担の軽減
サイト管理者や加害者と直接やり取りをすることは、精神的に大きな負担となります。弁護士が代理人として全ての交渉の窓口となることで、被害者は加害者と直接対峙する必要がなくなり、精神的なストレスから解放され、安心して日常生活を取り戻すことに専念できます。
まとめ
ネット上で誹謗中傷の被害に遭ってしまったら、動揺する中でも、まずは「①冷静になる(反応しない)」「②証拠を保全する」という2つの鉄則を思い出してください。特に、URLを含む画面全体のスクリーンショットなどの証拠を確保することは、その後のあらゆる可能性をつなぎとめるための生命線です。
そして、証拠を確保した後は、決して一人で抱え込まないでください。公的な相談窓口は無料で有益なアドバイスを提供してくれますが、投稿の削除や損害賠償請求といった具体的な解決を望むのであれば、法律の専門家である弁護士に相談することが不可欠です。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷問題に力を入れており、豊富な経験と実績がございます。初動対応の方法から、具体的な法的措置まで最善の解決を目指してサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
長瀬総合の情報管理専門サイト
情報に関するトラブルは、方針決定や手続の選択に複雑かつ高度な専門性が要求されるだけでなく、迅速性が求められます。誹謗中傷対応に傾注する弁護士が、個人・事業者の皆様をサポートし、適切な問題の解決、心理的負担の軽減、事業の発展を支えます。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
当事務所は多数の誹謗中傷の案件を担当しており、 豊富なノウハウと経験をもとに、企業の皆様に対して、継続的な誹謗中傷対策を提供しており、数多くの企業の顧問をしております。
企業の実情に応じて適宜顧問プランを調整することも可能ですので、お気軽にご連絡ください。