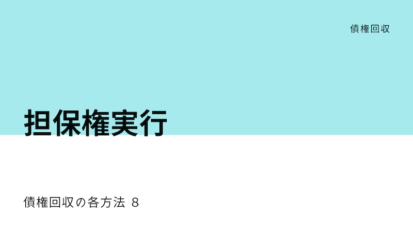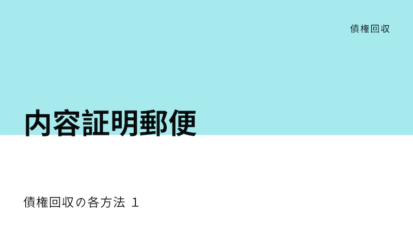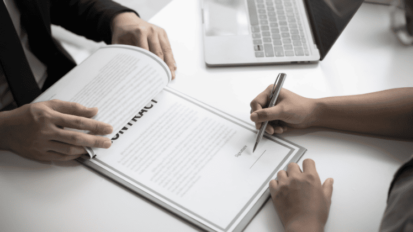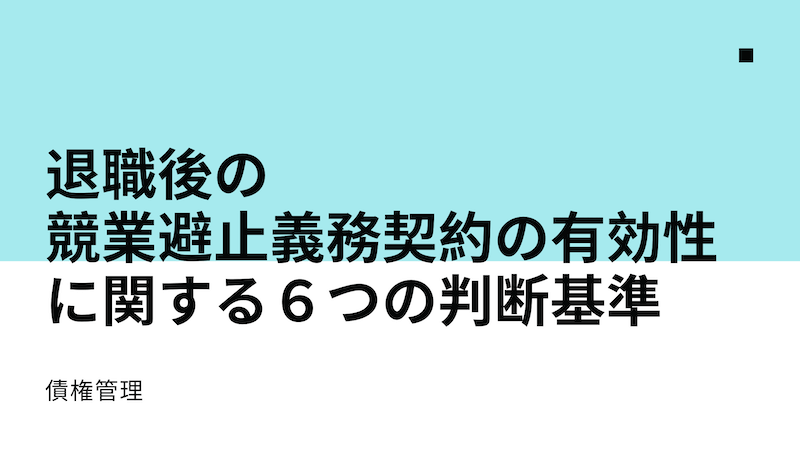はじめに
企業間取引で発生した債権(売掛金など)には、法律上の消滅時効という制度があり、一定期間(通常は5年)が経過すると回収する権利(債権)の行使ができなくなる恐れがあります。近年の民法改正で時効ルールが変更され(2020年4月施行)、企業法務担当者にとっては新しいルールに対応した時効管理が不可欠となりました。
一度時効が完成してしまうと、相手方が「時効援用」を主張した場合、債権を回収できないリスクが高くなります。そこで、時効更新(時効中断)の手段を適切に使い、時効期間が満了しそうになる前に必要なアクションを起こすことが重要です。本記事では、時効制度の基本や、時効管理と時効更新の手段について、解説します。債権を確実に回収するために、どのように時効をコントロールすべきか、そのポイントを学びましょう。
Q&A
Q1:時効の期間は何年ですか?
2020年4月の民法改正後、原則として債権の消滅時効は「債権者が権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できるときから10年間」のいずれか早い方が完成時効とされます(通称「5年・10年ルール」)。加えて、商事債権なども改正で一律5年に統一されるなど変化がありました。
Q2:時効期間が近づいたらどうやって更新すればよいのですか?
時効更新(以前の用語でいう時効中断)の手段として、
- 請求(裁判上の請求、支払督促など)
- 差押え・仮差押え・仮処分
- 債務の承認(相手が支払いを約束する念書など)
が代表的です。特に「裁判上の請求」は訴訟や支払督促手続きなど法的手続きを行うことにより、時効が中断(更新)され、新たに時効期間が再スタートします。相手が「確かに支払い義務がある」と認める「債務承認」も有力な手段です。
Q3:支払い督促などを使わず、単に請求書を送るだけでは時効を中断できないのですか?
単なる「内容証明郵便による請求書送付」などは、時効更新の効果を持ちません。したがって、裁判外の請求(内容証明郵便)だけでは時効は完成してしまうので、支払督促や裁判手続きなどの正式な手段を使う必要があります。
Q4:時効が完成してしまったら、もう回収は不可能ですか?
相手が時効を援用(主張)すると、法的には債権が消滅した扱いとなり、原則として回収が困難になります。ただし、相手が時効を援用せずに支払った場合、支払いを取り戻すことはできない(弁済として有効)という規定もあるので、現実問題としては相手が時効援用しないケースに期待するか、時効完成前にきちんと行動を起こすのが賢明です。
解説
改正民法による時効制度のポイント
- 5年または10年ルール
- 改正民法で「人が権利を行使できることを知った時から5年」「行使できる時から10年」のいずれか早い方で消滅時効が完成。ただし、商事債権や職業別の短期消滅時効は廃止され、一律5年の期間が基本化された。
- 裁判外の請求による完成猶予
- 請求はあくまでも時効の完成の猶予にとどまる。
- 時効を更新するには裁判上の請求や強制執行、債務者の承認などの正式な手段を使わなければならない。
- 債務承認による更新
- 債務者が支払いを一部でも行ったり、分割払い契約を新たに結んだり、「この請求は確かに存在する」と認める行為が債務承認となり、時効は更新される。
- ただし、一部支払いが必ずしも承認と認定されるかは具体的状況次第であり、契約書や念書など文書化しておくと確実。
時効管理の実務フロー
- 発生日・請求起算点の把握
- 売掛金などは商品を納品し、支払い期日が到来した日が請求権行使可能日となることが多い。
- 取引先ごとにシステムで発生日を登録し、そこから5年(または10年)の満了日を自動計算できるようにする。
- モニタリングとアラート
- 毎月や四半期ごとに、時効まで残り○か月の債権がないかチェックし、該当すれば担当者にアラートを送る。
- 営業と連携し、未回収のまま放置されていないかヒアリングを行い、相手方との交渉や法的手段に移る意思決定を促す。
- 時効更新手段の検討
- 満了日が近い場合、支払督促を申し立てたり、訴訟提起して時効更新を図る。あるいは相手との交渉で分割払い合意書(債務承認)を締結し、更新する。
- 試算して相手の支払い能力が低い場合は担保を取得する交渉も視野に。
- 法的回収措置
- 更新手段を講じても相手が応じない場合、本訴訟や支払督促、仮差押えなど強硬手段へ進み、最終的に強制執行で差し押さえを実行。
- 難航しそうなら弁護士代理の下で適切な戦略を立案し、回収の最大化を目指す。
代表的な更新(中断)手段と注意点
- 裁判上の請求(訴訟・支払督促)
- 訴訟を起こして、裁判所に訴状を提出した時点で時効が更新される。
- 訴訟取り下げや敗訴、却下となった場合は中断の効力が失われる可能性がある。
- 差押え・仮差押え・仮処分
- 保全手続きも時効更新の効果を生じる。
- ただし、手続きを取り下げたり保全が取り消された場合は中断効が失効する恐れがあり、手続き完了まで慎重に進める必要がある。
- 債務承認
- 相手方が「債務がある」ことを明確に認める行為。例えば一部でも支払いを受けたり、「支払い待ってほしい」と文書によりお願いされた場合も承認となりうる。
- ただし、立証が必要なので、承認の事実を客観的に示す書類(メール、契約書、念書など)を残すことが重要。
よくあるトラブル事例
- 内容証明で請求書を送ったが時効が更新されず
- 旧法の感覚で「内容証明郵便の請求書を送れば時効が中断する」と思いこんでいた企業が、更新されておらず、相手が時効完成を援用して回収不能に。
- 対策:内容証明郵便だけでは更新されないことを認識し、支払督促や訴訟など法的手続きを活用する。
- 一部受領を承認と認めてもらえない
- 相手が一部だけ支払ったため時効更新を主張するも、「これは別件の費用返金であり、本件債権には承認していない」と争われ、認められなかった。
- 対策:支払いが本件債権に対するものであることを文書化し、債務承認書や受領証を交わす。
- 訴訟取り下げで更新効消滅
- 時効直前に訴訟を提起したが、和解交渉がうまくいかず、いったん取下げを行ったところ時効更新効果が失効し、結果的に時効完成を許す結果に。
- 対策:訴訟取下げ前に必ず債務承認や再訴に備えた手続きを確保する。または和解成立まで取下げを保留。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、時効管理と時効更新に関して以下のようなサポートを提供しています。
- 債権管理体制の構築
- 企業内で発生ベースで売掛金や請求書を管理し、時効5年(または10年)に向けた定期的なモニタリングやアラートシステムの導入を助言。
- 取引先の決済状況を踏まえ、時効間近の案件に対して弁護士が早期介入し、未回収を防ぐスキームを提案。
- 裁判手続き・督促代理
- 時効完成前に支払督促や少額訴訟、通常訴訟などの法的手段を迅速に進める代理人業務。
- 仮差押えや差押えにより相手の財産を確保し、時効更新と同時に回収を一気に図ることも可能。
- 債務承認を確実にする契約書整備
- 分割払いの合意書や再契約を作成する際、「これは本件債務に対する承認である」といった文言を入れ、時効更新の効果を確実に得られる文案を作成。
- 口頭承認だけでなく、客観的証拠を残す方法をアドバイス。
まとめ
- 時効管理は企業の債権(売掛金など)を確実に回収するために必須のプロセスであり、民法改正(2020年4月)で大きくルールが変わった。
- 5年または10年の時効期間を見越して、会計システムやエクセル管理などで満了日を把握し、期日が近づいたら支払督促や訴訟を行う準備をする。
- 分割払い合意や一部入金でも、確実に債務承認を証拠化できれば時効更新が成立する。
- 弁護士と連携し、法的手段や保全処分を適切に選ぶことで、時効完成前に回収を図ったり、相手から債務承認を得る戦略をとり、未払を防ぐことができる。
長瀬総合の債権回収専門サイト
企業活動において債権・売掛金・請負代金等を回収できないというのは、企業活動に支障を来しかねません。
私たちは、経営者・企業の皆様が債権回収でお悩みになることを解消するとともに、持続的な成長の一助となることをお約束いたします。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス