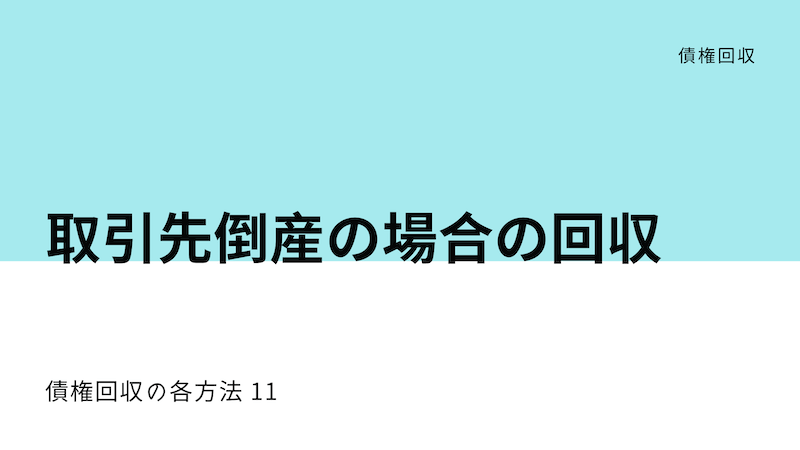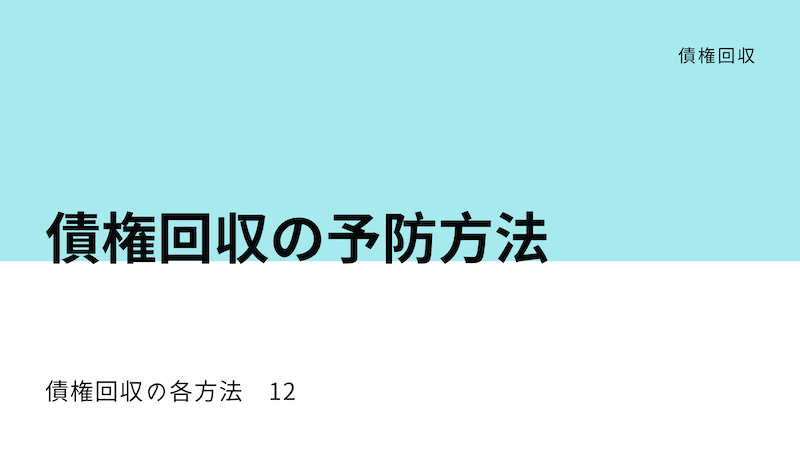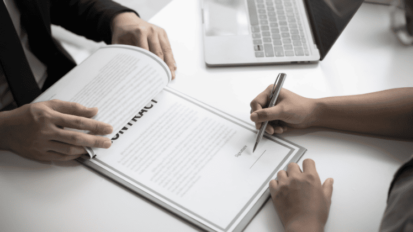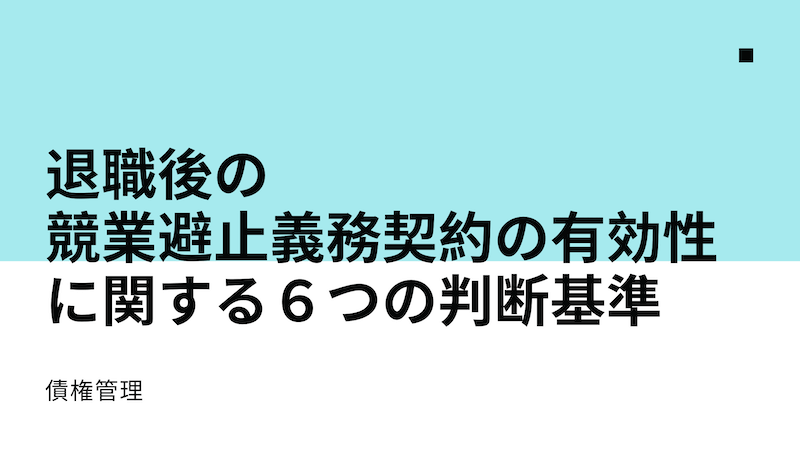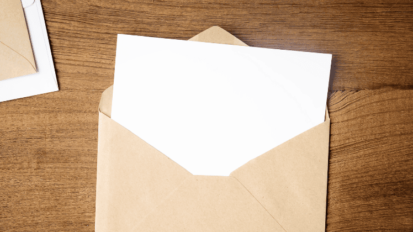はじめに
企業間取引や事故・損害賠償などの紛争が起きたとき、全てのケースを訴訟で解決するのは時間・コストの面で大きな負担となります。そこで、裁判外で示談・和解を行い、円満に解決を図る方法が広く活用されています。示談や和解では、当事者が話し合いにより互いに合意点を見つけ、契約書(示談書・和解書)を交わして紛争を終結させるのが一般的です。
一方で、示談交渉が不適切に進められると、合意内容が曖昧だったり、後から相手方が合意を覆すなどトラブルになることもあります。弁護士の助言を活用し、示談書や和解契約書を確実に作成することが重要です。本記事では、示談・和解交渉の進め方と、合意書の作成ポイント、実務上の注意点を解説します。紛争を最小限のコスト・時間で解決するためのポイントを整理しましょう。
Q&A
Q1:示談・和解とは何が違うのでしょうか?
一般的に「示談」と「和解」は類似の概念とみなされますが、厳密には次の違いがあります。
- 示談
紛争当事者が裁判外で話し合い、お互いの主張を譲り合いながら合意すること。交通事故の示談などが代表例。 - 和解
民法では「当事者が互いに譲歩し、紛争を終わらせる契約」と定義されます。示談とほぼ同義で使われることが多いですが、訴訟中に和解を成立させる「裁判上の和解」など、法的手続きにおける意味合いも含みます。
実務上は、どちらも「争いを終結させる合意」だと捉えて構いません。
Q2:示談・和解交渉のメリットは何でしょうか?
- 時間・費用の節約
裁判で長引くよりも早期解決が見込め、弁護士費用や手間を抑えられる。 - 非公開で進められる
裁判は原則公開だが、示談交渉は非公開で行われ、合意内容を外部に知られずに済む。 - 柔軟な合意
金銭問題だけでなく、将来の取引継続や謝罪文など、多岐にわたる条項を自由に設定できる。 - 当事者の納得
話し合いで合意するため、裁判の判決より当事者が納得しやすい面がある。
Q3:示談・和解交渉を行う際、どんな点に注意すべきですか?
代表的には以下の点が重要です。
- 事実関係と法的論点の整理
自社が主張したいポイントや証拠を明確にし、相手の主張と突き合わせて検討。 - 合意条件の具体性
金銭の金額や支払い方法、期限、違反時の対応などを曖昧にしない。 - 全ての争点を包含
後から「別の請求が残っていた」等が出ないよう、示談書・和解書で包括的に解決する。 - 内容証明や公正証書
合意ができたら文書化し、必要に応じて公正証書化(執行認諾文言付き)して強制執行を容易にする。
Q4:示談書を結んだ後、相手が合意を破った場合はどうなりますか?
通常の契約違反と同様に、損害賠償請求や強制執行に進むことが可能です。示談書に違約金条項や公正証書(執行認諾文言付き)を加えておくと、相手が支払わない場合に裁判手続きなしで差し押さえに進める利点があります。合意違反が発生したとき、示談書は「法的有効な契約」として強い証拠能力を持つため、裁判上の主張や執行がスムーズになります。
解説
示談・和解の流れ
- 当事者間の争点整理
- 問題となっている事実(代金未払い・損害賠償請求・取引契約違反など)や両者の主張をまとめる。証拠書類(契約書、請求書、メールなど)を集約し、論点を把握。
- 交渉開始
- まずは書簡・メール・電話などで相手方と接触し、代理人(弁護士)を立てるか検討。
- お互いの言い分が平行線をたどるなら、第三者(弁護士など)の調整やADR(裁判外紛争解決手続)の利用を検討する。
- 提案と譲歩
- 債権者側は「○○円を○日までに支払う」を要求し、債務者側は「分割払い」「減額」などの主張を行う。両者が落としどころを探る。
- 相手の要求が不当であれば根拠を示して反論し、譲れる範囲と譲れない範囲を明確に。自社の経営戦略やリスク許容度に基づき決定。
- 合意形成
- 金額や支払期日、条件(利息・遅延損害金・分割条件など)がまとまったら最終文書(示談書・和解書)を作成。
- 将来の係争防止のため、「本件に関し、本書が最終の合意であり、これ以外の請求をしない」といった清算条項を入れる。
- 合意の履行
- 合意後、相手が約束通りに支払う、または業務を実行することで紛争解決完了。
- もし履行されない場合、示談書を根拠に損害賠償や強制執行などを検討する。
示談書・和解書の作成ポイント
- 当事者の特定
- 会社名、代表者名、住所、法人番号などを正確に記載し、誰と誰が合意しているかを明確に。
- 事案の経緯と目的
- どんな紛争なのか、経緯や事実関係を簡潔に記載(例:A社はB社に商品を納入したが代金が支払われない、など)。
- 「本書は本件紛争を終局的に解決するための合意である」旨を明示して、紛争の終結を明確化。
- 合意内容(金銭条件・行為条件)
- 支払うべき金額・支払期日・分割払い詳細・遅延損害金の計算方法など具体的に定める。
- 金銭以外の引渡しやサービス提供義務がある場合は、その期限や範囲も明記。
- 清算条項(包括的解決)
- 「本件に関し、当事者は本書記載の内容以外に相互に一切の請求をしない」旨を挿入し、後から追加請求されるリスクを防ぐ。
- 複数の紛争要素がある場合は、すべてを一括して解決する条項を作る。
- 違反時の措置・執行方法
- 履行されない場合の違約金や損害賠償、公正証書(執行認諾文言付き)にするかどうかを検討。
- 強制執行を容易にするため、合意書を公正証書化する選択肢もある(相手の同意が必要)。
- 日付・署名押印
- 作成日と署名押印を行い、各当事者が同じ内容の原本を1通ずつ保持する。電子署名を使う場合は適切な電子契約サービスを利用し、改ざん防止を図る。
実務上の留意点
- 代理人選定
- 感情的対立が激しい場合や法律関係が複雑な場合、弁護士を代理人に立てると円滑に交渉が進みやすい。
- 企業内部の担当者だけでは経験不足で相手に押し切られる可能性がある。
- 情報開示と守秘義務
- 示談交渉には事実関係や財務情報の開示が伴う場合がある。互いに必要最小限の情報を出し合い、守秘義務を設定することも検討する。
- 特に企業のノウハウや顧客リストなど、秘密情報が絡むときはNDAを締結するか、示談書に守秘条項を挿入する。
- 期限管理とモニタリング
- 分割払い合意などの場合、入金期限をモニタリングし、遅延があれば即座に対応する。
- 長期的な履行義務がある場合、追加で契約書や念書を用意してコンプライアンス監査や定期報告を設けることもある。
- 感情的対立への対応
- 示談・和解は法律論だけでなく、心理的要素が大きい。相手の立場やメンツを考慮し、譲歩案を提示するなど人間関係面も配慮する。
- 話が平行線となる場合は、第三者調停や仲裁を利用し、冷静な場を設ける選択肢も有効。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、示談・和解交渉において以下のサポートを提供しています。
- 法的観点からの交渉代理
- 紛争の事実関係や契約書を分析し、依頼企業の立場を最適に主張しながら示談を進める。
- 相手方とダイレクトにやり取りすると感情的対立が悪化するケースでも、弁護士を通じて冷静な交渉を行い、合意形成が加速する。
- 示談書・和解書の作成
- 必要事項(支払い金額、期限、清算条項など)を漏れなくカバーし、後日の紛争が再燃しないよう詳細な契約文言を起案。
- 公正証書化が望ましい場合は、公証役場の手続きも含めて支援し、強制執行の可能性を高める。
- 損害額算定と交渉戦略立案
- 交通事故や業務上の損害賠償などで損害額の算定が複雑な場合、判例や業界基準を踏まえて根拠づけを行い、企業の損失をカバーするための請求金額を設定。
- 逆に相手から不当な高額請求が来た場合は、反論や過失相殺を主張し、妥当な金額まで圧縮する戦略を立てる。
- 合意不成立時の訴訟対応
- 示談・和解が不調に終わった場合、裁判へ移行する可能性があるが、その際も弁護士が一貫して事案を把握しているため、スムーズに移行できる。
- 必要に応じて仮差押えや強制執行を提案し、債権確保のための次の手を即座に打つ。
まとめ
- 示談・和解交渉は、紛争を裁判外で円満に解決するための有力な手段であり、合意内容をきちんと文書化(示談書・和解書)し、清算条項や違約金条項を含めることで、再燃リスクを防げる。
- 交渉は法律論だけでなく、相手との人間関係や心理的要素も大きい。感情的対立を避けるためには、弁護士代理を活用し、冷静な話し合いを進めるのが得策。
- 遅延損害金や分割払い、将来取引の継続など、柔軟な条件設定が可能な点が裁判との大きな違い。
- 弁護士と連携すれば、合意後に公正証書を作成し、履行が得られなかった場合の強制執行まで視野に入れた手続きを整えられ、より回収可能性を高めることができる。
長瀬総合の債権回収専門サイト
企業活動において債権・売掛金・請負代金等を回収できないというのは、企業活動に支障を来しかねません。
私たちは、経営者・企業の皆様が債権回収でお悩みになることを解消するとともに、持続的な成長の一助となることをお約束いたします。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス