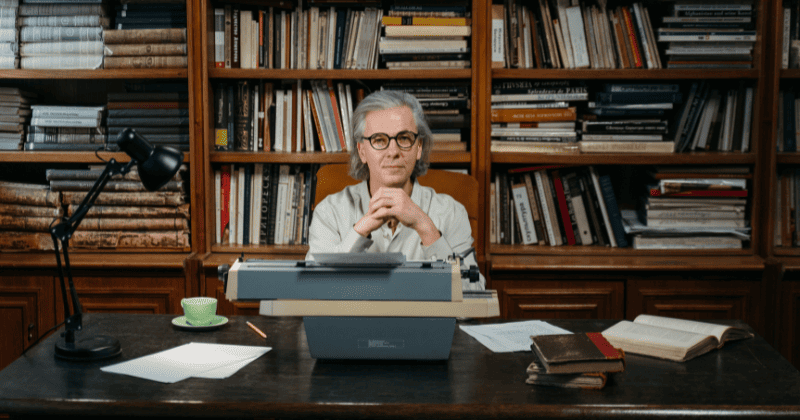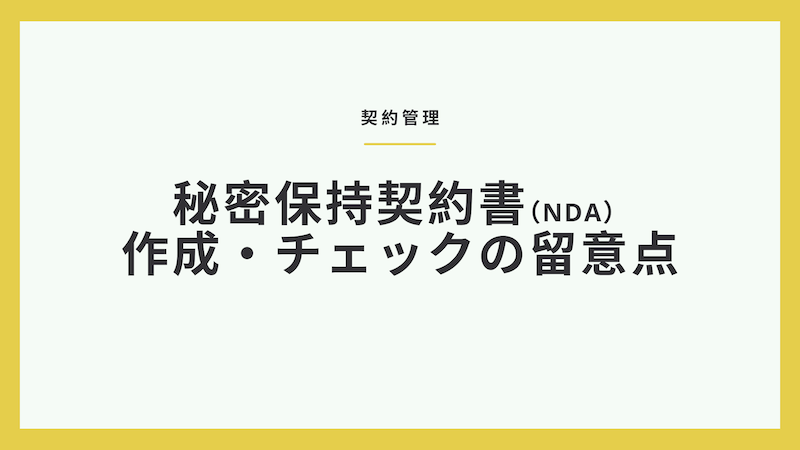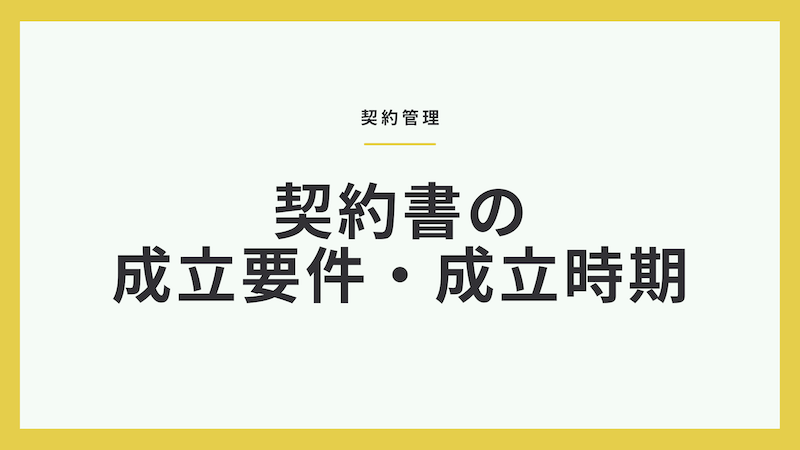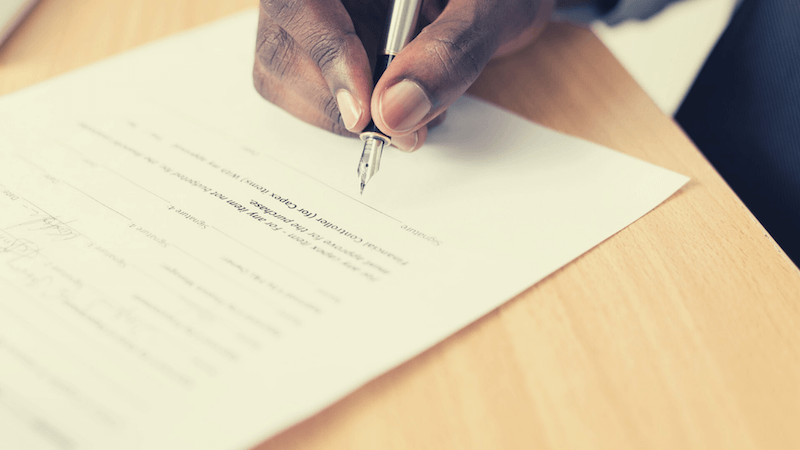はじめに
ライセンス契約(使用許諾契約)は、著作権や特許、商標、ノウハウなど知的財産を他社に使用させる際に結ばれる契約です。ソフトウェア、キャラクター、商標、技術特許など、対象が多岐にわたり、ロイヤリティの計算方法や契約範囲の設定を誤ると、金銭面・権利面で大きな紛争に発展するリスクがあります。
また、使用許諾契約では、ライセンサー(許諾者)とライセンシー(被許諾者)の間で権利の範囲、ロイヤリティ計算式、サブライセンスの有無などを具体的に定めないと、後日「勝手に第三者へ転貸した」「売上報告が不正」などのトラブルが頻発します。本記事では、ライセンス契約・使用許諾契約のチェックポイントを整理し、契約交渉と紛争防止の実践的な留意点を解説します。
Q&A
Q1:ライセンス契約と使用許諾契約は同じ意味ですか?
一般的に同義として扱われることが多いです。ライセンスという用語は主に特許や商標など工業所有権分野で用いられ、使用許諾は著作権などで使われることが多いですが、実質的には「権利所有者が他者に対し、特定の範囲で権利を使用させる契約」であり、名称の違いはあまり大きな意味を持ちません。
Q2:ライセンス契約書で入れておくべき項目は何でしょうか?
下記のような項目が代表的です。
- ライセンス対象(特許番号、商標登録番号、著作物特定など)
- 許諾範囲(地域、用途、期間、排他性、サブライセンスの可否)
- ロイヤリティ設定(定額、売上高に応じたロイヤリティ率、最小保証額など)
- 契約期間・更新・終了条項
- 権利侵害対応(侵害発見時にどちらが対応費用を負担するか)
- 秘密保持や競合他社への許諾制限
- 準拠法・管轄
これらを明確にしておくことでトラブルを回避しやすくなります。
Q3:ロイヤリティはどのように算定するのが一般的でしょうか?
定額方式や売上高の○%方式、ライセンス対象ごとの課金方式など多様な形があります。最初にイニシャルフィーを受け取り、その後は売上高に応じてロイヤリティを課す方法も多いです。また、ミニマムギャランティ(最低保証額)を設定して、被許諾者の販売努力を促す例も多く見られます。業種や契約目的に合わせて、検証可能な算定根拠を具体的に決めておくことが重要です。
Q4:ライセンス契約の使用範囲を超えた行為があったらどう対処すべき?
使用範囲を超えて無断で二次利用や再許諾が行われた場合は契約違反となり、差止請求や損害賠償請求が可能です。契約書で「使用範囲外の行為が発覚した場合は直ちに停止させるとともに、○○の違約金を支払う」など明記すると、実効性のある抑止力になります。さらに、違反行為が著しい場合は契約解除も検討します。契約時にしっかりと違反時の措置を定めておくことが必要です。
解説
ライセンス契約・使用許諾契約の主要条項
- 対象物の特定
- 特許番号、著作物のタイトルや登録番号、商標登録番号などを明示し、何をライセンスするのかを具体的に特定。曖昧な記載だと範囲をめぐる争いが起きやすい。
- 必要に応じて付属資料(図面、サンプル)を契約書に添付しておく。
- 許諾範囲・用途
- 「許諾権利は○○のためにのみ使用できる」「地域は日本国内限定」「複製・翻案・改変は認める/認めない」など、地理的範囲や用途、改変の可否を細かく設定。
- 排他的ライセンスか非排他的ライセンスかも明記。非排他の場合はライセンサーが第三者にも同様の許諾を行うことが可能。
- 独占・排他条項
- 独占的使用許諾を与える場合は、ライセンサー自身も利用できないのか、または自己利用は認めるのかを検討。
- 競合他社へのライセンスを禁止する「排他性」が強い条項は、独禁法に抵触するリスクも考慮する必要がある(特に市場支配力がある場合)。
- ロイヤリティ・報酬
- 定額方式(年間○万円)か、売上に対する○%のロイヤリティかを選択。合わせて支払い期日(四半期ごと、年1回など)や報告義務を定める。
- 売上報告の監査権をライセンサーが有するかどうかも明確化し、万が一報告が虚偽だった場合の違約金や契約解除事由を定めることが多い。
- サブライセンス(再許諾)の可否
- 被許諾者が第三者に再許諾できるかどうかを定める。サブライセンス可の場合、さらにロイヤリティがどう分配されるかなどの細則が必要。
- サブライセンス禁止の場合でも、具体的な例外を設けるかどうかを検討すると紛争予防につながる。
- 契約期間・解除事由
- 有効期間を明記し、更新の有無や再契約のプロセスを示す。契約違反(ロイヤリティ不払い、範囲外使用など)や破産・廃業などの場合に即時解除できる条項も必須。
- 効果的には「是正勧告後○日以内に改善がなければ解除可能」など催告手順を定める。
- 侵害対応・訴訟費用負担
- ライセンス対象が第三者に侵害された場合、誰が責任を持って対応(警告、差止訴訟)するのか、費用はどう分担するのかを決める。
- もしライセンス対象の権利自体が第三者から侵害を主張されたら、ライセンサーが防御するのか、ライセンシーも協力するのかなど、具体的な規定を設けると安心。
- 秘密保持・競合避止
- ライセンス契約に付随して、相手方にノウハウやソースコードなどの秘密情報を開示する場合は、別途NDAを締結するか、本契約内で秘密保持条項を設ける。
- 競合製品とのライセンスを禁止するなど、競業避止を盛り込むこともあるが、独禁法に触れないよう注意が必要。
- 保証・免責条項
- ライセンサーがライセンス対象の権利を正当に保有していること、第三者権利を侵害していないこと等を保証する。
- ただし、特定の範囲外では責任を負わない「免責条項」を設定するなど、バランスを考慮する。
- 準拠法・管轄
国内取引の場合は日本法を準拠法に、東京地裁などを専属管轄とするのが通例。国際取引では仲裁機関(ICCなど)を指定することも多い。
運用上の留意点
- 権利証拠・登記情報の確認
- 特許や商標ライセンスの場合、ライセンサーが本当に権利を持っているか特許公報や商標登録証を確認する。
- 著作権ライセンスであれば、著作物が本人のオリジナルである証明や、共同著作の場合の権利帰属などを慎重にチェックする。
- ロイヤリティ報告の監査
- 売上連動のロイヤリティ方式では、不正な売上計上や報告漏れが起きないよう、ライセンシーに対して売上報告を義務付け、その監査権限を契約書で確保する。
- 必要に応じて公認会計士など外部専門家による監査権を認める条項を入れることで、万一の不正を抑止。
- 契約更新時の再交渉
- 契約期間が満了近くなると、ロイヤリティ率や使用範囲の再交渉を行うことが多い。元契約の更新条項が曖昧だと自動更新になったり、終了か延長かでトラブルになる。
- 更新条件をあらかじめ定め(業績目標達成時に更新、ロイヤリティ率を段階的に改定など)、合理的に運用するとスムーズに再契約を結べる。
- 違反・解除後の対応
- 使用許諾を解除してもライセンシーが製品にロゴや技術を使い続ける恐れがある。契約書で撤去義務や在庫処分の扱いを定めておく。
- システム開発ライセンスなどはソースコードの返却義務や利用停止措置をどう行うか、詳細なルール設定が必要。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、ライセンス契約・使用許諾契約に関して以下のサポートを提供しています。
- 契約書作成・レビュー
特許や著作権、商標などのライセンス契約草案を法的観点で精査し、リスク条項(ロイヤリティ算定、サブライセンス可否、競合避止)を最適化。 - 権利調査・侵害対応
- ライセンス契約の対象となる知的財産が本当にライセンサーの権利か、第三者が先行権利を持たないかなど調査をアドバイス。
- 侵害が発生した際、差止請求や損害賠償請求の手続き、警告書の作成などを企業代理人として対応。
- 紛争処理・交渉代理
- ロイヤリティの支払いトラブルや許諾範囲外使用の紛争で、企業側代理人として交渉・調停・仲裁・訴訟をサポート。
- 調査で得た証拠を整理し、企業の正当性を主張し早期解決を図る戦略を立案。
- 契約管理とセミナー教育
- ライセンス契約が多数ある企業に対して、契約管理システムの導入支援や、担当者向けの研修・セミナーを提供。
- 最新の著作権法、その他法改正情報を共有し、継続的な契約書アップデートと社内コンプライアンス向上を図る。
まとめ
- ライセンス契約・使用許諾契約では、対象となる知的財産権や使用範囲、ロイヤリティ設定、違反時の対応など多くのポイントを明確化しないと、ロイヤリティ不払いや権利の逸脱使用などの紛争が生じやすい。
- 契約書の定義や条項(サブライセンス可否、排他性、期限、解除要件)をきちんと設計し、相手方との交渉で落としどころを探ることが大切。
- 知的財産の保護を万全にするため、契約締結前にライセンサーが権利を正当に保有しているか、侵害のリスクはないかなどの法的調査も重要。
- 弁護士のアドバイスを受け、紛争リスクを最小限に抑えながらライセンス契約を結び、企業の収益機会を最大化できるように制度設計を行うと良い。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス