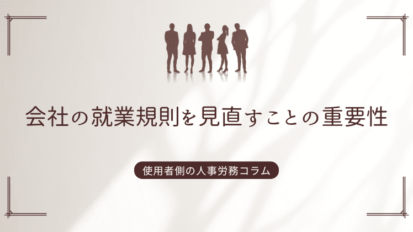はじめに
2016年から本格運用が始まったマイナンバー制度は、雇用保険や健康保険、厚生年金などの社会保険手続きを簡略化し、行政手続きの効率化を目指すものです。しかし、その一方で、個人番号(マイナンバー)は高いレベルの個人情報保護が要求され、企業には厳格な管理体制が求められます。
本記事では、マイナンバーを扱う際の実務フローや雇用保険・社会保険の手続き上の注意点、漏えいリスク対策などを、弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。企業がコンプライアンスを守りながら、マイナンバーのメリットを活用するためのポイントをご紹介します。
Q&A
Q1:なぜ雇用保険や社会保険の手続きにマイナンバーを使う必要があるのですか?
行政手続きを迅速化・効率化し、本人確認の精度を高めるためです。雇用保険や健康保険、年金手続きの申請書類には従来、多くの個人情報や確認書類が必要でしたが、マイナンバー導入により事務負担が軽減されるメリットがあります。一方、企業側には適正な取得・保管・廃棄の責任が課されます。
Q2:企業がマイナンバーを収集するのはいつ、どのように行えばいいのでしょうか?
従業員が雇用保険や社会保険の被保険者となる際、または扶養家族の社会保険手続きなど必要な場面で収集します。原則として必要最小限のタイミングで取得し、不要になったら速やかに削除・廃棄することが望ましいです。就業規則やマイナンバー管理規程で運用ルールを定め、本人確認(身分証明書など)も同時に行います。
Q3:マイナンバーを保管するとき、具体的にどのようなセキュリティが必要ですか?
マイナンバー法に基づき、企業は安全管理措置を講じる義務があります。たとえば、
- 紙媒体の場合:施錠できるキャビネットや専用保管庫で管理し、アクセス権限を限定する。
- 電子データの場合:暗号化やパスワード保護、アクセスログの記録などを実施。
- 取扱担当者の限定と研修。
漏えいが発生すると高額な罰金や社会的信用の損失につながる恐れがあるため、徹底した管理が必要です。
Q4:マイナンバーを使った手続きが終わったら、すぐに番号を廃棄する必要がありますか?
その手続き(雇用保険・社会保険)のためにマイナンバーを利用する必要がなくなったら、速やかに廃棄(または削除)するのが原則です。ただし、再利用が想定されるタイミング(例えば年末調整や続く保険手続きなど)がすでに近い場合は、必要性が継続していると判断できれば保管を続けられます。
いずれにせよ、保管期間や保管方法を社内で規程化し、運用上も厳格に管理しないとコンプライアンスリスクが高まります。
解説
マイナンバー管理体制の重要性
- 法令遵守とリスク回避
- マイナンバー法や個人情報保護法に違反すると、企業には刑事罰や行政処分、企業イメージ毀損など重大な影響が及ぶ。
- 特に漏えいが発覚した場合、メディア報道や顧客・従業員からの不信感で長期的なダメージを受けるリスクがあるため、万全な管理体制が必須。
- 業務効率化とメリット
- 正しく運用すれば、雇用保険・社会保険・源泉徴収などの行政手続きがスムーズになり、書類の簡略化や事務コスト削減が期待できる。
- ただし、メリットを最大化するには、企業側で電子申請やシステム連携を導入し、担当者が運用フローを十分に把握しておくことが必要。
- 従業員への説明と信頼構築
- マイナンバーを収集する際には、その利用目的や保管期間、安全管理措置を説明し、従業員が安心して提供できる環境を整える。
- 学生アルバイトや外国人社員など、マイナンバー制度を十分に理解していない人も多いため、丁寧な周知とサポートが欠かせない。
雇用保険・社会保険手続きの実務
- 雇用保険手続き
- 新規に従業員を雇い入れた際、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出するが、このときマイナンバーを記載することが一般的。
- 資格喪失届や離職票作成、保険給付手続きなどでもマイナンバーを扱うため、企業は正確な番号を収集・保管し、必要に応じて本人確認(運転免許証・パスポート等)を行う。
- 社会保険手続き
- 健康保険・厚生年金保険への加入(被保険者資格取得届)や扶養家族の認定(被扶養者届)などでマイナンバーを記載するケースが増えている。
- 企業の保険担当者がマイナンバーを扱う際、利用目的を超えて保存したり、他の用途に転用すると法違反になる恐れがある。導線を整備し、不必要な閲覧を制限することが重要。
- 電子申請と電子証明書
- 雇用保険・社会保険の各種届出について、電子申請が可能になっており、オンラインで提出する場合でもマイナンバーを入力して送信する仕組みが存在する。
- 電子証明書による電子署名や暗号化通信が行われるため、セキュリティは比較的高いが、企業はシステム導入や担当者の研修をしっかり行わないと入力ミスや漏えいのリスクがある。
マイナンバーの保管・廃棄ルール
- 必要最小限の収集
- マイナンバー法では、企業がマイナンバーを取り扱う場面は、税・社会保険・雇用保険など法令で定める手続きに限られる。不要なコピーやデータを保管することは原則禁止。
- 従業員本人や被扶養者のマイナンバーを安易に集めないよう、収集時に本当に必要かチェックリストを作成すると良い。
- 安全管理措置
- 組織的安全管理措置:マイナンバー取扱担当者の限定、社内規程の整備、監査体制の構築。
- 人的安全管理措置:取扱担当者への研修や誓約書の取得。
- 物理的安全管理措置:施錠可能なキャビネット、入退室管理、書類のシュレッダー廃棄など。
- 技術的安全管理措置:パスワードや暗号化、アクセス制限、ログ監視などITセキュリティを強化。
- 保存期間と廃棄
- 雇用保険被保険者資格取得届などの手続きが完了し、法定の保存期間(原則2年)を過ぎたら、マイナンバーは速やかに廃棄。
- 紙文書ならシュレッダー、電子データなら復元不能な方法で削除し、廃棄証明書やログを記録すると管理が徹底できる。
トラブル事例
- マイナンバーの漏えい事故
- 企業の担当者がUSBメモリにマイナンバー入りのファイルを保存し、自宅作業中に紛失。結果的に個人情報漏えいとして大きく報道され、企業が謝罪会見や追加コスト負担を強いられた例。
- 対策:社外への持ち出しを禁止・制限し、どうしても持ち出す場合は暗号化や厳格な承認手続きを義務づける。
- マイナンバーを無断で二次利用
- マイナンバーを従業員の社内IDに使うなど、法定以外の目的に流用し、従業員が「個人情報の不正利用だ」と主張したケース。
- 対策:利用目的を限定し、就業規則や社内マニュアルで「給与計算や保険手続きなど法令で定められた範囲以外で使わない」旨を明確化し、運用を徹底する。
- 担当者が無用に複製
- 社会保険手続きのために集めたマイナンバーを担当者が私的利用のために別のUSBメモリに保存し、外部に持ち出した例。企業が管理できず、従業員の不安が高まり、内部告発された。
- 対策:アクセス権限管理やUSB差し込みの制限をかけるなど、技術的な対策を講じる。担当者教育を定期的に実施。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、マイナンバー管理および雇用保険・社会保険手続きに関する以下のサポートを行っています。
- マイナンバー管理規程の策定・見直し
- 企業の規模や業務内容をヒアリングし、取得・保管・利用・廃棄までの各フェーズにおける具体的ルールを定めたマイナンバー管理規程を作成・改定します。
- 過去の漏えい事例や社内のIT環境を考慮し、最適な安全管理措置を提案します。
- 雇用保険・社会保険手続きの法的チェック
- マイナンバーを使用する雇用保険・社会保険手続きにおける書類作成や電子申請フローが適法か点検し、未加入リスクや手続き漏れを防止するアドバイスを行います。
- 外国人社員やパートタイム・アルバイトなど特殊ケースでのマイナンバー活用においても、個人情報保護と労務管理の両面からコンサルティングを提供します。
- 漏えい事故対応・弁護士対応
- 万が一、マイナンバー漏えい事故が発生した場合の初動対応や社内調査のサポート、被害拡大を防ぐためのガイドラインを提示します。
- 行政機関への報告義務(個人情報保護委員会など)や従業員への説明・謝罪、再発防止策の策定までをワンストップでサポートします。
- 研修・教育プログラムの実施支援
- 企業のマイナンバー担当者や全従業員を対象にしたコンプライアンス研修や、個人情報保護に関する教育プログラムの企画・講師派遣も行います。
- 実務的な事例を交えた研修で理解を深め、従業員のセキュリティ意識を高めることができます。
まとめ
- マイナンバーは雇用保険・社会保険手続きの効率化に役立つ一方、企業は高いレベルの個人情報保護と安全管理措置を講じる義務を負う。
- 収集・保管・利用・廃棄の各段階で正しい手続きを踏まず、漏えいや不正利用が起きると、企業は行政処分や損害賠償を負うリスクが大きい。
- 労働法や社会保険法の観点でも、雇用保険・厚生年金・健康保険加入の適正手続きでマイナンバーが活躍するが、未加入や手続き漏れがないよう注意。
- 弁護士の助言を受け、マイナンバー管理規程や社内体制を整え、万が一の漏えい事故にも迅速に対応できるよう準備することが重要。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス