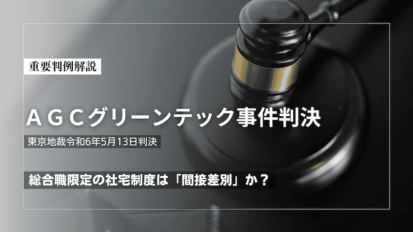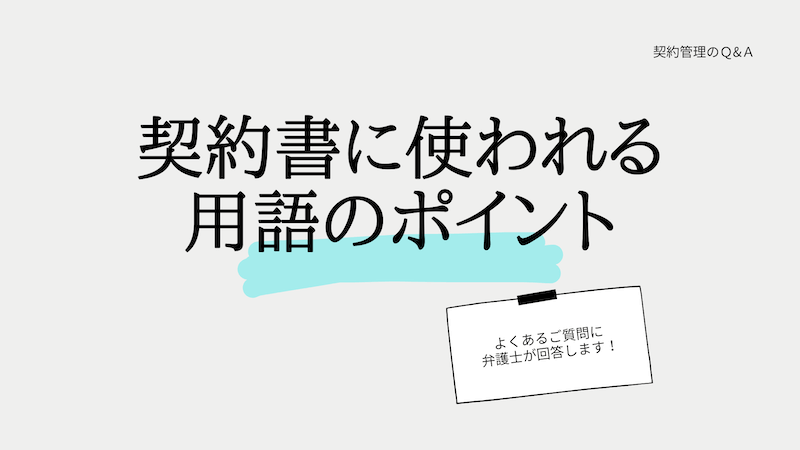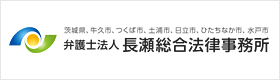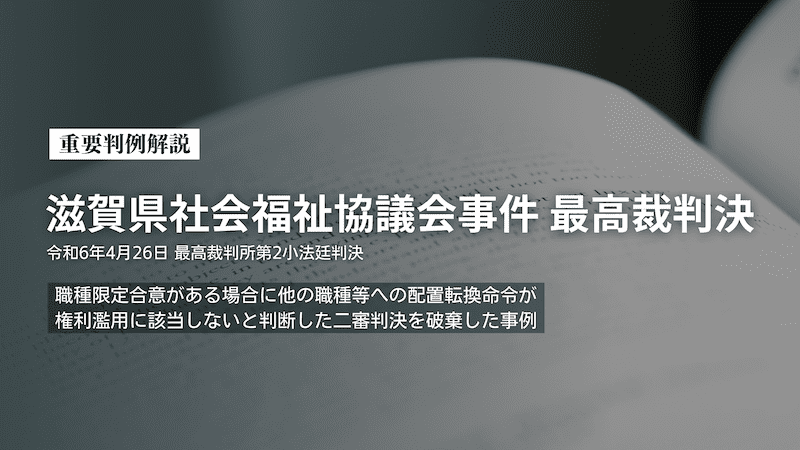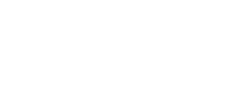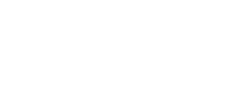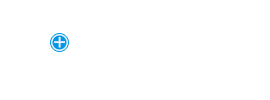〜同一労働同一賃金における福利厚生等の待遇差に関する判断要素〜
解説動画
こちらは、11月27日に開催したセミナーの動画です。
はじめに 本稿の趣旨
令和2年10月15日、無期労働契約の正社員と有期労働契約の時給制契約社員等の年末年始勤務手当、祝日給、扶養手当、病気休暇、夏期休暇及び冬期休暇等に関する労働条件の相違について、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるか否かが争われた裁判において、最高裁判決が下されました。
日本郵便株式会社に対する正社員と有期契約社員との待遇差に関する裁判は複数係属していましたが、今回の最高裁判決では、以下の3つの事件に関する判断が下されることになりました。
① 最高裁判所第一小法廷判決平成30年(受)第1519号 未払時間外手当金等請求控訴、同附帯控訴事件(以下「佐賀事件」と記載します。)
② 最高裁判所第一小法廷判決令和元年(受)第777号、第778号 地位確認等請求事件(以下「東京事件」と記載します)
③ 最高裁判所第一小法廷判決令和2年10月15日令和元年(受)第794号、第795号地位確認等請求事件(以下「大阪事件」と記載します。)
以下、本稿では、上記3つの事件をまとめて「本件最高裁判決」と記載します。また、日本郵便株式会社を「第1審被告」と記載するほか、本件における原告らを「第1審原告ら」と記載します。
本件最高裁判決は、正社員と異なり、有期契約社員に対し、①年末年始勤務手当、②祝日給、③扶養手当、④病気休暇、⑤夏期冬期休暇を支給ないし付与しないことは、不合理な待遇差にあたり、労働契約法20条に違反するという判断を示しました。
本件最高裁判決は、直近である令和2年10月13日に言い渡された大阪医科薬科大学事件最高裁判決(令和元年(受)第1055号、第1056号 地位確認等請求事件)、及びメトロコマース事件最高裁判決(令和元年(受)第1190号、第1191号 損害賠償等請求事件)と並んで、同一労働同一賃金に関する最高裁の考え方が示されるケースとして、高い注目を集めていました。
本件最高裁判決は、賞与に関する待遇差は不合理とはいえないと判断した大阪医科薬科大学事件最高裁判決、退職金に関する待遇差は不合理とはいえないと判断したメトロコマース事件最高裁判決とは異なり、福利厚生等に関する待遇差は不合理であると判断しました。
一連の最高裁判決が企業の人事労務に与える影響は決して小さいものではありません。
国は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)(以下「無期契約労働者」と記載します。)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)(以下「有期契約労働者」と記載します。)の間の不合理な待遇差の解消を目指す同一労働同一賃金を導入し、2020年4月1日より大企業を対象に短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パート有期法」と記載します。)を施行しました。
しかしながら、具体的に同一労働同一賃金の考え方において、どのような待遇差であれば合理性があるといえるのか、未だ明確になっているとは言い難い状況です。
本稿では、本件の事実関係の概要を整理するとともに、本件最高裁判決が与える実務上の影響について考察したいと思います。なお、本稿の内容は、あくまでも筆者の一考察に過ぎないことにご留意ください。
労働契約法20条の規制内容及び同一労働同一賃金ガイドラインの考え方
労働契約法20条の規制内容
本件最高裁判決を検討する前提として、労働契約法20条の規制内容について説明します。
労働契約法20条は、「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」と規定しています。
労働契約法20条は、同一の使用者に雇用されている有期契約労働者と無期契約労働者について、「期間の定めがあること」によって両者の労働条件に相違がある場合、①職務の内容、②当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに③その他の事情を考慮して、その相違が「不合理」なものであることを禁止した規定といえます。③その他の事情とは、「有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断する際に考慮されることとなる事情は、労働者の職務内容及び変更範囲並びにこれらに関連する事情に限定されるものではない」と判示されているように(長澤運輸事件最判平成30年6月1日)、広く諸事情が考慮されるものと解されます。
労働契約法20条は、「均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止)」であるといわれますが、かかる規定内容は、改正後のパート有期法第8条においても基本的に変わるものではないと解されます。
同一労働同一賃金ガイドラインの考え方
かかる労働契約法20条の解釈を明らかにした長澤運輸事件最判平成30年6月1日及びハマキョウレックス事件最判平成30年6月1日を踏まえ、国は、平成30年12月28日、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(以下「同一労働同一賃金ガイドライン」といいます。)を公表し、同一労働同一賃金に関する基本的な考え方及び各手当に関する考え方を例示しました。
もっとも、同一労働同一賃金ガイドラインにおいても、「事業主が、第3から第5までに記載された原則となる考え方等に反した場合、当該待遇の相違が不合理と認められる等の可能性がある。」と記載されているように、同一労働同一賃金ガイドラインのみでは、無期契約労働者と有期契約労働者との間の待遇差が直ちに違法とまでは断言できるわけではなく、待遇の相違が不合理といえるかどうかは、個別のケースによって判断されることになります。
したがって、同一労働同一賃金ガイドラインだけでは、無期契約労働者と有期契約労働者との間の福利厚生等に関する待遇差が合理性を有するといえるかどうかは判断できない場合があることに留意する必要があります。
なお、本件最高裁判決で判断された手当と同種のものとしてガイドラインに掲載されている例として、「病気休暇」が挙げられます。
参考までに、ガイドラインで掲載されている「病気休暇」に関する不合理な待遇差に関する考え方は、以下のとおりです。
1 ガイドラインの考え方
短時間労働者(有期雇用労働者である場合を除く。)には、通常の労働者と同一の病気休職の取得を認めなければならない。また、有期雇用労働者にも、労働契約が終了するまでの期間を踏まえて、病気休職の取得を認めなければならない。
2 問題とならない例
A社においては、労働契約の期間が1年である有期雇用労働者であるXについて、病気休職の期間は労働契約の期間が終了する日までとしている。
本件最高裁判決の概要
事案の概要
本件は、第1審被告と有期労働契約を締結して勤務し、又は勤務していた時給制契約社員又は月給制契約社員である第1審原告らが、無期労働契約を締結している正社員と第1審原告らとの間で、年末年始勤務手当、祝日給、扶養手当、夏期冬期休暇等に相違があったことは労働契約法20条に違反するものであったと主張して、第1審被告に対し、不法行為に基づき、上記相違に係る損害賠償を求めるなどの請求をするものです。
事実関係等の概要
本件最高裁判決における正社員と第1審原告ら有期契約社員の労働条件等は、以下の一覧表をご参照ください。
| 労働条件 | 正社員 | 期間雇用社員(時給制契約社員等)【原告】 |
|---|---|---|
| 契約期間 | 無期 | 有期 契約期間6ヶ月以内、更新可 |
| 労働時間 | 1日原則8時間、1週平均40時間 | 1日8時間以内、1週平均40時間以内 |
| 業務内容 | 旧一般職では、郵便外務事務、郵便内務事務等に幅広く従事し、昇任や昇格により役割や職責が大きく変動することを想定。 平成26年4月以降の新一般職では、郵便外務事務、郵便内務事務等の標準的な業務に従事し、昇任や昇格は予定されていない。 |
郵便外務事務または郵便内務事務のうち、特定の業務のみに従事し、各事務について幅広く従事することは想定されておらず、昇任や昇格は予定されていない。 |
| 人事評価 | 業務の実績そのものに加え、部下の育成指導状況、組織全体に対する貢献等の項目によって業績が評価されるほか、自己研鑛、状況把握、論理的思考、チャレンジ志向等の項目によって正社員に求められる役割を発揮した行動が評価される。 | 【時給制契約社員の人事評価】 上司の指示や職場内のルールの遵守等の基本的事項に関する評価が行われる。 担当する職務の広さとその習熟度 についての評価が行われる。 【月給制契約社員の人事評価】 業務を適切に遂行していたかなどの観点によって業績が評価される。 上司の指示の理解、上司への伝達等の基本的事項や、他の期間雇用社員への助言等の観点により、月給制契約社員に求められる役割を発揮した行動が評価される。 【正社員との違い】 正社員とは異なり、組織全体に対する貢献によって業績が評価されること等はない。 |
| 配置転換等 | 旧一般職を含む正社員には配転が予定されている。 ただし、新一般職は、 転居を伴わない範囲において人事異動が命ぜられる可能性があるにとどまる。 |
職場及び職務内容を限定して採用されている。 正社員のような人事異動は行われない。 郵便局を移る場合には、個別の同意に基づき、 従前の郵便局における雇用契約を終了させた上で、新たに別の郵便局における勤務に関して雇用契約を締結し直している。 |
| その他の状況 | 正社員に登用される制度が設けられており、人 事評価や勤続年数等に関する応募要件を満たす応募者について、適性試験や面接等 により選考される。 | |
本件の争点
本件では、正社員と第1審原告らとの間における、①年末年始勤務手当、②祝日給、③扶養手当、④病気休暇、⑤夏期冬期休暇等の待遇差が、労働契約法20条に違反するかどうかが争点となりました。
正社員と有期契約社員である第1審原告らとの間の待遇差は、以下の一覧表のようになります。
| 手当・福利厚生 | 正社員 | 期間雇用社員(時給制契約社員等)【原告】 |
|---|---|---|
| 年末年始勤務手当 | 12月29日から翌年1月3日までの間に実際に勤務したときに支給される。 12月29日から同月31日まで:1日4000円 1月1日から同月3日まで:1日5000円 ただし、実際に勤務し た時間が4時間以下の場合はそれぞれその半額 |
支給なし |
| 祝日給 | 正社員が祝日において割り振られた正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられて勤務したとき(祝日代休が指定された場合を除く。)及び祝日を除く1月1日から同月3日までの期間に勤務したときに支給される。 | 支給なし |
| 扶養手当 | 所定の扶養親族のある者に支給される。 扶養親族の種類等に応じて、扶養親族1人につき月額1500円~1万5800円 |
支給なし |
| 夏期冬期休暇 | 【夏期休暇】6月1日から9月30日まで 【冬期休暇】10月1日から翌年3月31日まで 各期間において、それぞれ3日まで与えられる有給休暇 |
付与なし |
| 病気休暇 | 私傷病等により勤務日 又は正規の勤務時間中に勤務しない者に与えられる有給休暇。 私傷病による 病気休暇は少なくとも引き続き90日間まで与えられる。 |
私傷病による病気休暇は1年に10日の範囲で無給の休暇が与えられる。 |
本件最高裁判決の判断内容
本件最高裁判決は、①年末年始勤務手当、②祝日給、③扶養手当、④病気休暇、⑤夏期冬期休暇の待遇差に関し、以下のように判示しました。
労働契約法20条の判断基準
本件最高裁判決(佐賀事件)は、福利厚生等に関する待遇差に関し、労働契約法20条違反の判断基準について以下のように判示しました。
有期労働契約を締結している労働者と無期労働契約を締結している労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が労働契約法20条にいう不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては、両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当である(最高裁平成29年(受)第442号同30年6月1日第二小法廷判決・民集72巻2号202頁)ところ、賃金以外の労働条件の相違についても、同様に、個々の労働条件の趣旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当である。
本件最高裁判決は、長澤運輸事件最高裁判決を引用した上で、「賃金以外の労働条件の相違についても、同様に、個々の労働条件の趣旨を個別に考慮すべき」であるという基準を示しました。
本件最高裁判決は、上記基準を踏まえ、福利厚生等に関する各手当について、趣旨から言及しています。
①年末年始休暇
第1審被告における年末年始勤務手当は、郵便の業務を担当する正社員の給与を構成する特殊勤務手当の一つであり、12月29日から翌年1月3日までの間において実際に勤務したときに支給されるものであることからすると、同業務についての最繁忙期であり、多くの労働者が休日として過ごしている上記の期間において、同業務に従事したことに対し、その勤務の特殊性から基本給に加えて支給される対価としての性質を有するものであるといえる。また、年末年始勤務手当は、正社員が従事した業務の内容やその難度等に関わらず、所定の期間において実際に勤務したこと自体を支給要件とするものであり、その支給金額も、実際に勤務した時期と時間に応じて一律である。
上記のような年末年始勤務手当の性質や支給要件及び支給金額に照らせば、これを支給することとした趣旨は、本件契約社員にも妥当するものである。そうすると、前記第1の2(5)~(7)のとおり、郵便の業務を担当する正社員と本件契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても、両者の間に年末年始勤務手当に係る労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができるものといえる。
本件最高裁判決は、①年末年始休暇の性質に関し、勤務の特殊性から基本給に加えて支給される対価であると判示しました。
また、本件最高裁判決は、①年末年始休暇は、業務の内容や難度等に関わらず、所定の期間に実際に勤務したこと自体が支給要件であり、支給金額も実際に勤務した時期と時間に応じて一律であると判示しました。
本件最高裁判決は、①年末年始休暇の性質や支給要件・支給金額にかんがみ、有期契約社員にも①年末年始休暇を支給する趣旨が妥当することから、正社員と異なり有期契約社員には支給しないことは不合理であると判断しました。
②祝日給
第1審被告における祝日給は、祝日のほか、年始期間の勤務に対しても支給されるものである。年始期間については、郵便の業務を担当する正社員に対して特別休暇が与えられており、これは、多くの労働者にとって年始期間が休日とされているという慣行に沿った休暇を設けるという目的によるものであると解される。
これに対し、本件契約社員に対しては、年始期間についての特別休暇は与えられず、年始期間の勤務に対しても、正社員に支給される祝日給に対応する祝日割増賃金は支給されない。そうすると、年始期間の勤務に対する祝日給は、特別休暇が与えられることとされているにもかかわらず最繁忙期であるために年始期間に勤務したことについて、その代償として、通常の勤務に対する賃金に所定の割増しをしたものを支給することとされたものと解され、郵便の業務を担当する正社員と本件契約社員との間の祝日給及びこれに対応する祝日割増賃金に係る上記の労働条件の相違は、上記特別休暇に係る労働条件の相違を反映したものと考えられる。
しかしながら、本件契約社員は、契約期間が6か月以内又は1年以内とされており、第1審原告らのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者も存するなど、繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく、業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれている。そうすると、最繁忙期における労働力の確保の観点から、本件契約社員に対して上記特別休暇を付与しないこと自体には理由があるということはできるものの、年始期間における勤務の代償として祝日給を支給する趣旨は、本件契約社員にも妥当するというべきである。
そうすると、前記第1の2(5)~(7)のとおり、郵便の業務を担当する正社員と本件契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても、上記祝日給を正社員に支給する一方で本件契約社員にはこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができるものといえる。
本件最高裁判決は、②祝日給に関し、最繁忙期における労働力の確保の観点から、本件契約社員に対して上記特別休暇を付与しないこと自体には理由があると判示しつつ、年始期間における勤務の代償として祝日給を支給する趣旨は、本件契約社員にも妥当すると判示しました。
本件最高裁判決は、②祝日給に関し、契約社員に支給しないことは不合理であると判断しました。
③扶養手当
第1審被告において、郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当が支給されているのは、上記正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、その生活保障や福利厚生を図り、扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的によるものと考えられる。このように、継続的な勤務が見込まれる労働者に扶養手当を支給するものとすることは、使用者の経営判断として尊重し得るものと解される。
もっとも、上記目的に照らせば、本件契約社員についても、扶養親族があり、かつ、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、扶養手当を支給することとした趣旨は妥当するというべきである。そして、第1審被告においては、本件契約社員は、契約期間が6か月以内又は1年以内とされており、第1審原告らのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど、相応に継続的な勤務が見込まれているといえる。そうすると、前記第1の2(5)~(7)のとおり、上記正社員と本件契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても、両者の間に扶養手当に係る労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができるものというべきである。
本件最高裁判決は、③扶養手当に関し、継続的な勤務が見込まれる労働者に扶養手当を支給するものとすることは、使用者の経営判断として尊重し得ると判示し、使用者の裁量があると述べつつも、契約社員について、扶養親族があり、かつ、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば扶養手当を支給する趣旨は妥当すると判示しました。
本件最高裁判決は、③扶養手当に関し、契約社員に支給しないことは不合理であると判断しました。
④夏期冬期休暇
上告人において、郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇が与えられているのは、年次有給休暇や病気休暇等とは別に、労働から離れる機会を与えることにより、心身の回復を図るという目的によるものであると解され、夏期冬期休暇の取得の可否や取得し得る日数は上記正社員の勤続期間の長さに応じて定まるものとはされていない。そして、郵便の業務を担当する時給制契約社員は、契約期間が6か月以内とされるなど、繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく、業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれているのであって、夏期冬期休暇を与える趣旨は、上記時給制契約社員にも妥当するというべきである。
そうすると、前記2(2)のとおり、郵便の業務を担当する正社員と同業務を担当する時給制契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても、両者の間に夏期冬期休暇に係る労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができるものといえる。
したがって、郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇を与える一方で、郵便の業務を担当する時給制契約社員に対して夏期冬期休暇を与えないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
本件最高裁判決は、④夏季冬季休暇の目的は、労働から離れる機会を与えることにより、心身の回復を図ることにあると判示した上で、④夏期冬期休暇の取得の可否や取得し得る日数は上記正社員の勤続期間の長さに応じて定まるものとはされておらず、契約社員にも同様の趣旨があてはまると判示しました。
本件最高裁判決は、④夏季冬季休暇に関し、契約社員に支給しないことは不合理であると判断しました。
⑤病気休暇
第1審被告において、私傷病により勤務することができなくなった郵便の業務を担当する正社員に対して有給の病気休暇が与えられているのは、上記正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、その生活保障を図り、私傷病の療養に専念させることを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的によるものと考えられる。このように、継続的な勤務が見込まれる労働者に私傷病による有給の病気休暇を与えるものとすることは、使用者の経営判断として尊重し得るものと解される。
もっとも、上記目的に照らせば、郵便の業務を担当する時給制契約社員についても、相応に継続的な勤が見込まれるのであれば、私傷病による有給の病気休暇を与えることとした趣旨は妥当するというべきである。そして、第1審被告においては、上記時給制契約社員は、契約期間が6か月以内とされており、第1審原告らのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど、相応に継続的な勤務が見込まれているといえる。
そうすると、前記第1の2(5)~(7)のとおり、上記正社員と上記時給制契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても、私傷病による病気休暇の日数につき相違を設けることはともかく、これを有給とするか無給とするかにつき労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができるものといえる。
したがって、私傷病による病気休暇として、郵便の業務を担当する正社員に対して有給休暇を与えるものとする一方で、同業務を担当する時給制契約社員に対して無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
本件最高裁判決は、⑤病気休暇の目的について、生活保障を図り、私傷病の療養に専念させることを通じて、その継続的な雇用を確保することにあると判示した上で、有休の病気休暇を付与するかどうかは、使用者の経営判断として尊重し得ると判示しました。
本件最高裁判決は、⑤病気休暇に関しては、使用者の裁量があると述べつつも、契約社員にも同様の趣旨があてはまると判示しました。
本件最高裁判決は、⑤病気休暇に関し、契約社員に支給しないことは不合理であると判断しました。
本件最高裁判決の実務上の影響
本件最高裁判決は、①年末年始勤務手当、②祝日給、③扶養手当、④病気休暇、⑤夏期冬期休暇という福利厚生に関する待遇差について、不合理であり労働契約法20条に違反すると判断しました。
本件最高裁判決が示した各手当の待遇差に関する考え方は、ガイドラインにも直接的な記載がないことから、今後の同種手当の待遇差の適法性を検討する上で参考になるものといえます。
一方、本件最高裁判決は、あくまでも事例判決にとどまるものです。
本件最高裁判決は、③扶養手当、④病気休暇の判断に関し、「使用者の経営判断として尊重し得る」と述べ、使用者の裁量に委ねられる余地がある法公営を示しつつ、結論としては正社員と契約社員の間の待遇差を不合理であると判断しました。本件最高裁判決の判示と結論をみると、結局最高裁は、どの程度であれば「使用者の経営判断として尊重し得る」と考えているのかが明らかではありません。
また、本件最高裁判決は、契約社員であっても「相応に継続的な勤務が見込まれている」ことを理由に、③扶養手当、④病気休暇、⑤夏期冬期休暇における待遇差は不合理であると判断しました。もっとも、具体的に契約社員がどの程度の期間勤務をして入れば、「相応に継続的な勤務が見込まれている」と評価されるのかも明らかにされていません。
本件最高裁判決によっても、福利厚生等に関する待遇差は、どの程度であれば不合理と評価されるのかは、なおも不明確さが残るままとなっています。
加えて、本件最高裁判決は、福利厚生に関する各手当の性質や趣旨に着目していますが、正社員と契約社員の職務の内容や、変更の範囲、その他の事情については正面から言及していない印象があります。
果たして、無期契約労働者と有期契約労働者の職務の内容や変更の範囲、その他の事情が、福利厚生に関する手当の待遇差についての不合理性の判断にどの程度影響するのかは不明瞭なままといえます。
今後も福利厚生等に関する無期契約労働者と有期契約労働者の待遇差に関しては、個別の裁判例の集積をみながら、合理性に関する判断基準を見極める必要があります。