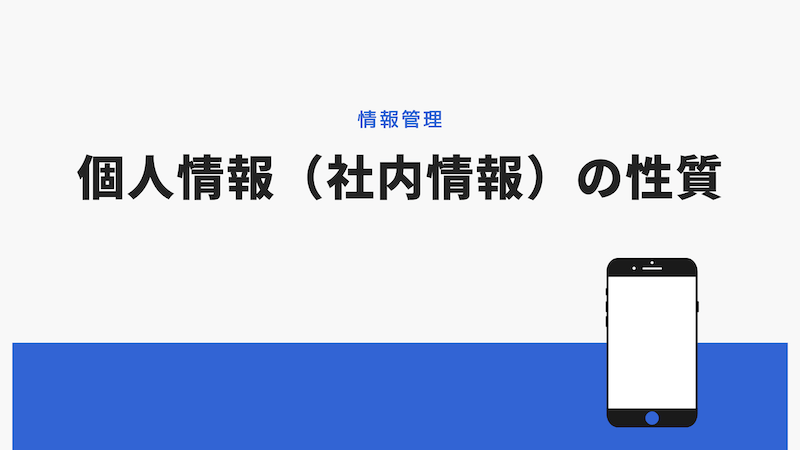はじめに
TwitterやInstagram、FacebookなどのSNS上で誹謗中傷被害を受けた場合、多くの人は「どう対処すればいいのか」「どのような手続きが必要なのか」分からずに困惑することでしょう。SNS特有の匿名性と拡散力により、被害が深刻化しやすいのが特徴です。しかし、適切な法的手続きを踏めば、投稿の削除や加害者の特定、損害賠償の請求などを行う道が開けます。
本稿では、SNSで誹謗中傷を受けた場合の主な法的手続きの流れを解説します。投稿の削除依頼や発信者情報開示請求、示談交渉や裁判といったステップを、それぞれどのように進めればいいのか、弁護士に相談するメリットは何かといった観点からまとめました。被害を受けた側が安心してSNSを利用できる環境を取り戻すための参考になれば幸いです。
Q&A
Q1:SNSで誹謗中傷を受けた場合、すぐに警察に通報すべきでしょうか?
まずは投稿内容が名誉毀損や侮辱、脅迫などの犯罪に該当するかどうかを確認し、必要性があれば警察へ相談する選択肢もあります。ただし、警察が事件性を認めなかったり、不起訴になるケースもあるため、並行して弁護士に相談し、民事上の手続き(削除依頼、発信者情報開示請求など)も進めるのが有効です。
Q2:SNS運営会社に削除依頼を出しただけで解決することはありますか?
投稿が各社のガイドラインに違反していると判断されれば、削除される場合もあります。しかし、削除されなかったり、根強く拡散している場合は、仮処分など法的手段を用いて強制的に削除を実現する方法を検討すべきです。
Q3:発信者情報開示請求にはどれくらい時間と費用がかかるのでしょうか?
一般的には、数カ月〜半年程度かかることが多いです。費用は案件の難易度によって異なりますが、弁護士費用(着手金・成功報酬など)や裁判所に支払う費用、翻訳費用などが発生する場合もあります。具体的な見積りは弁護士に相談して確認するとよいでしょう。
Q4:加害者を特定し、示談交渉や損害賠償請求をするメリットは何ですか?
直接謝罪を求めたり、二度と誹謗中傷しないよう誓約書を取り付けたり、精神的被害に対する慰謝料を得たりといった効果が期待できます。また、加害者が特定された事実が周知されれば、誹謗中傷の再発や模倣犯を抑止する意味合いもあります。
Q5:弁護士を利用せずに自力で法的手続きを行うのは難しいですか?
法律や判例の知識、書面作成、裁判所手続きの進行管理など、高度な専門性が必要です。誹謗中傷被害者が自力で全てを行うのは困難かつ時間的・精神的負担が大きいため、弁護士に依頼するのが現実的です。
解説
誹謗中傷被害を受けた際の全体的な流れ
- 証拠の確保
- SNSの誹謗中傷投稿をスクリーンショットや録画で保存
- 投稿者のアカウント名、投稿URL、日時などを記録し、改ざんされない形で保全
- SNS運営会社への削除依頼・通報
- ガイドライン違反の可能性があれば、運営会社へ報告し削除を要請
- ただし、削除に応じてもらえないことも多い
- 弁護士への相談
- 違法性の判断、法的手続きの選択肢を検討
- 費用や見通しを聞き、委任契約を締結
- 発信者情報開示請求・仮処分
- SNS運営会社やプロバイダを相手に裁判手続きで投稿者を特定、または投稿削除を求める
- 示談交渉または裁判手続き
- 投稿者を特定できれば損害賠償や謝罪を要求し、交渉不成立なら裁判
- 裁判所の判決に従い、賠償金支払いや投稿削除を実現
主な法的手続きの詳細
- 投稿削除依頼(運営会社への報告)
- SNS各社のガイドラインに基づき、「名誉毀損・侮辱・差別・暴力的・ポルノ・プライバシー侵害」などのカテゴリで通報する
- 具体的にどの部分が違反かを指摘し、スクリーンショットなどを添付すると審査が早い
- 仮処分による強制削除
- 運営会社が応じない場合、裁判所から「表示差止め命令」を出してもらう手段
- 投稿が名誉毀損など違法行為に該当すると判断されれば、強制力を持って削除が実現
- 発信者情報開示請求
- 加害者を特定するため、SNS運営会社やプロバイダに対してIPアドレスやログ情報の開示を求める訴訟
- 一般的には、投稿から数カ月以内に手続きを始めないと、ログが消失するリスクが高い
- 損害賠償請求・示談交渉
- 加害者が判明すれば、示談による謝罪広告や慰謝料の支払いを求める交渉が行われる
- 被害者の実害や精神的苦痛の度合いに応じて金額が設定される
- 刑事告訴・警察対応
- 名誉毀損罪や脅迫罪、侮辱罪など、犯罪が疑われる場合は警察に被害届や告訴状を提出
- 捜査機関と連携して加害者を追及
法的手続きにおける注意点
- 証拠保全が最優先
- SNS上の投稿は削除やアカウント凍結で消失するリスクがあるため、早期にスクリーンショットを撮る
- 日時やURL、ID、投稿内容がはっきり分かる形で保全
- 時効やログ保存期間に留意
- IPアドレスなどログ情報は通常数カ月で消去されることが多い
- 誹謗中傷から時間が経過しすぎると特定が困難になる
- 仮処分・裁判手続きの費用と期間
- 発信者情報開示請求や仮処分には裁判所への提出書類や印紙代、弁護士費用がかかる
- 数カ月〜1年程度の時間がかかる可能性がある
- 海外サーバー・海外在住者への対応
- 国際的な司法手続きが絡み、困難度が増す場合がある
- 国際裁判管轄や海外の法律事務所との連携が必要になる可能性
弁護士に相談するメリット
法的観点からの削除依頼・通報文書作成
誹謗中傷が法的にどのような違反となるかを弁護士が整理し、SNS運営会社やプロバイダへの書面を作成することで、説得力の高い削除依頼や発信者情報開示請求が可能になります。
仮処分や発信者情報開示請求の迅速な進行
専門知識と経験を持つ弁護士が、裁判所へ仮処分申立書や開示請求訴状を提出し、手続きをリードするため、個人が対応するよりもスピード感と成功率が上がります。
示談交渉・損害賠償請求で被害回復
加害者が特定された場合、謝罪広告や金銭的賠償を求めることで実質的な被害回復を図れます。弁護士が代理人となり、感情的衝突を避けながら冷静に交渉を進められます。
精神的負担の軽減と長期的サポート
誹謗中傷被害者は強い苦痛を抱えがちですが、弁護士が窓口となることで、そのストレスを大幅に和らげることができます。顧問契約などを結べば、SNSリスクを含む様々な法務トラブルに継続的に備えられます。
まとめ
SNS誹謗中傷被害の法的手続きフロー
- 証拠保全(スクショ等)
- 運営会社への削除依頼・通報
- 弁護士への相談
- 仮処分・発信者情報開示請求
- 示談交渉 or 裁判手続き
注意点
- ログ保存期間の問題→ なるべく早期に行動
- 海外サーバー・海外在住者だと難易度UP
- 証拠保全が成功率を左右
弁護士に相談するメリット
- 削除依頼や開示請求を法的根拠に基づき迅速に対応
- 示談交渉・裁判手続きで被害回復を目指せる
- 精神的負担を軽減し、長期的リスク管理が可能
SNSで誹謗中傷を受けた場合、放置すれば被害が拡大し、名誉や信用を大きく損なう恐れがあります。早期に証拠を確保し、弁護士など専門家と連携して適切な法的手続きを踏むことで、投稿の削除や加害者特定、損害賠償請求などの救済手段を得られます。
お困りの際は、弁護士法人長瀬総合法律事務所までご相談ください。
長瀬総合の情報管理専門サイト
情報に関するトラブルは、方針決定や手続の選択に複雑かつ高度な専門性が要求されるだけでなく、迅速性が求められます。誹謗中傷対応に傾注する弁護士が、個人・事業者の皆様をサポートし、適切な問題の解決、心理的負担の軽減、事業の発展を支えます。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
当事務所は多数の誹謗中傷の案件を担当しており、 豊富なノウハウと経験をもとに、企業の皆様に対して、継続的な誹謗中傷対策を提供しており、数多くの企業の顧問をしております。
企業の実情に応じて適宜顧問プランを調整することも可能ですので、お気軽にご連絡ください。