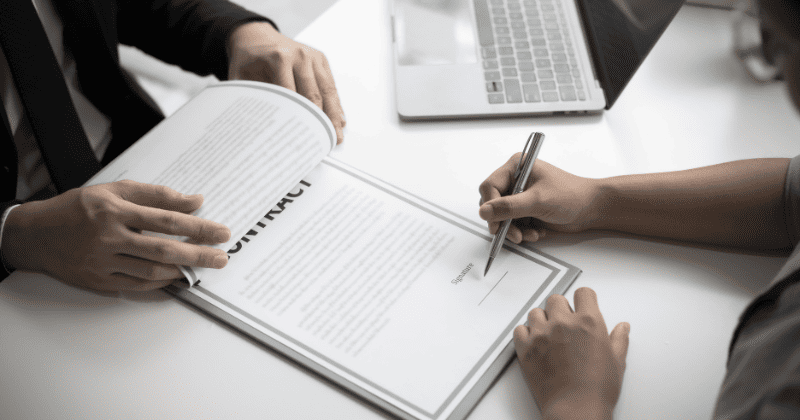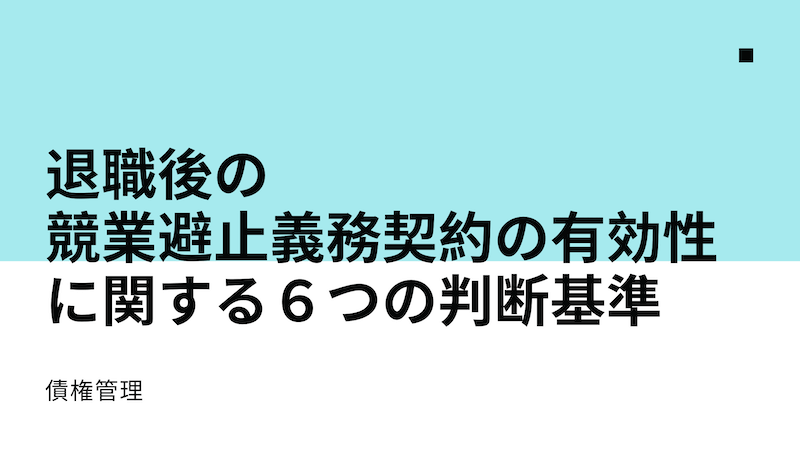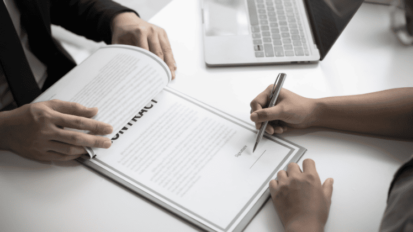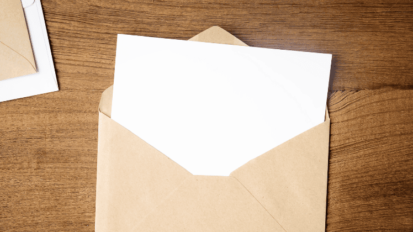はじめに
企業間取引では、代金の支払い時期や方法をどう設定するかが、キャッシュフロー管理とリスク回避のうえで非常に重要な要素となります。さらに、支払いが期日を過ぎた場合にどう対応するか、遅延損害金を定めることで、相手方の支払意思を高めたり、損失を補填する効果が期待できます。しかし、実務では「特に規定を置かないまま受注・納品している」「遅延損害金率を明文化していない」など不備が多く、支払い遅延や未払いリスクが表面化しやすいのが現状です。
本記事では、契約書で支払い条件を設定する際の基本ポイントや、遅延損害金規定の適正な設定方法、法的リスクや実務上の注意点を解説します。契約段階から代金回収のフローを確立し、企業のキャッシュフローを安定させるためにも、しっかり条文化しておくことが重要です。
Q&A
Q1:契約書に支払い条件を明記するメリットは何でしょうか?
支払い条件(支払期日・支払方法・遅延時対応など)を明記することで、売掛金やサービス代金の回収リスクを減らせます。お互いに納得した条件が文書化されることで、後から「言った・言わない」の紛争が起きにくくなります。また、期日を越えたら自動的に遅延損害金が発生するなどのペナルティを定めれば、相手方が支払いを早めるインセンティブとなり得ます。
Q2:遅延損害金は法律で決まった利率があるのでしょうか?
民事上の法定利率は2020年4月の改正民法施行により年3%(固定)から変動制(当面は3%)に移行しています。ただし、契約書に特約として「支払い遅延の場合は年14.6%の損害金を支払う」など任意の利率を設定することも可能です。ただし、あまりに高い利率を設定すると公序良俗違反と判断される可能性もあり、年14.6%以下程度が実務上多くの企業が採用している水準です。
Q3:支払いサイト(末締め翌月末払いなど)を長く設定しても問題ありませんか?
下請法の観点から「不当に長い支払いサイト」は違法とみなされるリスクがあります。特に下請取引で60日を超えるサイトを設定する際は注意が必要です。さらに、自社のキャッシュフローも悪化しやすいため、ビジネスの安定を考慮して適正な支払いサイトを設定することが望ましいです。
Q4:支払い方法を手形にする場合、どんなリスクがありますか?
手形は受け取っても期日に不渡りになる可能性があり、現金化を確実に保証しない点がリスクです。また、手形の受取から現金化までにタイムラグがあるため、自社のキャッシュフローに影響する場合もあるうえ、不渡りが2回出た企業は倒産と同様の扱い(銀行取引停止)となり、完全回収が困難になります。最近は電子手形や振込に移行する企業が増えていますが、手形を使う場合は信用調査や担保策を検討することが重要です。
解説
支払い条件を定める意義
- キャッシュフロー管理
- 企業が取引で発生する売掛金をいつ回収できるかを明確にすることで、仕入や人件費などの支払いとバランスを取り、資金繰りを安定化できる。
- 反対に、支払いサイトを曖昧にすると予測が立たず、資金計画が狂い、財務状況に大きなリスクが生じる。
- 紛争防止
- 契約書で支払い期日を明確にしていないと、「いつまでに払えばいいのか」「なぜ請求が遅いのか」といったトラブルが起きやすい。
- 遅延損害金を設定することで、支払期限を経過した後の損害を補填しやすくなる。また、相手方の支払い意欲を高める効果も。
- 法令・下請法対応
- 下請法上、下請取引では60日以内の現金払いを原則とする規制に留意が必要。
- 契約書や注文書に適切な項目を記載していないと下請法違反となり、行政処分(勧告・指導)のリスクがある。
契約書で定めるべき支払い条件
- 支払い期限・日付
- 「月末締め翌月末日払い」など具体的な期日を記載し、特別な事情がある場合を除き延長しない条文を作る。
- 例えば海外取引なら「インボイス発行後30日以内の送金」「B/L(船荷証券)のコピー提出後○日払い」など貿易慣行に合わせる。
- 支払い方法(振込・手形・現金など)
- 銀行振込が一般的だが、手形払いを取り決める場合は支払サイト(手形期日)や振出日を明確化。
- 国際取引ではL/C(信用状)を使う場合もあり、その際はL/C条件(有効期限、引き取り書類)を契約書で言及することが多い。
- 遅延損害金の利率
- 契約書で年○%と明示し、相手方がデフォルトすると自動的に遅延損害金が発生する仕組みを設定。
- 民法の法定利率(変動制)を適用せず、年14.6%など一定の高め利率を交渉で盛り込むことが実務上よくある。
- 期限の利益喪失条項
- 1回の遅延であっても、残りの分割分含めて一括支払いを求めることができる旨を定めることで、相手方を早期に支払わせる圧力となる。
- 銀行融資契約などでよく見られる条項だが、商取引でも有効。
- 支払いに関する立替費用・振込手数料負担
- 振込手数料をどちらが負担するか、または折半か。企業の国際取引で双方が海外送金手数料をめぐってトラブルになることもある。契約書で明記し、不要な紛争を防ぐ。
遅延損害金規定の設計
- 遅延損害金の利率決定
- 先述のとおり、契約書で任意の利率を定めることが可能だが、高すぎる利率は無効とされる恐れがある(公序良俗違反)。多くの企業が年14.6%前後を目安に採用。
- 国際取引で海外の法例を適用する場合、それぞれの国の法定利率を調査する必要がある。
- 発生時点
- 「支払期日の翌日から遅延損害金が発生する」等を明確に記載。
- 分割払いの場合、各分割分の支払いが遅れた時点から発生するのか、一括期限の利益喪失後から発生するのかを設定する。
- 計算式と端数処理
- 日割りで計算するのが一般的で、「遅延損害金=未払金額 × 利率 × (遅延日数 ÷ 365日)」などと規定する例もある。月ベースや小数点端数の繰上げ・切捨て方法を決めてもよい。
- 支払い優先順位
- 相手方から部分的に支払があった場合、元本と損害金のどちらに充当するかを定める。多くの場合、利息や遅延損害金に先に充当し、残りを元本にあてる形とする。
実務上のリスク管理
- 定期的な契約見直し
- 取引が長期化するほど市況や経営環境が変化するため、支払いサイトや利率が現在のリスクに合わなくなる可能性がある。
- 定期的に契約書の改訂を検討し、相手方の信用状態に合わせて条件を修正する。
- モニタリングと督促体制
- 支払い期日の管理をシステム化し、未入金があれば担当者にアラート。電子契約などでデジタル管理する企業も増えている。
- 遅延が発覚次第、素早く督促し、問題が解決しなければ遅延損害金の請求に踏み切る。いたずらに様子を見ると回収困難が大きくなる。
- 国際取引での考慮
- 国外取引では適用法や送金手数料、為替リスクなど注意点が増える。支払い遅延が生じた場合の強制執行の難しさを想定し、遅延損害金に加えてL/Cや保証状などの導入を検討する。
- 合意書/覚書での解決
- 支払いが滞った場合、分割払いなどに合意するときは合意書(債務承認公正証書など)を締結し、将来の法的手続き(強制執行)をスムーズにする方法もある。
- 公正証書に執行認諾文言を付すことで、裁判なしで強制執行が可能となり、回収力が高まる。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、支払い条件や遅延損害金規定に関して、以下のようなサポートを提供しています。
- 契約書レビュー・改定サポート
- 既存の取引契約書を検討し、支払い期日や遅延損害金、分割払い合意などの条項を整備し、企業のキャッシュフロー確保に寄与。
- 新規契約の場合、取引先の信用リスクを考慮して支払い条件や担保設定を提案し、契約書に反映。
- 督促・回収代理
- 期日を過ぎた債権について、内容証明郵便の送付や電話交渉を弁護士が代行。相手が応じない場合は支払督促や少額訴訟、通常訴訟へのステップを提示。
- 遅延損害金や弁護士費用の請求を適切に主張し、最短時間での回収を目指す。
- 法的リスク・独禁法・下請法
- 下請事業者に不当に長い支払いサイトを押し付けていないか、下請法や独禁法上の問題がないかを診断。
- 特に親事業者として支払い条件がきびしくないか検討し、是正が必要であれば改善策を提案する。
- 継続的サポート(顧問契約)
- 企業が大量の契約を取り扱う場合、定期的な法務レビューや従業員への研修で支払い条件や遅延損害金の規定運用を最適化。
- 紛争が生じた際もスムーズに早期解決を図り、企業側の損害を最小限に抑える。
まとめ
- 契約書で支払い条件(支払期日・方法・サイト)を明確化し、さらに遅延損害金を設定することで、不払い・遅延のリスクを抑え、回収を容易にできる。
- 遅延損害金利率は契約で自由に定められるが、実務上は年14.6%以下が標準的。高すぎると公序良俗違反で無効の可能性がある。
- 支払いサイト(末締め翌月末払いなど)の設定は企業のキャッシュフローに直結し、下請取引の場合は下請法の規制に留意する。
- 弁護士の助言を受けて契約書を整備し、督促・法的回収のフローを構築すれば、未払いリスクに強い企業体制を築ける。
長瀬総合の債権回収専門サイト
企業活動において債権・売掛金・請負代金等を回収できないというのは、企業活動に支障を来しかねません。
私たちは、経営者・企業の皆様が債権回収でお悩みになることを解消するとともに、持続的な成長の一助となることをお約束いたします。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス