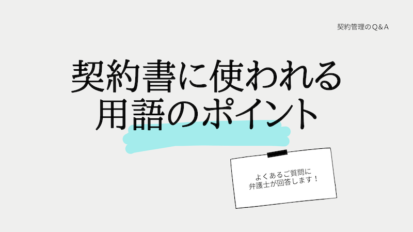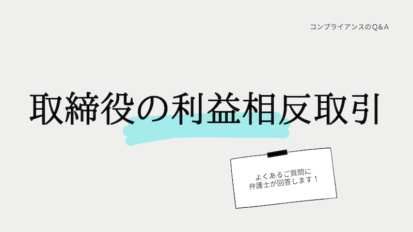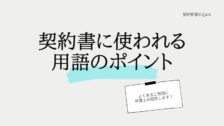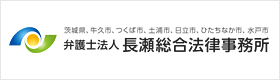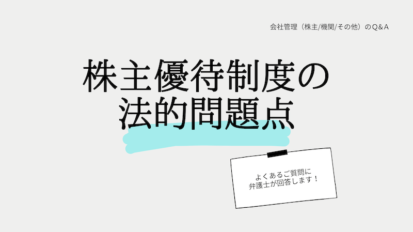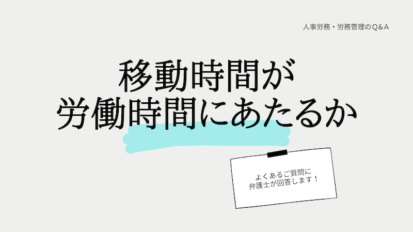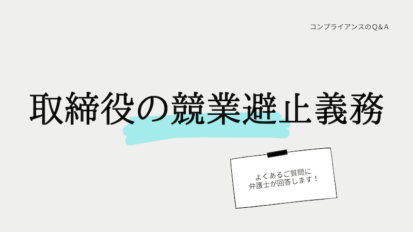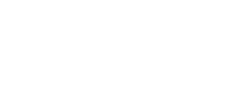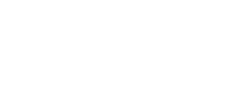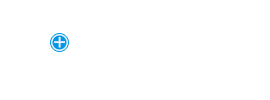残業代・労働時間・休日対応に関する留意点について、解説しております。
目次
- 【使用者向け】労働時間—自宅待機命令中の社員に対する賃金支払義務
- 【使用者向け】健康管理①—傷病休業からの復職
- 【使用者向け】労働時間—研修期間中の年休取得に対する会社の時季変更権
- 【使用者向け】労働時間—休憩時間中の待機対応と労働時間
- 【使用者向け】労働時間—社員による無断残業への対応
- 【使用者向け】労働時間—社員による無断残業に対する防止策
- 【使用者向け】労働時間—休日出勤をした社員への割増賃金の要否
1 【使用者向け】労働時間—自宅待機命令中の社員に対する賃金支払義務
【質問】
社員Xについて、当社の顧客情報、営業情報を漏洩させた疑いがあることから、事実関係の調査及び証拠隠滅防止のため、Xに対して2週間の自宅待機命令を下しています。
現在、事実関係を調査している最中ですが、調査の結果Xによる情報漏洩が確認された場合、Xに対する懲戒処分を下す予定です。
調査結果が判明するまで、会社はXに対して、自宅待機期間に相当する賃金を支払う義務があるでしょうか。
【回答】
業務命令としての自宅待機命令を行う場合、会社は当該自宅待機期間に相当する賃金支払義務を負うため、Xに対して当該期間に相当する賃金を支払う必要があります。
【解説】
懲戒処分としての自宅待機命令及び業務命令としての自宅待機命令
自宅待機命令には、懲戒処分としての「出勤停止」(自宅待機)と、業務命令としての自宅待機の2種類に大別することができます。
この点、懲戒処分としての「出勤停止」とは、服務規律違反に対する制裁として労働契約を存続させながら労働者の就労を一定期間禁止することをいいます。出勤停止中は賃金が支給されず、勤続年数にもカウントされないのが通常です。
これに対して、業務命令としての自宅待機命令とは、解雇や懲戒解雇の前提として、事実関係の調査及び処分を決定するまでの間、就業を禁止することをいいます。
社員には会社に対する労務提供義務がある一方、会社に対する就労請求権はない(読売新聞社事件(東京高裁昭和33年8月2日判タ83号))ことから、会社は、就業規則上の根拠がなくても業務命令としての自宅待機命令を下すことが認められています(日通名古屋製鉄作業事件(名古屋地裁平成3年7月22日労判608号)、ネッスル(静岡出張所)事件(静岡地裁平成2年3月23日労判567号))。
自宅待機命令の有効性—業務命令権の濫用
前述のとおり、会社は業務命令としての自宅待機を下す権限が認められていますが、業務命令権の濫用とならないためには、「それ相当の事由」が存在することが必要とされています。
この点、派遣社員との不倫を非難するはがきが取引先に出回った営業担当社に対して、有給の自宅待機を命じた事案において、裁判所は、「自宅待機・・・も、労働関係上要請される信義則に照らし、合理的な制約に服すると解され、業務上の必要性が希薄であるにもかかわらず、自宅待機を命じあるいはその期間が不当に長期にわたる等の場合には、自宅待機命令は、違法性を有するものというべきである」と判示しています(ただし、当該事案においては、裁判所は、結論として、当該従業員について「そのままセールス活動を続けさせることは業務上適当ではな」いとして、2年間の有給自宅待機命令を有効と判示しています)。
このように、業務命令としての自宅待機が業務命令権の濫用とならないよう、自宅待機の期間が不当に長期にわたること等のことがないよう留意する必要があります。
自宅待機期間中の賃金支払義務
自宅待機期間中、社員は会社に対して労務を提供していないことから、会社は社員に対して賃金を支払う必要はないとも思えます。
しかし、債務の履行不能の場合の反対給付請求権の有無に関する民法536条2項及び労基法26条より、会社が社員に対して賃金を支払うことなく就労を拒否できる場合とは、当該就労拒否が会社の責に帰すことのできない事由に基づく場合に限定されており、会社は原則として、社員の自宅待機期間中の賃金支払義務を負うこととされています(京阪神急行電鉄事件(大阪地裁昭和37年4月20日))。
ただし、事故発生、不正行為の再発のおそれなど、社員の就労を許容しないことについて実質的理由が認められる場合には、例外的に賃金支払義務を負わないこととされています(日通名古屋製鉄作業事件)。
ご相談のケースについて
ご相談のケースでは、懲戒処分の前提としての事実調査のために自宅待機命令を下していることから、業務命令としての自宅待機命令を行う場合といえます。
当該自宅待機の期間は2週間ですので不当に長期とはいえず、業務命令権の濫用に該当せず適法な自宅待機命令と考えられます。もっとも、事故発生、不正行為の再発のおそれなど、社員の就労を許容しないことについて実質的理由が認められる場合でない限り、原則として会社は当該自宅待機期間中に相当する賃金支払義務を負うため、Xに対して当該期間に相当する賃金を支払う必要があります。
2 【使用者向け】健康管理①—傷病休業からの復職
【質問】
当社の社員Xは、趣味のツーリング中の事故で大けがをし、3ヶ月間の傷病休職を取得していました。
このたび、傷病休職期間満了直前に、Xから、「現場監督業務は厳しいものの、内勤はできるので内勤業務に変更させてもらって復職できないか」という復職希望を受けています。
従前の現場監督業務に復帰できないのであれば、休職期間満了とともに解雇することも検討していますが、Xの希望どおり業務を変更して復職させる必要があるのでしょうか。
【回答】
傷病休職期間の満了時において、従前の業務に復帰できるほど回復してはいないものの、より簡易な業務であれば就業でき、かつXが当該業務を希望する場合には、会社は当該業務への復職について検討する義務があり、かかる検討をせずに解雇することは解雇権の濫用として無効となる可能性があります。
【解説】
傷病休職とは
法律上明確な定義はありませんが、「休職」とは、ある従業員について労務に従事させることが不能又は不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対して労働契約関係そのものは維持させながら労務への従事を免除すること又は禁止することをいいます。
かかる「休職」のうち、「傷病休職」とは、業務外の傷病による長期欠勤が一定期間(3ヶ月〜6ヶ月程度が通常)に及んだときに行われ、当該期間中に傷病から回復し就労可能となれば復職となり、他方、回復しないまま当該期間満了となれば自然退職又は解雇となるものをいいます。
「治癒」の判断基準
前述のとおり、傷病期間中にけが等が回復せず就労可能とならなかった場合、退職又は解雇となる可能性があるため、いかなる場合に「治癒」したものといえるかが問題となります。
この点、裁判例では、復職の要件となる「治癒」とは、「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に服したときをいう」とされ(平仙レース事件(浦和地裁昭和40年12月16日))、ほぼ回復したものの従前の職務を遂行する程度には回復していない場合には、復職は労働者からの権利としては認められない、とされています。
なお、当該「治癒」の立証責任は、復職を希望する労働者側にあります。
簡易な業務への復職希望者への対応
病気療養のため現場監督業務の代わりに内勤業務を希望した労働者に対する無給の自宅待機命令について、最高裁は、「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、・・・当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務を提供することができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である」として、自宅待機命令を無効としています(片山組事件(最高裁平成10年4月9日労判736号))。
かかる最高裁判例を受けて、裁判例は、傷病休職期間満了時において、従前の業務に復帰できる状態ではないものの、より簡易な業務には就くことができ、そのような業務での復職を希望する者に対しては、使用者は現実に配置可能な業務の有無を検討する義務がある、と判断するようになっています(JR東海事件(大阪地裁平成11年10月4日労判771号))。
そして、休職期間が満了した労働者に対して、かかる検討をせずに軽易な業務を提供しないまま自然退職又は解雇を行った場合には、解雇権濫用として無効となります。
ご相談のケースについて
ご相談のケースでは、Xは傷病期間満了直前において、従前の業務よりも簡易な内勤業務への復職を希望していることから、会社には現実にXを配置可能な内勤業務がないか、その有無を検討する義務があるものといえます。
したがって、かかる検討をせずにXを解雇することは、解雇権の濫用として無効となる可能性があります。
3 【使用者向け】労働時間—研修期間中の年休取得に対する会社の時季変更権
【質問】
当社では、毎年7月に社員に対して業務に関連する法規制・倫理規制等について集合研修を実施しています。研修期間は1週間で、毎日2時間程度の研修を予定しています。
このたび、社員Xから、当該研修期間に重なる日程での年休申請を受けましたが、基本的に全社員がこの集合研修に参加することを義務づけているため、会社としては別の日に変更してもらえないか検討しています。
会社はXに対して、研修期間に重ならない期間で有給を取得するよう、変更することができるでしょうか。
【回答】
Xに対する時季変更権が認められるかは、当該集合研修の内容・必要性、研修期間、参加の非代替性等を考慮してケースバイケースで判断されます。
ご相談のケースでの研修の内容が一般的な法規制・倫理規制等の研修に留まり、X本人が参加しなくても事後的なE—ラーニング等で補えるのであれば、会社による時期変更権の行使が認められない可能性があります。
【解説】
社員の年次有給休暇
労基法39条5項は、「使用者は、・・・有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と規定しています。
この点、最高裁判決によれば、労働者たる社員がその有する休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは、客観的に「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当し、かつ、これを理由として使用者たる会社が時季変更権を行使しない限り、社員による時季指定によって、会社の承認がなくても社員は年次有給休暇を取得する、と解しています(全林野白石営林署未払賃金請求事件(最高裁昭和48年3月2日労判171号))。
したがって、他の時季の有給申請を希望する会社としては、「会社の承認がない以上、年休取得は認められない」と主張することはできず、別途時季変更権を行使する必要があります。
社員の時季指定権
もっとも、社員による時季指定にも一定の限界があります。
たとえば、タクシーの運転手が深夜乗務を拒否するために行った年次有給休暇の時季指定について、権利の濫用であり無効とした裁判例があります(東京高裁平成11年4月20日労判1682号)。
この場合、会社が時期変更権を行使しなくても、そもそも権利の濫用として社員による年次有給休暇は成立しないこととなります。
会社の時季変更権
前述のとおり、会社の時季変更権は、社員による年休の時季指定権の効果発生を阻止するものといえます。その行使方法としては、「指定された年休日には事業の正常な運営を妨げる事由が存在する」という内容のものであれば足り、請求された年休について、単に「承認しない」という意思表示であっても時季変更権行使の意思表示に当たるとされています。
問題は、いかなる場合に時季変更事由である「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか、ですが、当該労働者の年休指定日の労働がその労働者の担当業務を含む相当な単位の業務の運営にとって不可欠であり、かつ、代替要員を確保するのが困難であることが必要とされています。したがって、たとえ業務運営に不可欠な社員からの年休申請であっても、会社が代替要員確保の努力をしないまま直ちに時季変更権を行使することは認められません。
一般的には、他の社員の休暇・欠勤の状況等により必要な人員確保が困難である場合、特定の時季に行うことが重要である業務について代替要員による対応では業務の遂行が困難又は意味をなさない場合等が「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当する、と解されています。
研修期間中の年休取得と時季変更権
年休申請期間における業務が日常的なルーティンワークではなく、集合研修等、以前から予定されていた特別な業務である場合には、「事業の正常な運営を妨げる」場合に該当するとして、会社による時季変更権が認められやすいといえますが、この場合も一切の年休取得が認められないわけではありません。
当該集合研修の内容・必要性、研修期間、参加の非代替性(本人が参加しなければならないか)等を考慮して判断され、研修自体に高度の必要性があり、参加が非代替的な場合(本人が参加してこそ意味がある場合)は、当該社員が研修を欠席しても予定された知識、技能の習得に不足を生じさせないと認められない限り、会社は時季変更権を行使することができる、とされています(日本電信電話事件(最高裁平成12年3月31日労判781号))。
ご相談のケースについて
Xに対する時季変更権が認められるかは、当該集合研修の内容・必要性、研修期間、参加の非代替性等を考慮してケースバイケースで判断されます。
ご相談のケースでの研修の内容が一般的な法規制・倫理規制等の研修に留まり、X本人が参加しなくても事後的なE—ラーニング等で補えるのであれば、会社による時期変更権の行使が認められない可能性があります。
4 【使用者向け】労働時間—休憩時間中の待機対応と労働時間
【質問】
当社では、セキュリティ上の観点から、交代制でビル管理者を配置しており、ビル管理社は仮眠室で待機し、警報が作動したり電話が鳴ったりしたときには24時間態勢で必要な対応をとることとしています。
このたび、ビル管理者Xから、「仮眠室での待機時間も労働時間に当たるはずなので、その分の賃金を払って欲しい」との要求を受けました。たしかに仮眠時間中でも電話が鳴ることはちょくちょくありますし、電話ほどではないにせよ、警報が作動したことも一度や二度ではありません。しかし、基本的には仮眠時間として休憩してもらっているのですから、その分の賃金を支払う必要はないと考えているのですが、当社は賃金支払義務を負うのでしょうか?
【回答】
Xは、警報が作動したり電話が鳴ったりしたときには24時間態勢で必要な対応をとることが義務づけられていたことからすると、仮眠時間中も労働からの解放が保障されていたとはいえず、過去の判例に照らしても仮眠室での待機は労働時間に該当する可能性が高いといえます。
したがって、会社には、Xの仮眠時間に相当する賃金を支払う義務を負う可能性が高いと思われます。
【解説】
労働時間とは
労働時間とは、使用者の指揮命令下で、労働力を提供した時間をいいます。
三菱重工業長崎造船所事件最高裁判決(最高裁平成12年3月9日労判778号)によれば、労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に決まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めいかんにより決定されるべきものではない」と判示しています。
したがって、実作業に従事している時間だけでなく、作業の準備や後処理を行っている時間、また、待機している時間も実労働時間に含まれます。
休憩時間とは
休憩時間とは、勤務時間の途中で、社員が精神的、肉体的に一切の労働から離れることを保障されている時間をいい、労働時間には含まれず(労基法32条)、賃金支払い義務の対象とはなりません。
他方、現実に作業はしていないものの、会社からいつ就労の要求があるかもしれない状態で待機している、いわゆる手待時間は、完全に労働から離れることを保障されている時間とはいえないため、休憩時間には該当せず、労働時間となります。
仮眠室での待機と休憩時間
仮眠室での待機が労働時間に該当するのか、それとも休憩時間に該当するのかの判断基準について、大星ビル管理事件最高裁判決(最高裁平成14年2月28日労判822号)は、「労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」としつつ、「労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が・・・労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たる」と判示しています。
続けて、最高裁は、「仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務づけられて」いて、「その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務づけがなされていないと認めることができるような事情」がないとして、労働時間にあたる、と結論付けています。
なお、行政解釈も、電話や来客対応のために待機している時間は労働時間になる、と解しています(平成11年3月31日基発168号)。
ご相談のケースについて
Xは、警報が作動したり電話が鳴ったりしたときには24時間態勢で必要な対応をとることが義務づけられていたことからすると、仮眠時間中も労働からの解放が保障されていたとはいえず、過去の判例に照らしても仮眠室での待機は労働時間に該当する可能性が高いといえます。
したがって、会社には、Xの仮眠時間に相当する賃金を支払う義務を負う可能性が高いと思われます。
5 【使用者向け】労働時間—社員による無断残業への対応
【質問】
最近のワークライフバランスを尊重する風潮を受け、また、残業代による人件費の高騰を防ぐべく、当社では定時に帰宅できるよう効率的な業務の遂行を励行し、無駄な残業をやめるよう繰り返し社員にアナウンスしてきています。
ところが、社員の一部には、自宅に居場所がないのか生活費を稼ぎたいからかはわかりませんが、残業時間の管理がいわゆる自己申告制であることをいいことに、必要もないのに就業時間後も居残り、残業時間として申告しています。この問題社員が担当している業務は、基本的には帳簿を管理する等の単純な事務作業であり、到底勤務時間内に終了できない量ともいえないのですが、何度注意しても居残り残業を止めようとせず、困っています。
この場合でも、会社はこの社員に対して残業代を支払わなければいけないのでしょうか?
【回答】
会社が明示的に残業命令をしていなくても、社員による勝手な残業を放置していると、黙示的な残業命令があったものとして、会社に時間外労働に係る割増賃金の支払義務が肯定される可能性があります。
ご相談のケースでは、従前から定時での帰宅を励行し、無駄な残業を止めるよう繰り返しアナウンスしてきており、また、問題社員に対しても直接残業を止めるよう注意してきていること、さらに業務量も労働時間内に終了できるような量であり時間外労働をせざるを得ない客観的な事情があるとはいえないと思われますので、黙示の残業命令は認められる可能性は低く、会社が残業代として割増賃金を支払う必要はないものと思われます。
【解説】
労働時間と時間外労働
「労働時間—休憩時間中の対応と労働時間」で解説したとおり、労働時間とは、使用者の指揮命令下で、労働力を提供した時間をいいます。
三菱重工業長崎造船所事件最高裁判決(最高裁平成12年3月9日労判778号)によれば、労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に決まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めいかんにより決定されるべきものではない」と判示しています。
したがって、会社の残業命令がないなど、会社の指揮命令下になく、社員が勝手に居残って作業をしている場合、「労働時間」に含まれないため、本来であれば労働基準法上の時間外労働として取り扱う必要はありません。
黙示の時間外労働
もっとも、「使用者の指揮命令」は、明示的である必要はなく、「使用者の明示又は黙示の指示により業務に従事する」場合も労働時間に含まれるとされており、黙示的な残業命令であっても会社の指揮命令下にあったものと判断されることとなります(神代学園ミューズ音楽院事件(東京高裁平成17年3月30日労判905号)、静岡県教育委員会事件(最高裁昭和47年4月6日労判153号))。
具体的には、残業で業務を処理することを当然のこととして上司が黙認していた場合や、業務上やむを得ない事由があり時間外労働をしていた場合など、時間外労働をせざるを得ない客観的な事情がある場合には、黙示の時間外労働命令があったものと認められる傾向にあります。
たとえば、工事管理者が勤務時間外に業務を行っていたことについて、「業務が所定労働時間内に終了し得ず、残業が恒常的となっていたと認められる」として、黙示の残業指示があったと認定し、労働時間制を肯定した裁判例(とみた建設事件(名古屋地裁平成3年4月22日労判589号))や、従業員が勤務時間外に業務を行っていたことについて、従業員が業務内容や勤務時間を詳細に記録して提出し、上司がその内容を確認していたことから、「時間外勤務を知っていながらこれを止めることはなかったというべきであり、少なくとも黙示の時間外勤務命令は存在した」として、労働時間制を肯定した裁判例(ピーエムコンサルタント(契約社員年俸制)事件(大阪地裁平成17年10月6日労判907号))等があります。
ご相談のケースについて
仮眠室での待機が労働時間に該当するのか、それとも休憩時間に該当するのかの判断基準について、大星ビル管理事件最高裁判決(最高裁平成14年2月28日労判822号)は、「労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」としつつ、「労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が・・・労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たる」と判示しています。
続けて、最高裁は、「仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務づけられて」いて、「その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務づけがなされていないと認めることができるような事情」がないとして、労働時間にあたる、と結論付けています。
なお、行政解釈も、電話や来客対応のために待機している時間は労働時間になる、と解しています(平成11年3月31日基発168号)。
ご相談のケースについて
前述のとおり、会社が明示的に残業命令をしていなくても、社員による勝手な残業を放置していると、黙示的な残業命令があったものとして、会社に時間外労働に係る割増賃金の支払義務が肯定される可能性があります。
ご相談のケースでは、従前から定時での帰宅を励行し、無駄な残業を止めるよう繰り返しアナウンスしてきており、また、問題社員に対しても直接残業を止めるよう注意してきていること、さらに業務量も労働時間内に終了できるような量であり時間外労働をせざるを得ない客観的な事情があるとはいえないと思われますので、黙示の残業命令は認められる可能性は低く、会社が残業代として割増賃金を支払う必要はないものと思われます。
6 【使用者向け】労働時間—社員による無断残業に対する防止策
【質問】
最近のワークライフバランスを尊重する風潮を受け、また、残業代による人件費の高騰を防ぐべく、当社では定時に帰宅できるよう効率的な業務の遂行を励行し、無駄な残業をやめるよう繰り返し社員にアナウンスしてきています。
ところが、社員の一部には、自宅に居場所がないのか生活費を稼ぎたいからかはわかりませんが、残業時間の管理がいわゆる自己申告制であることをいいことに、必要もないのに就業時間後も居残り、残業時間として申告しています。この問題社員が担当している業務は、基本的には帳簿を管理する等の単純な事務作業であり、到底勤務時間内に終了できない量ともいえないのですが、何度注意しても居残り残業を止めようとせず、困っています。
こうした問題社員による無断残業を防ぐためには、どのようにしたらよいでしょうか。
【回答】
会社は労働時間管理義務を負っているところ、会社が適切な労働時間管理を怠ったために社員が残業時間の立証ができない場合、社員からの残業代支払請求に対して会社側に不利な事実認定がなされる可能性もあることから、業務フローを見直す等して社員の労働時間・残業労働を適切に管理することが大切です。
また、労働時間の管理方法にはいくつかの方法がありますが、自己申告制は無駄な残業を誘発するおそれ等もあることから、上司による事前チェックを要する事前命令制へ変更することも検討に値します。
【解説】
会社の労働時間管理義務
「労働時間—社員による無断残業」で解説したとおり、会社が明示的に残業命令を発していなくても、社員による勝手な残業を黙認していると、黙示の残業命令があったものして、会社が当該時間外労働に係る割増賃金の支払義務を負う可能性があります。
この点、会社は、労働基準法上、賃金台帳調整義務の一環としての労働時間記録義務や、労働時間の記録に関する書類等の労働関係重要書類保存義務等の労働時間管理義務を負っており(労基法108条、労基法施行規則54条1項、労基法109条)、かかる義務に違反した場合、罰則を科され得ます(労基法120条1号)。
また、残業の存在自体は明らかであるものの、会社が適切な労働時間管理を怠ったために社員が残業時間の立証ができない場合、社員の立証負担が軽減され、概括的に残業時間を推認し社員の割増賃金請求を認めた裁判例もあるとおり(京都銀行事件(大阪高裁平成13年6月28日労判811号)、ゴムイナキ事件(大阪高裁平成17年12月1日労判933号))、会社が適切な労働時間管理義務を怠った結果、会社側に不利な認定がされてしまう場合もあります。
このように、社員による無断残業を防ぐためだけでなく、会社には労働時間管理義務の一環として、社員の申告した残業時間が実際の労働時間と合致しているか、確認する義務があります。
社員の労働時間の適切な管理
実務上、社員の労働時間を管理する方法として、上司による現認や、タイムカード、ICカードによる方法等があります。また、研究開発職等、一定の裁量の範囲内で自己管理の下に業務を行うホワイトカラー社員が多い職場においては、自己申告制が採用されているケースもあります。
もっとも、自己申告制のデメリットとして、労働時間の管理が中途半端な場合、業務処理上必要のない居残り残業を誘発したり、実際に残業した時間よりも少なく申告するサービス残業を固定化するおそれがあります。
かかる事態を受け、厚労省は、自己申告制の労働時間管理にについて会社が講ずべき措置として、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年4月6日基発339号)において、以下の措置を講ずるよう掲げています。
- 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
- 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
- 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定する等の措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当ての低額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
業務フロー及び残業管理方法の見直し
会社による適切な労働時間の管理ももちろん大切ですが、そもそも会社の業務フローが残業を前提としたものになっていないかを見直すことも重要です。会社の業務計画に無理がないか、人員が適正に配置されているか等、再度確認することが大切です。
また、前述のとおり、自己申告制には問題が多いことから残業の自己申告制自体を廃止し、事前に上司による残業命令がない場合は残業を一切認めない事前命令制に変更するといった対策も考えられます。具体的には、残業を行う社員が、上司に対して残業の要否及び見込み終了時間を記載した残業申請書を就業時間内に提出し、上司が就業時間内に残業命令を出すこととなります。事前命令制では、上司が残業の要否を事前にチェックするため、残業代稼ぎを目的とした居残り残業や、自発的なサービス残業を未然に防ぐことが期待できます。
7 【使用者向け】労働時間—休日出勤をした社員への割増賃金の要否
【質問】
当社は広告物の印刷業を営んでおり、原稿の締切直前はいつも繁忙期となり、一部の社員は休日に出勤する場合もあります。そのため、当社の就業規則では、こうした繁忙期に休日出勤した社員に対して代休を付与することとしていますが、とくに休日出勤に係る割増賃金を支払う旨の規定は置いておりません。
ところが、このたび、休日出勤をした社員Xから、代休取得申請とともに、「休日出勤をしたのだから、その分の割増賃金を支払って欲しい」との請求を受けました。当社はXに対して、代休だけでなく割増賃金も支払わなければならないのでしょうか。
【回答】
代休を取得したとしても、Xが休日に出勤して休日労働をした事実に代わりはありませんので、会社はXに対して代休取得を認めるとともに、休日労働に係る割増賃金を支払う義務を負います。
なお、実務上は、代休日の消滅した賃金請求権と、当該割増賃金を相殺して、割増部分のみ支払うのが一般的です。
【解説】
休日振替と代休
代休と類似した概念として休日振替があるところ、休日振替とは、定められた休日と所定労働日を「事前に」変更することをいい、振替の結果休日とされた日のことを振替休日といいます。
これに対して、代休とは、事前に休日の変更をせず、休日労働させた代わりに、「事後的に」所定労働日の労働義務を免除して休ませることをいいます。
このように、両者は事前の振替か事後の振替かという違いがあるとともに、労基法上の取扱いも異なります。
具体的には、休日振替によって、本来の休日が労働日となるため、当該休日における労働について三六協定(労基法36条1項)も休日労働の割増賃金の支払も不要となります。ただし、休日振替によって労働時間が週40時間を超えることになる場合は、超えた部分が時間外労働となるため、三六協定又は臨時の必要の要件(労基法33条1項)、時間外労働割増賃金(労基法37条1項)が必要となることに留意する必要があります。
代休の付与
これに対して、代休の場合、休日振替と異なり休日は休日のままとして取り扱われるため、社員を休日に労働させた事実はそのまま残ります。
したがって、上記三六協定又は臨時の必要の要件、割増賃金等の休日労働に係る規制が適用されることになります。
なお、労基法上、会社には社員に対して代休を与えるべき義務は規定されていないため、就業規則等、労働契約で代休を付与する旨の定めがない限り、社員に対して代休を付与する義務はありません。
また、就業規則等において代休に関する規定を置く場合であっても、それが労基法上の制度でない以上、取得手続や申請期間等の代休のないようについては会社が自由に定めることができるとともに、代休日の定め方について週休制原則(労基法35条)は適用されません。
ご相談のケースについて
Xに対して代休を与える必要があるかは、労基法の問題ではなく、就業規則等に代休付与に関する定めがあるか否かによります。ご相談のケースでは、会社の就業規則中に代休付与に関する規定があるとのことですので、労働契約上、会社はXに対して代休を付与する必要があります。
次に、Xに対して割増賃金を支払う義務があるかですが、代休を取得したとしても、Xが休日に出勤して休日労働をした事実は変わりませんので、会社はXに対して代休とともに休日労働に係る割増賃金を支払う義務を負います。
なお、実務上は、代休日の消滅した賃金請求権と、当該割増賃金を相殺して、割増部分(35%)のみ支払うのが一般的です。
菅野和夫「労働法第十一版」(株式会社弘文堂)
(注)本記事の内容は、記事掲載日時点の情報に基づき作成しておりますが、最新の法例、判例等との一致を保証するものではございません。また、個別の案件につきましては専門家にご相談ください。