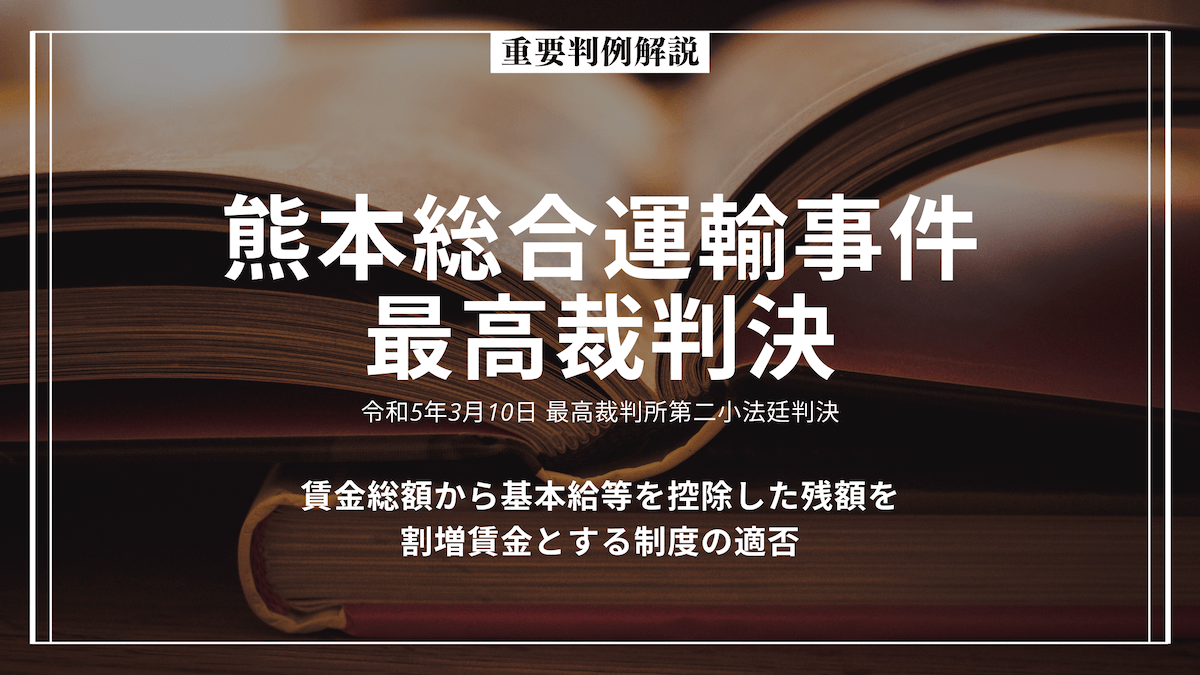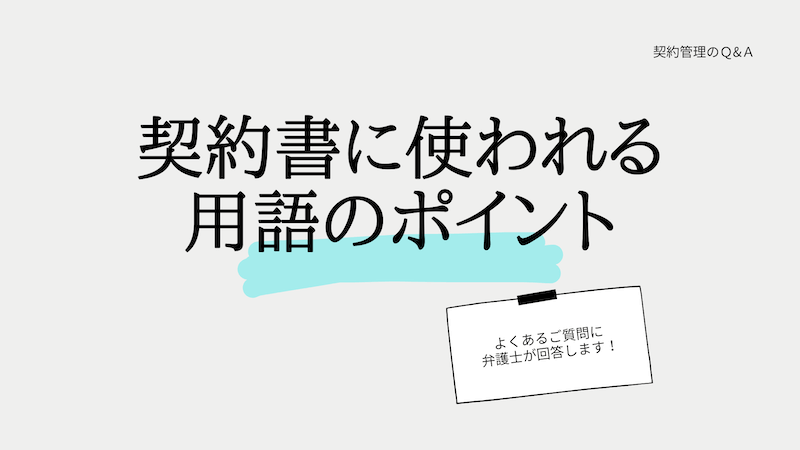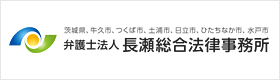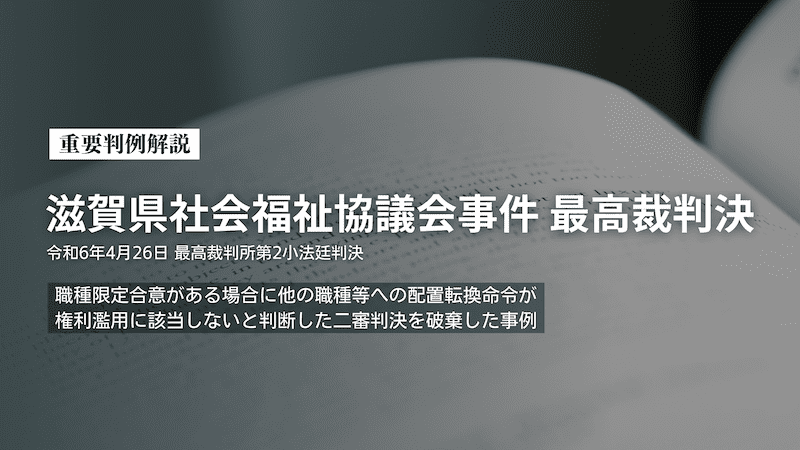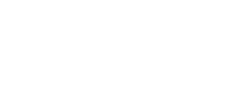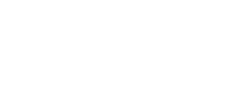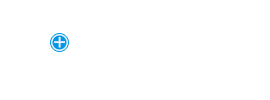(令和5年7月20日 最高裁判所第一小法廷 判決)
同一労働同一賃金における定年後再雇用職員の基本給・賞与等の待遇差
Ⅰ はじめに 本稿の趣旨
令和5年7月20日、最高裁判所第一小法廷において、正職員(無期雇用)と定年後再雇用職員(有期雇用)との間における①基本給及び②賞与に関する待遇差について、労働契約法20条に違反するか否かが争われた裁判の判決が下されました(令和4年(受)第1293号地位確認等請求事件・令和5年7月20日 最高裁判所第一小法廷 判決)。
なお、以下では、特に断りがなければ、本件の第一審原告(定年後再雇用職員)を単に「原告」、第一審被告(株式会社)を単に「被告」と表記します。
本件は、自動車学校で勤務していた原告ら定年退職後再雇用された嘱託職員が、正職員との間の待遇差が不合理であると訴えた事案です。
本件の審理経過は以下のとおりです。
-
- 第一審:令和2年10月28日 名古屋地方裁判所民事第1部 判決(PDF)|裁判所HP
- 第二審:令和4年3月25日 名古屋高等裁判所 判決
- 第三審:令和5年7月20日 最高裁判所第一小法廷 判決(PDF)|裁判所HP
第一審は、①基本給に関し、原告ら嘱託職員の基本給が正職員定年退職時の基本給の60%を下回る限度で労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる、②賞与に関し、基本給を正職員定年退職時の60%の金額を乗じた結果を下回る限度で労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる、という判断を下したことで、大きな注目を集めました。
第二審も、原審の判断を維持し、①基本給及び②賞与に関する原告ら嘱託職員と正職員の待遇差は、60%を下回る限度で違法であると判断しました。
基本給及び賞与は、一般に労働契約に基づく労働の対償の中核であり、およそ人を雇用するすべての企業において、労働条件を設定する上で避けて通ることができない労働条件の一つといえます。
一方、定年後再雇用労働者に対しては、基本給、賞与を始めとした労働条件について、定年前とは大きな相違を設定するという賃金体系を採用する企業は少なくありません。
こうした賃金体系を採用する企業にとって、定年退職後再雇用された嘱託職員と正職員との間の基本給及び賞与に関する待遇差が違法であると判断した本件は、今後の賃金体系を再考する上で注目されていました。
第一審、第二審のいずれも①基本給及び②賞与に関する原告ら嘱託職員と正職員の待遇差は違法であると判断する中、最高裁がどのような判断を下すかが注目されていました。
このような経過を辿る中、最高裁は、①基本給及び②賞与に関する待遇差に関し、原審(第二審)の判断は労働契約法20条の解釈を誤った違法があるとして破棄した上、本件の審理を原審である名古屋高等裁判所に差し戻すという判断を下しました。
本稿では、本件の事実関係の概要を整理するとともに、本件が与える実務上の影響について考察したいと思います。なお、本稿の内容は、あくまでも筆者の一考察に過ぎないことにご留意ください。
※第一審である令和2年10月28日名古屋地方裁判所民事第1部判決の解説は、以下の論考をご参照ください。
[blogcard url=”https://houmu.nagasesogo.com/media/column/column-2781/”]
本件の概要
1 事案の概要
本件は、自動車学校の経営等を目的とする株式会社である被告を定年退職した後に、有期労働契約を被告と締結して就労していた原告らが、無期労働契約」という。)を被告と締結している正職員との間に、労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張して、被告に対し、不法行為に基づき、上記相違に係る損害賠償を求めるなどの請求をするものです。
2 事実関係等の概要
(1)労働条件の相違等
本件における正職員と原告ら嘱託職員の労働条件等は、以下の一覧表をご参照ください。
| 労働条件 | 正職員 | 定年退職後再雇用者(嘱託職員) (原告2名) |
|---|---|---|
| 就業規則 | 正職員に適用される就業規則及び給与規程 | 嘱託規程 |
| 定年制 | 満60歳が定年であり、定年に達した日の翌日に退職 | 期間1年間の有期労働契約を締結し、これを更新することで原則として65歳まで再雇用する |
| 基本給 | 一律給+功績給 | 嘱託職員の賃金体系は勤務形態によりその都度決め、賃金額は本人の経歴、年齢その他の実態を考慮して決める 正職員定年退職時に比べ減額して支給 |
| 役付手当 | 正職員が主任以上の役職に就いている場合、当該役職の区分に応じて支給する | 支給なし |
| 家族手当 | (1)所得税法上の控除対象配偶者、(2)満20歳未満で所得税法上の扶養親族に該当する子女を扶養家族とする場合、その人数に応じて支給する | 支給なし |
| 皆精勤手当 | 正職員が所定内労働時間を欠落なく勤務した場合に支給する | 正職員定年退職時に比べ減額して支給 |
| 敢闘賞 | 施設ごとに定めた基準に基づき、正職員が1か月に担当した技能教習等の時間数に応じ、職務精励の趣旨で支給する | 正職員定年退職時に比べ減額して支給 |
| 賞与 | 夏季及び年末の2回 各季の賞与は、各季で正職員一律に設定される掛け率を各正職員の基本給に乗じ、さらに当該正職員の勤務評定分(10段階)を加算する方法で算定される |
原則として支給しない 例外的に、正職員の賞与とは別に勤務成績を勘案して支給することがある 嘱託職員一時金として支給されていた |
| 項目 | 内訳 | 金額 |
|---|---|---|
| 被告の正職員の基本給 | 被告全体の正職員の基本給平均額 | 月額14万円前後 |
| 若年正職員の基本給平均額 | 月額約11万2000円から約12万5000円 | |
| 勤続30年以上の正職員の基本給平均額 | 月額約16万7000円から約18万円 | |
| 平成25年賃金センサス 産業計・男女計・学歴計 55歳ないし59歳 |
「きまって支給する現金支給額」 | 月額37万3500円(男計であれば42万0900円) |
| 「所定内給与額」 | 月額35万1300円(男計であれば39万4800円) | |
| 「年間賞与その他特別給与額」 | 年額101万1900円(男計であれば118万4900円) | |
| 平成25年賃金センサス 産業計・男女計・学歴計 60歳ないし64歳 |
「きまって支給する現金支給額」 | 月額27万5800円(男計であれば29万6300円) |
| 「所定内給与額」 | 月額26万2100円(男計であれば28万1100円) | |
| 「年間賞与その他特別給与額」 | 年額49万7000円(男計であれば54万3300円) | |
| 平成26年賃金センサス 産業計・男女計・学歴計 55歳ないし59歳 |
「きまって支給する現金支給額」 | 月額38万3600円(男計であれば43万2600円) |
| 「所定内給与額」 | 月額36万8000円(男計であれば40万6100円) | |
| 「年間賞与その他特別給与額」 | 年額108万9700円(男計であれば127万7800円) | |
| 平成26年賃金センサス 産業計・男女計・学歴計 60歳ないし64歳 |
「きまって支給する現金支給額」 | 月額28万0600円(男計であれば30万0500円) |
| 「所定内給与額」 | 26万6500円(男計であれば28万4700円) | |
| 「年間賞与その他特別給与額」 | 年額55万1600円(男計であれば60万6300円) | |
| 原告1 | 定年退職時の基本給 | 月額18万1640円 |
| 嘱託職員時の基本給【45%以下】 | 1年目が月額8万1738円 その後低下し、最終年まで月額7万4677円 |
|
| 定年退職前の3年間の賞与 | 1回当たり平均約23万3000円 | |
| 嘱託職員時の一時金(賞与と同時期) | 1回当たり8万1427円から10万5877円 | |
| 原告2 | 定年退職時の基本給 | 月額16万7250円 |
| 嘱託職員時の基本給【48.8%以下】 | 1年目が月額8万1700円 その後低下し、最終年まで月額7万2700円 |
|
| 定年退職前の3年間の賞与 | 1回当たり平均約22万5000円 | |
| 嘱託職員時の一時金(賞与と同時期) | 1回当たり7万3164円から10万7500円 |
※ 原告とは「一審原告」、被告とは「一審被告」をいう。
(2)職務内容等の異同
また、正職員と原告ら嘱託職員の職務内容等の異同については、以下のように整理されています(第一審)。
- ① 原告2名は、正職員を定年退職し嘱託職員となって以降も、従前と同様に教習指導員として勤務をしていた。
- ② 再雇用に当たり主任の役職を退任したこと以外、定年退職の前後で、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(「職務の内容」)に相違はなかった。
- ③ 当該職務の内容及び配置の変更の範囲(「職務内容及び変更範囲」)にも相違はなかった。
3 本件の争点
本件では、正職員と原告ら嘱託職員との間における、①基本給、②皆精勤手当、③敢闘賞、④家族手当、⑤賞与の待遇差が、労働契約法20条に違反するかどうかが争点となりました。
4 本件の争点に関する判断経過
上記争点に関し、第一審及び第二審の判断の概要は以下のとおりです。
| 争点 | 第一審 (名古屋地判R2.10.28) |
第二審 (名古屋高判R4.3.25) |
第三審 (最高裁R5.7.20) |
|---|---|---|---|
| 基本給 | 嘱託職員時の基本給が正職員定年退職時の基本給の60%を下回る限度で違法 | 嘱託職員時の基本給が正職員定年退職時の基本給の60%を下回る限度で違法 | 違法ではない (原審に差し戻す) |
| 家族手当 | 違法ではない | 違法ではない | – |
| 皆精勤手当 | 減額は違法 | 減額は違法 | – |
| 敢闘賞 | 減額は違法 | 減額は違法 | – |
| 賞与 | 基本給を正職員定年退職時の60%の金額を乗じた結果を下回る限度で違法 | 基本給を正職員定年退職時の60%の金額を乗じた結果を下回る限度で違法 | 違法ではない (原審に差し戻す) |
5 原審(第二審)の判断
前記のとおり、原審(第二審)は、第一審の判断を維持し、③家族手当の待遇差は違法ではないものの、②皆精勤手当、③敢闘賞に加え、①基本給及び⑤賞与に関する待遇差も違法であると判示しました。
原審(第二審)の判断概要は、以下のとおりです。
被上告人らについては、定年退職の前後を通じて、主任の役職を退任したことを除き、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲に相違がなかったにもかかわらず、嘱託職員である被上告人らの基本給及び嘱託職員一時金の額は、定年退職時の正職員としての基本給及び賞与の額を大きく下回り、正職員の基本給に勤続年数に応じて増加する年功的性格があることから金額が抑制される傾向にある勤続短期正職員の基本給及び賞与の額をも下回っている。このような帰結は、労使自治が反映された結果でなく、労働者の生活保障の観点からも看過し難いことなどに鑑みると、正職員と嘱託職員である被上告人らとの間における労働条件の相違のうち、被上告人らの基本給が被上告人らの定年退職時の基本給の額の60%を下回る部分、及び被上告人らの嘱託職員一時金が被上告人らの定年退職時の基本給の60%に所定の掛け率を乗じて得た額を下回る部分は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。
6 第三審(最高裁)の判断内容
これに対し、最高裁は、①基本給及び⑤賞与の点について新たな判断を下しました。
(1)労働契約法20条の判断基準
最高裁は、労働契約法20条違反の判断基準について、メトロコマース事件最高裁判決(最高裁判所第三小法廷判決令和2年10月13日)(令和元年(受)第1190号、第1191号 損害賠償等請求事件)を引用し、以下のように判示しました。
[blogcard url=”https://houmu.nagasesogo.com/media/column/column-2274/”]
労働契約法20条は、有期労働契約を締結している労働者と無期労働契約を締結している労働者の労働条件の格差が問題となっていたこと等を踏まえ、有期労働契約を締結している労働者の公正な処遇を図るため、その労働条件につき、期間の定めがあることにより不合理なものとすることを禁止したものであり、両者の間の労働条件の相違が基本給や賞与の支給に係るものであったとしても、それが同条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得るものと考えられる。もっとも、その判断に当たっては、他の労働条件の相違と同様に、当該使用者における基本給及び賞与の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸事情を考慮することにより、当該労働条件の相違が不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべきものである(最高裁令和元年(受)第1190号、第1191号同2年10月13日第三小法廷判決・民集74巻7号1901頁参照)。
第一審は、ハマキョウレックス事件最高裁判決を引用し労働契約法20条に違反するかどうかの評価根拠事実に関する主張立証責任の所在を明確にした上で、長澤運輸事件最高裁判決も引用し、定年退職後再雇用されたことを、労働契約法20条の不合理性の判断要素である「その他の事情」として考慮することを明示していましたが、最高裁はメトロコマース事件最高裁判決の判断枠組みを採用したことになります。
本件最高裁は、「当該使用者における基本給及び賞与の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸事情を考慮する」と明示し、性質や目的を考慮することを正面から提示したことになります。
(2)①基本給について
以上を踏まえ、本件最高裁は、①基本給に関する待遇差について、以下のように判示しました。
※下線部は筆者追記
以上を前提に、正職員と嘱託職員である被上告人らとの間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について検討する。
ア
前記事実関係によれば、管理職以外の正職員のうち所定の資格の取得から1年以上勤務した者の基本給の額について、勤続年数による差異が大きいとまではいえないことからすると、正職員の基本給は、勤続年数に応じて額が定められる勤続給としての性質のみを有するということはできず、職務の内容に応じて額が定められる職務給としての性質をも有するものとみる余地がある。
他方で、正職員については、長期雇用を前提として、役職に就き、昇進することが想定されていたところ、一部の正職員には役付手当が別途支給されていたものの、その支給額は明らかでないこと、正職員の基本給には功績給も含まれていることなどに照らすと、その基本給は、職務遂行能力に応じて額が定められる職能給としての性質を有するものとみる余地もある。
そして、前記事実関係からは、正職員に対して、上記のように様々な性質を有する可能性がある基本給を支給することとされた目的を確定することもできない。
また、前記事実関係によれば、嘱託職員は定年退職後再雇用された者であって、役職に就くことが想定されていないことに加え、その基本給が正職員の基本給とは異なる基準の下で支給され、被上告人らの嘱託職員としての基本給が勤続年数に応じて増額されることもなかったこと等からすると、嘱託職員の基本給は、正職員の基本給とは異なる性質や支給の目的を有するものとみるべきである。
しかるに、原審は、正職員の基本給につき、一部の者の勤続年数に応じた金額の推移から年功的性格を有するものであったとするにとどまり、他の性質の有無及び内容並びに支給の目的を検討せず、また、嘱託職員の基本給についても、その性質及び支給の目的を何ら検討していない。
イ
また、労使交渉に関する事情を労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮するに当たっては、労働条件に係る合意の有無や内容といった労使交渉の結果のみならず、その具体的な経緯をも勘案すべきものと解される。
前記事実関係によれば、上告人は、被上告人X1及びその所属する労働組合との間で、嘱託職員としての賃金を含む労働条件の見直しについて労使交渉を行っていたところ、原審は、上記労使交渉につき、その結果に着目するにとどまり、上記見直しの要求等に対する上告人の回答やこれに対する上記労働組合等の反応の有無及び内容といった具体的な経緯を勘案していない。
ウ
以上によれば、正職員と嘱託職員である被上告人らとの間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある。
本件最高裁は、基本給の①性質と②目的という点に関し、正職員と嘱託職員の間には相違があると指摘した上で、③労使交渉に関する事情を「その他の事情」として考慮する場合には労使交渉の結果だけでなく具体的な経緯も勘案すべきであると指摘し、原審の労働契約法20条の解釈適用には誤りがあると判断しました。
(3)⑤賞与について
次に、本件最高裁は、⑤賞与に関する待遇差について、以下のように判示しました。
※下線部は筆者追記
次に、正職員と嘱託職員である被上告人らとの間で賞与と嘱託職員一時金の金額が異なるという労働条件の相違について検討する。
前記事実関係によれば、被上告人らに支給された嘱託職員一時金は、正職員の賞与と異なる基準によってではあるが、同時期に支給されていたものであり、正職員の賞与に代替するものと位置付けられていたということができるところ、原審は、賞与及び嘱託職員一時金の性質及び支給の目的を何ら検討していない。
また、上記イのとおり、上告人は、被上告人X1の所属する労働組合等との間で、嘱託職員としての労働条件の見直しについて労使交渉を行っていたが、原審は、その結果に着目するにとどまり、その具体的な経緯を勘案していない。
このように、上記相違について、賞与及び嘱託職員一時金の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある。
最高裁は、賞与に関しても、基本給と同様、原審が賞与及び嘱託職員一時金の性質及び支給の目的を検討していない、労使交渉について結果に着目するだけで具体的な経緯を勘案していない、ことを理由に、原審の労働契約法20条の解釈適用には誤りがあると判断しました。
Ⅱ 本件の実務上の影響
本件最高裁は、基本給及び賞与に関する待遇差に関し、原審(第二審)の判断は労働契約法20条の解釈を誤った違法があるとして破棄した上、本件の審理を原審である名古屋高等裁判所に差し戻すという判断を下しました。
本件第一審及び第二審は、基本給及び賞与に関する待遇差について、基本給に関する待遇差について、詳細な金額の対比をした上で、不合理性の評価を基礎づける事実と、妨げる事実を整理するなどして検証していました。
しかしながら、本件最高裁は、正職員と嘱託職員に対する基本給及び賞与の性質と目的の異同、並びに「その他の事情」としての労使交渉は結果だけでなく具体的な経緯も勘案する必要があると指摘し、原審(第二審)の解釈適用を誤っていると判断しました。
本件最高裁の今後の影響として考慮すべき事項として、以下の点が挙げられます。
1 基本給・賞与の待遇差も違法となる可能性自体は否定されていない
本件は、結論として基本給及び賞与に関する待遇差を違法と判断した第二審の判断を破棄・差し戻していますが、基本給及び賞与に関する待遇差がすべて違法ではないとは判断していません。
本件最高裁も、「両者の間の労働条件の相違が基本給や賞与の支給に係るものであったとしても、それが同条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得るものと考えられる。」と述べ、基本給及び賞与に関する待遇差が違法となる場合があることを認めてはいます。
2 差し戻し後の判断を待つ必要がある
本件最高裁は、原審(第二審)が基本給及び賞与の性質及び目的、また労使交渉の具体的な経緯を考慮していないことを理由に破棄・差し戻しをしています。
差し戻し後の名古屋高等裁判所において、どのような性質及び目的等の相違であれば、どの程度の待遇差が許容されるのかという判断を改めて見る必要があります。
3 まとめ
本件判決を受けて、定年退職後再雇用の従業員の基本給を見直すことを検討する企業が出てくることも予想されます。
本件は、最高裁が正職員と定年退職後再雇用された嘱託職員の間の基本給及び賞与の待遇差に関する判断をしたものですが、基本給及び賞与の待遇差が労働契約法20条に違反すると判断した裁判例はごく少数に限られているということが現状です。
基本給の待遇差を違法と判断した裁判例としては、長澤運輸第1審判決(東京地判平成28年5月13日)と学校法人産業医科大学(第2審)(福岡高判平成30年11月29日)があります。もっとも、長澤運輸事件第1審判決は、その後の控訴審判決及び最高裁判決によって、基本給の待遇差は違法ではないと判断されたため、実務上の影響はあまりないと考えられます。
本件第一審及び第二審は、基本給及び賞与の待遇差を違法と判断したため、実務上も注目されていましたが、今回の最高裁判決を受けて、基本給及び賞与の待遇差が違法と認められるケースは相当程度限定されるのではないかという印象も受けます。
企業としては、本件判決の影響を検討しつつ、今後の裁判の動向や他の事例の集積を待った上で、基本給や賞与等、特に重要な賃金体系の見直しを図ることが望ましいかと思われます。
Ⅲ 参考ページ
[blogcard url=”https://houmu.nagasesogo.com/media/column/column-2781/”]
[blogcard url=”https://houmu.nagasesogo.com/media/column/column-2274/”]
リーガルメディアTVのご案内
弁護士法人 長瀬総合法律事務所のYouTubeチャンネル「リーガルメディア企業法務TV」では、様々な分野の問題を弁護士が解説する動画を配信中です。

メールマガジンのご案内
弁護士法人 長瀬総合法律事務所では、定期的にメールマガジンを配信しております。セミナーの最新情報、所属弁護士が執筆したコラムのご紹介、「実務に使用できる書式」の無料ダウンロードが可能です。
顧問サービスのご案内
当事務所の顧問サービスは、企業が法的紛争に直面する前に予防策を講じ、企業の発展を支援するためのサポートを提供しています。人事労務、企業法務、労務管理に関する問題に経験とノウハウを持ち、多くの企業をサポートしてきました。
顧問サービスは複数の費用体系をご用意しており、貴社のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたします。ご興味をお持ちの方は、下記バナーより弁護士費用ページをご覧いただき、詳細等、お気軽にお問い合わせ下さい。