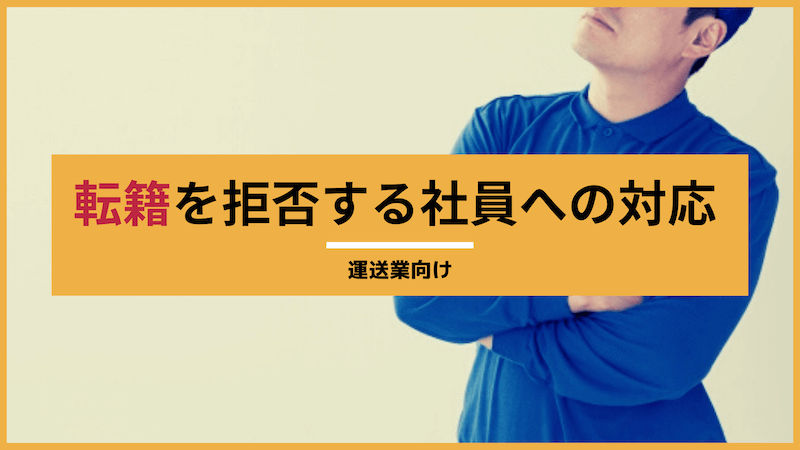はじめに:公式記録が作られるポイント
交通事故発生後、ドライバーが最初に対峙する公的機関が「警察」です。この警察とのやり取り、すなわち「事故の報告」「実況見分への立ち会い」「供述調書の作成」は、その後の示談交渉や裁判の行方を左右する“公式記録”を形成する、重要なプロセスです。
道路交通法で定められた警察への報告は、運転者の法律上の「義務」であり、これを怠ることは許されません。そして、事故直後の現場で行われる「実況見分」で作成される実況見分調書は、後の過失割合を判断するための重要な客観的証拠の一つとなります。この公式記録の作成過程において、ドライバーが不正確な説明をしたり、不利な内容の書類に安易に署名・押印してしまったりすると、後からそれを覆すことは困難です。会社としては、ドライバーが冷静に、かつ慎重に、事実に基づいて対応できるよう、日頃から正しい知識を教育しておく責任があります。
本稿では、警察への報告義務の重要性から、実況見分、供述調書作成の各段階で、ドライバーが具体的にどう振る舞うべきか、会社として何を指導すべきかについて、法的な注意点を解説します。
「警察への報告義務」
道路交通法第72条第1項は、交通事故があったときの措置として、運転者等に警察への報告を義務付けています。
- 報告義務の対象
公道での事故はもちろん、スーパーの駐車場など不特定多数の車両が自由に出入りできる場所での事故も対象となります。相手がいない自損事故であっても、ガードレールなどの公共物を損傷させた場合は報告義務があります。たとえ自社の車両を傷つけただけであっても、保険(特に車両保険)を利用する際には、警察が発行する「交通事故証明書」が必要となるため、報告は事実上必須です。 - 報告義務を怠るリスク
- 刑事罰: 報告義務違反として「3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金」が科される可能性があります。
- 事実関係の証明困難: 警察という公的機関による客観的な記録がなければ、後日、相手方との間で事故態様をめぐり「言った・言わない」の水掛け論になり、自社の正当性を証明することが著しく困難になります。
会社は、ドライバーに対して「どんなに些細な事故でも、必ず警察に報告すること」を、会社の絶対的なルールとして徹底させる必要があります。
その後の運命を左右する「実況見分」への立ち会い
警察への報告後、事故現場で警察官によって行われるのが「実況見分」です。これは、事故の客観的な状況を記録し、図面や写真を含む「実況見分調書」を作成するための捜査活動であり、この調書がその後の交渉や裁判における「公式な事故の物語」となります。一度作成されると大きな証拠能力を持つため、この場で曖昧な態度を取ることは許されません。
立ち会い時の心構え
- 冷静さと誠実さ: 動揺せず、警察官の質問には誠実な態度で答えます。
- 事実のみを話す: 見ていないこと、覚えていないことを、推測や想像で話してはいけません。「~だったと思う」「~かもしれない」という曖昧な表現は避け、記憶が確かなことだけを話します。不明な点は「分かりません」と正直に伝えることが重要です。
- 主張すべき点は、具体的に: 相手の急な飛び出しや速度超過など、事故の原因となった相手の行動があれば、具体的に指摘します。「相手がすごいスピードで…」ではなく、「法定速度40 km/hの道路を、私の感覚では60 km/h以上は出ていたように感じました」など、できるだけ具体的に説明します。
- 指示・確認の徹底: 警察官から「ブレーキ痕はここからですね」「衝突地点はこのあたりですか」などと確認を求められた際、もし自分の認識と異なれば、その場で「いいえ、私の記憶とは違います。もう少し手前です」と、明確に訂正を求めます。
「供述調書」の作成
実況見分と並行して、または後日、警察署で、事故の当事者として話した内容をまとめた「供述調書」が作成されます。これは、警察官がドライバーの供述を文章化したものであり、実況見分調書と並ぶ重要な証拠です。しかし、これはドライバーが話した言葉の逐語録ではなく、警察官というフィルターを通して再構成された文章であることを理解しなければなりません。
供述調書作成時の注意点
- 読み聞かせを厳しくチェックする
調書が完成すると、警察官がその内容を読み聞かせるか、自分で読むよう促されます。一言一句、注意深く内容を確認してください。 - 納得できない点があれば、妥協しない
自分の発言の意図と違う表現になっていないか、不利な内容に誘導されていないか、事実と異なる記載がないか、チェックします。少しでも疑問があれば、その場で訂正・修正を要求します。 - 署名・押印は、完全な同意の証
供述調書の末尾にある署名・押印は、「この調書に書かれている内容は、すべて私の話したことと相違ありません」と認めたことを意味します。一度署名・押印すれば、後から「本当は違うことを話した」と主張しても、裁判で覆すことはこんなんです。納得できる内容になるまで、安易に署名・押印すべきではありません。
客観的証拠「ドライブレコーダー」
ドライブレコーダーの映像は、事故態様を明らかにする客観的な証拠です。自社の正当性を証明できる映像(相手の信号無視が映っているなど)であれば、積極的に警察や保険会社に提出すべきです。逆に、自社に不利な映像が記録されている場合、提出する法的な義務はありません。しかし、相手方も提出を求めてくる可能性や、隠蔽したと見なされるリスクも考慮する必要があります。このような場合の対応は、ケースバイケースで慎重な判断が求められるため、弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
警察への対応は、単に事故の状況を説明するだけの作業ではありません。それは、その後の民事・刑事・行政の責任問題の基礎を形作る、重要な作業です。会社は、全ドライバーに対し、「警察への報告は絶対的な義務であること」「実況見分や供述調書では、事実に反すること、曖昧なことは決して認めないこと」「署名・押印は慎重の上にも慎重を期すこと」を、日頃から教育しなければなりません。正しい知識と毅然とした態度こそが、いざという時にドライバー自身と、会社を守るための武器となるのです。
長瀬総合の運送業専門サイト
2024年4月1日からの働き方改革関連法施行により、物流業界での働き方が今までと大きく異なっていきます。
違反してしまうと刑事罰の対象になってしまうので、運送・物流業を営む方の対策は必須です。
「どうしたら良いかわからない」という方は当事務所までご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス