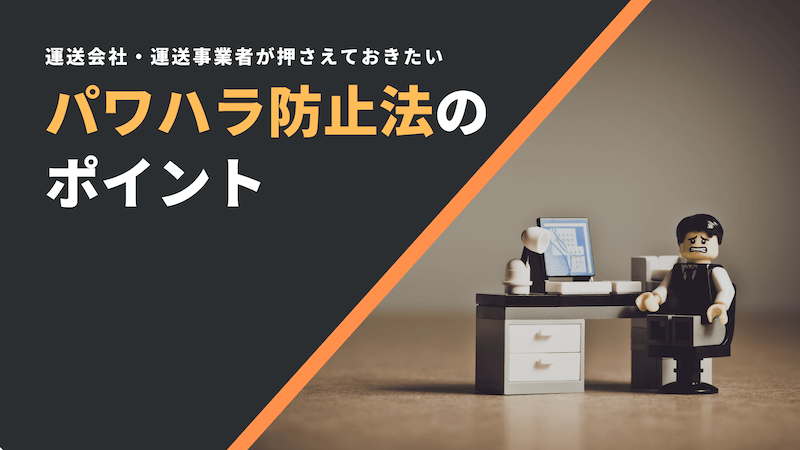はじめに
少子高齢化が急速に進む中、運送業界においても、経験豊富で貴重な戦力である高齢ドライバーの活躍が不可欠となっています。2021年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法により、企業には、65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業機会を確保する「努力義務」が課せられました。
多くの運送事業者が、定年を迎えたドライバーを「再雇用」や「勤務延長」といった形で、引き続き雇用しています。しかし、その際の労働条件の設定には、細心の注意が必要です。「定年後だから、給料を大幅に下げても問題ないだろう」「健康状態は本人の自己申告に任せておけばよい」といった安易な対応は、思わぬ法務リスクを招きます。
特に、「同一労働同一賃金」の原則や、高齢ドライバー特有の健康・安全管理の問題は、避けては通れない重要なテーマです。本記事では、定年を迎えたドライバーを再雇用する際に、企業が遵守すべき法的ルールと、トラブルを防ぐための労働条件設定のポイントについて解説します。
Q&A
Q1. 60歳で定年を迎えたドライバーを、嘱託社員として再雇用します。給料を定年前の半分にしても、法的に問題はないのでしょうか?
「半分にする」こと自体が直ちに違法となるわけではありませんが、慎重な判断が必要です。「同一労働同一賃金」の原則(パートタイム・有期雇用労働法)に基づき、定年前と後で、職務内容、責任の程度、配置の変更の範囲が同じであれば、単に「定年後の再雇用だから」という理由だけで賃金を引き下げることは、不合理な待遇格差として違法と判断されるリスクがあります。賃金を引き下げるのであれば、それに見合う職務内容の変更(例:長距離から地場輸送へ、運行管理の補佐業務へ変更など)が必要です。
Q2. 70歳までの就業機会の確保は「努力義務」とのことですが、何もしなくても罰則はないのでしょうか?
現時点で、70歳までの就業機会確保措置を講じなかったことに対する直接的な罰則はありません。しかし、これは単なる努力目標ではありません。国は、助成金などを通じて企業の取り組みを後押ししており、社会的にも高齢者の就業意欲に応えることが求められています。また、人手不足が深刻な運送業界において、経験豊富な高齢ドライバーは貴重な人材です。安定して働ける制度を整備することは、企業の競争力維持に直結する重要な経営課題と捉えるべきです。
Q3. 高齢ドライバーの健康状態が心配です。会社として、どのような健康管理をすべきでしょうか?
法定の健康診断はもちろんのこと、会社はより一歩進んだ健康管理を行うことが望ましいです。特に、加齢に伴いリスクが高まる脳血管疾患や心臓疾患、SAS(睡眠時無呼吸症候群)などに着目した健康管理が重要です。具体的には、国や業界団体の助成金を活用して「脳ドック」や「SASスクリーニング検査」の受診を推奨・補助したり、産業医と連携して、個々の健康状態に応じた乗務の可否や、勤務内容の調整(夜間運転や長距離運転の制限など)を検討したりすることが、安全配慮義務を果たす上で必要です。
解説
高年齢者雇用安定法が企業に求める義務
まず、法律が企業に何を求めているのかを正確に理解しましょう。
① 65歳までの雇用確保(義務)
事業主は、定年を65歳未満に定めている場合、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
- 65歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
多くの企業が「3」の継続雇用制度を導入しています。これは、希望者全員を対象としなければなりません。
② 70歳までの就業機会の確保(努力義務)
事業主は、65歳から70歳までの労働者について、以下のいずれかの措置を講ずるよう努めなければなりません。
- 70歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度の導入
- 業務委託契約の締結: 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 社会貢献事業への従事: 会社が実施・出資する社会貢献事業に従事できる制度の導入
最重要テーマ「同一労働同一賃金」と再雇用後の労働条件
定年後の再雇用で最もトラブルになりやすいのが、賃金をはじめとする労働条件の設定です。ここで鍵となるのが、「同一労働同一賃金」の原則です。
原則の考え方
正社員と、パートタイム・有期雇用労働者(再雇用された嘱託社員など)との間で、職務内容などが同じであるにもかかわらず、基本給や賞与、各種手当、福利厚生といったあらゆる待遇について、不合理な差を設けることを禁止するものです。
再雇用における注意点
単に「定年後の再雇用である」という事実だけを理由として、賃金を一律に引き下げることは、この原則に違反し、違法と判断されるリスクがあります。裁判例でも、定年前と同じ業務内容・責任で働いているにもかかわらず、賃金だけを大幅に引き下げたケースで、会社側の敗訴が確定した例(長澤運輸事件 最高裁判決)があります。
合理的な待遇差を設定するためのポイント
賃金などの待遇に差を設けるのであれば、その差が「不合理ではない」と説明できる、客観的な理由が必要です。
- 職務内容の変更
定年前は管理職として部下の指導も行っていたが、再雇用後は一ドライバーとして乗務に専念する。 - 責任の程度の変更
長距離・夜間運行といった負担の重い業務から外し、近距離の地場輸送のみを担当させる。 - 配置転換の範囲の変更
定年前は全国転勤の可能性があったが、再雇用後は特定の営業所での勤務に限定する。 - その他の事情
定年退職時に退職金が支払われていることや、老齢厚生年金を受給しながら働くことなども、一定程度は考慮され得ます。
重要なのは、これらの職務内容の変更などを、雇用契約書や労働条件通知書で明確に文書化し、本人に丁寧に説明して合意を得ることです。
安全配慮義務の観点から見た「高齢ドライバーの健康・安全管理」
高齢ドライバーの雇用を継続する上で、会社は、加齢に伴う心身機能の変化を十分に理解し、通常以上に高度な安全配慮義務を負うと考えるべきです。
健康状態の客観的な把握
- 法定の健康診断に加え、脳ドックや心疾患検診、SAS検査などの受診を積極的に推奨・支援する。
- 診断結果に基づき、産業医や主治医の意見を聴取し、乗務の可否や乗務させるべき業務内容を慎重に判断する。
運転適性の客観的な把握
- 国土交通省が認定する「適性診断」を定期的に受診させ、運転能力の経年変化を客観的に把握する。
- 視野の広さ、反応速度、認知機能などの診断結果を、乗務計画の策定に反映させる。
無理のない勤務環境の整備
- 本人の希望や健康状態に応じ、夜間勤務や長時間運転、悪天候時の運行を免除・制限する。
- 荷役作業など、身体的負担の大きい付帯業務を軽減する。
- 最新の安全運転支援装置(衝突被害軽減ブレーキ、ドライブレコーダーなど)が搭載された車両を優先的に割り当てる。
これらの配慮は、高齢ドライバー本人を守るだけでなく、事故を未然に防ぎ、会社の経営リスクを低減するために必要です。
弁護士に相談するメリット
高齢ドライバーの再雇用は、高年齢者雇用安定法、パートタイム・有期雇用労働法、労働契約法(安全配慮義務)など、複数の法律が複雑に絡み合う分野です。
- 就業規則・継続雇用規程の整備
最新の法令や判例に基づき、貴社の実態に合った継続雇用制度に関する規程を整備します。「同一労働同一賃金」の原則に違反しない、リスクの少ない賃金テーブルの設計などを助言します。 - 再雇用契約書の作成・リーガルチェック
個々のドライバーの職務内容の変更点を具体的に反映し、待遇差の合理性を明確にした、法的に有効な再雇用契約書(労働条件通知書)を作成します。 - 安全配慮義務に関する体制構築支援
高齢ドライバーの健康管理や安全教育について、会社としてどこまで配慮すべきか、法的な観点から具体的な体制構築をアドバイスし、安全配慮義務違反のリスクを低減します。 - 労使トラブルへの対応
再雇用後の待遇をめぐって従業員とトラブルになったり、事故が発生して会社の責任が問われたりした場合に、会社の代理人として交渉や訴訟に対応します。
まとめ
人手不足が深刻化する運送業界において、意欲と経験のある高齢ドライバーは、かけがえのない貴重な財産です。法律上の義務だからと形式的に対応するのではなく、彼らが長年培ってきたスキルと経験を最大限に活かし、安全に、そして安心して働き続けられる環境を整備することが、これからの運送事業者には求められます。
「同一労働同一賃金」の原則を正しく理解し、職務内容に見合った公正な待遇を設定すること。そして、加齢に伴う心身の変化に配慮した、きめ細かな健康・安全管理を徹底すること。この2つが、高齢ドライバーの再雇用を成功させ、企業の持続的な成長に繋げるための鍵となります。
再雇用後の労働条件設定や、安全管理体制の構築に少しでもご不安があれば、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。法務リスクをクリアし、すべての世代のドライバーがいきいきと活躍できる職場作りを、我々がサポートいたします。
長瀬総合の運送業専門サイト
2024年4月1日からの働き方改革関連法施行により、物流業界での働き方が今までと大きく異なっていきます。
違反してしまうと刑事罰の対象になってしまうので、運送・物流業を営む方の対策は必須です。
「どうしたら良いかわからない」という方は当事務所までご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス