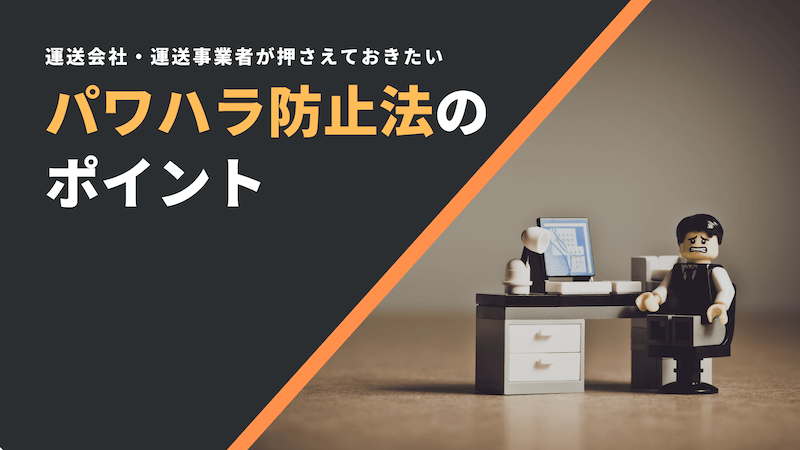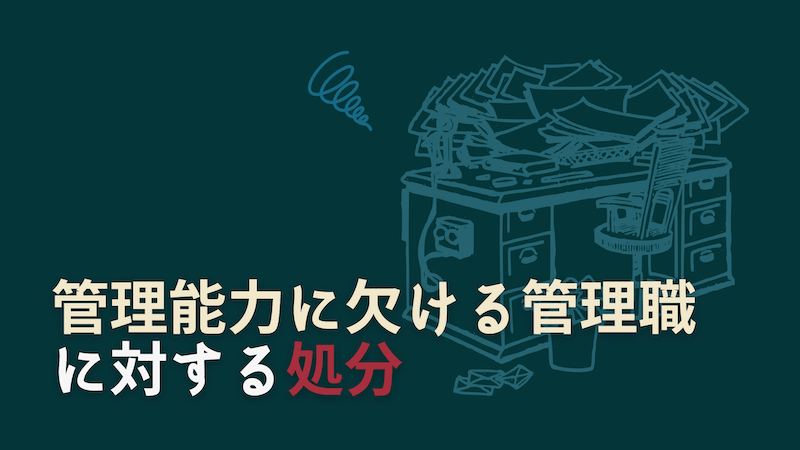はじめに
「指導のつもりだったが、パワハラだと訴えられた」「ドライバーが荷主からセクハラを受けているようだ」。このような職場におけるハラスメントは、被害者の尊厳を傷つけ、心身に深刻なダメージを与える許されない行為であると同時に、会社にとって極めて重大な経営リスクです。
2022年4月からは、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が中小企業にも完全施行され、職場におけるパワーハラスメント防止措置を講じることが、すべての事業者の「義務」となりました。もちろん、セクシャルハラスメントやマタニティハラスメント対策も、男女雇用機会均等法などで同様に義務付けられています。
特に運送業界は、上下関係が厳しい社風、長時間労働によるストレス、ドライバーが一人で行動する時間の長さ、荷主との力関係といった、ハラスメントが発生・潜在化しやすい特有の構造を抱えています。対策を怠れば、貴重な人材の流出、職場全体の士気の低下、生産性の悪化を招くだけでなく、会社の「安全配慮義務違反」や「使用者責任」を問われ、多額の損害賠償を請求される可能性があります。
本記事では、会社に義務付けられたハラスメント防止措置の具体的な内容と、運送業界で起こりがちなハラスメントの事例、そして会社が今すぐ構築すべき実効性のある対策について解説します。
Q&A
Q1. 熱心に指導しているだけなのに、部下から「パワハラだ」と言われないか心配です。どこからがパワハラになるのでしょうか?
法律上のパワーハラスメントは、①職場における優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの、という3つの要素をすべて満たすものを指します。重要なのは②の「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」かどうかです。例えば、業務上のミスに対して、人格を否定するような暴言を吐いたり、他の従業員の前で大声で長時間叱責したり、指導とは無関係な雑用を強制したりする行為は、指導の範囲を逸脱し、パワハラと認定される可能性が高いです。
Q2. 法律で「相談窓口」を設置する義務があると言われましたが、具体的に何をすればよいのですか?
まず、ハラスメントに関する相談担当者を決めます。人事・総務担当者などが一般的ですが、男女両方の担当者を置くことが望ましいです。その担当者の氏名や連絡先を、ポスターの掲示や社内通達などで全従業員に明確に周知します。相談者が安心して話せるよう、プライバシーが守られる個室を準備することも重要です。また、社内の担当者には相談しにくいケースも想定し、弁護士事務所などの外部機関を相談窓口として契約することも有効な手段です。
Q3. ドライバーが、荷主や取引先の担当者から暴言やセクハラを受けているようです。社外の人からのハラスメントに、会社はどう対応すべきですか?
会社は、自社の従業員が安全に働ける環境を整える義務(安全配慮義務)を負っているため、たとえ加害者が社外の人間であっても、問題を放置してはなりません。まず、被害を受けたドライバーから事実関係を詳しくヒアリングします。その上で、会社の責任者から、荷主側の責任者に対して、事実を伝えて厳重に抗議し、担当者の変更や再発防止策を強く求めるべきです。それでも改善されない悪質なケースでは、取引の見直しや、弁護士を通じた法的措置も検討する必要があります。
解説
今や企業の常識!法律が企業に義務付ける4つのハラスメント防止措置
パワハラ防止法などの法律は、企業に対して、ハラスメントを防止するために以下の措置を講じることを義務付けています。これらの措置は、パワハラ、セクハラ、マタハラに共通して求められます。
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 就業規則等に「ハラスメントを行ってはならない」旨の方針を明確に規定し、違反者には厳正に対処する旨を定める。
- 社内報、パンフレット、ポスターなどで、ハラスメントの内容や方針を従業員に周知・啓発する。
- ハラスメントに関する研修を定期的に実施する。
(2) 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 相談窓口をあらかじめ定め、従業員に周知する。
- 相談担当者が、相談内容や状況に応じて適切に対応できるようにする。
(3) 職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- 相談があった場合、速やかに事実関係の正確な確認を行う。
- 事実が確認できた場合、速やかに被害者に対する配慮の措置(加害者との隔離など)を行う。
- 事実が確認できた場合、速やかに加害者に対する措置(懲戒処分など)を適正に行う。
- 再発防止措置を講じる。
(4) 上記の措置と併せて講ずべき措置
- 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を従業員に周知する。
- 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、従業員に周知・啓発する。
これらの措置を講じていない場合、行政による助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わなければ企業名が公表される可能性があります。
運送業界で起こりがちなハラスメントの具体例
運送業界特有の環境は、以下のようなハラスメントの温床となり得ます。
パワーハラスメントの例
- 身体的な攻撃
添乗指導中に頭を叩く、胸ぐらをつかむ。 - 精神的な攻撃
「お前は頭が悪い」「給料泥棒」などの人格を否定する暴言。他の従業員の前での執拗な叱責。 - 人間関係からの切り離し
特定のドライバーだけを飲み会や情報共有の場から意図的に外す。挨拶をしても無視する。 - 過大な要求
到底時間内に終わらない無理な運行スケジュールを押し付ける。業務と無関係な私的な雑用を強制する。 - 過小な要求
ベテランドライバーの気に入らない新人に対し、いつまでも簡単な仕事しか与えず、成長の機会を奪う。
セクシャルハラスメントの例
- 容姿やプライベートについて、執拗にからかったり、質問したりする。
- 食事やデートに執拗に誘う。
- 不必要な身体的接触。
- わいせつな画像を事務所内で閲覧したり、見せたりする。
- 特に、女性ドライバーや事務員が被害に遭いやすい傾向があります。
- 荷主等、外部からのハラスメント
- 納品がわずかに遅れたことに対し、大声で罵倒する。
- 契約外の力仕事や、長時間にわたる荷待ちを当然のように強要する。
- ドライバーの性別や年齢を理由に、差別的な発言をする。
ハラスメントを許さない職場を作るための具体的アクション
義務付けられた措置を、実効性のあるものにするためのポイントは以下の通りです。
経営トップの断固たる決意表明
朝礼や全体会議の場などで、社長自らの言葉で「我が社は、いかなるハラスメントも絶対に許しません。ハラスメントは、仲間を傷つけ、会社の未来を破壊する犯罪行為です」と、繰り返し強くメッセージを発信することが、何よりも効果的です。
就業規則への具体例の明記
懲戒処分の対象となるハラスメント行為として、前述のような具体例を可能な限り列挙します。これにより、「これくらいは大丈夫だろう」という甘い考えをなくさせ、何が罰せられるのかを明確に示します。
相談しやすい窓口の工夫
「相談担当者が上司の友人だから相談しにくい」といった事態を避けるため、複数の相談ルートを設けます(例:人事担当者、信頼できる役員、外部の弁護士事務所など)。相談方法は、面談だけでなく、電話やEメール、無記名の手紙でも受け付けるなど、ハードルを下げることが重要です。
管理職研修の徹底
ハラスメント対策の鍵は、管理職の意識改革です。特に「指導とパワハラの境界線」について、具体的なケーススタディを用いて徹底的に研修します。「良かれと思ってやった指導」が、パワハラと認定された裁判例などを学ぶことが有効です。
アンケートの実施
定期的に、無記名でハラスメントに関するアンケートを実施し、潜在的な問題を早期に発見する努力も重要です。
弁護士に相談するメリット
ハラスメント問題の対応は、事実認定の難しさや、関係者のプライバシーへの配慮など、高度な専門性を要します。
- 実効性のある社内規程の整備
パワハラ防止法などの法令に完全に対応し、かつ運送業の実態に即した就業規則やハラスメント防止規程の作成を、ゼロからサポートします。 - 信頼性の高い外部相談窓口の提供
弁護士が「外部相談窓口」となることで、従業員は「相談しても秘密が守られる」「公平に対応してくれる」という安心感を持つことができ、潜在的な問題が顕在化しやすくなります。 - 質の高いハラスメント研修の実施
弁護士が講師となり、最新の裁判例や法的な視点を交えた実践的な研修を実施します。これにより、従業員のハラスメントに対する意識を効果的に高めることができます。 - 事案発生時の調査・対応サポート
ハラスメントの相談があった際に、中立的な第三者として事実関係の調査(ヒアリングなど)を行います。調査結果に基づき、懲戒処分の妥当性や、再発防止策について、法的な観点から具体的な助言を提供します。
まとめ
ハラスメントのない職場環境を作ることは、もはや企業の社会的責任であり、事業を継続していくための必須条件です。対策を怠り、ハラスメントが一度発生・発覚すれば、会社が受けるダメージは計り知れません。
特に、日々の業務で多くのストレスに晒されているドライバーが、さらに職場の人間関係で疲弊するようなことがあっては、安全運行など望むべくもありません。風通しが良く、誰もが尊重される職場環境を構築することこそが、離職率を下げ、優秀な人材を惹きつけ、会社の持続的な成長を実現するための最良の道です。
「うちは大丈夫」と思わず、この機会に自社のハラスメント対策を総点検してください。何から手をつければよいか分からない場合は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。ハラスメントリスクから会社と従業員を守るための、具体的で実効性のある体制構築を、我々が支援いたします。
長瀬総合の運送業専門サイト
2024年4月1日からの働き方改革関連法施行により、物流業界での働き方が今までと大きく異なっていきます。
違反してしまうと刑事罰の対象になってしまうので、運送・物流業を営む方の対策は必須です。
「どうしたら良いかわからない」という方は当事務所までご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス