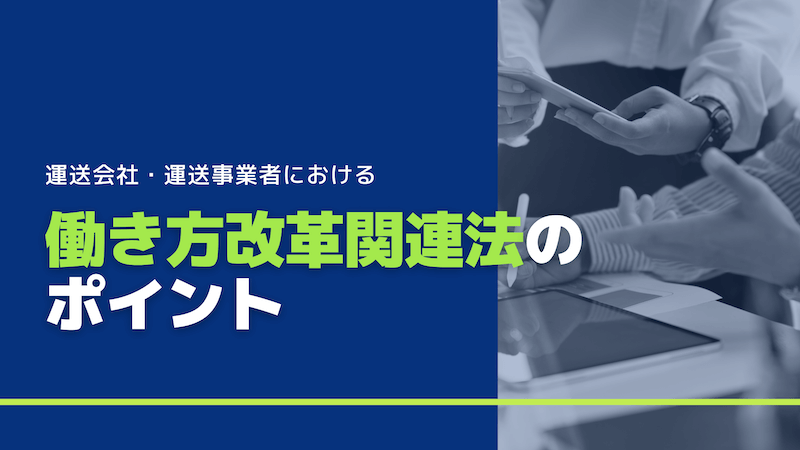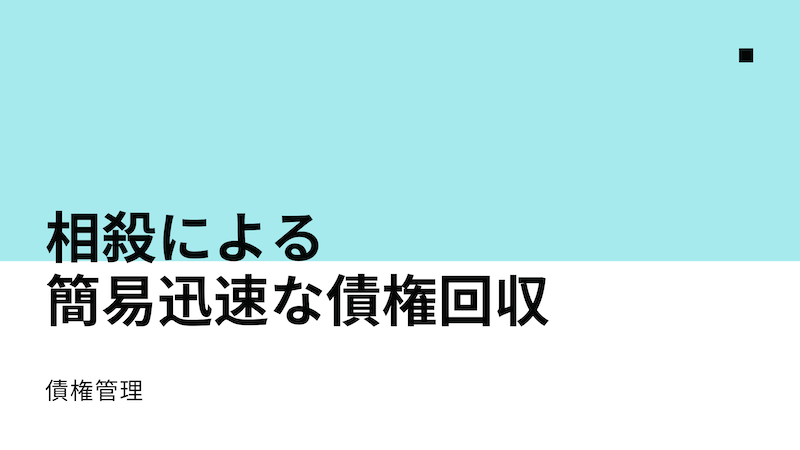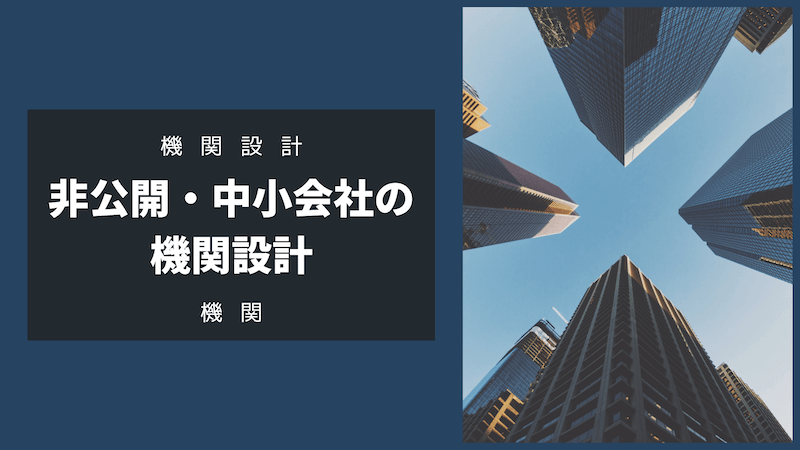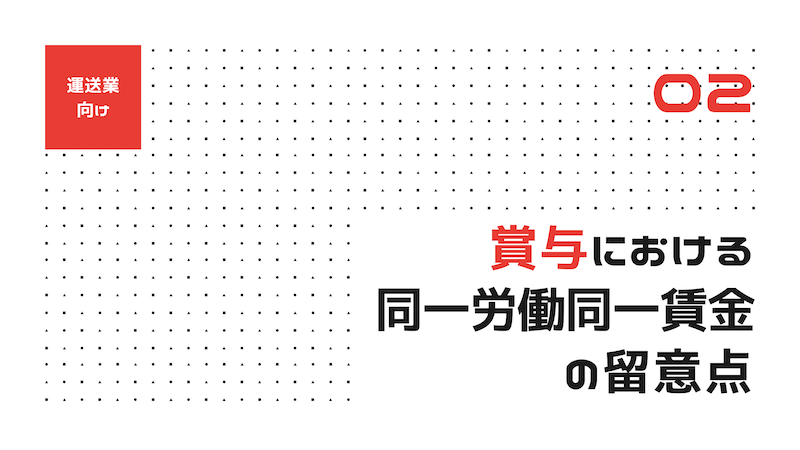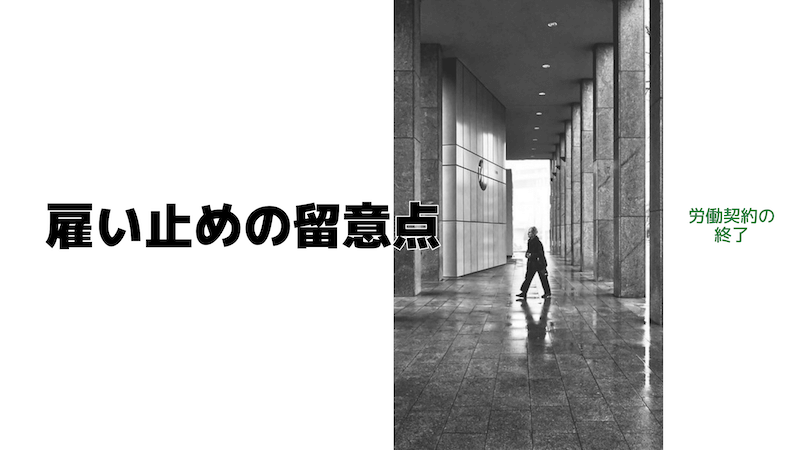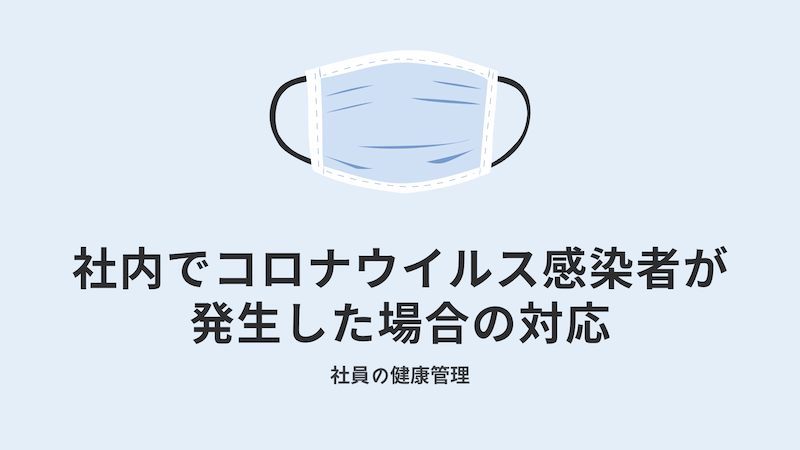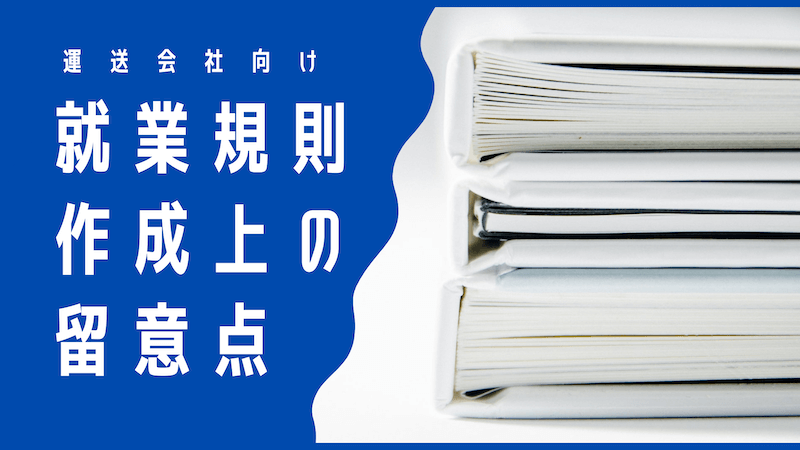はじめに
運送業界において、頻発し、かつ経営に与えるダメージが甚大な労務トラブル。それが、退職したドライバーなどからの「未払い残業代請求」です。その請求額は、一人あたり数百万円にのぼることも珍しくなく、複数の従業員から同時に請求されれば、会社の存続を揺るがしかねません。
この未払い残業代請求の最大の争点となるのが、「固定残業代(みなし残業代)制度」の有効性です。「うちは毎月、固定残業代として手当を払っているから大丈夫」と考えている経営者様、その認識は大変危険です。運送会社が導入している固定残業代制度の多くが、法的に定められた厳格な要件を満たしておらず、裁判で「無効」と判断されるケースが後を絶ちません。
制度が無効と判断されれば、これまで支払ってきた固定残業代は、残業代としての効力を失い、単なる基本給の一部と見なされます。その結果、会社は過去に遡り、残業時間に応じた割増賃金を“全額”支払い直さなければならないという、最悪の事態に陥ります。本稿では、この固定残業代制度が有効と認められるための法的要件を、最高裁判所の判例に基づき解説します。
Q&A:固定残業代に関するよくある質問
Q1. 給与明細の「業務手当」や「乗務手当」が、固定残業代のつもりなのですが、それではダメなのでしょうか?
ダメです。判例上、固定残業代として認められる大前提は、通常の労働時間の対価である部分(基本給など)と、時間外労働の対価である割増賃金部分が「明確に区分」されていることです。「業務手当」といった名称では、その手当が一体何の対価なのかが不明確であり、残業代の支払いとは認められません。給与明細や雇用契約書において、「固定残業代」という名称で、その金額を明確に記載する必要があります。
Q2. 固定残業代として定めた時間を超えて残業が発生した場合、その分の差額は必ず支払わなければなりませんか?
はい、必ず1円単位で支払わなければなりません。例えば、「固定残業代5万円(30時間分)」と定めているドライバーが、ある月に40時間残業した場合、超過した10時間分の割増賃金を、給与に上乗せして支払う義務があります。この差額の支払いを怠った場合、固定残業代制度全体が無効と判断される大きな要因となります。「固定残業代を払っているから、いくら残業させても給料は同じ」という考えは、法律上通用しません。
Q3. 採用時に、固定残業代の仕組みを説明し、本人が「納得してサインした」雇用契約書があれば、法的に有効になりますよね?
本人の同意があることは重要ですが、それだけでは有効になりません。労働基準法は、労働者を保護するための「強行法規」であり、たとえ労使間で合意があったとしても、法律で定められた要件(明確区分性など)を満たさない契約は無効となります。裁判所は、契約書の文面だけでなく、その運用実態も含めて、制度の有効性を厳しく判断します。本人がサインしているからといって、決して安心はできません。
あなたの会社は大丈夫? 制度の有効性を分ける「3つの要件」
近年の最高裁判所の判例により、固定残業代制度が有効と認められるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があると解される傾向にあります。
要件①:明確区分性
これが最も重要な要件です。賃金総額のうち、通常の労働時間の対価である部分(基礎賃金)と、時間外労働等の対価である割増賃金の部分(固定残業代)とが、雇用契約書や給与明細上で、金額的に明確に区別されていなければなりません。
- OK例:「基本給 250,000円」「固定残業代 70,000円」
- NG例:「月給 320,000円(固定残業代を含む)」「基本給+業務手当 320,000円」
「基本給に含む」といった曖昧な表記は、ほぼ100%無効と判断されます。
要件②:対価関係の明確性
その固定残業代が、何時間分の、どの種類の割増賃金(時間外・休日・深夜)に対する対価なのかが、明確に示されている必要があります。
- OK例:「固定残業代70,000円は、月40時間分の時間外労働に対する割増賃金として支払う」
- NG例:「固定残業代70,000円を支払う」 (何時間分か不明確)
要件③:差額支払いの合意と履行
実際の残業時間が、固定残業代の対象となる時間を超えた場合には、その超過分に対する割増賃金を、別途支払う旨が合意されており、かつ、実際に支払われていなければなりません。この差額精算が適切に行われていない場合、制度全体が「残業代を定額で頭打ちにする脱法的なもの」と見なされ、無効となります。
制度無効の財務的インパクトと法改正への対応
固定残業代制度が無効と判断された場合、会社が被る経済的ダメージは壊滅的となりえます。これまで「固定残業代」として支払っていた金額は、残業代としての性格を完全に否定され、割増賃金を計算するための「基礎賃金」に組み込まれます。会社は、この増額された基礎賃金を元に、過去の全残業時間に対する割増賃金を再計算し、支払う義務を負います。
この未払い残業代の請求は、過去3年間に遡って行うことができ、将来的には5年となる予定です。さらに、裁判所は、会社の違反が悪質であると判断した場合、未払い残業代と同額の「付加金」の支払いを命じることができ、支払総額は実質的に倍増する可能性があります。
加えて、2023年4月1日から、中小企業においても月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられました。固定残業代制度の設計にあたっては、この二段階の割増率構造を正確に反映させなければなりません。
自社の制度を今すぐ総点検!
手遅れになる前に、以下の3つの書類をすぐに確認してください。
- 雇用契約書(労働条件通知書)
基礎賃金と固定残業代が明確に区分され、固定残業代が何時間分の対価であるかが明記されていますか? - 就業規則(賃金規程)
上記の内容が、会社のルールとして正式に規定されていますか?月60時間超の50%割増率に対応した計算方法が規定されていますか? - 給与明細
基礎賃金と固定残業代の項目が明確に分かれていますか?毎月の残業時間数と、固定残業時間を超過した分の差額が記載されていますか?
一つでも「No」があれば、赤信号です。専門家に相談の上、就業規則と雇用契約書を見直し、全従業員から再合意を取り付ける(契約を巻き直す)必要があります。
まとめ
固定残業代制度は、運送事業者にとって、経営の根幹を揺るがす最大のリスク要因です。「うちは昔からこうだから」「みんな納得しているはず」という思い込みは、もはや通用しません。法的な要件を満たさない固定残業代制度は、会社が気づかないうちに巨額の簿外債務を抱え込んでいるのと同じ状態です。問題が表面化する前に、一刻も早く専門家へ相談し、予防法務に取り組むことが、会社を未払い残業代請求のリスクから守る、確実で、コストの低い手段なのです。
長瀬総合の運送業専門サイト
2024年4月1日からの働き方改革関連法施行により、物流業界での働き方が今までと大きく異なっていきます。
違反してしまうと刑事罰の対象になってしまうので、運送・物流業を営む方の対策は必須です。
「どうしたら良いかわからない」という方は当事務所までご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス