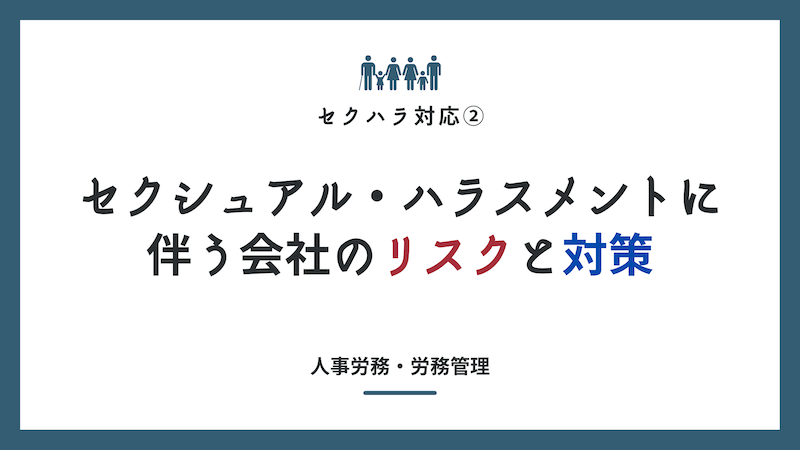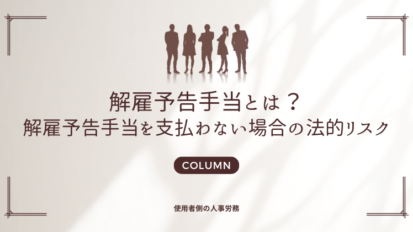はじめに
職場でのハラスメント問題が起きた際、企業が内部だけで対応しようとしても、調査の公正性や法的観点の不足などで限界がある場合が多いです。また、パワハラ防止法の下、ハラスメント対策の不備が指摘されると行政指導や企業イメージの悪化につながるリスクもあります。そこで、外部専門家との連携が効果的となります。
本記事では、弁護士・社労士など外部専門家を活用するメリットや、具体的な連携方法、ハラスメント防止・解決にどのように貢献できるかをまとめています。企業が公正かつ迅速にハラスメント事案に対処するためにぜひご活用ください。
Q&A
Q1. ハラスメント問題には社労士と弁護士、どちらに依頼すればいいですか?
ハラスメント防止の就業規則整備や労務管理全般に関しては社労士が力を発揮し、調査の適正手続き・懲戒処分の有効性検討、紛争対応(訴訟・調停)など法的手続きが絡む場合は弁護士が中心となります。両者が連携することで、労務管理と法務対応の両面をフォローできます。
Q2. 弁護士はどのような場面で特に必要ですか?
主にハラスメント事案の調査や加害者への懲戒処分決定、損害賠償請求や労働審判など紛争対応を行う際に弁護士のサポートが不可欠です。また、就業規則のハラスメント規程整備や外部相談窓口として弁護士を活用するなど、多様なシーンで力を発揮します。
Q3. 社労士を活用するメリットは何ですか?
社労士は社会保険・労働保険手続きの専門家であり、就業規則の作成や労務管理のアドバイスに強みがあります。ハラスメント対策で就業規則を改定したり、労働時間管理や健康診断制度などメンタルヘルス面も含む労働管理全般を整える際、社労士のサポートが効果的です。
Q4. 外部専門家を窓口にするハラスメント相談とはどういう仕組みですか?
企業が弁護士や社労士など外部専門家に委託し、ハラスメントのホットラインを運営してもらう方式です。従業員が社内に言いにくい場合でも、外部専門家を経由すれば匿名性や守秘義務が担保され、安心して相談できるメリットがあります。会社としても早期発見に繋げられます。
Q5. 外部専門家の費用が心配ですが、どのようにコストを削減できますか?
まずは顧問契約などで月額固定費を抑えつつ、必要なときに相談・依頼できる体制を構築する企業が増えています。また、事務所によっては初回相談無料や成果報酬型など様々なプランがあるので、複数の専門家と比較検討して費用対効果の高い契約を結ぶことをお勧めします。
解説
弁護士との連携
- ハラスメント調査・報告書作成
企業内でパワハラやセクハラ疑惑が生じた際、弁護士が適正な調査手続を指導し、事実認定や報告書取りまとめをサポート。内部調査では第三者委員会に弁護士を入れる場合もある。 - 懲戒処分の適法性検討
加害者を懲戒解雇や降格に処する場合、就業規則や判例に照らして過度に重いかどうかを判断し、処分の有効性を担保する。 - 紛争対応・示談交渉
被害者が労働審判や損害賠償請求を起こした時、企業の立場で訴訟対応・示談交渉を行う。 - 外部相談窓口の構築
弁護士が外部窓口として直接相談を受けるホットラインを運営し、通報者の守秘と客観的視点を確保。
社労士との連携
- 就業規則・ハラスメント規程の整備
社労士が労働基準法・労働関係諸法令の視点から、企業の就業規則にハラスメント禁止条項や処分規定を盛り込み、法的要件を満たす形に整備。 - 労務管理体制の構築
長時間労働や健康診断管理が不十分だとハラスメントリスクが高まりやすい。社労士が勤怠管理システムや健康診断の実施など全体の労務管理をサポート。 - 相談・研修サポート
社労士が企業向けにハラスメント防止研修を実施したり、従業員からの一次相談窓口を担うケースもある。
外部専門家活用モデル
- 顧問契約モデル
毎月一定額で弁護士・社労士と顧問契約し、ハラスメント発生時の調査アドバイスや書類チェックなどを随時依頼。費用が予算化しやすい。 - スポット相談モデル
ハラスメント疑惑が生じたタイミングのみ単発で調査依頼や法的検証を行う。コストは抑えやすいが、対応スピード面で顧問契約に比べ不利な場合も。 - 外部ホットライン運用
弁護士または社労士事務所が通報窓口として稼働し、社員からの通報を受け付け、公平に報告を行う。会社は迅速に事実確認を行う体制を整える。
注意点・デメリット
- 過度なコスト
外部専門家への依頼は費用が発生するが、放置して大きな紛争化した場合のリスクと比べれば有益性は高い。 - 情報漏えいリスク
外部専門家との契約で守秘義務を徹底し、社内情報が不当に外部に漏れないよう契約内容を確認。 - 契約範囲
顧問契約の場合、ハラスメント以外の法務相談も含むのか、スポット依頼はどこまで対応してもらうのか、事前に範囲を明確化。
弁護士に相談するメリット
ハラスメント問題は、法的知識と労務管理の実務が複雑に絡み合う領域です。弁護士に相談することで得られる主なメリットは以下のとおりです。
- 企業内で発生した事案への即応
事実調査の指導、被害者保護・加害者処分などのアドバイスを通じて紛争の深刻化を防ぐ。 - 就業規則やハラスメント規程の整備
社労士連携とあわせ、企業方針や懲戒規定を法的観点でレビューし、抜け漏れを修正。 - 外部ホットライン機能
弁護士が直接通報を受け付ける体制を整え、通報者保護と公正性を確保。 - 訴訟リスク対応
被害者や加害者から訴えられた場合も、弁護士が代理人として交渉・裁判を主導し、企業の負担を最小限に。
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、ハラスメント全般の防止策や紛争処理において、豊富な事例経験と実務的な提案を行っています。
まとめ
- 外部専門家(弁護士・社労士)との連携は、ハラスメント対策において不可欠です。社労士は労務管理・就業規則整備、弁護士は調査・懲戒・紛争対応を主に担当し、双方の強みを掛け合わせることで効果的な防止策や問題解決が期待できます。
- 弁護士との契約形態としては、顧問契約で日常的に相談できる体制や、スポット契約で必要なときに依頼する方法があります。コストとスピード、企業のリスク許容度を勘案して最適な選択をしましょう。
- 外部窓口として弁護士や社労士がホットラインを受け付けるケースも増えており、従業員が安心して相談できる環境を提供し、早期発見と対応を実現します。
- 弁護士に相談すれば、ハラスメント問題の法的リスクを多角的に評価し、就業規則の再点検や懲戒処分の適法性判断、さらには紛争対応までサポートが得られます。
企業のハラスメント対策が高度化するなか、外部専門家との連携は企業イメージを守り、従業員の安心・安全な労働環境を確保する有力な手段です。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス