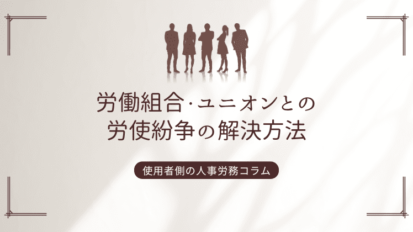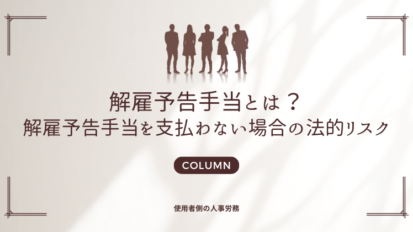はじめに
近年、モラルハラスメント(モラハラ)やカスタマーハラスメント(カスハラ)が職場での深刻な問題として注目されています。モラハラは、職場の上司や同僚、あるいは部下からも含め長期的に続く精神的な嫌がらせや言葉の暴力を指し、一方でカスハラは顧客や取引先から過剰なクレームや罵倒行為があり、従業員が大きなストレスを受けるケースを指します。
本記事では、モラハラ・カスハラそれぞれの定義と具体例、そして企業がどのように対処・防止すればよいかを解説します。職場での精神的ダメージを防ぐため、社員保護と事業運営を両立する施策が重要です。
Q&A
Q1. モラルハラスメント(モラハラ)とはどういう行為ですか?
モラハラは精神的な嫌がらせを意味し、表立った暴力やセクシャル要素はないが、長期的な言葉や態度によって相手を追い詰める行為です。具体的には、無視・冷笑・陰口、過度な批判や侮辱的言動、仕事上での過小評価などが挙げられます。
Q2. カスタマーハラスメント(カスハラ)は従業員保護の観点で何か法律はあるのでしょうか?
直接的に「カスハラ防止法」は存在しませんが、労働契約法の安全配慮義務やパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)などに基づき、「顧客からの著しい迷惑行為に対しても、企業は従業員を保護しなければならない」という考え方が近年広がっています。実際に国によるガイドラインでも、カスタマーハラスメントへの対策が推奨されています。
Q3. モラハラとパワハラとの違いは何ですか?
パワハラは「職務上の優位性を背景にした、業務の適正範囲を超える言動」を中心に定義されていますが、モラハラはより人格否定的な嫌がらせや陰湿な精神的圧迫を指す概念で、必ずしも上司部下の関係に限らない場合もあります(同僚間、部下から上司への場合など)。つまり、モラハラは精神的攻撃に焦点を当てたハラスメントと言えます。
Q4. カスハラに遭った従業員をどう保護すればいいですか?
まずは従業員からの報告・相談を受けやすい相談窓口を設置し、適切に事案を把握します。顧客からの過度なクレームや暴言があれば、従業員を交替させるなどして被害を拡大させない。必要に応じて、会社が顧客に注意・警告を行ったり、状況次第で警察対応も検討する場合があります。
Q5. モラハラ・カスハラ対応を怠ると企業はどんな責任を負いますか?
従業員がメンタル不調や退職を余儀なくされた場合、企業が安全配慮義務違反で損害賠償責任を負うリスクがあります。また、パワハラ防止法の観点で、社内のハラスメント対策不備を行政から指摘され、行政指導や社名公表が行われる可能性も否定できません。
解説
モラハラの具体例と特徴
- 長期的・陰湿
大声で怒鳴るよりも、毎日のように冷嘲的な態度をとり続けるなど、気づきにくいが精神的ダメージが大きい。 - 言葉に残らない形での嫌がらせ
無視、意図的に情報を共有しない、陰口を言いふらすなど、形に残りにくい手段が使われる。 - 被害者が自分を責めやすい
明確なハラスメント表現がないため、「自分が悪いのでは」と被害者が思い込んでしまい、発覚が遅れるケースも。
カスタマーハラスメント(カスハラ)の事例
- 長時間のクレーム電話
業務に支障をきたすほど執拗に文句を言い続け、従業員が休憩も取れない状態。 - 人格否定的な暴言
「こんな店員は使えない」「頭がおかしい」など、必要以上に人格を攻撃。 - 過剰要求
法的・契約的に認められないような過度なサービスや金品を要求し、断ると従業員を恫喝。 - SNSでの誹謗中傷
接客対応が気に入らないと言って、従業員の容姿や名前をSNS等で誹謗する。
企業の防止策と対応
- 相談窓口の充実
社員がモラハラやカスハラを感じたらすぐに報告できるよう、社内外に相談窓口を設置し、通報者保護を徹底。 - ルール整備・指針の策定
就業規則やハラスメント規程にモラハラ・カスハラへの対応方針を明文化する。顧客対応マニュアルも含めて整備。 - 研修・啓発活動
全従業員・管理職を対象に定期研修を行い、モラハラ・カスハラを許さない職場文化を育成。 - 被害者保護・加害者対応
モラハラ加害者には懲戒処分や配置転換。カスハラ加害者(顧客)には担当者交替、場合によっては取引停止や警察相談など。
具体的な対処フロー
- 問題発覚
被害者が相談窓口に駆け込む、同僚が気付いて通報する、あるいは管理職が異常を感知する。 - 初動ヒアリング
事実確認のために被害者や周囲の証言を集める。証拠となるメールや録音がないか確認。 - 加害者・顧客への対応
社員加害者なら内部調査を行い懲戒処分を検討。顧客なら対応担当を交替し、改善しない場合は取引停止等も選択肢。 - フォローアップ
被害者のメンタル面フォローや配置転換、職場環境改善を実施。必要に応じて再発防止策を打ち出し、社内広報。
弁護士に相談するメリット
モラハラ・カスハラ問題は、対外的・対内的にトラブルが大きくなる可能性をはらんでいます。弁護士に相談すると、以下のサポートが得られます。
- 就業規則やハラスメント規程の作成・見直し
モラハラ・カスハラに対応する具体的条項を加え、懲戒基準や対応フローを整える。 - 顧客対応マニュアル策定
カスハラに悩む企業へ、従業員がどう対応・エスカレーションすべきかマニュアル化。 - 事実調査・紛争解決
従業員間のモラハラ事件や顧客とのカスハラトラブルで問題が深刻化した場合、調停・裁判などにおける法的戦略を立案。 - 研修や相談窓口の外部委託
弁護士が外部窓口として機能し、従業員が安心して通報できる体制を構築。企業のイメージを守りつつ問題解決を図る。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、モラルハラスメント・カスタマーハラスメント事案を解決してきた経験から、企業への具体的かつ実践的な助言を行います。
まとめ
- モラハラは長期的・陰湿な精神的嫌がらせ行為、カスハラは顧客や取引先からの過度なクレーム・暴言などを指す。
- いずれも従業員の精神的健康を損ない、安全配慮義務違反や企業イメージ損失につながる重大リスクとなる。
- 企業は就業規則での明確な規定や相談窓口の整備、管理職研修の実施、被害者保護策や加害者処分などの対応フローを整えておく必要がある。
- 弁護士に相談すれば、規程の整備から顧客対応マニュアル作成、トラブル時の法的戦略まで包括的にサポート可能で、モラハラ・カスハラによる企業リスクを最小化できる。
企業としては、モラルハラスメントもカスタマーハラスメントも見過ごさず、早期に適切対応することが従業員保護と企業評判維持の要となります。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス