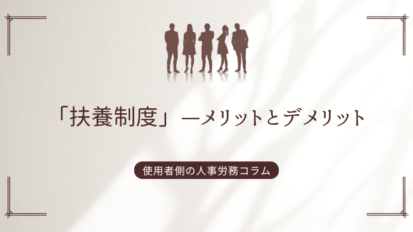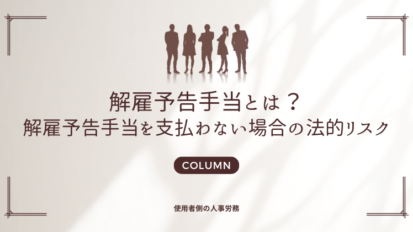はじめに
企業がハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラなど)の調査を行い、事実が認定されると、次に重要なのは加害者・被害者への具体的な対応です。加害者に対しては相応の懲戒処分や再発防止策を施し、被害者については配置転換や精神的フォローなど再被害防止のための措置が求められます。これらを怠ると、企業が安全配慮義務違反や是正措置の不備を指摘され、さらにリスクが拡大する恐れがあります。
本記事では、ハラスメントが認定された後に企業が行うべき加害者・被害者対応を、弁護士法人長瀬総合法律事務所が具体的に解説します。実態確認後の適切なフォローが、被害回復と再発防止において重要です。
Q&A
Q1. ハラスメントが事実と認定されたら、加害者には必ず解雇をしなければならないのでしょうか?
必ずしも解雇とは限りません。就業規則の懲戒規程に基づき、事案の重大性に応じて以下のような処分を検討します。
- 口頭注意 / 厳重注意 / 減給 / 出勤停止 / 降格 / 懲戒解雇
ハラスメントの内容や被害者への影響、加害者の反省度合いなどを踏まえ、過度に重くないバランスの取れた処分を決定することが重要です。
Q2. 被害者は加害者と同じ部署のままにしておいて大丈夫でしょうか?
被害者の意向や精神的状態を考慮し、配置転換や加害者との物理的な分離を検討するケースが多いです。被害者が望むなら別部署・別フロアへの異動も考えられます。ただし、被害者の負担だけを増やす処置にならないよう、加害者を異動させることも検討すべきです。
Q3. 被害者へのフォローはどのようなものが求められますか?
代表的には以下が挙げられます。
- 医療機関の受診やカウンセリングの手配
- 職場環境調整(加害者と席を離す・シフトを調整するなど)
- 上司・人事担当による定期的フォロー面談
- 休職制度の適用(メンタル不調が深刻な場合)
このとき、被害者が二次被害を受けないよう留意する必要があります。
Q4. 加害者が「事実はない」と否定し続けている場合はどう対処すればいいですか?
企業が客観的調査でハラスメント行為が認められたならば、就業規則に従って懲戒処分を行うことが可能です。加害者が否定しても、会社が集めた証拠に基づいて処分理由を丁寧に説明することが大切。必要に応じて弁護士の助言を得ながら、法的リスクを最小化する手続きを踏むべきです。
Q5. ハラスメント再発防止のためには何をすればいいでしょうか?
既存の就業規則やハラスメント規程の見直し、管理職研修の強化、社内アンケートや定期モニタリングなどが考えられます。今回の事案を教訓として、組織全体の問題点(評価制度やコミュニケーション風土など)を改善することが再発防止につながります。
解説
加害者への対処
- 懲戒処分の決定
- 事案の重大性や頻度、被害者の精神的被害の度合いなどを考慮し、就業規則の懲戒条項に基づいて処分内容(減給・出勤停止・降格・懲戒解雇など)を選定。
- 過度に重い処分は無効とされるリスクがあるが、軽すぎると再発防止効果に疑問が残るためバランスが必要。
- 加害者の配置転換など
被害者と別部署にする、業務上で接触しないようシフトを組むなどの措置でトラブルの再燃を防ぐ。 - 教育・研修の受講
加害者本人にハラスメント防止研修などを受講させ、自身の行為が違法・不適切であったと認識させる。 - 再発防止計画
加害者が復職した後も定期フォロー面談を設け、改善状況をモニタリング。
被害者へのフォロー
- 心理的サポート
会社負担でカウンセリングや産業医面談を手配し、必要なら心療内科受診を勧める。 - 配置転換・勤務配慮
被害者が加害者と顔を合わせるだけで強いストレスを感じる場合、業務上の接点を避ける配置転換や在宅勤務など柔軟に対応。 - 休職制度の活用
メンタル不調が深刻な場合は休職を認め、給与面や保険手続きなどの支援を行う。 - 二次被害の防止
社内で被害者への風評や嫌がらせが起きないよう、管理職が注意喚起し、情報管理を徹底。
再発防止策
- ハラスメント規程の見直し
今回の事案で不足や曖昧さが露呈したら、規程を補強し、新たな条項や懲戒基準を追加。 - 管理職への研修強化
指導とハラスメントの違いや、加害者・被害者への対応法などを詳細に指導。 - 社内アンケートやモニタリング
定期的に従業員アンケートを実施し、ハラスメントの発生状況や職場環境の悪化を早期察知。 - 相談窓口の充実
内部窓口に加え、外部弁護士など専門家を窓口として導入し、相談者の安心感を高める。
企業の安全配慮義務と責任
- 安全配慮義務違反
企業は従業員の安全・健康に配慮する義務がある。ハラスメントが放置されて被害者が心身に損害を被った場合、損害賠償責任を負うリスク。 - 法的リスク
パワハラ防止法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法などの関連法でハラスメント防止が義務付けられているため、行政指導や社名公表も懸念される。
弁護士に相談するメリット
ハラスメント事案で加害者・被害者対応を適切に行うためには、慎重な事実認定と法的根拠に基づく処分・救済が必要です。弁護士に相談することで、以下の利点があります。
- 懲戒処分の適法性判断
事実関係と就業規則を照らし合わせ、懲戒解雇や減給などが過度に重くないか、あるいは軽すぎないかを判断。 - 被害者フォロー策の提案
配置転換やカウンセリング手配など具体的かつ法的に確実な対処を指南。 - 紛争リスクの回避
- 被害者がさらなる被害を受けないよう二次被害防止を図り、加害者とのトラブル再燃を防ぐ。
- 万一労働審判や裁判となった場合、証拠整理や企業の立場を最適に主張する。
- 再発防止策の策定サポート
ハラスメント規程改訂や管理職研修の企画など、社内制度強化をバックアップ。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、様々なハラスメント問題の解決に携わった経験から、企業の実態にあった実用的な施策を提案・実行支援しています。
まとめ
- ハラスメントの事実が認定された後、企業は加害者に対する適切な懲戒処分や配置転換などの再発防止策、被害者への十分なフォロー(心理的サポート、職場配置配慮など)を行う責任があります。
- 処分が過度に重すぎても軽すぎても問題となるため、就業規則の懲戒規程を踏まえ、事案の重大性や被害状況を慎重に考慮して決定する必要があります。
- 被害者を守りつつ、職場全体の風土改善を図るためには、再発防止策として就業規則改訂や管理職教育、相談窓口の充実などが重要です。
- 弁護士に相談し、加害者・被害者対応の適正手続きや法的リスク、再発防止策を一体的に検討することで、企業リスクを大幅に低減できます。
ハラスメントは企業の信頼を損なう重大なリスク。調査後の対応こそが、被害者救済と再発防止の要となりますので、誠実かつ迅速に行うことが大切です。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス