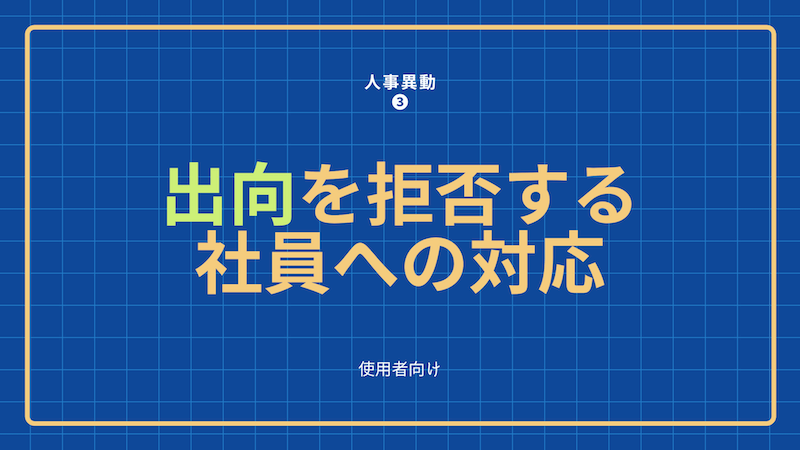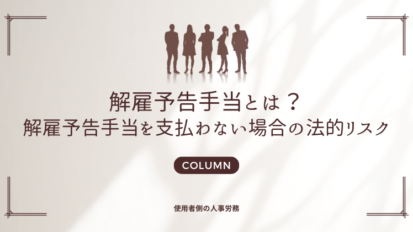はじめに
職場でハラスメントや不正行為の疑いが持ち上がった場合、第三者委員会を設置し、社内調査だけでは不十分な公正性を確保することが求められる場面があります。とりわけ、組織上の上位者が関与している場合など、内部調査だけでは忖度やバイアスが介入するリスクが高いです。そこで、外部の弁護士や有識者を交えた第三者委員会が客観的に事実を調査・報告書を作成し、問題解決を図る手法が注目されています。
本記事では、第三者委員会の意義や選任方法、調査の進め方・報告書の作成ポイントなどを、弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。企業が不祥事やハラスメント問題に適切に対応し、社会的信用を維持するために重要な指針となるでしょう。
Q&A
Q1. なぜ第三者委員会が必要なのでしょうか?内部調査ではダメなのですか?
内部調査だけだと会社の上層部や調査担当と利害関係があることが多く、公正性や客観性が疑われるリスクがあります。第三者委員会は、独立した外部の専門家(弁護士や公認会計士など)を含むことで、透明性を高め、外部や被害者からの信頼を得やすい点が大きなメリットです。
Q2. どんな場合に第三者委員会を設置するのが一般的ですか?
例えば、大規模なハラスメント問題や企業不正(経理不正・粉飾決算など)、役員クラスが関与している疑いがある場合などに設置されることが多いです。社内調査では公正を担保できないと考えられる事案で、社会的影響が大きい場合に委員会が活用されます。
Q3. 第三者委員会のメンバーは誰が選ぶのですか?
企業が選任しますが、「第三者」の独立性を確保するため、外部弁護士や公認会計士、学識経験者などを含めることが原則とされています。会社の利害関係者(顧問弁護士や社内者)が多すぎると「第三者性」に疑問が生じ、社会的信用を得られません。
Q4. 第三者委員会の調査が進む中で、企業はどう関与すればよいですか?
基本的に第三者委員会は独立した視点で調査を行うため、企業は調査資料の提供や関係者へのアクセス許可など必要な協力をします。ただし、企業が過度に介入したり報告書の内容を修正させようとするのは第三者性を損なう行為として問題視される可能性が高いです。
Q5. 第三者委員会の報告書には法的拘束力があるのですか?
報告書自体は法的拘束力を持つ「判決」ではありませんが、公表されることが多いため社会的影響が大きいです。企業は報告書の提言を踏まえ、改善策を実行しなければ対外的信用を失うリスクが高まります。
解説
第三者委員会設置のメリット
- 公正性・透明性の確保
- 外部有識者が調査することで、会社内部のしがらみや利害関係を排除しやすい。
- 被害者や社会への説得力が高まる。
- 企業イメージの回復
大規模ハラスメントや不正事件が発生した際、第三者委員会を通じて厳正な調査を行う姿勢を示すことで、株主や取引先の信頼を得やすい。 - 包括的な再発防止策
第三者視点での報告書により、問題の本質を探り、改善提言が示されるため、企業が抜本的改革を行うきっかけになる。
第三者委員会の選任方法・構成
- 選任主体
会社(取締役会や監査役など)が決議で設置を決める場合が多い。 - メンバー選定
- 弁護士(特にハラスメントや企業不祥事に詳しい専門家)や会計士、学識経験者など、会社と独立した外部有識者を中心に構成。
- メンバーが会社の利害関係者だと第三者性が疑われる。顧問弁護士や社外役員を入れる場合は十分に独立性を検討する。
- 委員長・事務局
具体的な調査活動を統括する委員長と、書類作成・調整を行う事務局機能を設置する。
調査手続の進め方
- 調査範囲の確定
どのハラスメント事案を対象とするのか、どれだけ過去に遡るのかなど調査範囲を明確化。 - 資料収集・ヒアリング
当該ハラスメントに関連するメール、チャット履歴、録音データなどを取得。被害者・加害者・目撃者への事情聴取を行い、公正なプロセスを担保。 - 報告書の作成
事実認定や原因分析を行い、客観的根拠に基づいて結論を導く。さらに、再発防止策や改善提案も盛り込む。 - 報告書の公表と後始末
- 報告書を社内外に公表するかどうか、どの範囲で公表するかは企業の判断だが、社会的注目度が高い場合は原則公表が求められやすい。
- 報告書の提言に基づき、加害者処分や組織改革を実行。
実務上の注意点
- 企業の関与の仕方
企業は調査資料や関係者リストを提供するなど協力するが、調査過程や報告書の内容には介入しない。 - 守秘義務と公正性
委員会メンバーは調査情報を第三者に漏らさない守秘義務を負うと同時に、被害者や加害者への配慮を行う。 - 時間とコスト
第三者委員会は一定の期間(数カ月程度)と、弁護士等への報酬・事務経費など相応のコストがかかる。企業として十分な予算とスケジュールを確保。 - 紛争リスク管理
報告書作成後、加害者や被害者が不満を抱く場合もある。結果に不服な者が裁判に訴える可能性を想定し、法的リスクを十分に検討する必要がある。
弁護士に相談するメリット
第三者委員会を活用するには、設置目的の明確化や公正なメンバー選定、調査手続の適正運営など多岐にわたる専門知識が要ります。弁護士に相談することで得られる利点は以下のとおりです。
- 委員選定と設置準備
外部有識者(複数の弁護士)をどう選ぶか、企業との利害関係をどう排除するかなど、適切なメンバーを確保するためのアドバイス。 - 調査手順・証拠収集の指導
事実認定にあたって必要な文書やヒアリング手法を提案し、後日の紛争リスクを回避できる手続き設計を支援。 - 報告書チェック
法的に不正確な表現や、当事者の権利保護に不足がある場合、弁護士が補正提案を行い法的リスクを軽減。 - 紛争対応
報告書に対して当事者が異議を唱え裁判となった場合、弁護士が企業を代理して主張立証を行い、ダメージを最小化する。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、ハラスメントや不祥事に対応する第三者委員会の立ち上げから運営、報告書作成後のフォローまで、多角的にサポートが可能です。
まとめ
- 第三者委員会は、企業が社内不祥事やハラスメントを調査する際に、外部専門家を交えて公正・客観的に事実確認する仕組みです。
- 選任されるメンバーの独立性や、調査範囲・方法を明確化しないと、「第三者性がない」と批判され、報告書の信用性が損なわれます。
- 報告書公表後の改善提案や再発防止策を企業が実行することが重要であり、無視すると企業イメージや信頼を大きく損ねるリスクがあります。
- 弁護士に相談すれば、第三者委員会設置のノウハウ提供や調査手続きのアドバイス、紛争時の対応まで、一貫した専門サポートを受けられます。
大きな不祥事やハラスメント事案が起きた際、迅速かつ適正な第三者委員会調査が社会的信用を守る鍵となるため、企業は委員会設置に関するルールづくりも視野に入れておくことが望ましいです。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス