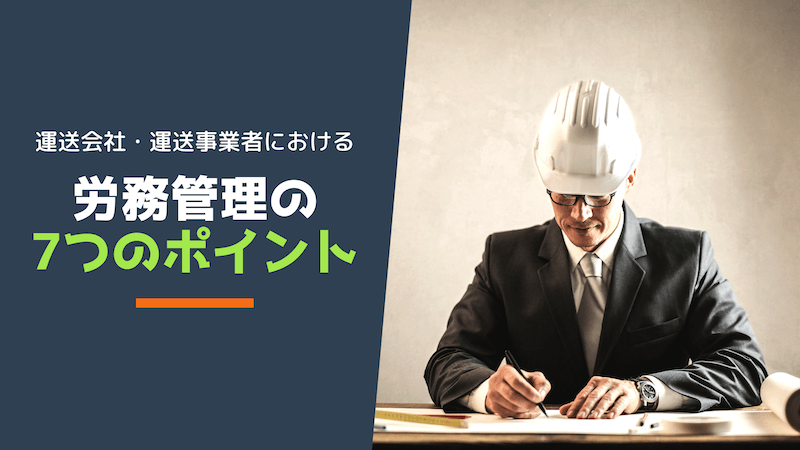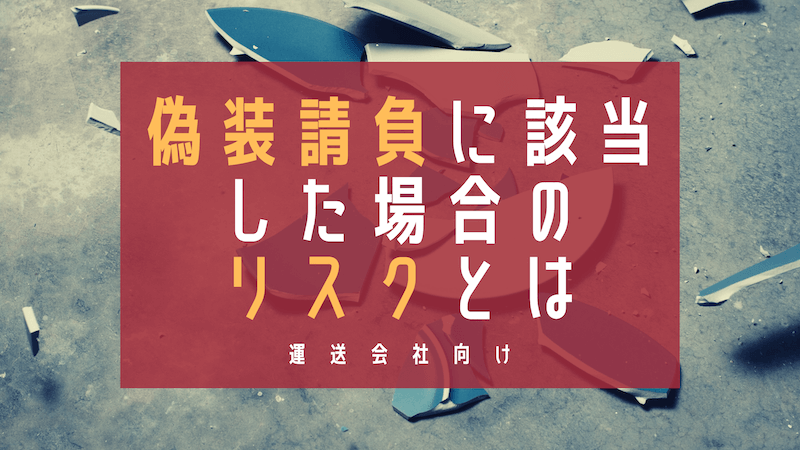はじめに
2024年4月1日、運送業界における働き方が根本から変わる法改正が全面的に施行されました。その核心が、自動車運転業務に対する「時間外労働の上限規制(年960時間)」です。多くの経営者様や労務管理ご担当者様が、この「960時間」という数字を強く意識されていることと存じます。
しかし、この規制を「守るべき努力目標」や「行政指導の対象となる程度」と軽く考えてはいないでしょうか。それは、極めて危険な認識です。この上限規制は、労働基準法という強行法規に定められた絶対的なルールであり、違反した場合には「罰則(刑事罰)」が科される犯罪行為となり得ます。
罰金や懲役といった直接的な罰則はもちろんのこと、違反の事実は運輸局による行政処分、荷主からの信頼失墜、金融機関の評価低下、そして何より人材の採用難や離職といった、事業の存続そのものを揺るがす深刻な法務リスクを連鎖的に引き起こします。
本記事では、時間外労働の上限規制に違反した場合に科される罰則の具体的な内容と、それがもたらす罰金だけでは済まない、恐るべき経営上のリスクについて解説します。
Q&A
Q1. 「年960時間」の上限には、休日労働の時間も含まれるのでしょうか?
いいえ、「年960時間」という上限の計算には、原則として休日労働の時間は含まれません。これはあくまで「時間外労働」の限度時間です。
しかし、注意すべき点が2つあります。第一に、別の規制である「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」「時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月のいずれの平均も80時間以内」というルールには、休日労働が含まれます。
第二に、休日労働をさせた場合、その分の割増賃金(35%以上)の支払い義務はもちろん発生します。時間管理上は別カウントですが、労務管理全体で一体的に捉える必要があります。
Q2. 罰則を受けるのは、会社(法人)だけですか?社長や運行管理者も対象になりますか?
労働基準法違反の罰則は、「両罰規定」が適用されます。これは、違反行為を行った従業員個人だけでなく、その事業主である法人も罰する、という規定です。
さらに、法人の代表者(社長など)や、労務管理の責任者(役員、部長、運行管理者など)が違反行為の計画や実行を主導していたと判断されれば、その個人が「実行行為者」として処罰の対象となる可能性があります。
つまり、会社に罰金が科されるだけでなく、社長個人に懲役刑や罰金刑が科されるリスクもゼロではないのです。
Q3. 違反が発覚した場合、すぐに警察に逮捕されたりするのでしょうか?
通常、労働基準法違反は、まず労働基準監督署による調査(臨検監督)から始まります。その中で違反が発覚した場合、是正勧告や指導が行われ、改善を促されるのが一般的です。
しかし、違反が極めて悪質である(長時間労働を意図的に隠蔽していた、虚偽の報告をしたなど)、あるいは再三の是正勧告に従わないといったケースでは、労働基準監督官は特別司法警察職員としての権限を行使し、逮捕・送検といった刑事事件として手続きを進めることがあります。
つまり、「いきなり逮捕」の可能性は低いものの、対応を誤れば刑事事件に発展しうる重大な問題であることに変わりはありません。
解説
1. 「年960時間」規制の法的根拠 – 労働基準法第36条の改正
そもそも、なぜ「年960時間」という上限が設けられたのでしょうか。これは、働き方改革関連法による労働基準法第36条の改正に根拠があります。
会社が従業員に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働(時間外労働)をさせるには、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)との間で書面による協定、いわゆる「36協定(サブロクきょうてい)」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
この36協定を結んだとしても、時間外労働には「月45時間・年360時間」という原則的な上限があります。しかし、臨時的な特別な事情がある場合には、「特別条項付き36協定」を結ぶことで、この上限を超えることが認められてきました。
今回の法改正で、自動車運転業務については、この特別条項を用いた場合であっても、超えてはならない上限として「年960時間」が設定されたのです。これは、ドライバーの健康を守り、過労死や過労運転による事故を防ぐための、社会的な要請に応える措置です。
2. 違反した場合の罰則 – 「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」
年960時間の上限規制に違反した場合、労働基準法第119条に基づき、事業者には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。この罰則の重みを、いくつかの観点から理解する必要があります。
- 刑事罰であることの重大性
これは行政指導や過料ではなく、「前科」がつく刑事罰です。法人の場合はもちろん、前述の通り、代表者や担当役員個人が処罰されれば、その人の経歴に前科が記録されることになります。 - 両罰規定による責任者の処罰リスク
「会社がやったことだから、自分は関係ない」という言い訳は通用しません。裁判例では、労務管理を実質的に担当していた取締役や支店長などが処罰の対象となったケースもあります。運行管理者も、ドライバーの労働時間を直接管理する立場にあるため、無関係ではいられません。 - 違反の意図は問われない
「上限を超えているとは知らなかった」「管理が甘かった」という過失であっても、処罰の対象となり得ます。結果として上限を超えてしまったという事実があれば、違法性が問われるのです。
3. 罰則だけではない!違反によって生じる重大な法務リスク
上限規制違反のリスクは、刑事罰だけに留まりません。むしろ、事業経営に与えるダメージは、以下の二次的、三次的なリスクの方が大きいかもしれません。
リスク①:運輸局による行政処分
労働基準法違反は、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の対象となります。運輸局は労働基準監督署と連携しており、労基法違反の情報は共有されます。
違反が確認されれば、事業計画の変更命令、車両の使用停止、事業の停止、そして最も重い「一般貨物自動車運送事業の許可の取消し」といった行政処分が下される可能性があります。
たった30日の営業停止でも、その間の売上はゼロになり、固定費の支払いや荷主との信頼関係維持が困難になるなど、経営への打撃は計り知れません。
リスク②:高額な未払い残業代請求訴訟
時間外労働の上限規制を違反しているということは、多くの場合、労働時間管理が杜撰であることを意味します。
これは、退職したドライバーや在職中のドライバーから、過去に遡って未払い残業代を請求される格好の材料となります。裁判で会社の主張が認められなければ、過去3年分(将来的には5年に延長)の未払い残業代に加え、同額の「付加金」の支払いを命じられることもあります。
従業員一人あたり数百万円、場合によっては数千万円規模の支払義務が発生するケースも珍しくありません。
リスク③:社会的信用の失墜と事業環境の悪化
法令違反で送検されたり、行政処分を受けたりした事実は、報道などを通じて公になります。一度「ブラック企業」というレッテルを貼られてしまえば、そのダメージは深刻です。
- 荷主・元請けからの取引停止
コンプライアンスを重視する荷主は、法令違反の運送会社との取引を敬遠します。 - 金融機関からの融資ストップ
銀行は、企業のコンプライアンス体制を厳しく見ています。法令違反は、融資の審査において重大なマイナス評価に繋がります。 - 採用難・人材流出
企業の評判は、インターネットを通じて瞬く間に広がります。労働環境の悪い会社に、新たな人材は集まりません。既存の優秀なドライバーも、将来に不安を感じて離職してしまいます。
4. 違反を防ぐためのコンプライアンス体制構築
これらの破滅的なリスクを回避するためには、付け焼き刃の対策ではなく、組織としてのコンプライアンス体制を構築することが不可欠です。
- 経営トップの強いコミットメント
まず、社長自身が「法令遵守は経営の最優先課題である」という強い意志を示し、社内に明確なメッセージを発信することがスタートです。 - 労働時間の客観的な記録・管理
デジタルタコグラフや勤怠管理システムを導入し、誰が見ても疑義のない客観的な労働時間データを蓄積します。 - 36協定の適切な運用
協定の内容を全従業員に周知徹底し、上限時間を超えそうな従業員がいないか、常にモニタリングする仕組みを構築します。 - 運行管理者と労務管理者の連携
運行管理者は日々の運行指示を、労務管理者は労働時間全体の管理を担います。両者が密に連携し、個々のドライバーの労働時間に関する情報をリアルタイムで共有する体制が重要です。 - 定期的な研修の実施
経営層から一般の従業員まで、全社的にコンプライアンス研修を定期的に行い、法改正の内容や違反のリスクに対する意識を高め続けます。
弁護士に相談するメリット
時間外労働規制に関する問題は、放置すればするほど深刻化します。運送業に精通した弁護士は、予防法務から有事対応まで、強力な盾となります。
- 労働基準監督署・運輸局の調査への対応
突然の調査(臨検監督)や監査が入った場合、経営者に代わって、あるいは同席して、専門家の立場で冷静かつ的確に対応します。不利益な回答をしてしまうリスクを防ぎ、是正勧告を受けた場合も、実現可能な改善計画の策訂をサポートします。 - 訴訟リスクの最小化
未払い残業代請求のリスクを診断し、訴訟に発展する前に、交渉による早期解決(和解)を目指します。また、訴訟に強い賃金規程や就業規則の整備を支援し、「そもそも訴えられない会社」作りをサポートします。 - 刑事事件化の回避
万が一、悪質な違反と見なされ、刑事事件に発展しそうな場合でも、早期の段階から労働基準監督署と折衝し、起訴を回避するための弁護活動を行います。 - 予防法務体制の構築
貴社の実態に合わせ、どこに法務リスクが潜んでいるかを診断し、それを解消するための具体的なコンプライアンスプログラムの構築を、ゼロからお手伝いします。
まとめ
時間外労働の「年960時間」規制への違反は、単なる「計算ミス」や「管理不足」では済みません。それは、懲役刑さえあり得る「犯罪行為」であり、罰金、行政処分、民事訴訟、信用の失墜という、事業の存続を脅かす四重苦のリスクを招きます。
「うちは大丈夫」「今までも何とかなってきた」という意識は、もはや通用しません。この規制を遵守することこそが、2024年以降の運送業界で生き残るための最低条件です。
コンプライアンスは、コストではなく、未来への投資です。ドライバーが安心して働ける環境を整えることが、結果的に事故を防ぎ、人材を定着させ、荷主からの信頼を勝ち取り、企業の持続的な成長に繋がります。
自社の労務管理体制に少しでも不安を感じる経営者様は、問題が表面化する前に、ぜひ一度、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。手遅れになる前の「予防法務」が、貴社の未来を守ります。
長瀬総合の運送業専門サイト
2024年4月1日からの働き方改革関連法施行により、物流業界での働き方が今までと大きく異なっていきます。
違反してしまうと刑事罰の対象になってしまうので、運送・物流業を営む方の対策は必須です。
「どうしたら良いかわからない」という方は当事務所までご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス