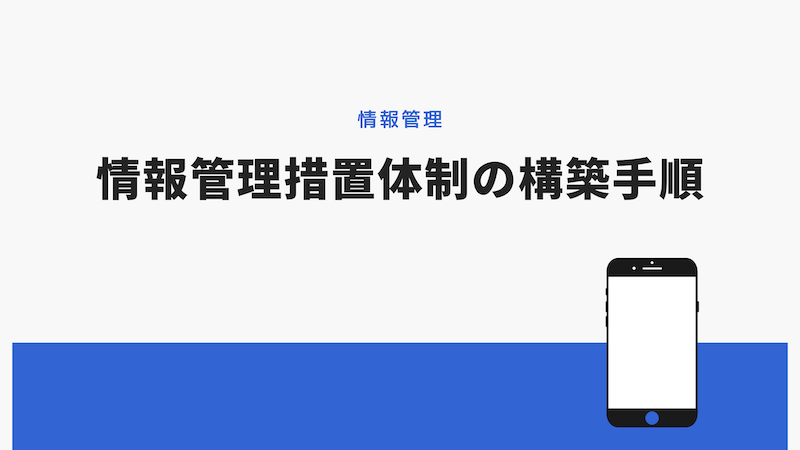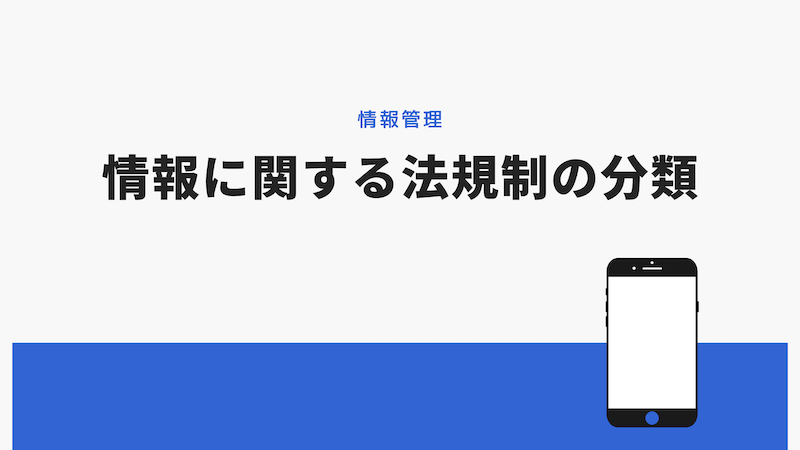はじめに
Twitter(現X)やInstagram、匿名掲示板、オンラインゲームなど、インターネットの世界では、本名ではなく「ハンドルネーム」や「アカウント名」を使って活動することが一般的です。そこで多くの人が抱く疑問が、「ハンドルネームに対する悪口は、法的に問題になるのだろうか?」というものです。
「ゲーム内で使っているだけのキャラクター名を馬鹿にされた」
「SNSの匿名アカウントに『死ね』と書かれた」
このようなケースで、名誉毀損や侮辱罪は成立するのでしょうか。また、投稿者を特定して損害賠償を請求することは可能なのでしょうか。
この記事では、ネット上の名前のあり方(実名・ハンドルネーム・匿名)と、権利侵害が認められるための重要な法的要件である「同定可能性」との関係について、弁護士が分かりやすく解説します。
Q&A
Q1. 私のSNSアカウントは本名も顔写真も出しておらず、誰だか分からないはずです。このアカウントに対して「こいつは職場でも無能」と書かれました。名誉毀損にはなりませんよね?
名誉毀損が成立するためには、その書き込みが「現実世界のあなた」に向けられたものだと第三者が見て分かること(同定可能性)が必要です。確かにお名前や顔写真を出していない場合、同定可能性は低いと判断される傾向にあります。しかし、もしあなたがそのアカウントで、勤務先の業界や職種、日々の業務内容など、あなたのことを知る人が見れば「これは〇〇さんのことだ」と推測できるような情報を発信していた場合は、同定可能性が認められ、名誉毀損が成立する可能性があります。
Q2. オンラインゲーム内で、私が長年使っているキャラクター名(ハンドルネーム)に対して、「〇〇(キャラクター名)はチート行為をしている詐欺師だ」とチャットで言いふらされました。訴えることはできますか?
このケースも、そのゲーム内のキャラクター名が、「現実世界のあなた」と結びつくか(同定可能性)が最大のポイントになります。例えば、あなたがそのキャラクター名を使ってゲーム実況の動画配信をしていたり、SNSアカウントを運用していたりして、そのキャラクターがコミュニティ内で「あなた自身」として広く認識されているような状況であれば、同定可能性が認められる可能性が高まります。逆に、そのゲーム内でしか使っておらず、現実のあなたとの結びつきが全くない場合は、キャラクターへの誹謗中傷と見なされ、あなた個人の権利侵害とは認められない可能性が高いでしょう。
Q3. 会社の同僚が、私のことをイニシャルを使ってブログに「営業部のSは、取引先から賄賂をもらっている」と書いていました。名誉毀損になりますか?
イニシャルや伏字であっても、名誉毀損が成立する可能性は十分にあります。重要なのは、そのイニシャルが使われている文脈です。「営業部のS」という記載に加えて、ブログの他の記事の内容や、登場人物の関係性などから、その会社の内情を知る人が読めば「これは佐藤さんのことに違いない」と客観的に特定できるような状況であれば、同定可能性は認められます。
解説
権利侵害が成立するための大前提「同定可能性」とは?
ネット上の誹謗中傷で、名誉毀損やプライバシー侵害といった権利侵害を主張するためには、「その誹謗中傷が、特定の個人や法人に向けられたものである」という事実が、法的に認められる必要があります。
つまり、問題の書き込みを読んだ第三者が、「ああ、これは現実世界の〇〇さんのことを言っているんだな」と分かる状態でなければならないのです。この、誹謗中傷の対象が、現実世界の誰であるかを特定できることを、法律用語で「同定可能性(どうていかのうせい)」と呼びます。
この「同定可能性」が認められない限り、たとえどれだけひどい悪口が書かれていても、原則として、特定の個人の権利が侵害されたとは見なされず、法的な請求(削除や損害賠償)は困難になります。
ケース別に見る「同定可能性」の判断基準
では、どのような場合に同定可能性が認められるのでしょうか。ネット上で使われる名前のタイプ別に見ていきましょう。
【ケース1】実名での誹謗中傷
例:「鈴木太郎(東京都世田谷区在住)は、詐欺で逮捕歴がある」
これは最も分かりやすいケースです。氏名が直接記載されているため、誰に対する権利侵害であるかが明白であり、同定可能性は問題なく認められます。
仮に同姓同名の人物がいたとしても、「東京都世田谷区在住」といった付随情報によって対象者が特定できるため、結論は変わりません。
【ケース2】ハンドルネーム・アカウント名での誹謗中傷
例:「アカウント名@hoge_hogeは、盗作ばかりしている」
ここが最も判断が分かれる、デリケートな部分です。ハンドルネームへの誹謗中傷が、現実世界の本人への権利侵害と認められるかどうかは、そのハンドルネームと本人の結びつきの強さ、すなわち同定可能性の有無にかかっています。
裁判例などを踏まえると、以下のような事情がある場合に同定可能性が認められやすくなります。
プロフィール等で現実の情報を公開している
アカウントのプロフィール欄に、本名、顔写真、勤務先、出身校などを記載している。
投稿内容から本人が推測できる
日常的に、自身の職業、家族構成、居住地域、趣味など、私生活に関する情報を発信しており、知人が見れば本人だと分かる。
ハンドルネームが社会的に本人と同一視されている
- そのハンドルネームを使って書籍を出版している、講演活動をしている。
- そのハンドルネームで活動する著名なブロガー、YouTuber、プロゲーマー、イラストレーター、VTuberなどで、ファンの間では「ハンドルネーム=本人」という認識が確立している。
逆に、そのSNSやゲームの中だけでしか使っておらず、現実世界の情報を一切発信していない、完全に匿名のハンドルネームについては、同定可能性が否定される可能性が高くなります。
【ケース3】イニシャル・伏字・その他の属性情報での誹謗中傷
例:「茨城県U市のN総合法律事務所の弁護士Nは、腕が悪い」
氏名が直接書かれていなくても、同定可能性が認められるケースは多々あります。
上記の例では、「茨城県U市」「N総合法律事務所」「弁護士N」という複数の情報を組み合わせることで、その地域や業界の関係者が見れば、どの弁護士を指しているか容易に特定できるでしょう。このように、断片的な情報であっても、それらを総合的に判断し、一般の読者が対象者を特定できると認められれば、同定可能性は肯定されます。
「侮辱罪」における同定可能性
名誉毀損が「人の社会的評価」という外部的な名誉を守るものであるのに対し、侮辱罪は「個人の名誉感情(プライド)」という内面的な名誉も保護の対象とします。
そのため、侮辱罪については、名誉毀損ほど厳密な同定可能性が要求されない、と解釈される余地もあります。
しかし、そうだとしても、「誰に」向けられた侮辱なのかが全く不明な状態では、犯罪として成立させることは困難です。最低限、書き込みをした本人と被害者の間など、一定の範囲で被害者が誰であるか分かる状態にあることが必要と考えられます。
弁護士に相談するメリット
ハンドルネームへの誹謗中傷で法的措置を検討する際、最大の壁となる「同定可能性」の有無の判断は、過去の裁判例などを踏まえた専門的な分析が必要不可欠です。
- 同定可能性についての的確な法的見通し
弁護士は、あなたのアカウントの運用状況や、投稿内容、コミュニティでの知名度などを詳しくヒアリングし、過去の判例と照らし合わせて、同定可能性が認められるかどうかの的確な見通しを立てることができます。 - 同定可能性を立証するための戦略的なアドバイス
同定可能性を裁判所などに認めてもらうためには、証拠が必要です。ハンドルネームと現実のあなたを結びつけるための証拠(過去の投稿、プロフィール情報、第三者からの評価など)をどのように集め、どのように主張すれば説得力を持つか、専門的な観点から戦略を立て、アドバイスします。 - 困難なケースでも諦めない姿勢
一見すると同定可能性が低く、法的措置が難しいと思われるようなケースでも、弁護士はあらゆる角度から証拠を検討し、主張を組み立てることで、解決の道筋を探ります。
まとめ
ネット上で使われるのがハンドルネームや匿名アカウントであっても、誹謗中傷は決して許されるものではありません。そして、そのハンドルネームが、現実世界のあなたと客観的に結びつけて認識できる(=同定可能性がある)場合には、名誉毀損や侮辱罪が成立し、加害者の責任を追及できる可能性があります。
「どうせハンドルネームだから」と泣き寝入りする前に、まずはご自身のアカウントが、現実世界のあなたとどの程度結びついているかを振り返ってみてください。そして、その判断に迷ったら、諦めずに弁護士にご相談ください。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、「こんなケースでも訴えられるだろうか」といったご相談にも、親身に対応いたします。初回相談は無料ですので、お一人で悩まず、ぜひお気軽にお問い合わせください。
長瀬総合の情報管理専門サイト
情報に関するトラブルは、方針決定や手続の選択に複雑かつ高度な専門性が要求されるだけでなく、迅速性が求められます。誹謗中傷対応に傾注する弁護士が、個人・事業者の皆様をサポートし、適切な問題の解決、心理的負担の軽減、事業の発展を支えます。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
当事務所は多数の誹謗中傷の案件を担当しており、 豊富なノウハウと経験をもとに、企業の皆様に対して、継続的な誹謗中傷対策を提供しており、数多くの企業の顧問をしております。
企業の実情に応じて適宜顧問プランを調整することも可能ですので、お気軽にご連絡ください。