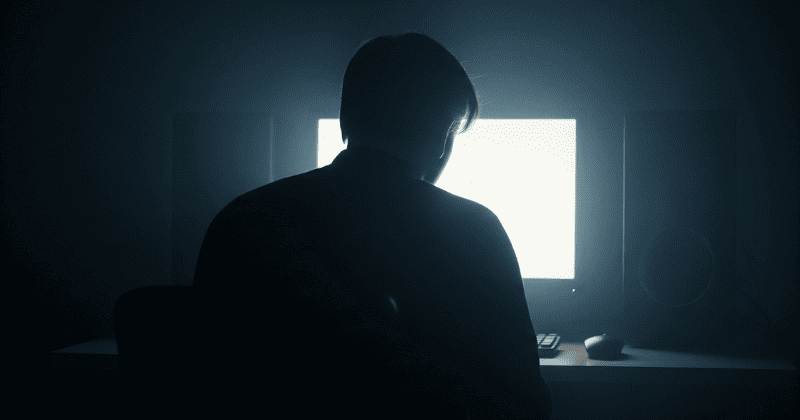はじめに
「ネットでの嫌がらせがひどい。これは犯罪ではないのか?」
「悪質な書き込みをした相手に、法的な罰を与えたい」
SNSや掲示板での誹謗中傷被害が深刻化する中、このような憤りや疑問を感じる方は少なくありません。ネット上の誹謗中傷は、単なるマナーやモラルの問題にとどまらず、刑事罰の対象となる「犯罪」に該当するケースが数多く存在します。
誹謗中傷の加害者に対しては、民事上の責任として損害賠償(慰謝料)を請求することに加えて、刑事上の責任として処罰を求める「刑事告訴」という手続きを取ることが可能です。
この記事では、ネットの誹謗中傷によって成立しうる主な犯罪の種類、それぞれの成立要件や科される刑罰について、詳しく解説します。ご自身の受けた被害がどのような犯罪にあたる可能性があるのかを知り、加害者の責任を追及するための一歩としてお役立てください。
Q&A
Q1. ネットの掲示板で「お前の家を燃やしてやる」「子どもに危害を加える」と書かれました。身の危険を感じるのですが、これは何という犯罪になりますか?
あなたやご家族の生命、身体、財産などに害を加えることを告知する書き込みは、「脅迫罪」に該当する可能性が高いです。脅迫罪は、相手を畏怖させる(怖がらせる)ような害悪の告知を行うことで成立します。実際に相手が恐怖を感じたかどうかは関係なく、客観的に見て人を怖がらせるに足りる内容であれば罪に問うことができます。「殺す」「燃やす」「危害を加える」といった内容は、脅迫罪の典型例です。身の安全に関わる問題ですので、速やかに証拠を保存し、警察や弁護士に相談することをお勧めします。
Q2. 経営している飲食店の口コミサイトに、「この店で食事をしたら食中毒になった」「店内でゴキブリを見た」などと嘘の情報を書き込まれ、客足が遠のいてしまいました。これは犯罪として訴えることはできますか?
嘘の情報を流して店の評判を落とし、業務を妨害する行為は、「信用毀損罪」や「偽計業務妨害罪」といった犯罪に該当する可能性があります。
「信用毀損罪」は、嘘の情報を流して人の経済的な信用や社会的評判を傷つける犯罪です。「偽計業務妨害罪」は、人をだましたり、勘違いさせたりするような手段を用いて、正常な業務運営を妨害する犯罪です。今回のケースでは、嘘の書き込みによってお店の信用を傷つけ、客足を遠のかせるという業務妨害の結果も生じているため、両方の罪に問える可能性があります。
Q3. 誹謗中傷で加害者を「刑事告訴」することと、民事で「損害賠償請求」することは、何が違うのでしょうか?両方同時にできますか?
「刑事告訴」と「損害賠償請求」は、目的と手続きが全く異なりますが、両方を同時に進めることは可能です。
- 刑事告訴
目的は「加害者に国の法律に基づいて刑事罰(懲役や罰金など)を与えてもらうこと」です。手続きは、警察や検察といった捜査機関に対して行います。 - 損害賠償請求
目的は「加害者の行為によって受けた精神的・経済的な損害を金銭で賠償してもらうこと」です。手続きは、加害者本人との交渉や、裁判所を通じた民事訴訟によって行います。
つまり、刑事告訴は「処罰」を、損害賠償請求は「賠償」を求める手続きです。弁護士に依頼すれば、刑事告訴を進めながら、並行して民事での損害賠償請求(示談交渉や訴訟)を行うといった、両面からのアプローチが可能です。
解説
民事責任と刑事責任の違い
ネット誹謗中傷の加害者が負う法的責任には、大きく分けて「民事責任」と「刑事責任」の2種類があります。
- 民事責任
被害者が受けた損害を、加害者が金銭などで賠償する責任です。これは当事者間の問題を解決するためのものであり、被害者が加害者に対して、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求(慰謝料請求など)を行います。 - 刑事責任
社会のルール(法律)を破ったことに対して、国が加害者に刑罰(懲役、禁錮、罰金など)を科すものです。これは社会の秩序を維持するためのもので、警察や検察が捜査を行い、裁判所が刑罰を決定します。
被害者が主体となって進めるのが民事手続き、国家機関が主体となって進めるのが刑事手続き、とイメージすると分かりやすいでしょう。
それでは、具体的にどのような行為が「犯罪」として刑事罰の対象になるのか、代表的な罪名をみていきましょう。
名誉毀損罪(刑法230条)
ネット誹謗中傷で最も典型的な犯罪の一つです。
成立要件
「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損した」場合に成立します。
- 公然と
不特定多数の人が閲覧できるネット掲示板やSNSなどが該当します。 - 事実を摘示し
内容の真偽を問わず、「Aは前科がある」「B社の製品は欠陥品だ」のように、人の社会的評価を低下させる具体的な事実を挙げることを指します。 - 人の名誉を毀損した
人の社会的評価を低下させる危険を生じさせた場合に成立します。実際に社会的評価が低下したことまでは必要ありません。
法定刑
3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金
特徴
名誉毀損罪は「親告罪」です。これは、被害者などからの告訴がなければ、検察官が加害者を起訴(公訴提起)できない犯罪を意味します。告訴できる期間は、原則として「犯人を知った日から6ヶ月」と定められています。
侮辱罪(刑法231条)
名誉毀損罪と並んで、誹謗中傷で問題となりやすい犯罪です。
成立要件
「公然と」「人を侮辱した」場合に成立します。名誉毀損罪との違いは、「具体的な事実の摘示」を伴わない点です。「バカ」「アホ」「死ね」「きもい」といった、相手を軽蔑する抽象的な表現や罵詈雑言がこれにあたります。
法定刑
1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料
特徴
2022年の刑法改正により、法定刑が大幅に引き上げられ、厳罰化されました。これにより、悪質なネット上の悪口に対する抑止効果が期待されています。侮辱罪も名誉毀損罪と同様に「親告罪」であり、公訴時効は厳罰化に伴い1年から3年に延長されました。
信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条、234条)
企業や店舗、個人事業主などがターゲットにされやすい犯罪です。
信用毀損罪(刑法233条前段)
成立要件
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」「人の信用を毀損した」場合に成立します。
「信用」とは、主に支払い能力や経済的な信頼性、さらには提供する商品・サービスの品質に対する社会的な信頼を指します。
例:「あの店は使い回しの食材を使っている」「A社は倒産寸前だ」などと嘘の情報をネットに書き込む行為。
偽計業務妨害罪(刑法233条後段)
成立要件
「偽計を用いて」「人の業務を妨害した」場合に成立します。
「偽計」とは、人をだましたり、勘違いさせたりするような策略を用いることです。
例:飲食店に無言電話を何十回もかける、ECサイトに大量のいたずら注文を入れる行為。
威力業務妨害罪(刑法234条)
成立要件
「威力を用いて」「人の業務を妨害した」場合に成立します。
「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことです。暴行や脅迫だけでなく、大声で怒鳴り続ける、店内に居座るなどの行為も含まれます。
例:市役所のウェブサイトに「爆破予告」を書き込み、職員に避難や警戒をさせて正常な業務を妨害する行為。
法定刑
いずれも、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
脅迫罪(刑法222条)
生命や身体への危険を感じさせる悪質な書き込みは、脅迫罪にあたります。
成立要件
「本人又はその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」「人を脅迫した」場合に成立します。
「害悪の告知」の内容は、客観的に相手を怖がらせるに足りるものであれば足ります。相手が実際に怖がったかどうかは問われません。また、脅し文句を実現するつもりがなくても罪は成立します。
法定刑
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
特徴
脅迫罪は「非親告罪」であり、被害者の告訴がなくても捜査機関が捜査し、起訴することができます。身の危険を感じた場合は、ためらわずに警察に相談することが重要です。
その他の関連する犯罪
上記以外にも、ネット上の行為が以下のような犯罪に該当する可能性があります。
- リベンジポルノ防止法違反
元交際相手などの私的な性的画像・動画を本人の同意なくネット上に公開する行為。 - ストーカー規制法違反
SNSのDMなどを利用して、特定の相手に執拗なつきまとい行為やメッセージの送信を繰り返す行為。 - 著作権法違反
他人が作成した文章、イラスト、写真などを無断でコピーして自分のサイトやSNSに掲載する行為。
弁護士に相談するメリット
ネット誹謗中傷で刑事罰を求めたいと考えたとき、弁護士に相談・依頼することで、多くのメリットが得られます。
- 犯罪立証の的確な見通し
どのような書き込みが、どの犯罪の構成要件に該当するのかを法的な観点から的確に判断します。証拠が十分か、刑事事件として立件される可能性があるかなど、専門家としての見通しをお伝えできます。 - 告訴状の作成と提出
刑事告訴を行うには、「告訴状」を作成して捜査機関に提出する必要があります。弁護士は、被害事実や処罰を求める意思を法的に説得力のある形で記載した告訴状を作成します。弁護士が代理人として告訴状を提出することで、警察も事件として受理しやすくなる傾向があります。 - 警察への対応
被害届や告訴状を提出した後も、警察から事情聴取の要請などがあります。弁護士が間に入ることで、警察とのやり取りをスムーズに進めることができます。万が一、警察がなかなか捜査を進めてくれない場合にも、弁護士から状況の確認や捜査を促すといった対応が可能です。 - 民事・刑事の両面サポート
刑事告訴で加害者の処罰を求めつつ、並行して、発信者情報開示請求で投稿者を特定し、民事の損害賠償請求を進めることができます。弁護士であれば、これら一連の手続きをすべてワンストップで対応し、被害回復に向けたトータルサポートを提供できます。 - 加害者との示談交渉
刑事事件では、加害者側から示談(和解)の申し入れがあるケースが少なくありません。加害者は、被害者との示談が成立することで、刑が軽くなる可能性があるためです。弁護士は、被害者の代理人として、精神的苦痛に見合った適切な金額の示談金を獲得できるよう、加害者側と交渉します。
まとめ
ネット上での安易な誹謗中傷が、懲役刑や罰金刑といった重い刑事罰の対象となる「犯罪」であることをご理解いただけたでしょうか。悪質な書き込みによって心身やビジネスに深刻な被害を受けた場合、泣き寝入りする必要は一切ありません。
- 名誉毀損罪
具体的な事実を挙げて社会的評価を下げる行為 - 侮辱罪
「バカ」「死ね」など抽象的な悪口 - 信用毀損罪・業務妨害罪
嘘の情報を流して店の評判を落とす、業務を妨害する行為 - 脅迫罪
「殺すぞ」「火をつける」など生命・身体に危険を感じさせる行為
これらの犯罪に該当する可能性がある場合は、刑事告訴によって加害者の刑事責任を追及することが可能です。刑事告訴は、民事上の損害賠償請求とは別の手続きであり、両方を同時に進めることもできます。
刑事手続きは専門性が高く、個人で進めるのは困難な道のりです。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、ネット誹謗中傷に関する刑事告訴・民事請求の双方に豊富な経験と実績がございます。「加害者を法的に罰してほしい」「二度と同じ被害に遭わないようにしたい」とお考えの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。あなたにとって最善の解決策を一緒に見つけ、その実現に向けて全力でサポートいたします。
長瀬総合の情報管理専門サイト
情報に関するトラブルは、方針決定や手続の選択に複雑かつ高度な専門性が要求されるだけでなく、迅速性が求められます。誹謗中傷対応に傾注する弁護士が、個人・事業者の皆様をサポートし、適切な問題の解決、心理的負担の軽減、事業の発展を支えます。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
当事務所は多数の誹謗中傷の案件を担当しており、 豊富なノウハウと経験をもとに、企業の皆様に対して、継続的な誹謗中傷対策を提供しており、数多くの企業の顧問をしております。
企業の実情に応じて適宜顧問プランを調整することも可能ですので、お気軽にご連絡ください。