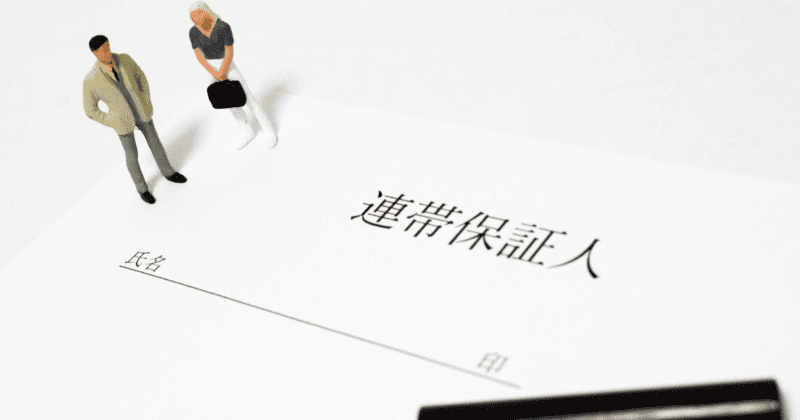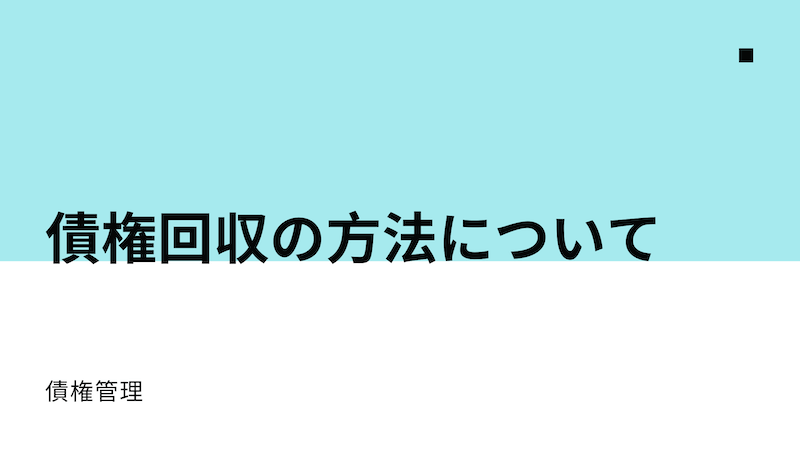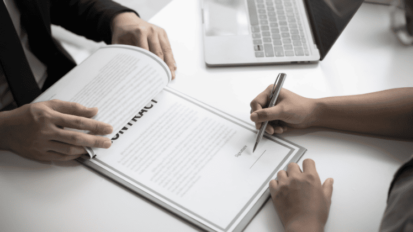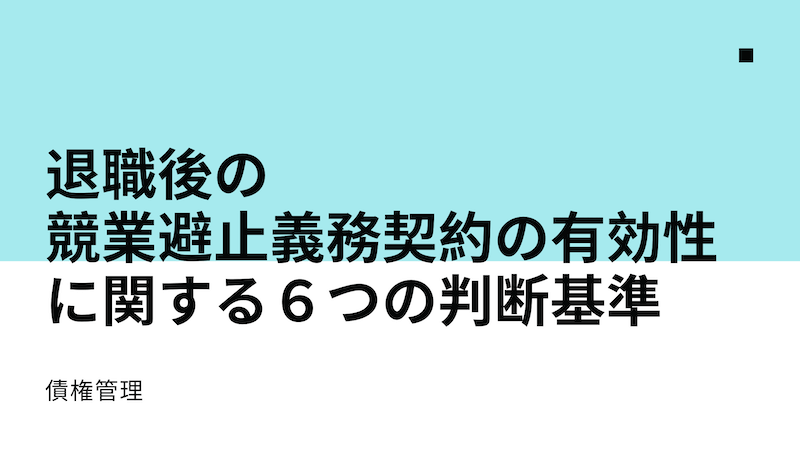はじめに
企業が取引先に商品やサービスを提供し、後払いを認める際、売掛金が未回収になるリスクを抑えるために、連帯保証や担保権の設定を検討するケースがあります。たとえば、取引先の代表者に連帯保証を求める、あるいは不動産や在庫などを担保に取ることで、債権を保全し、万が一の場合でも強制執行による回収が可能となります。
一方で、連帯保証を求めすぎると「過度な負担」であると批判されたり、新たな法改正(個人保証の規制強化)に抵触する懸念もあります。担保権の設定にも登記費用や融資慣行の問題などが絡みます。本記事では、連帯保証と担保権を活用する際のメリット・問題点を解説し、企業が安全かつ適切に債権回収を確保するためのポイントを提供します。
Q&A
Q1:連帯保証とは何ですか?
連帯保証は、債務者が支払いをできないとき(またはしないとき)に、連帯保証人が債務者と同等の責任を負って支払い義務を果たすことを約束する契約です。通常の保証契約と異なり、連帯保証では「催告の抗弁」や「検索の抗弁」がないため、債権者は債務者に請求せず直接連帯保証人に全額を請求できます。企業間取引では、社長個人が会社債務を連帯保証する例が典型です。
Q2:個人保証について法改正があったそうですが、何が変わったのですか?
2020年4月の民法改正では、個人保証に関して保証人保護を強化する規定が追加されました。具体的には、事業用融資で個人が保証人となる場合、貸主は保証人に対し、主たる債務者(借り手)の財務状況など必要な情報を提供しなければならない、また、高額保証を防ぐために公正証書で意思確認する仕組みが導入されています。企業が代表者に安易に個人保証を求めることが制限される方向へ進んでいます。
Q3:担保権にはどんな種類がありますか?
一般的には以下が代表例です。
- 不動産抵当権:不動産に設定し、債務不履行時に競売して優先的に弁済を受ける。
- 動産譲渡担保:在庫や機械設備などを担保にする。
- 債権譲渡担保:売掛金などの債権を担保にする。
- 質権:有価証券や動産を質入れして引き渡しを受ける形の担保。
企業が安全に取引先の財産から回収するため、どれを活用するかは状況に応じて異なります。
Q4:連帯保証や担保を取っても回収できない場合はありますか?
あります。例えば、連帯保証人が無資力(財産や収入がない)だと回収できませんし、担保物件が額面より大幅に価値が低下していれば十分な弁済を得られません。また、設定手続きや登記にミスがあったり、他の債権者が既に優先担保権を持っている場合、回収順位が下がり満額回収が困難となることも。担保評価や優先順位の確認が大切です。
解説
連帯保証を活用するメリットとリスク
メリット
- 保証人から直接回収できるため、債務者が支払不能でも担保的機能を果たす。
- 追加交渉なしで連帯保証人に請求可能で、迅速な回収が期待できる。
- 取引先の代表者や資産家に保証を求めることで、支払い遅延を抑止する効果もある。
リスク・問題点
- 個人保証は民法改正で手続きが厳しくなり、保証契約締結時に適切な情報開示や公正証書が必要なケースがある。
- 過度に高額な保証を求めると「優越的地位濫用」と批判されるリスク。
- 保証人自身が無資力の場合、結局回収できない。資産状況を調べる必要がある。
実務上の注意
- 連帯保証契約の文言を契約書や保証契約書に明記し、債務名義として公正証書化できるようにすると強制執行が簡易になる。
- 代表者の交代や個人保証の解除条件なども考慮し、会社の合併や分割時に保証関係をどう継承するか検討が必要。
担保権の活用と担保設定手順
- 不動産抵当権
- 借主または取引先が所有する土地や建物を抵当に取り、登記簿に抵当権設定登記を行う。
- 借主が返済できない場合、不動産を競売して回収可能。
- 登記費用・税金が発生し、登記順位が先の抵当権より後だと満額回収ができない可能性がある。
- 動産譲渡担保
- 在庫や原材料、機械設備などを担保にする。通常は占有改定(実物は債務者が使い続けつつ、所有権は担保に)で設定するが、動産譲渡登記を活用することも可能。
- 価値評価が難しく、流動資産の場合は変動が激しい。保全力は不動産に比べて劣ることが多い。
- 債権譲渡担保
- 取引先の売掛金や受取手形を担保にして、譲渡登記を行う。取引先が倒産した場合でも、担保として譲渡された債権を直接回収できる。
- 二重譲渡のリスクや、第三者対抗要件(登記または確定日付公正証書)を満たす手続きが重要。
- 質権
- 有価証券や動産を現実に引き渡して質入れする。物理的に占有するため、実務では保管コストや活用制限があり、あまり用いられないが、確実な担保力がある。
担保権設定のメリットと問題点
- メリット
- 債務不履行時に速やかに強制執行し、担保物件から優先弁済を受けられるため、貸倒リスクを大幅に減らせる。
- 一度担保を設定すれば、追加の契約なしで回収を実行できる(ただし、手続きには競売などを経ることが多い)。
- 問題点
- 設定コスト(登記費用や弁護士費用)が発生し、また担保評価が困難だと貸付や取引条件が曖昧になる。
- 担保設定後に先順位の権利者が現れた場合、実質的に担保価値が下がるリスクがある。
- 動産や売掛金の担保は流動性が高いため価値が変動し、管理が難しい。
- 契約書整備
- 担保契約書を作り、対象物件や極度額(上限額)、実行の条件などを明確に規定。
- 保証契約や担保権設定契約が「不明確」だと、後から「契約は無効」と争われる恐れがあるため、法律専門家のチェックが望ましい。
企業実務での活用事例
- 中小企業への売掛金取引で連帯保証
- 取引先(中小企業)の代表者に連帯保証を求めるケース。ただし、個人保証規制(法人代表者保護)に留意し、適切な情報提供を行い公正証書で締結するなど手続きを踏む。
- 代表者に資産があれば回収可能性が高まるが、無資力だとあまり意味がない。
- 不動産担保設定
- 大口取引や融資で、不動産を担保に設定し、抵当権登記を行う。相手が期限内に返済・支払いできないと競売をかけられるので、支払遅延抑止効果が大きい。
- 土地・建物の評価や先順位抵当権の調査が必須。
- 動産・売掛金担保(ABL)
- 在庫や機械設備を担保にして融資する仕組み(動産譲渡登記)、または売掛金を担保にする制度(債権譲渡登記)。
- 問題は評価額や変動、譲渡登記手続きの手間などがあり実務負荷が大きいが、無担保よりは安全性が高い。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、連帯保証・担保権設定に関して以下のサービスを提供しています。
- 保証契約・担保契約書の作成・チェック
- 個人保証の規制や担保登記の実務に精通し、適法かつ有効な連帯保証契約や抵当権設定契約を起案。
- 保証人・担保提供者の権利保護やリスクを考慮しつつ、企業の回収安全性を高めるバランスを追求。
- 実行手続きサポート
- 債務不履行が起きた場合、競売申立てや不動産売却手続きなどを弁護士が代理。連帯保証人から直接回収する際の交渉や法的手段も対応可能。
- 再交渉・和解案の提示
- 債務者・保証人が困難を訴えた場合、分割払いや追加担保の提供を交渉し、貸倒を回避する戦略を提案。
- 法的手段に踏み切るか和解するかのメリット・デメリットを企業と共に検討し、最適な解決を目指す。
まとめ
- 連帯保証と担保権は企業が取引先に対して債権回収を確実にするための強力な手段だが、個人保証の規制強化や担保設定の費用・手続きなど、活用には注意が必要。
- 個人保証(代表者保証など)を求める場合は、民法改正で導入された説明義務や公正証書手続きに留意し、無資力な保証人では意味がない点も考慮する。
- 担保権として不動産抵当権、動産譲渡担保、債権譲渡担保などがあり、登記や管理コストをかけることで優先弁済権を確保し、債務不履行時に財産を強制的に処分できるメリットを享受できる。
- 弁護士の助言を得ることで保証契約・担保契約が適法に有効化され、実際に債権回収が必要となった場合も競売・差押えなどの法的手続きが円滑に進められる。
長瀬総合の債権回収専門サイト
企業活動において債権・売掛金・請負代金等を回収できないというのは、企業活動に支障を来しかねません。
私たちは、経営者・企業の皆様が債権回収でお悩みになることを解消するとともに、持続的な成長の一助となることをお約束いたします。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス