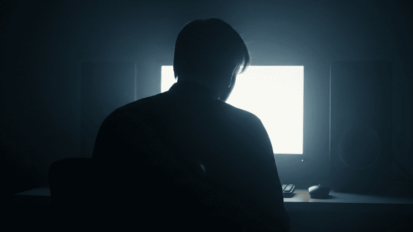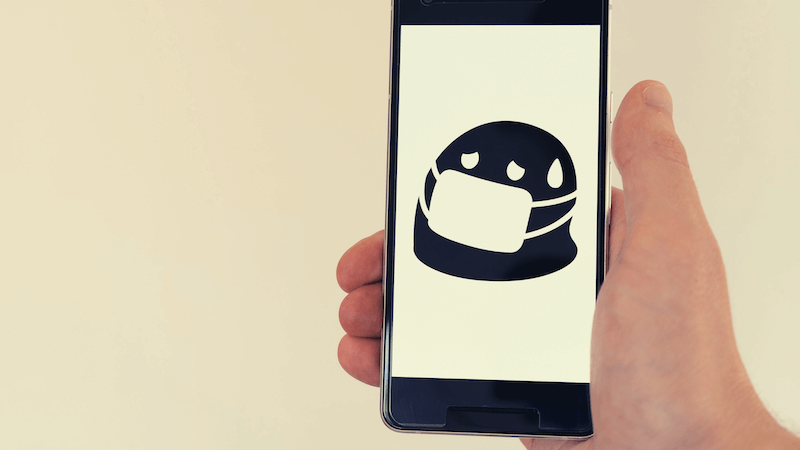はじめに
SNSが便利なコミュニケーション手段として定着した一方、一度誹謗中傷や不適切な情報が発信・拡散されると、被害が爆発的に大きくなるリスクがあります。いわゆる「二次被害」とは、一度投稿された不適切情報を他のユーザーがリツイート・シェア・引用投稿などを通じて広め、被害対象がさらに深刻なダメージを受ける状況を指します。
たとえば、企業に対する根拠のないデマがSNSで拡散され、顧客離れや取引停止など二次的な損害が発生するケースが散見されます。また、個人情報が流出して二次被害・三次被害が波及する例も後を絶ちません。本稿では、SNS拡散による二次被害のリスクを中心に、炎上対策やリスク管理のポイントを解説します。
Q&A
Q1:なぜSNS拡散による二次被害が起きやすいのでしょうか?
SNSは「いいね」「リツイート」「シェア」「引用投稿」など拡散の仕組みが充実しており、興味を引く内容(スキャンダル、過激な批判など)は一気に多くのユーザーに届きやすいからです。また、一次情報の真偽が十分に検証されないまま広まるため、被害が拡大しがちです。
Q2:SNS拡散による二次被害の具体例を教えてください。
企業への根拠のない不祥事の噂が一人のユーザーによって投稿され、それを面白がった第三者がリツイートして急速に広まり、最終的に大手メディアが取り上げる形で社会問題化してしまうケースなどがあります。個人情報の晒し(ドキシング)も、拡散による二次被害の代表例です。
Q3:SNSで炎上してしまった場合、企業はどう対処すればいいですか?
まずは事実関係を迅速に確認し、問題があれば公式に謝罪・改善策を示すことが重要です。デマであれば根拠を示して訂正を求める対応をとり、必要であれば削除依頼や法的措置を検討します。弁護士のアドバイスを受けて危機管理を行うとスムーズです。
Q4:逆に、拡散されている投稿を安易にリツイートしたりシェアしたりすると、法的責任を負う可能性がありますか?
あります。リツイートやシェアが他人の権利侵害(名誉毀損やプライバシー侵害)を拡大させた場合、違法性の認識があったかなど、状況次第で責任を問われる可能性は否定できません。
Q5:二次被害を未然に防ぐ方法はありますか?
企業の場合、定期的なSNSモニタリングやリスク管理体制の構築、従業員向けのSNSポリシー整備などが挙げられます。個人であれば、個人情報の取り扱いに十分注意し、不用意に投稿や共有を行わないことが重要です。
解説
二次被害が起こるメカニズム
- 一次投稿
- 誹謗中傷やデマ、個人情報などが最初に投稿される
- 投稿者が意図せず(または意図的に)根拠のない情報を流布する
- 興味を引き、拡散が始まる
- 過激・スキャンダラスな内容ほどユーザーの興味を惹き、多数のリツイートやシェアが発生
- 一部のユーザーが面白がって話を盛り、事実無根の付加情報を加える
- 被害者が気づかないうちに情報が大規模拡散
- その間、被害対象(企業・個人)は知らずに信用低下や顧客離れなどの損害を被る
- 炎上が過熱し、メディアが報道する段階にまで発展することも
二次被害が深刻化する理由
- SNSの瞬発力・拡散力
- 短時間で数千〜数万のユーザーに届く可能性がある
- 検索エンジンにもキャッシュが残り、半永久的に表示されるリスク
- 情報の断片化・誤認
- リツイートやまとめサイトによる引用で、情報が切り取られたり編集されたりして真意が歪められる
- 結果的に誤情報が「事実」として広まる
- 炎上による“加熱効果”
- 一度注目されると、多くのユーザーが便乗して批判や過激な言葉を投げかける
- 被害対象が反論や修正を行っても、収束しないどころかさらに拡散する場合がある
二次被害の具体例
- 企業デマ拡散→顧客離れ
「あの食品メーカーは衛生管理がずさんらしい」「○○店員が暴言を吐いた」など不確実な情報が拡散し、売上に大打撃 - 個人情報流出→嫌がらせの連鎖
住所や電話番号、家族構成などがSNSで晒され、無言電話や郵便物の嫌がらせが発生 - 政治的・社会的議論の過熱→個人攻撃
特定の議題に対して主張をしたユーザーが攻撃対象となり、誹謗中傷やプライバシー暴露が二次被害として起こる
二次被害のリスク管理・対策
- 定期的なモニタリング
- 「自社名」「サービス名」「製品名」などを定期的に検索し、SNS・掲示板・ブログでの書き込みを早期発見
- 専門の口コミ監視ツールやGoogleアラートを活用
- SNS炎上対策マニュアルの整備
- 万一炎上した場合、誰がどのような手順で謝罪・事実確認・改善策を公表するか明文化
- 社内の迅速な情報共有が鍵
- プライバシー対策・個人情報管理
- 従業員や個人がSNSに投稿する際のルールを設定し、個人情報や機密情報を安易に発信しない
- 個人利用でも勤務先や自宅情報などを不用意に公開しない
- 弁護士と連携した削除依頼・法的措置
- 誹謗中傷の一次投稿を削除できれば、二次拡散を抑えられる
- 運営会社が応じない場合は仮処分や発信者情報開示請求で再発防止を図る
弁護士に相談するメリット
炎上への初動対応サポート
企業がSNS炎上に直面した場合、弁護士は速やかに法的リスクを判断し、公表すべき謝罪文や改善策の内容、タイミングなどをアドバイスします。誤った対応がさらなる二次被害を招く恐れがあるため、専門家の知見が活きます。
削除依頼・加害者特定手続きの迅速化
名誉毀損やプライバシー侵害など、違法性のある投稿についてはSNS運営会社へ削除要請を行い、応じない場合は仮処分や発信者情報開示請求を起こすことができます。弁護士が書面を整備し、裁判所手続きを代行することで、被害拡大のリスクを抑えられます。
示談交渉・損害賠償請求
二次被害で損失を被った企業や個人が加害者に損害賠償を求める場合、弁護士が示談交渉を担当することで、感情的対立を抑えながら適正な賠償を得やすくなります。二次被害を再燃させないための和解条項設定なども考慮できます。
長期的リスク管理
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、SNSポリシーや内部コンプライアンス体制の構築支援、定期的なリスクアセスメントなどを通じて、企業や個人が長期的にネット上のトラブルから身を守るためのサポートを提供しています。
まとめ
- 二次被害の定義と発生メカニズム
- 一度投稿された不適切情報がリツイート・シェアなどで拡散
- 被害対象が気づかぬうちに大規模化・深刻化
- SNS拡散による二次被害の例
-
- 企業へのデマ拡散→売上低下
- 個人情報の流出→嫌がらせ・ストーカー被害
- 政治的・社会的発言に対する個人攻撃→誹謗中傷の連鎖
- 対策ポイント
- 定期的モニタリングと早期発見
- SNS炎上対策マニュアルの整備
- プライバシー保護と社内SNSルール
- 適切な法的手段の活用
- 弁護士との連携メリット
-
- 炎上時の初動対応・謝罪文アドバイス
- 運営会社への削除要請や発信者情報開示請求
- 示談交渉・損害賠償手続き
- 長期的リスクマネジメント
二次被害が起こると、その収束には多大な時間とコストを要します。早めのモニタリングと、万が一被害が発生した際には弁護士法人長瀬総合法律事務所など専門家へ相談し、法的手段を含む最善策を検討することが大切です。
長瀬総合の情報管理専門サイト
情報に関するトラブルは、方針決定や手続の選択に複雑かつ高度な専門性が要求されるだけでなく、迅速性が求められます。誹謗中傷対応に傾注する弁護士が、個人・事業者の皆様をサポートし、適切な問題の解決、心理的負担の軽減、事業の発展を支えます。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
当事務所は多数の誹謗中傷の案件を担当しており、 豊富なノウハウと経験をもとに、企業の皆様に対して、継続的な誹謗中傷対策を提供しており、数多くの企業の顧問をしております。
企業の実情に応じて適宜顧問プランを調整することも可能ですので、お気軽にご連絡ください。