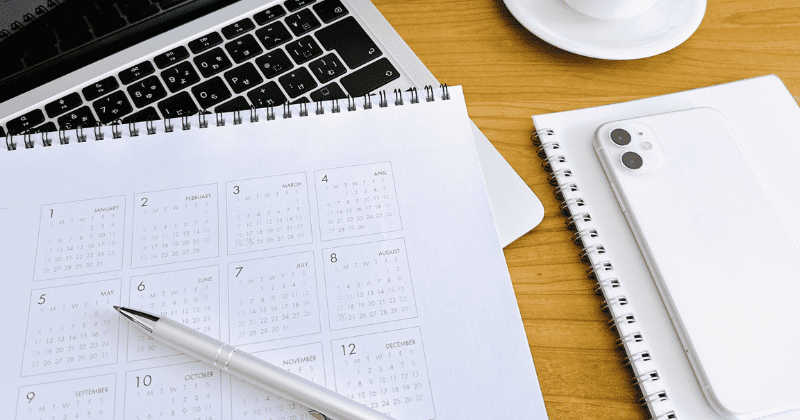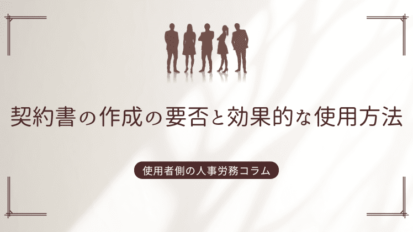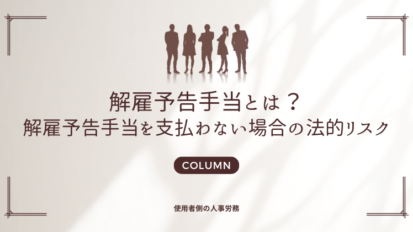はじめに
労働者が心身のリフレッシュや私用の処理などを目的に取得する年次有給休暇は、労働基準法で強く保護されています。とりわけ、2019年の法改正で「年5日の有給休暇の時季指定義務」が企業に課せられ、従業員に少なくとも5日は有給休暇を取らせることが義務付けられました。
しかし、実際には「有給休暇が取りにくい職場」や「消化義務をどう管理すればいいか不明」など、企業側の対応に悩みが多いことも事実です。本記事では、年次有給休暇の基本ルールや付与日数、管理簿の作成、違反時のリスクなどを整理します。自社の有給休暇管理のご参考となれば幸いです。
Q&A
Q1. 年次有給休暇の付与日数はどう決まりますか?
労働基準法第39条に基づき、継続勤務6カ月以上、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日の有給休暇を付与するところからスタートします。以降、継続勤務年数が増えるに従って付与日数も増え、6.5年以上勤務の場合は20日が最大です。所定労働日数が週4日以下のパートタイマーなどは、労働日数に応じた比例付与が行われます。
Q2. 年5日消化義務とは具体的に何をすればいいのですか?
2019年の改正労基法で、「年10日以上の有給休暇が付与される労働者」に対して、企業は少なくとも5日については時季を指定して取得させることが義務付けられました。従業員が自発的に5日以上取得した場合は問題ありませんが、取得が進まない場合は企業が時季指定を行い、有給休暇を取らせなければなりません。
Q3. 企業が勝手に有給休暇を割り当ててもいいですか?
年5日消化義務に関しては、「従業員の希望を聞いたうえで企業が時季指定」することが認められています。ただし、従業員の希望を無視して一方的に設定するのはトラブルの原因となりやすいため、あくまで労使協議や個別ヒアリングで柔軟に時季を調整することが望ましいです。
Q4. 有給休暇を取らせないと罰則がありますか?
年5日消化義務を履行しない場合、労働基準法上の罰則(30万円以下の罰金)が適用される可能性があります。また、従業員が訴えた場合は労働基準監督署の是正勧告を受けることも考えられます。
Q5. 年次有給休暇の管理簿はどのように作ればいいですか?
企業は、年次有給休暇の管理簿を作成し、労働者ごとに付与日や残日数、取得状況などを明確に記録する義務があります。Excelや専用ソフト、クラウドシステムなどを活用して管理するケースが多いです。
解説
年次有給休暇の基本ルール
- 付与要件
- 6カ月以上継続勤務、かつ全労働日の8割以上出勤した場合、最初の有給休暇10日が付与される。
- 以降、1年ごとに勤続年数に応じて日数が増え、最大20日。
- 時効
- 有給休暇は2年で時効消滅するため、付与から2年を経過した分は消えてしまう。
- 取得申請と時季変更権
- 従業員が有給休暇を申請した場合、時季変更権(業務に支障がある場合に変更を求める権利)を行使しない限り、企業は認める必要がある。変更権を行使する場合でも、代替の休暇時季を提示するなどの配慮が必要。
年5日の取得義務
- 対象者
年10日以上の有給休暇が付与される労働者(一般的なフルタイム社員や週4日以上勤務のパートなど)。 - 企業の責務
従業員が自発的に5日以上取得していない場合は、企業が時季指定を行い、有給休暇を取得させる。 - 従業員の希望考慮
企業が時季を指定する際は、従業員の意向を尊重しつつ、業務に支障の少ないタイミングを選ぶ。 - 違反時の罰則
この義務に違反すると30万円以下の罰金が科される可能性がある。
有給休暇管理簿の作成
- 記載事項
- 付与日、付与日数、取得日、残日数など、法令で指定された項目を従業員ごとに管理。
- 保存期間
3年間の保存義務。 - 電子化
Excelやクラウドシステムで管理している企業が多い。適正にバックアップし、すぐに出力できる形で保管。
実務でのポイント
- 計画的付与制度
あらかじめ会社と労働者代表で協定を締結し、有給休暇の一部を計画的に取得させる制度。年5日の義務をよりスムーズに達成可能。 - 繁忙期・閑散期の調整
特定の時期に全員が休むと業務に支障が出る場合、時季変更権を適切に行使し、別の時期に代わりの休暇を付与する。 - パートタイム・派遣社員への対応
週所定労働日数に応じた比例付与を忘れない。付与日数と年5日義務の対象を間違わないよう注意。 - 有休取得率向上への取り組み
働き方改革の流れで、従業員の有給休暇取得率は企業イメージにも影響。業務引継ぎや交代要員確保など、取りやすい環境づくりを推進。
弁護士に相談するメリット
有給休暇の付与・管理を適切に行わないと、時季指定義務違反や未消化日数をめぐるトラブルに発展するリスクがあります。弁護士に相談することで、以下のサポートが可能です。
- 就業規則・有休管理規程の整備
法令や判例を踏まえて、付与基準や取得手続き、計画的付与制度などを明確に定める。 - 年5日取得義務の履行支援
どの従業員が何日取っているかを管理し、取得不足の従業員に適切な時季指定を促す仕組みを構築。 - トラブル対応
有休の不承認をめぐる紛争や、退職時の未消化分請求などで問題が起きた際に、法的観点から最適な解決策を提案。 - 人事・労務担当者向け研修
有給休暇管理のポイントや罰則規定、実務ノウハウを社内研修で分かりやすく解説するなどのサービスも提供。
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、企業の有給休暇管理に関するご相談を多数手掛けており、サポート体制を整えています。
まとめ
- 年次有給休暇は、6カ月以上勤務かつ全労働日数の8割以上出勤で付与され、勤続年数に応じて最大20日まで増えるのが基本です。
- 年5日の時季指定義務があり、年10日以上付与される労働者に対しては少なくとも5日を取得させなければなりません。違反時には罰則があります。
- 有給休暇の取得状況を正確に把握するために、有給休暇管理簿を作成し、付与日・取得日・残日数などをしっかり管理する必要があります。
- 弁護士のサポートを受ければ、就業規則の整備や計画的付与制度の導入、さらには有休取得率向上に向けた具体的アドバイスなどを得られ、トラブル未然防止に役立ちます。
年次有給休暇は、従業員の健康やモチベーション維持にとっても重要な制度です。法令遵守と適切な管理で、有給休暇が取得しやすい職場づくりを進めましょう。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス