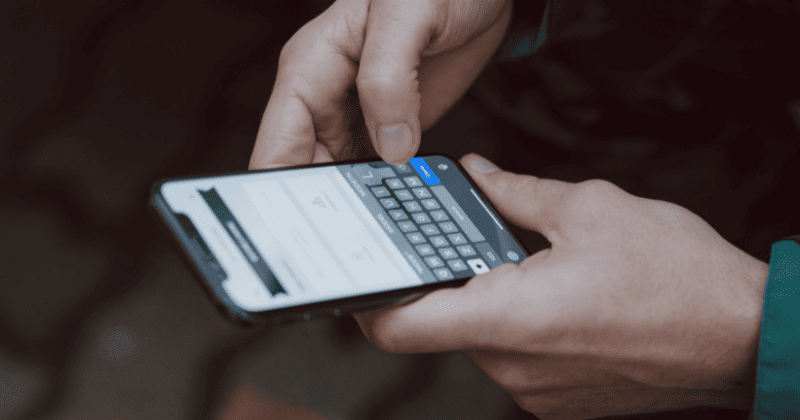はじめに
X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなど、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用者が爆発的に増加した現代。誰もが簡単に情報を発信でき、瞬時に世界中へ拡散される仕組みは便利な一方で、深刻な誹謗中傷問題を引き起こす舞台にもなっています。企業や店舗だけでなく、個人が名誉を傷つけられるケースも後を絶ちません。
本稿では、SNS上での誹謗中傷がなぜ増加しているのか、その背景や特徴、そして被害者や企業が被るリスクなどを解説します。SNSの特性を理解することで、誹謗中傷の発生を予防し、あるいは被害を最小限にとどめるご参考となれば幸いです。
Q&A
Q1:SNSでの誹謗中傷はなぜ増えているのでしょうか?
SNSは匿名性が高く、投稿や拡散が手軽であるため、加害者が罪悪感を持たずに他者を攻撃してしまうケースが増えています。また、コロナ禍などによる社会不安やストレスが背景にあり、鬱憤をSNSで晴らす人が増加しているとも考えられます。
Q2:SNSでの誹謗中傷はすぐに拡散されてしまうのでしょうか?
はい。SNSの「いいね」や「リツイート」「シェア」機能によって、投稿が瞬時に多くのユーザーに届き、一度拡散すると取り返しがつかないほど広がることがあります。
Q3:SNSでの誹謗中傷が法律で禁止されていることを知らない人は多いのですか?
実際、「ただの意見表明」や「冗談」と思って投稿している人も少なくありません。名誉毀損や侮辱、業務妨害などに該当し得る行為であることを意識せずに発信してしまい、後になってトラブルになるケースは多々あります。
Q4:SNSの投稿者は本当に特定できるのでしょうか?
発信者情報開示請求などの法的手続きを踏めば、加害者を特定できる可能性があります。完全に匿名と思われるアカウントでも、IPアドレスやログ情報をたどることで判明するケースがあります。
Q5:企業や個人がSNSアカウントを運営する際に、誹謗中傷対策として気をつけるべきことはありますか?
まずはSNSポリシーを策定し、運用ガイドラインを明確にすることが重要です。従業員教育も含め、炎上リスクを下げる措置をとりましょう。また、定期的なモニタリングや、万一誹謗中傷が発生した際の初動対応マニュアルを整備しておくと安心です。
解説
SNSにおける誹謗中傷が増加する背景
- 匿名性と気軽さ
- SNS上では本名を出さずに投稿できる場合が多く、書き込みへの心理的ハードルが低い
- 「バレにくい」「簡単に発信できる」という認識が、誹謗中傷を誘発しやすい
- 拡散力の高さ
- 1回の投稿が「いいね」やリツイート、シェアなどで瞬時に何百何千ものユーザーに届く
- デマや悪質な内容ほど面白がられて拡散されやすい傾向がある
- 情報の即時性と蓄積性
- リアルタイムで情報が流れるため、感情的な投稿をそのまま発信してしまう
- 一度ネット上に書き込まれた情報は、検索エンジンなどを通じて半永久的に残る可能性がある
- 社会的ストレスの高まり
- コロナ禍による不安や、経済的・社会的なストレスをSNSで発散しようとする人が増えた
- 不満や鬱憤を他者への攻撃として向けるケースが目立つ
SNS誹謗中傷の特徴
- ターゲットが個人・企業を問わない
- 有名人だけでなく、一般人や中小企業、店舗にも誹謗中傷が及ぶ
- 個人情報の晒し(ドキシング)や、企業の内部情報漏洩なども発生しやすい
- 連鎖的・集団的攻撃
- 誰かが批判的な投稿をすると、それに便乗するユーザーが増え、集団的にターゲットを攻撃する炎上が起こる
- 相互に煽り合い、過激化しやすい
- 真偽の検証が難しい
- 投稿者は具体的な根拠を示さないまま「○○会社は詐欺だ」などと書き込みがち
- 一度拡散されると、事実と異なる情報でも多数の人が信じてしまう可能性がある
- 被害が長期化・拡大化するリスク
- SNSの特徴として、投稿が削除されない限り検索やリツイートなどでいつでも再燃する
- 被害者が自力で対処できず、精神的負担が長期にわたる場合も少なくない
SNS誹謗中傷がもたらすリスク
- 企業のブランドイメージ・売上への打撃
- デマや悪評が拡散し、顧客離れや取引先の信用低下が起きる
- 業務妨害に発展するケースもある
- 個人への深刻な精神的ダメージ
- 名誉毀損や侮辱、プライバシー侵害が行われると、被害者がうつ状態になるなどの深刻な結果を招く
- 自殺に至る例も報道されるほど被害は重大
- 企業内部の混乱
- SNS上のクレームや誹謗中傷によって従業員が萎縮したり、社内秩序が乱れたりする
- 適切な炎上対応策を持たない場合、一気に評判を失うリスクが高い
- 二次被害・三次被害の可能性
- 炎上をきっかけに他のユーザーやメディアが注目し、さらなる拡散と悪評の増幅が起こる
- 被害回復に長い時間とコストが必要になる
弁護士に相談するメリット
SNS特有の違法性判断と削除依頼
SNSの仕組みを理解し、どのような投稿が名誉毀損や侮辱、業務妨害などに該当するかを法的に整理する必要があります。弁護士はこれらを的確に判断し、SNS運営会社への削除要請手順をスムーズに進められます。
発信者情報開示請求・損害賠償
悪質な誹謗中傷に対しては、投稿者を特定し、損害賠償を請求することで再発防止を図れます。弁護士が開示請求から示談交渉・裁判手続きまで一括で対応するので、被害者側の負担が軽減されます。
SNS炎上対応・危機管理体制の整備
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、ネット炎上への初動対応マニュアルや社内SNSポリシー、従業員向け研修のサポートなど、総合的なリスクマネジメント支援を行っています。万が一のトラブル時にも迅速に専門的なアドバイスを受けられます。
長期的視点でのブランド保護
法的措置だけでなく、誹謗中傷が繰り返されないような企業の体制づくり、ネットリテラシーの向上をサポートすることも弁護士の重要な役割です。長期的なブランディング保護の観点から、適切な対策を提案してもらえます。
まとめ
- SNSでの誹謗中傷増加の背景
- 匿名性と気軽さ
- 拡散力の高さ
- 社会的ストレスの高まり
- 誹謗中傷の特徴とリスク
- 短期間で爆発的に拡散
- ターゲットが個人・企業を問わない
- 精神的被害、ブランドイメージ毀損など長期的なダメージ
- 弁護士への相談メリット
- 違法性の判断と削除依頼サポート
- 加害者特定・損害賠償請求で再発防止
- 炎上対応マニュアルやSNSポリシーの整備支援
SNSは現代社会において必要不可欠なコミュニケーションツールである反面、誹謗中傷の温床にもなり得ます。被害を最小限に抑えるには早期対応が鍵です。もしSNS上で悪質な書き込みを発見した場合は、まずは弁護士などの専門家へご相談いただき、法的措置や危機管理対応を検討してみてください。
長瀬総合の情報管理専門サイト
情報に関するトラブルは、方針決定や手続の選択に複雑かつ高度な専門性が要求されるだけでなく、迅速性が求められます。誹謗中傷対応に傾注する弁護士が、個人・事業者の皆様をサポートし、適切な問題の解決、心理的負担の軽減、事業の発展を支えます。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
当事務所は多数の誹謗中傷の案件を担当しており、 豊富なノウハウと経験をもとに、企業の皆様に対して、継続的な誹謗中傷対策を提供しており、数多くの企業の顧問をしております。
企業の実情に応じて適宜顧問プランを調整することも可能ですので、お気軽にご連絡ください。