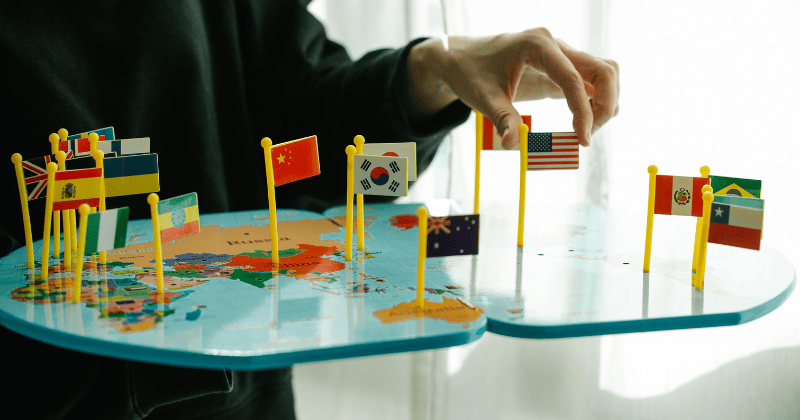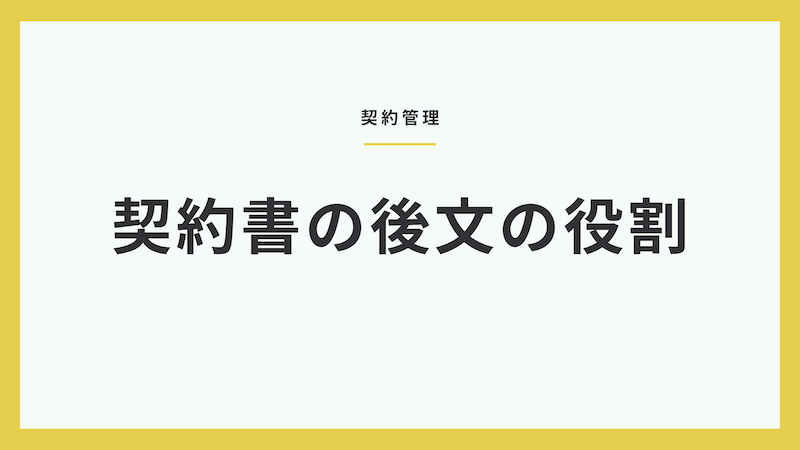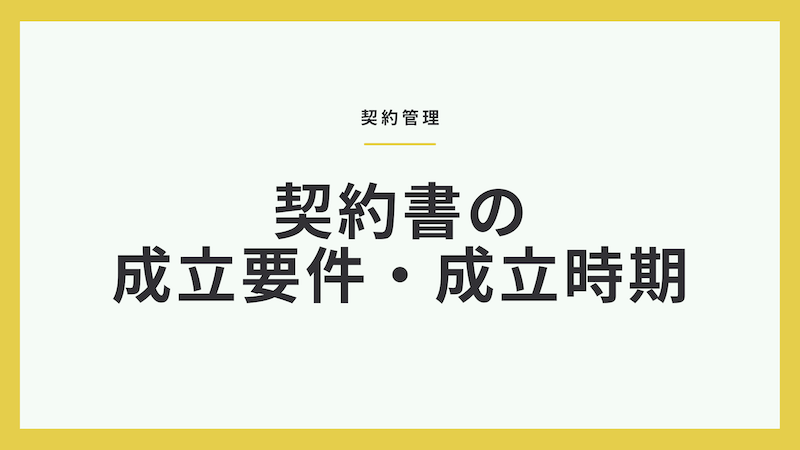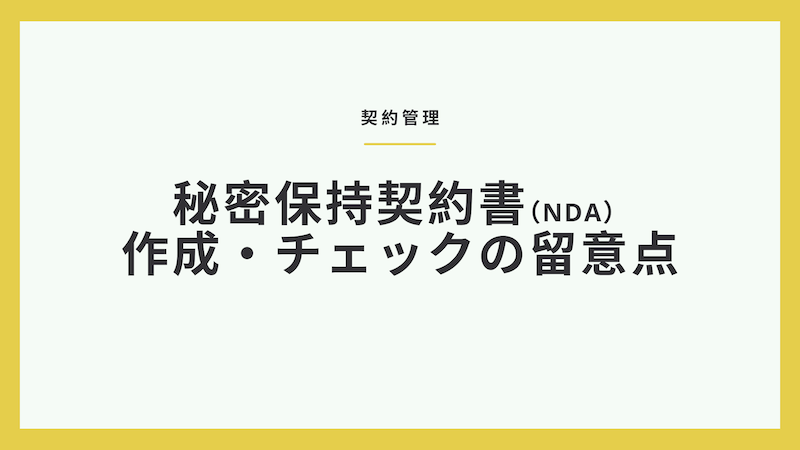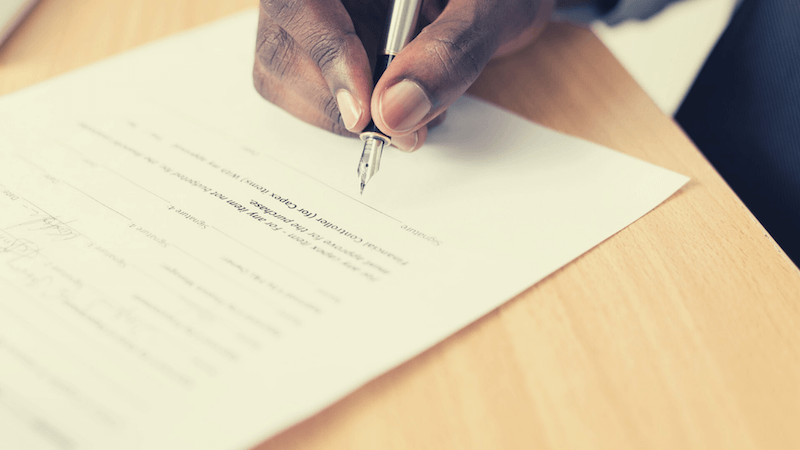はじめに
グローバル化が進む現在、多くの企業は海外の取引先と契約を締結する機会が増えています。しかし、国際取引には各国の法体系や文化、商慣習が入り混じるため、紛争リスクが高まりやすいのが実情です。その際、契約書で準拠法(どの国の法律を適用するか)や裁判管轄(どの国の裁判所・仲裁機関が紛争を扱うか)を明確にしないと、後に多大なコストと時間がかかる紛争に発展する可能性があります。
例えば、日本企業が欧米企業と契約を結ぶ場合に米国法や英法を準拠法とするケースがある一方、紛争が起きれば米国での訴訟費用が膨大となり、企業経営に深刻なダメージを与えかねません。本記事では、国際契約書における準拠法・裁判管轄の設定方法や、仲裁条項の活用など、グローバル契約で必要な法的リスク管理を解説します。
Q&A
Q1:なぜ国際契約で準拠法や裁判管轄を定める必要があるのでしょうか?
国際取引では、当事者が異なる国に所在し、それぞれの国内法が異なるため、トラブルが生じた際にどの国の法律を適用するかを明確にしないと、紛争解決が非常に複雑になるからです。また、「裁判をどこの国の裁判所でやるか」も決めないと、相手国の裁判所に強制される可能性があり、企業に不利に働くリスクがあります。契約締結時に準拠法と裁判管轄を合意することで、紛争時の予測可能性とコスト管理がしやすくなります。
Q2:裁判管轄は必ず裁判所を指定しなければならないのですか?
必ずしも裁判所(訴訟)を指定する必要はなく、仲裁条項を設けて、国際仲裁機関(ICC仲裁、SIAC仲裁等)を利用する方法があります。仲裁は迅速かつ非公開で行われ、国際商事取引ではよく用いられます。裁判所管轄を指定する場合は、自国の裁判所や相手国の裁判所を明記するほか、「どちらか一方の国」のみに専属合意管轄を設定するなど、交渉で決定します。
Q3:仲裁を選ぶメリット・デメリットは何ですか?
メリット
- 非公開で手続きが進み、企業の機密や評判を保護しやすい。
- 迅速に解決しやすい(ただしケースバイケース)。
- 国際仲裁合意があれば、外国の裁判所を経ずに直接、国境を越えた執行ができる(ニューヨーク条約による)。
デメリット
- 仲裁機関の費用が高額になる場合がある。
- 手続きの適用ルール(国際仲裁規則)に精通した弁護士や仲裁人が必要で、専門性を要する。
解説
準拠法の設定方法とポイント
- 自国法を選ぶメリット
- 自社が慣れ親しんだ法律で紛争を処理でき、法的リスクを把握しやすい。弁護士や判例リソースも豊富にある。
- 通常は自分の本拠地でビジネスを展開する側が自国法を準拠法に希望するが、相手方の交渉力によっては拒否される可能性もある。
- 相手国法を選ぶ場合
- 大企業や強い交渉力を持つ相手から求められ、日本企業がやむを得ず相手国法を受け入れるケース。
- 自国の法律ではないため、訴訟コストが大きくなるリスクがあり、契約交渉時にはロイヤリティや価格にそのリスクを織り込むことがあり得る。
- 国際私法と強行法規
- 準拠法を指定しても、受注地の強行法規(労働法、下請法など)は排除できない場合がある。完全に相手国の法律を避けることはできないため、契約書で明示的にどう扱うか検討が必要。
裁判管轄・仲裁合意の重要性
- 専属的合意管轄
- 「本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄とする」などと定め、他国の裁判所に持ち込まれるのを防ぐ。
- 相手方にとっては日本での訴訟が負担となるため、交渉で対立するポイントになりやすい。
- 国際仲裁機関の選定
- 「国際商業会議所(ICC)仲裁」「シンガポール国際仲裁センター(SIAC)」などを契約条項で指定し、紛争が起きた場合にその機関で仲裁を受けることを合意。
運用上の留意点
- 契約書への明記
- 契約書の終盤で「準拠法は○○法とする」「本契約に関する紛争は○○地の裁判所に専属管轄を置く」などの条項を必ず入れる。
- 国際仲裁を選ぶ際は、仲裁機関や規則(ICC規則、JCAA規則など)、仲裁地、仲裁言語を明記する。
- バトルオブフォーム
- 国際取引では、双方が独自の約款を提示し、どの約款が契約内容となるか(バトルオブフォーム)で揉める場合がある。
- その結果、準拠法や裁判管轄が明確にならないリスクがあるため、契約書の最終合意時に文書一体化条項を設け「本書が両当事者の完全合意」と規定する。
- 相手国での執行可能性
- いくら自国の裁判所で勝訴判決を得ても、相手国で強制執行できなければ実効性がない。
- 継続的な法改正のフォロー
- 国際取引は各国の法改正や通商条約、経済制裁の影響を受けることがある。特に輸出規制や関税政策が変わると契約条件の見直しが必要。
- 定期的に契約書を見直し、改定プロセスや覚書による修正を柔軟に行える体制を作ることが望ましい。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、グローバル契約の準拠法・裁判管轄設定に関して、以下の支援を行っています。
- 契約書レビュー・作成(英語対応)
- 国際取引契約書(英文)を法的観点からレビューし、準拠法や裁判管轄、仲裁条項のメリット・デメリットを企業の状況に合わせて提案。
- 多言語(英語)でのドラフト作成もサポート。
- リスク管理体制構築
- 契約書のレビューやアップデートで、企業の国際法務を継続的にサポート。
まとめ
- グローバル契約では、準拠法や裁判管轄を定めないと、トラブル時に「どの国の法律で裁くか」「どの裁判所で争うか」が不透明となり、予測不能なコストと時間がかかる紛争に陥りやすい。
- 準拠法を自国法にするメリット、相手国法や第三国法を採用するデメリットを踏まえたうえで交渉し、契約書に明記することが重要。
- 裁判より国際仲裁を選択するケースも多く、仲裁条項や仲裁機関(ICC、SIAC等)の選定で迅速かつ秘密裡に紛争を解決可能。ただし費用面や専門性も考慮する必要がある。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス