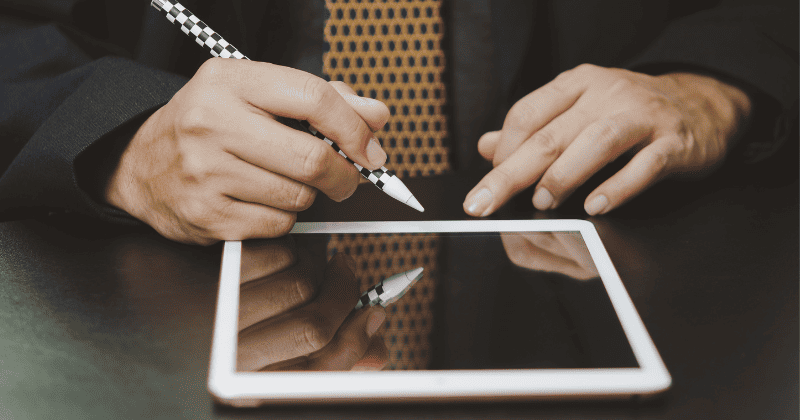はじめに
押印文化が強かった日本においても、近年では電子契約や電子署名の活用が急速に広がっています。企業がクラウド上で契約書を締結することで、書面・押印のやり取りが不要となり、契約業務の効率化やコスト削減が期待できるだけでなく、リモートワークの普及を背景に非対面での契約締結が可能となりました。
一方で、電子署名法や電子帳簿保存法の理解が不十分なまま電子契約を導入すると、締結の有効性やセキュリティリスク、改ざん防止措置の不備など法的リスクが生じる場合があります。本記事では、電子契約や電子署名を導入する際に検討すべき法的ポイントや運用上の注意点を解説します。
Q&A
Q1:電子契約と電子署名はどう違うのですか?
電子契約は、契約当事者が書面の代わりに電子データで契約を締結することを指し、これ自体は契約の形態を示すものです。電子署名は、電子ファイルに署名者を識別し改ざんを防止するために付与される技術的手段であり、「誰がサインしたか」を証明する機能を果たします。契約の締結に電子署名を使うことで、契約書の法的有効性や立証力を高められます。
Q2:電子契約に判子(押印)は不要なのですか?
2021年以降の法改正や運用見直しにより、原則として押印は不要です。電子署名法に適合する電子署名を用いることで、契約書への押印と同等の法的効果を得られます。また、民法上も書面に押印が必須という規定はなく、電子データで合意が成立すれば契約は有効です。ただし、一部の官公庁の手続きや特殊分野では依然として押印が求められる場合があるため、個別のケースで要確認です。
Q3:電子契約の導入で注意すべきセキュリティやリスクは何でしょうか?
- 改ざん防止
電子署名やタイムスタンプを活用し、契約書が後から改ざんされないようにする。 - 署名者の真正性
署名者が本当にその人であることを証明するため、電子認証局など信頼された機関の電子証明書を使う。 - データ管理・バックアップ
電子契約書をクラウドに保管する場合、アクセス権限やバックアップを適切に管理し、紛失・漏洩のリスクを減らす。 - 法令・ガイドライン適合
電子帳簿保存法や個人情報保護法、業法などに応じた対応(保存期間、検索要件など)を整備。
Q4:電子署名の種類(実質署名型、立会人型など)はどれを選ぶべきですか?
一般的なクラウド型電子契約サービス(立会人型署名)は、手軽に利用できる一方で、厳格な本人確認をそこまで行わない場合もあります。本当に証拠力を高めたい場合は実質署名型(当事者それぞれに電子証明書を発行し、電子署名法に基づく厳格な認証を行う)を検討すべきです。取引先との合意や業界慣行によってどのレベルの電子署名が必要か変わるので、契約内容の重要度やリスクに合わせて選択するのが大切です。
解説
電子契約の法的有効性
- 民法上の契約成立要件
- 日本では、意思表示の合致により契約は成立するとされ、書面や口頭かを問わない。電子契約も当事者が合意すれば原則として有効。
- 電子契約の場合は、合意事実を客観的に立証できる仕組み(電子署名や認証)があれば、証拠力が向上する。
- 電子署名法
- 電子署名法では、適正な手続き(認証局の証明書など)を経て付与された電子署名は、書面での自署押印と同等の効力を持つと規定。
- これにより、電子的にやり取りした契約書でも、適切な電子署名が付与されていれば法的に署名押印と同価値と認められる。
- 電子帳簿保存法
- 税務書類や契約書を電子保存する場合の要件を定める。改ざん防止措置や検索機能などが求められ、電子署名・タイムスタンプの付与が推奨される。
- 適切に要件を満たせば、紙での保存をせず電子データのまま保管可能となり、保管コスト削減や検索性向上が期待できる。
- 業法との整合
- 特定商取引法や不動産業法など、一部業種・業法で書面交付が義務付けられる場面がある。近年、電子交付の容認が進んでいるが、まだ規制が残る分野もあるため個別に確認が必要。
電子契約導入のメリットと課題
- メリット
- 契約締結のスピードアップ:郵送や対面押印が不要になり、遠隔地でも瞬時に契約締結可能。
- コスト削減:紙代、印紙代、郵送費を削減し、ペーパーレス化で保管スペースも不要。
- リモートワーク対応:コロナ禍で在宅勤務が増加する中、電子契約で非対面でも業務を進めやすい。
- 課題・リスク
- 証拠力の問題:単なるPDFデータにサイン画像を貼っただけでは、改ざん防止策が弱く、法的紛争で証拠力が低下する可能性。
- 相手方の同意:取引先によっては電子契約に馴染みがなく、書面押印を求められるケースが残る。
- 業法規制:建設業法や不動産取引など一部分野で電子契約の可否を注意しなければならない。
- 導入ステップ
- まず契約管理体制を見直し、どの契約を優先的に電子化するか選定。次に電子契約サービスや電子署名プラットフォームを導入し、社内フローを整備。
- 取引先にも電子契約のメリットを説明し、納得してもらう交渉が必要。必要なら相手先の法務部や経営陣を巻き込み、合意形成を図る。
電子契約書の要件とセキュリティ
- 改ざん防止(電子署名・タイムスタンプ)
- 電子署名にハッシュ値や電子証明書を組み合わせ、後から契約書データが変更されれば署名無効と分かる仕組み。タイムスタンプを付与することで契約締結日時の証明も同時に行える。
- クラウドサービス利用の場合、サービス事業者が改ざん防止措置を提供しているかをチェックする。
- 署名者の本人確認
- 電子署名法上、「作成者が真正に存在することを証明する機能」が求められる。簡易的な「立会人型」電子契約ではメールアドレス等で認証するが厳格性が劣る。
- より厳格な「実質署名型」では公的個人認証や商業登記認証局の証明書を使うなど、セキュリティレベルが高い。どのレベルが必要かは契約内容の重要度による。
- 保管・バックアップ
- 終了後の電子契約書を企業内サーバやクラウド上に保管し、アクセス権限を適切に設定。誤削除やシステム障害に備え、バックアップも取り、リカバリ可能な仕組みを構築。
- 電子帳簿保存法に適合する形で、検索機能や定期検証を行い、監査や税務調査にも対応しやすくする。
- ログ管理
- 電子契約締結の過程(署名日時、IPアドレスなど)を記録するログ管理により、後で紛争が起きた際に「本当に当事者が承認したか」を立証しやすくする。
- サービス提供者が自動でログを取得する仕組みが多いが、契約書をダウンロード・保存する際のログも活用できるようにするのが望ましい。
想定される紛争事例と回避策
- 相手方が電子契約の有効性を後から否定
- 「電子署名はしたが、担当者が勝手にやった。会社は承認していない」と言い出す。
- 対策:企業印相当の実質署名型を用い、担当者権限を企業内で明確化し、契約締結の承認フローを記録しておく。
- 電子契約書が改ざんされた可能性
- 片方が「契約書を改ざんしている」と主張し、締結後に条文が書き換えられたと争うケース。
- 対策:タイムスタンプや電子署名で改ざん不可能な仕組みを導入し、各当事者が同じ電子データを保管する形にしておく。
- 書面が必要な場面で電子契約を使用してしまう
- 一部の業種・業法では押印書面が義務化されている取引が残る。知らずに電子契約で結んだ場合、手続き不備で有効性が疑われる。
- 対策:対象外の取引や要押印の法規を事前に洗い出し、電子契約に適さないものは従来通り紙契約を行う。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、電子契約・電子署名の導入・運用において、以下のサポートを行っています。
契約フロー設計
- 企業内で電子契約システムを導入する際、承認フローや権限管理を法的観点からアドバイス。
- 対象外取引の選定や紙の押印を廃止する際の社内コンセンサスづくりもサポート。
紛争予防と対応
- 電子契約導入時に想定される紛争リスク(本人否認、改ざん主張など)を整理し、必要な証拠保全やログ管理の方法を提案。
- 実際に契約履行段階で紛争が起きた場合、企業側代理人として交渉・訴訟で電子契約の有効性を立証し、解決へ導く。
まとめ
- 電子契約と電子署名の導入は、契約締結の効率化やコスト削減、リモートワーク対応など多くのメリットがあるが、法的リスク(改ざん防止、本人確認など)を理解せずに導入するとトラブルに発展しうる。
- 電子署名法で認められた署名を使うことで、紙の署名押印と同程度の法的有効性が得られるが、実運用でセキュリティ対策やログ管理を適切に行う必要がある。
- 電子帳簿保存法や各業法の規定を考慮し、紙保存義務が残る業種や取引形態では注意が必要。
- 弁護士と連携し、電子契約の導入フロー整備やサービス選定、契約書の適法性確認、紛争発生時の対応などを行うことで、企業はリスクを最小限に抑えながらメリットを最大化できる。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス