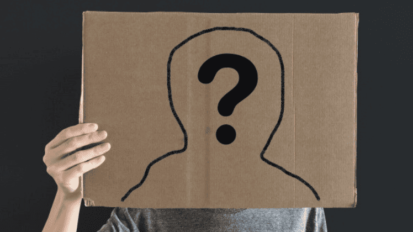はじめに
口コミサイトやSNSの活用が一般的となった現代では、企業・店舗がオンラインでの評価を上手にコントロールし、ブランドイメージを高めることが重要です。ただし「コントロール」といっても、やらせ投稿や不正操作は違法・不正競争行為にあたるリスクがあります。本当に必要なのは、「顧客のリアルな声を吸い上げ、誠実に対応して改善する」ことで、結果的に口コミの質が向上し、評判が好転するという正攻法です。
本稿では、実際に企業や店舗がオンラインの口コミ対策を成功させた複数の事例を取り上げ、どのような施策を打つことでネガティブ評価が改善し、ポジティブな評価が拡散したのかを解説します。口コミ対策に悩む担当者の方は、具体的な事例からヒントを得て、自社に活かしていただければと思います。
Q&A
Q1:口コミ対策とは具体的に何をするのですか?
企業や店舗に対する口コミやレビューをモニタリングし、誹謗中傷や不満の多い点を把握したうえで、サービス改善や誠実な返信を行うことで評価の向上を図ることです。また、やらせ投稿や不正な操作ではなく、あくまでも正しい方法で顧客満足度を高め、好意的な口コミを増やす施策を指します。
Q2:ネガティブな口コミが多い場合、すぐに削除依頼を出すべきでしょうか?
内容に明らかな事実誤認や誹謗中傷が含まれれば削除依頼を検討しても良いですが、単純に「接客が悪い」「料理がまずい」などの感想レベルであれば、まずは改善や誠実な対応を示すほうが効果的です。すべてを削除しようとすると逆効果になる場合もあります。
Q3:ポジティブな口コミを増やす有効な方法はありますか?
顧客が高い満足度を得られるよう、サービス品質や接客対応を根本的に改善することが第一です。加えて、SNS上や自社サイトで「口コミ投稿を歓迎する」姿勢を見せたり、協力してくれた顧客に感謝のメッセージを送るなど、小さなコミュニケーションの積み重ねが大切です。
Q4:成功事例を真似するだけで、必ずうまくいくのでしょうか?
企業や店舗ごとに状況や顧客層が異なるため、成功事例を参考にしつつ、自社の特性やリソースに合わせてカスタマイズすることが重要です。そのためにも事例の“本質”を理解する必要があります。
Q5:口コミ対策で弁護士が関与するのはどのような場面ですか?
誹謗中傷が明らかに名誉毀損や侮辱、業務妨害にあたる場合、投稿の削除依頼や発信者情報開示請求などが必要となります。また、悪質な口コミを放置して炎上し、会社の信用が大きく毀損されるリスクがある場合にも、危機管理の一環として弁護士のアドバイスが有効です。
解説
想定事例1:飲食店がクレームを顧客満足度向上に繋げるケース
背景
都内の飲食店Aは、オープン当初こそ話題性で客足が多かったものの、口コミサイトに「店員の接客が雑」「料理の提供が遅い」という不満が続出。すぐに星1や星2の低評価が増え、客足が減少していた。
取り組み
- 店長が直接クレーム内容を調査
口コミサイトで指摘された具体的な事項を洗い出し、スタッフミーティングで共有。 - 接客マニュアルの見直し
挨拶やオーダー確認、提供スピードに関するチェック項目を細かく設定。定期的にロールプレイングを実施。 - お詫びと改善の告知
SNSと店内ポスターで「お客様のご意見を基に改善を行いました」と周知。 - 感謝の返信
誠実なクレームやアドバイスをくれた口コミ投稿者には、店長が直接お礼のコメントを投稿(個人情報に配慮しつつ)。
想定事例2:ECサイトの低評価レビューを“有益なヒント”に変えるケース
背景
化粧品を扱うECサイトBは、新商品のリップクリームに対して「香りがきつい」「ベタつきが気になる」とネガティブレビューが相次ぎ、新規顧客の購入を阻害していた。
取り組み
- レビュー内容の分析
どの点に不満が集中しているかを抽出し、製品担当や研究部門と共有。 - 改良版の開発・案内
香料を控えめにし、テクスチャを軽くする試作品を短期間で作成。定期購買会員向けに試供品を配布し、意見を再収集。 - レビュー返信の強化
感想や改善要望に対し、担当者が感謝と改良予定を丁寧に返信。「皆様の声を反映した新バージョンをお試しください!」と誘導。
想定事例3:ホテルがSNSでの炎上を封じ込めるケース
背景
地方のリゾートホテルCで、宿泊客が「部屋がカビ臭い」「スタッフの対応が雑」とSNS上に複数投稿して拡散。瞬く間に”ブラックホテル”扱いされ、予約キャンセルが相次いだ。
取り組み
- 緊急対策チームを編成
支配人やマーケティング担当等も含めてSNS対策会議を実施。 - 事実調査と改善報告
問題の部屋や清掃状況を即座に点検し、カビの発生箇所を修繕。スタッフの接客研修を強化し、状況をSNSで報告。 - 公式アナウンスと謝罪
ホテルの公式アカウントで「不備があり申し訳ない」「改善策を講じました」と誠実に表明。顧客の不安解消に努める。 - 個別に返信・問い合わせ対応
苦情を投稿したアカウントにはDMで謝罪と再宿泊の優待提案を行い、可能な限り信頼回復を図る。
成功事例に共通するポイント
- 誠実な態度と迅速な対応
- ネガティブ口コミを「うちには関係ない」と放置せず、早い段階で当事者意識を持って対処
- 謝罪や感謝の姿勢を明確にすることで、投稿者や他のユーザーから「ここは真面目に改善しようとしている」と好意的に受け取られる
- 問題点の具体的把握と根本改善
- 実際に何が問題なのかを抽象的に考えるのではなく、具体的にピンポイントで対策
- クレームの背後にはサービス改善のヒントがあるという前向きな意識
- 適切な法的手段の併用
- 悪質な誹謗中傷や根拠のない書き込みには、弁護士に相談しつつ削除依頼や警告文を送るなど、毅然とした対応をとる
- ポジティブ情報の発信強化
- 公式SNSやブログ、口コミサイトの返信機能などを通じて改善策や新サービスを積極的に周知
- 顧客のポジティブレビューや成功体験談をシェアすることで、ネガティブ情報を上回る印象を形成
弁護士に相談するメリット
誹謗中傷レベルの口コミへの対処
悪質な口コミに対しては法的根拠を示した対応が必要になる場面があります。弁護士は投稿内容の違法性を判断し、削除依頼や発信者情報開示請求をサポートします。
リスクマネジメント体制の強化
ネット上の口コミは常に変化し、企業の評判を左右します。弁護士の助言を得ながら危機管理体制を整え、万が一の炎上や悪評拡散にも迅速に対応できるよう準備することが可能です。
示談交渉・損害賠償請求
加害者が明らかに誹謗中傷を行っている場合、示談交渉や損害賠償を求める裁判手続きが必要となることもあります。弁護士が間に入ることで冷静な交渉が期待でき、企業イメージのさらに悪化を防ぎつつ解決を図れます。
法的視点での改善施策提案
口コミ対策の成功には、「どのような表現や行為が違法になりうるのか」を理解しておくことが大切。弁護士は企業の施策が法的リスクを伴わないかチェックし、安全な範囲で口コミ対策をサポートします。
まとめ
口コミ対策成功事例のポイント
- 迅速に反応し、誠実な態度で問題を認める
- 具体的に改善策を打ち出し、顧客へ周知する
- 悪質な誹謗中傷には法的措置も検討し、毅然とした態度を示す
- ポジティブ情報を積極的に発信し、ネガティブ評価を上回る
弁護士の役割
- 誹謗中傷・名誉毀損への法的対応
- 危機管理体制づくりや炎上対策のコンサルティング
- 適法かつ効果的な口コミ対策の提案
成功事例を見ると、「やらせや不正は行わず、顧客の声を真摯に受け止め、迅速かつ具体的な改善を図る」ことが共通の成功要因であるとわかります。そして、万が一の深刻な誹謗中傷やトラブルが起こった場合にも、弁護士のような専門家のサポートを得ることで、企業の評判を守りつつ、スムーズな解決を目指せます。
長瀬総合の情報管理専門サイト
情報に関するトラブルは、方針決定や手続の選択に複雑かつ高度な専門性が要求されるだけでなく、迅速性が求められます。誹謗中傷対応に傾注する弁護士が、個人・事業者の皆様をサポートし、適切な問題の解決、心理的負担の軽減、事業の発展を支えます。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
当事務所は多数の誹謗中傷の案件を担当しており、 豊富なノウハウと経験をもとに、企業の皆様に対して、継続的な誹謗中傷対策を提供しており、数多くの企業の顧問をしております。
企業の実情に応じて適宜顧問プランを調整することも可能ですので、お気軽にご連絡ください。