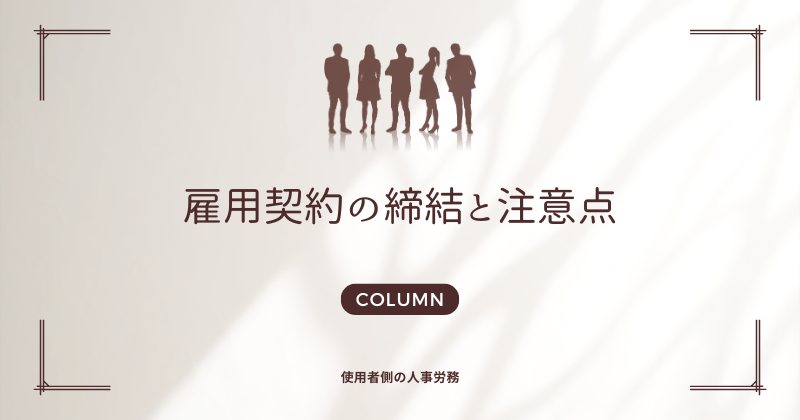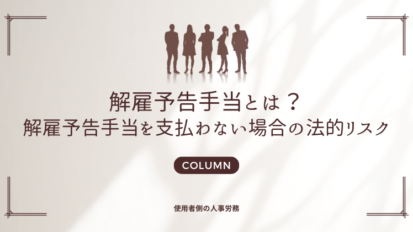はじめに
従業員が法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合、その時間外労働分には残業代(割増賃金)を支払うことが法律で義務付けられています。しかし、残業代の計算方法は企業ごとに異なり、中には固定残業制(みなし残業制)を取り入れている企業もあります。
正しい残業代の算定基礎を把握し、法定割増率をきちんと適用していないと、未払い残業代問題が発生し、従業員との紛争や労働審判・訴訟に発展するリスクが高まります。本稿では、残業代計算の基本と共に、月給制やみなし残業を導入している場合の注意点などを解説します。
日常的に従業員が残業する企業の経営者や人事・労務担当者の皆さまが適切な残業代管理を行う際の一助となれば幸いです。
Q&A
Q1. 残業代の割増率はどのくらいですか?
労働基準法で定める基本的な割増率は以下のとおりです。
- 時間外労働(法定労働時間超過):25%以上
- 深夜労働(22時~翌5時):25%以上
- 休日労働(法定休日):35%以上
また、月60時間超の時間外労働に対しては、割増率50%以上が必要(中小企業も猶予措置が終了)となるなど、細かなルールがあります。
Q2. 月給制の場合、残業代はどう計算するのでしょうか?
基本的には、月給を1カ月の所定労働時間(または平均所定労働時間)で割り、1時間あたりの「賃金単価」を求め、それに割増率をかけて時間外労働時間を乗じるのが一般的です。企業によっては各種手当を含めた算定基礎額を用いる必要がある場合もありますので、就業規則・賃金規程を整理することが大切です。
Q3. みなし残業(固定残業代)制度を導入していれば、残業代を追加で払わなくてもいいのですか?
みなし残業代(固定残業代)制度を導入していても、想定した残業時間数を超える時間外労働が発生した場合は、追加の残業代を支払わなければなりません。また、制度を導入するには、就業規則や労働契約書で明確に「何時間分の残業を含むか」を示すなど、一定の要件を満たす必要があります。
Q4. 「管理監督者」なら残業代を払わなくていいのでしょうか?
労働基準法第41条で「管理監督者」には労働時間・休憩・休日の規定が適用されない旨が定められていますが、店長職だからといって無条件に管理監督者と認められるわけではありません。実際には職務内容や権限、給与水準などを総合的に見て厳格に判断されます。名ばかり管理職と判断されれば、未払い残業代が発生するリスクが高いです。
Q5. タイムカードがない場合はどう計算すればいいですか?
労働時間を把握する方法として、タイムカードやICカード打刻、PCログなど客観的な記録を残すことが望ましいです。もしもタイムカードがない場合、出勤簿や社員の自己申告をもとに補完することになりますが、客観性が乏しいとトラブルの原因になります。企業は労働時間を正確に把握する義務がありますので、何らかの形で客観的な記録を残す仕組みを導入しましょう。
解説
残業代計算の基本式
残業代(割増賃金)を算出する基本的な式は下記のとおりです。
残業代=(1時間あたりの所定労働時間算定基礎額)×割増率×時間外労働時間
- 算定基礎額
通常は「基本給+各種手当(割増賃金の計算基礎に算入すべきもの)」を合計した額。ただし、通勤手当や住宅手当など一部手当は除外できる場合があります。 - 割増率
法定時間外(25%以上)、深夜(25%以上)、休日(35%以上)など。 - 時間外労働時間
実際に法定労働時間を超えて働いた時間数。
月給制の場合の具体的計算例
(例)月給30万円(基本給27万円+固定手当3万円)の従業員
- 1カ月の所定労働時間を160時間とする。
- 割増賃金の算定基礎額:月給から通勤手当等を除外した後の金額が対象。たとえば、全額を算定基礎に含める場合は30万円。
- 1時間あたりの賃金単価:300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円
- 割増率25%で計算:1,875円 × 1.25 = 2,343.75円(1時間あたり)
- 残業が10時間あった場合の残業代総額:2,343.75円 × 10時間 = 23,437.5円
実際には賃金規程や就業規則で「算定基礎に含める手当・除外する手当」が定義されているはずなので、企業の制度に沿った形で計算します。
みなし残業制・固定残業代制度の注意点
- 制度導入時の要件
- 「何時間分の残業代を含むか」を明確にし、超過分は別途支払う旨を労働契約書などに明記。
- 固定残業代がいくらなのか、通常の賃金部分はいくらなのかを区別できるようにしておく。
- みなし時間を超えた場合の精算
例えば「月30時間分の時間外労働をみなし」とした場合、実労働が30時間を超えた分については追加で支払う必要がある。 - 不当に安い固定残業代はNG
みなし残業分の割増賃金が実際の計算基礎を下回っていると、未払い残業代が発生するリスクが高い。
管理監督者と割増賃金
- 管理監督者とは
経営者と一体的な立場として経営上の重要事項に関与する権限や、出退勤の自由裁量、相応の処遇(管理職手当・給与水準など)が与えられているか等を総合判断する。 - 名ばかり管理職
実態が一般の従業員と変わらないのに「店長」「支店長」と呼んでいるだけの場合、労基法上の管理監督者とは認められず、未払い残業代が発生する可能性が高い。 - 注意点
管理監督者でも、深夜労働・休日労働の割増賃金は支払わなければならない。完全に無制限で残業代が免除されるわけではない。
トラブルを防ぐ労働時間管理のポイント
- 客観的な勤怠記録
タイムカード、ICカード打刻、PCログ、スマホ打刻など、実働時間を正確に把握できる仕組みが必要。 - 36協定の締結・遵守
法定労働時間を超えて労働させる場合、労働組合または過半数代表との間で36協定を締結し、労働基準監督署に届出する義務がある。 - 定期的な自己申告の検証
自己申告制のみでは不十分。申告内容が実際のログと矛盾しないかチェックする。 - 長時間労働の抑制
- 従業員の健康管理の観点からも、長時間残業の横行は避ける。月60時間超の残業に対する割増率アップが適用される点にも注意。
弁護士に相談するメリット
正しい残業代の計算方法を整備するうえで、弁護士が関与する利点は以下のとおりです。
- 就業規則・賃金規程の適法性チェック
固定残業代の設定や管理監督者の基準、各種手当の定義などを確認し、未払い残業代リスクを軽減。 - 紛争時の迅速対応
従業員から未払い残業代を請求された場合、証拠保全や交渉戦略、労働審判・訴訟への対応などを一括サポート。 - 36協定や変形労働時間制導入のアドバイス
適法に長時間労働をさせるための法的手続きや、変形労働時間制の導入要件などを専門家の視点でサポート可能。 - 最新判例・法改正への対応
労働法分野は改正や判例の動向が多いため、弁護士の情報収集力を活かして常に最新の基準を反映。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、残業代問題の予防策やトラブル対応実績を多数有しています。必要に応じて早期にご相談いただければ、最適なソリューションをご提示いたします。
まとめ
- 残業代の計算方法を誤ると、未払い残業代として大きな金銭トラブルにつながるリスクが高いといえます。
- 法定割増率(25%以上・35%以上など)や月60時間超の割増率アップ、深夜割増などのルールを正確に把握しましょう。
- 固定残業代制度(みなし残業)を導入していても、想定時間を超えた分や制度設計が不明瞭な場合は追加支払いが必要になるなど、リスクがあります。
- 管理監督者として残業代を支払わなくても良いとされるケースは限定的で、名ばかり管理職に該当すれば未払い残業代のリスクが高まります。
- 弁護士に相談することで、就業規則や賃金規程の整備からトラブル対応まで専門的なサポートが受けられ、法的リスクを軽減できます。
適切な残業代の計算は、企業と従業員の信頼関係を守るうえでも欠かせません。ぜひ本記事を参考に、自社の制度や実務を見直してみてください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス