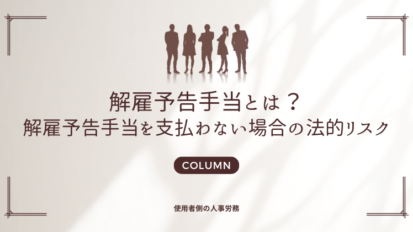はじめに
人手不足や多様な働き方の浸透に伴い、定額残業代(固定残業代)制度やみなし労働時間制など、労働時間管理を簡便化するための仕組みが注目されています。これらの制度を上手に活用できれば、給与計算の効率向上や事務負担の軽減が期待できますが、一方で、制度設計や運用方法を誤ると未払い残業代や労使トラブルに発展するリスクがあります。
本記事では、定額残業代制度・みなし労働時間制の基本的な仕組みと導入時の注意点をわかりやすく解説します。もし運用を誤れば、後に高額の残業代請求を受ける可能性もあるため、ご留意ください。
Q&A
Q1. 定額残業代とみなし労働時間制は同じものですか?
厳密には異なる制度です。定額残業代(固定残業代)は「一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含めて支給する」という賃金形態の工夫であり、みなし労働時間制は労働基準法上の制度で、「実際の労働時間にかかわらず一定時間働いたものとみなす」仕組みを指します。どちらも要件や運用を誤ると未払い残業代のリスクが生じます。
Q2. 固定残業代制度を導入すれば、残業代を追加で支払わなくてもいいのですか?
いいえ。固定残業代制度を導入していても、みなしの残業時間を超過した場合は追加の残業代が必要になります。また、固定残業代を実際の割増賃金相当額以上に設定しているかどうか、労働契約書や賃金規程で明確に区分しているかなど、適切な手続きを踏まないと無効と判断されるおそれがあります。
Q3. みなし労働時間制にはどのような種類がありますか?
大きく分けて「事業場外労働のみなし労働時間制」と「裁量労働制」(専門業務型・企画業務型)があります。事業場外みなしは外回りの営業など、実際の労働時間を管理しにくい業務に適用されやすく、裁量労働制は研究職や高度専門職などに適用される場合があります。ただし、いずれも厳格な導入要件が定められており、形式的に当てはめるだけでは認められません。
Q4. みなし労働時間制を導入すると、残業代は支払わなくてもいいのですか?
一部の裁量労働制を除き、法定休日労働や深夜労働などは割増賃金が必要ですし、労使協定や就業規則で定められた時間を超えた部分には追加の割増賃金が生じる可能性があります。完全に残業代が不要になるわけではありません。
Q5. 制度導入後、労働者から未払い残業代を請求された場合、どうすればいいですか?
まずは労働契約書・就業規則・労使協定などの内容と運用実態を照らし合わせ、適法に制度を運用していたかを確認します。もし、制度設計上の不備や適用の誤りが判明したら、速やかに是正して従業員に未払い分を支払うなど早期対応が求められます。トラブルが大きくなりそうな場合、弁護士への相談が有効です。
解説
定額残業代(固定残業代)制度の仕組み
- 制度概要
通常の賃金に「○時間分の時間外労働割増賃金」を上乗せして固定支給する。例えば「月給30万円(うち固定残業代5万円=30時間分)」など。 - 導入のメリット
毎月の給与計算がシンプルになる。従業員も残業代の金額を予測しやすい。 - リスク・注意点
- 実際の時間外労働がみなし時間を超えた場合、追加の残業代を支払わないと未払い残業代が発生する。
- 固定残業代部分と基本給部分を明確に区別し、就業規則や契約書に記載。みなし時間数も具体的に記載する。
- 固定残業代部分が想定する残業時間と割増賃金相当額を下回らないよう、定期的に検証が必要。
みなし労働時間制の種類と導入要件
- 事業場外労働のみなし労働時間制(労基法38条の2)
- 営業職など、外回りで労働時間を厳密に把握しにくい場合に適用。
- 要件:指揮監督が及びにくく、自己管理の度合いが高い業務であること、社内でどの程度指示を受けるかなどの具体的検討。
- 社内で業務指示やメール・電話で拘束している場合は「事業場外」とみなされないリスクがある。
- 専門業務型裁量労働制(労基法38条の3)
- 研究職やコンピュータープログラマー、弁護士などの高度な専門業務について、労働時間を労使協定で定めた「みなし時間」とする制度。
- 要件:対象業務の範囲が法律や省令で限定されている。労使協定の締結・届出、衛生委員会での意見聴取など厳格な手続きが必要。
- 企画業務型裁量労働制(労基法38条の4)
- 企業の中枢で企画・立案・調査・分析を行う管理業務などが対象。
- 要件:労使委員会での5分の4以上の多数決による決議、労働基準監督署への届出など。対象業務の明確化。
制度導入時の共通注意点
- 明確な就業規則への記載
定額残業代の金額やみなし時間数、みなし労働時間制の対象業務やみなし時間などを具体的に規定し、労働者への説明を尽くす。 - 労使協定の締結・行政への届出
裁量労働制や事業場外みなし労働時間制を導入する場合は、必ず労使協定の締結や労働基準監督署への届出が必要。 - 実態との乖離を防ぐ
みなし時間を設定していても、実際にはそれ以上の時間拘束があったり、会社の指揮監督が常時及んでいると「みなし労働時間制」とは認められない可能性がある。 - 健康管理措置
みなし労働時間制や固定残業代制度下でも、従業員の長時間労働を放置すると過労リスクが高まる。面接指導や産業医の活用など健康配慮義務を徹底する。
運用上のトラブル事例
- 固定残業代が「名ばかり」であると判断されたケース
月給のうち固定残業代として5万円支給していたが、実際には40時間分の残業代に満たない額だった。社員が訴え、未払い残業代が請求される。 - 事業場外労働のみなし時間制が認められなかったケース
外回り営業を想定していたが、実態として毎日訪問先や行動予定を上司に報告し、電話指示も頻繁だったため、実質的に社内監督が及んでいたと判断され、みなし制が無効化。 - 専門業務型裁量労働制の対象業務外だったケース
プログラマーの裁量労働制を導入していたが、実態は単純作業が多く、「高い専門性を要する業務」とは認められず未払い残業代を請求される。
弁護士に相談するメリット
定額残業代制度やみなし労働時間制を適法かつ適切に導入・運用するには、弁護士の関与が大きな安心材料となります。
- 制度設計のチェック・アドバイス
固定残業代の金額設定や就業規則への記載方法、裁量労働制の対象業務選定など、法律に照らしてリスクを洗い出し、最適なアドバイスを行う。 - 労使協定締結の支援
労働組合または過半数代表との協議や労使委員会の運営など、複雑な手続きをサポートし、行政への届出をスムーズに進める。 - トラブル対応
従業員から未払い残業代を請求された場合、制度の正当性を主張・立証するために必要な書類や証拠を整理し、紛争解決を図る。 - 健康配慮義務や安全衛生管理に関する助言
長時間労働を抑制しつつ、従業員の健康状態を管理する具体的施策についても法的視点で提案が可能。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、多数の企業法務・労働事件に携わった経験を活かし、柔軟かつ実効的なサポートを提供しています。
まとめ
- 定額残業代(固定残業代)制度やみなし労働時間制は、正しく導入・運用すれば労使双方にメリットがある一方、要件や手続きを誤ると未払い残業代請求や制度無効化のリスクが高まります。
- 固定残業代を導入する場合は、「何時間分の残業を含むか」を明確にし、超過分の追加支払いを確実に行う必要があります。
- みなし労働時間制(事業場外労働、裁量労働制)の適用には、労働基準法上の厳格な要件や労使協定・届出などの手続きが伴います。実態が伴わないと無効となる可能性があります。
- 弁護士のサポートを受ければ、就業規則・労使協定の整備から、紛争対応、健康管理措置へのアドバイスなどを包括的に受けることができ、企業リスクを軽減できます。
制度の適正な運用で従業員との信頼関係を維持し、トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ本記事を参考に今一度自社の運用状況を点検してみてください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス