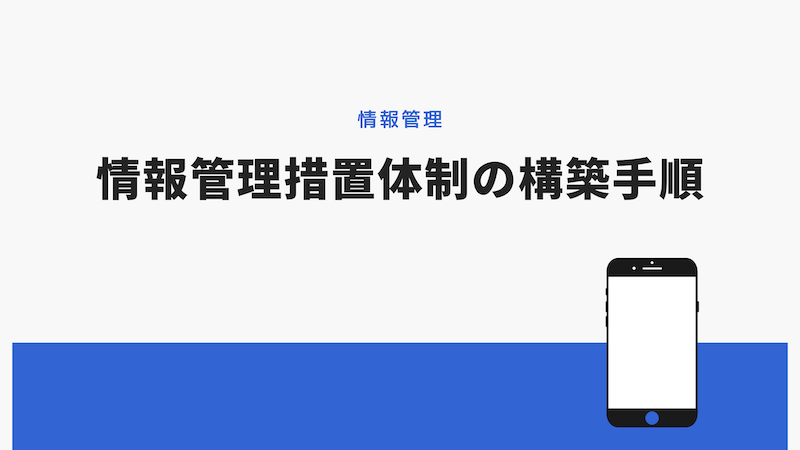はじめに
口コミサイトやSNS運営会社に対して、削除依頼を行ったものの、「削除を拒否された」「何の返答もない」「削除要件を満たさないと判断された」といった場面に遭遇するケースがあります。事実誤認や誹謗中傷レベルの投稿だとしても、運営会社側が「規約違反に当たらない」とみなせば対応が得られないことは珍しくありません。
本稿では、そうした削除依頼が通らない場合の追加対応策に焦点を当て、具体的にどのような手段を検討すればよいのかを解説します。放置すれば企業や店舗の評判を大きく損なう恐れがある以上、「運営会社が動いてくれないから仕方ない」で終わらせず、次のステップに進むための選択肢を知っておくことが大切です。
Q&A
Q1:削除依頼が拒否される理由は何ですか?
たとえば「書き込みが運営会社の規約違反と断定できない」「投稿内容が個人の感想の範囲内と判断された」「法的に問題があるとは言い切れない」などが理由として挙げられます。運営会社は、基本的に中立的な立場で投稿内容を判断するため、明確な違法性がないと判断すると削除しないことが多いです。
Q2:削除依頼が通らない場合、もう解決策はないのでしょうか?
いいえ、まだ複数の手段が残されています。たとえば「仮処分の申し立て」「発信者情報開示請求→損害賠償請求」「逆SEO(検索結果対策)」など、さらに踏み込んだ対応策が考えられます。
Q3:仮処分って何ですか?
仮処分とは、裁判所の判断によって「掲載情報の差し止め(削除)」を一時的に命じる手続きです。本訴(本格的な裁判)を行わず、緊急的に削除を実現したい場合に用いられます。裁判所の命令であるため、運営会社も従わざるを得ません。
Q4:発信者情報開示請求はどう役立ちますか?
誹謗中傷の投稿者を特定できれば、損害賠償請求や刑事告訴などを行い、問題投稿を止めることを狙えます。加害者との示談交渉を進めることにより、投稿削除や謝罪文を引き出せる場合もあります。
Q5:逆SEO(検索結果対策)って合法ですか?
逆SEOそのものは「ネガティブな情報が検索結果上位に表示されないようにする」ための手法であり、違法ではありません。ただし、悪質な手段を使って他サイトに迷惑をかける行為は不正競争防止法などに抵触する可能性があります。専門家の助言を得ながら適切に行う必要があります。
解説
削除依頼が通らないケースでの追加対応策
- 再度の交渉・追加証拠の提示
- 運営会社に再度問い合わせる際に、さらに詳しい証拠や法的根拠を示す。
- 「この部分がどのように名誉毀損や信用毀損にあたるのか」を具体的に説明することで、対応が変わる可能性がある。
- 仮処分の申し立て(裁判手続き)
- 裁判所に「投稿の削除」を仮処分として命じてもらう。
- 運営会社が応じない場合でも、裁判所の命令があれば強制力が高い。
- 弁護士のサポートがほぼ必須となる。
- 発信者情報開示請求→加害者特定→示談交渉・損害賠償請求
- 投稿者を特定できれば、直接交渉して削除や謝罪を求めることが可能。
- 名誉毀損や侮辱、業務妨害として損害賠償を請求する裁判を起こすケースもある。
- 逆SEOなどの検索結果対策
- ネガティブ情報が検索結果の上位に来ないよう、ポジティブ情報や公式サイトを上位表示させる対策。
- 一定のSEO知識が必要となる。
- 公式サイトやSNSでの事実説明・ブランドイメージ回復策
- デマや事実誤認であれば、公式アナウンスを出し、正しい情報を広く周知する。
- 被害が拡大する前に自社の見解や証拠を示し、信頼回復に努める。
仮処分のポイント
- 仮処分とは
本来の裁判(本訴)より先に、差し迫った被害を防ぐため、裁判所に暫定的な命令を出してもらう手続き。ネット上の投稿削除を目的とする場合、「表示差止めの仮処分」を申し立てる。 - 手続きの流れ
- 弁護士と相談し、仮処分申立書を作成
- 裁判所へ提出し、審尋(ヒアリング)を受ける
- 申請が認められれば、運営会社に削除を命じる仮処分命令が出る
- メリット・デメリット
-
- メリット:本訴よりも短期間で結果を得られる。強制力が高い。
- デメリット:申請に費用や書面作成が必要。違法性の明確な立証が求められる。
発信者情報開示請求の流れ
- 任意削除依頼と並行して準備
- 削除が難しければ、投稿者を特定するための資料を集め始める。
- サイト運営会社・プロバイダに対する「情報開示」の請求
- プロバイダ責任制限法に基づいて、IPアドレスやログを開示するよう要求。
- 運営会社が応じない場合、裁判所を通じた手続き(発信者情報開示請求の訴訟)に進む。
- 投稿者特定→示談交渉 or 損害賠償請求
- 特定後、投稿者が会社内の人物だったケースや、競合他社の可能性もある。
- 悪質ならば刑事告訴や民事訴訟(損害賠償)を検討。加害者との交渉で削除や謝罪を引き出すことが期待できる。
逆SEO(検索結果対策)の概要
- 目的
「悪質な口コミや誹謗中傷の記事が検索上位に表示される」ことを防ぎ、企業の公式ページやポジティブ情報を上位表示させる。 - 手法
- ポジティブなコンテンツを増やす・被リンクを得るなど、正攻法のSEO対策
- 悪質サイトに対して、検索エンジンのガイドライン違反を通報する方法などもある
- 注意点
グレーゾーンの手法(クローキングやスパム報告の乱用など)は違法・不正競争的なリスクがある
弁護士に相談するメリット
拒否されても諦めずに次のステップへ
運営会社が削除を拒否しても、仮処分や発信者情報開示などの法的手段が残っています。弁護士が状況を分析し、「次にどの方法を選択すれば目的を達成しやすいか」を提案します。
仮処分申立て・裁判手続きの代行
専門的な知識が求められる仮処分や裁判手続きについて、弁護士が代理人として動くことで、書面作成や立証がスムーズに進みます。裁判所に納得してもらえるだけの違法性の主張や証拠提出を行い、迅速な解決を目指せます。
発信者情報開示請求からの損害賠償
投稿者を特定し、損害賠償請求を進めるための一連の流れを一括で任せられます。示談交渉を弁護士が行うことで、感情的対立を避け、冷静な話し合いを可能にします。
リスクマネジメント全般のサポート
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、ネットの誹謗中傷・名誉毀損対応に限らず、企業法務やリスクマネジメント全般のコンサルティングも提供しています。口コミ炎上だけでなく、従業員のSNS利用ポリシーなど総合的な対応策を構築できます。
まとめ
- 削除依頼が通らない場合の対処法
- 再度の交渉・追加証拠提示
- 仮処分(裁判所による差止め命令)
- 発信者情報開示請求 → 損害賠償請求・示談交渉
- 逆SEO(検索結果対策)
- 公式サイトやSNSでの正しい情報発信
- 仮処分のメリット
-
- 裁判所の命令のため強制力が高い
- 長期の裁判を待たずに速やかに削除を実現できる
- 発信者情報開示請求の利点
-
- 投稿者を特定し、示談交渉や損害賠償請求が可能に
- 繰り返し誹謗中傷を受ける場合でも、加害者特定により再発防止が期待できる
- 諦めずに次のステップへ
-
- 運営会社が拒否しても、まだ手段は残されている
- 弁護士に相談し、最適な解決策を選びたい
削除依頼が通らなかったからといって、問題投稿を「もう仕方ない…」と放置すると、さらに被害が拡大するリスクがあります。早期に状況を整理し、弁護士などの専門家へ相談することで、新たなアプローチや強制力のある手段を検討し、問題解決への道筋を見つけられるはずです。
長瀬総合の情報管理専門サイト
情報に関するトラブルは、方針決定や手続の選択に複雑かつ高度な専門性が要求されるだけでなく、迅速性が求められます。誹謗中傷対応に傾注する弁護士が、個人・事業者の皆様をサポートし、適切な問題の解決、心理的負担の軽減、事業の発展を支えます。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
当事務所は多数の誹謗中傷の案件を担当しており、 豊富なノウハウと経験をもとに、企業の皆様に対して、継続的な誹謗中傷対策を提供しており、数多くの企業の顧問をしております。
企業の実情に応じて適宜顧問プランを調整することも可能ですので、お気軽にご連絡ください。