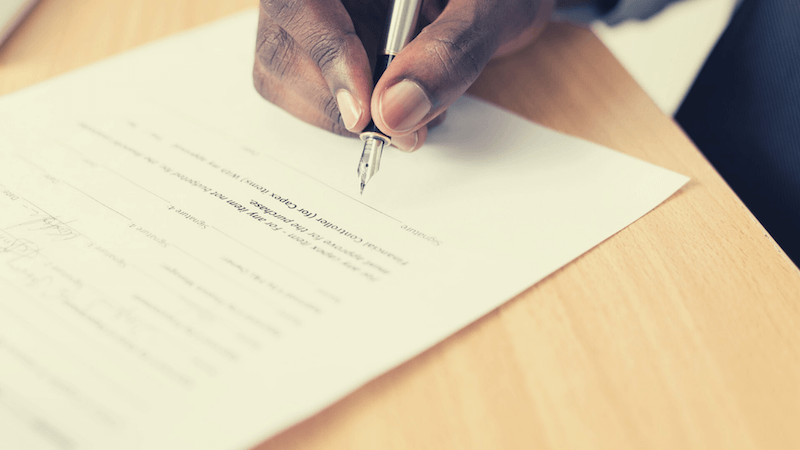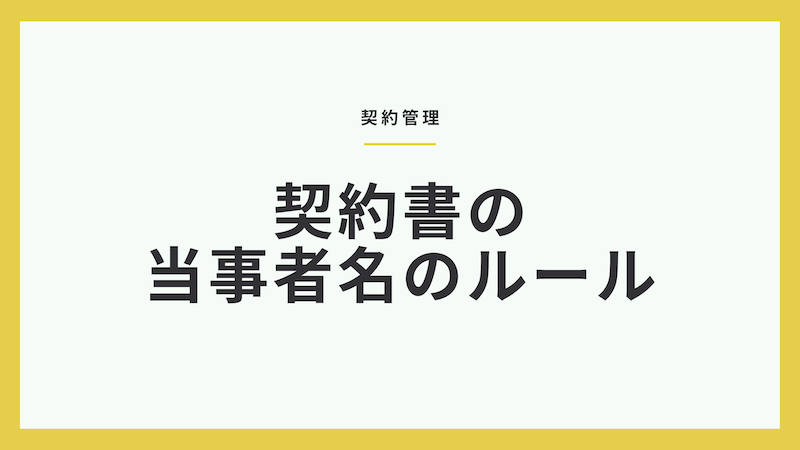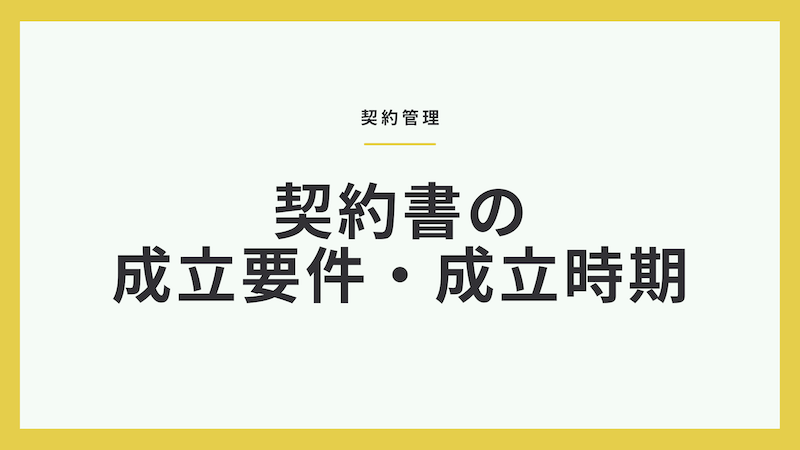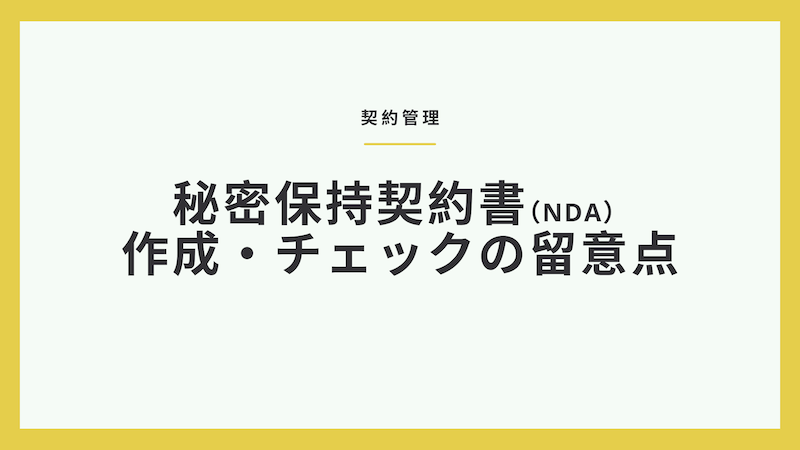はじめに
企業間取引において最も基本的な契約形態のひとつである売買契約。商品や製品、原材料などのモノを売買するときに交わす契約書は、一見シンプルなようでいて、リスクマネジメントを考慮した条項設定を怠ると未払い代金や瑕疵(かし)対応、損害賠償といった紛争につながる恐れがあります。特に取引先との継続的な関係を考慮すると、相手方に不利益すぎる条項の押し付けや、逆に自社に不利な条項を受け入れるなどの極端な内容は避けなければなりません。
本記事では、売買契約書をレビュー・チェックする際に、必ず確認すべき注意点を解説します。価格や支払い条件、納品と検収、瑕疵担保・契約不適合責任など、重要条項を正しく設定することで、企業の利益を守り、将来的な紛争リスクを低減できます。
Q&A
Q1:売買契約の契約書では、最初に何を確認すべきでしょうか?
まずは契約当事者の名称や所在地、代表者名などが正確かどうかを確認します。法人格(株式会社・合同会社など)が誤って記載されていると契約自体の有効性に疑義が生じます。次に、契約対象物(商品や製品の名称・型番など)と金額(単価や総額・消費税の扱い)をはっきりさせ、納期や支払い期限などの基本情報を再チェックします。
Q2:代金の支払い条件はどのように設定すべきですか?
代金支払い条件は、支払い期日、支払い方法(振込・手形など)、遅延損害金率を明記するのが一般的です。特に、売掛金の回収リスクを考慮し、遅延損害金の利率を定めておくことで、相手方の支払いを督促しやすくなります。月末締め翌月末払いなど締日を決める場合も多いですが、締日と支払日が明確かを確認し、曖昧な表現を避けましょう。
Q3:瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは何ですか?
瑕疵担保責任は、売買の対象物に隠れた欠陥(不具合)があった場合、売主がその修理や損害賠償を負う制度を指します。2020年の民法改正後は、名称が契約不適合責任に変わり、引き渡された物が契約内容に適合しない場合に買主が追完請求(修理や交換など)を求められるほか、代金減額や損害賠償請求、さらに契約解除まで可能となりました。
売買契約書では責任期間や免責範囲を定めることで、どの程度まで売主が負担を負うかを調整できます。
Q4:検収条項を設けるメリットは何でしょう?
検収条項により、買主が物の受領後一定期間で検品し、異常があれば売主に通知する義務を負う形を明記できます。これにより、不良品の早期発見・対応が促進され、買主の遅延報告による不利な事態を避けることが可能です。売主としても、検収期間を過ぎた後に買主が瑕疵を主張してくるリスクを低減できるため、紛争予防として効果的です。
解説
売買契約書の代表的条項
- 当事者条項
契約の冒頭で、契約当事者の正式名称・本店所在地・代表者名を明記し、甲・乙などの略称を定義します。法人登記情報と一致しているか確認が重要。 - 目的・契約対象物
- 「本契約は、甲が製造・販売する製品○○を乙が購入することを目的とする」「製品の名称・品番・数量・仕様書の添付」などを明記する。
- 必要に応じて附属文書(仕様書・図面)を契約書に添付し、双方が同じ認識を持てるようにする。
- 価格・支払い条件
- 「本製品の価格は別紙価格表に基づく」「支払期日は○日までとし、○○銀行振込による」「遅延損害金は年○%とする」など細かく記載。
- 消費税の内外税表示も誤解なく示す(「本契約の対価は別途消費税を加算する」といった文言など)。
- 納期・納品・検収
- 納品場所、納期、納品方法(輸送手段や梱包仕様)、引き渡し時期を明示する。
- 検収の手順(受領後○日以内に検品し、異常があれば書面で通知など)を定めることで、引き渡し後の不具合対応をスムーズに。
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- 民法改正後の用語にあわせ、「契約不適合が判明した場合、買主は○日以内に売主へ通知し、売主は修理・交換など追完義務を負う」等の条文を設ける。
- 責任追及可能な期間(例えば引き渡し後6か月以内など)を設定し、潜在的リスクをコントロールする。
- 危険負担・所有権移転時期
- 所有権や危険負担がいつ移転するかを明確化する。通常は「引き渡し完了時に買主へ所有権が移転する」などと規定。
- 国際取引ではインコタームズ(EXW、FOB、CIF等)を参照し、運賃・保険・通関手続きの分担を決めることが多い。
- 契約期間・解除
通常の有期契約なら期間と更新方法、解除理由を明記。長期取引でも「特定条件(支払い遅延○日超過など)があれば催告なく解除できる」といった特別条項を設けることが多い。 - 損害賠償・免責
違反が発生した場合の損害賠償請求範囲(直接損害・間接損害・逸失利益)をどう扱うかを決める。中小企業においては高額な損害賠償リスクを抑えるために責任上限額を設ける場合もある。 - 反社会的勢力排除条項
相手方が反社会的勢力と関係する場合は契約を解除できる旨を定め、経営リスクを回避する。昨今のコンプライアンス重視の流れでは標準的条項となりつつある。 - 準拠法・裁判管轄
国内取引の場合は日本法を準拠法とし、東京地裁などを専属的合意管轄とする事例が多い。国際取引の場合は仲裁機関を指定することもある。
売買契約書レビューの実務ポイント
- 価格や数量の明示、総額か単価か
- 買い手の視点では、価格変更条項(相場変動がある商品など)の有無、売り手の視点では数量や品質基準の柔軟性を確保しておくかなどを検討。
- 総額契約の場合でも、追加発注や仕様変更の際にどう価格を決めるかを明記すると紛争回避につながる。
- 納品責任と遅延ペナルティ
- 売り手が納品遅延した場合に違約金や遅延損害金を求められるか。また、買い手が納期を厳しく要求するならば、売り手としては不可抗力条項で自然災害やサプライチェーン遅れをカバーする手立てを設ける。
- リスク転嫁と保険
- 高額な製品や輸送リスクのある取引では、運送途中の破損や盗難に対する責任を誰が負うか事前に合意し、必要に応じて保険加入を義務付ける。
- 売買対象が高価格な機器の場合は「買主が受領後に保険加入し、事故時には保険金で対応する」と定めるケースもある。
- 瑕疵担保(契約不適合)と保証期間のバランス
- 売り手は、長期の保証期間を設定しすぎると不意のコスト増が発生するリスクがある。買い手は不具合に対する補償を手厚くしたいが、契約内容により交渉が必要。
- ソフトウェアや機械装置など複雑な製品の場合、保守契約や別途サービス契約を締結し、保証範囲と有償サポートを区別する例が一般的。
- 秘密保持や競業避止
- 製品の設計図やノウハウが共有される場合、NDA(秘密保持契約)を含め、情報の使用範囲や漏洩時の責任を定義。
- OEM契約などでは、買い手が独自ブランドで販売する際、競業避止条項を設けて自社の技術や顧客情報を保護する。
紛争事例と回避策
- 代金未払い
納品後に買い手が支払いを渋り、回収不能となる事例。契約時に手付金を受領したり、分割払いの都度納品する、所有権留保を定めるなど、債権保全策を講じることでリスクを軽減。 - 瑕疵の範囲をめぐる対立
- 瑕疵担保(契約不適合)責任を負う期間や範囲が不明確で、買い手が後から「初期不良だ」と主張し、売り手が「使用上の不注意だ」と反論するケース。
- 対策:契約書で初期不良の定義や、外部第三者検査機関の利用などの紛争解決フローを定めておく。
- 納期遅延による損害賠償
- 買い手が納期遅れで大きな機会損失を被ったとして売り手に巨額賠償を請求。契約書に損害賠償の上限や特別損害の免責を設定していなかったため、売り手が高額負担を迫られる例。
- 対策:契約時に「通常損害のみを賠償対象とし、間接損害・逸失利益は除く」や「上限金額を○円または契約金額の×%とする」条文を入れておく。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、売買契約書に関し以下のサポートを行っています。
- 契約書レビュー・作成支援
- 企業が作成した売買契約書や取引先から提示されたドラフトを法的観点からチェックし、リスク条項や修正案を提案。
- ビジネス実態に沿ったオーダーメイドの契約書作成も対応可能で、契約交渉時の助言や同行も行います。
- 債権回収対策
- 代金未払いリスクを最小化するため、所有権留保や損害賠償条項、遅延損害金の定めなど、契約段階での債権保全策をアドバイス。
- 未払いが実際に起きた場合の内容証明送付や訴訟対応、強制執行などもスムーズにサポート。
- 紛争対応・訴訟代理
- 納品物の不具合や納期遅延、損害賠償請求など紛争が生じた際、企業側代理人として交渉・調停・訴訟に対応。証拠整理や専門家意見を踏まえ、最適な解決策を提案します。
- 国際売買契約の紛争にも精通しており、海外仲裁機関や外国裁判所での対応についてもアドバイスを行います。
- 業務効率化・契約デジタル化
- 契約件数が多い企業に対して、契約管理システムの導入や電子契約プラットフォームの活用を提案し、ワークフローと審査プロセスの見直しを支援。
- 最新の電子署名法規やクラウドサービス利用規程を踏まえ、電子契約移行に伴う法的留意点を指導します。
まとめ
- 売買契約書は企業間取引の根幹を支える重要な文書であり、当事者確認、契約期間、対価、納品、瑕疵担保(契約不適合)など基本的な条項を完備しておくことがトラブル防止の第一歩。
- 支払い条件や損害賠償、契約解除、反社会的勢力排除など、近年のビジネス慣習やリスクに対応した条項を入れることで、取引の安全性を高められる。
- 弁護士のレビューを受けることで、契約書に潜む潜在的なリスクを洗い出し、必要に応じて修正・交渉を行うことが可能。
- 紛争が起きた場合でも、契約書に明記されたエビデンスをもとに迅速に解決しやすくなり、債権回収や損害賠償請求などの手続きを有利に進められる。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス