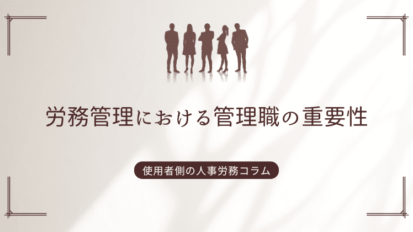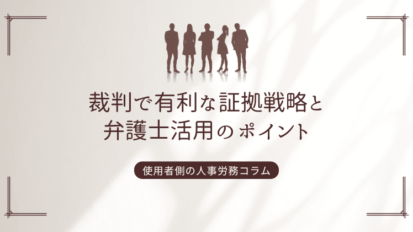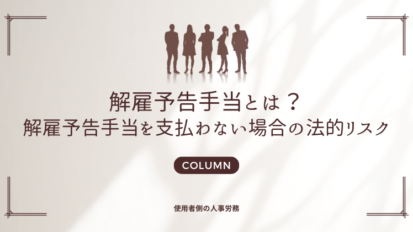はじめに
近年、内部通報制度(社内ホットライン)や相談窓口の整備が、企業にとって重要なコンプライアンス体制として認識されています。パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)でもハラスメント相談窓口の設置が義務付けられ、従業員が安心して不正行為やハラスメントを通報できる仕組みづくりが求められます。
一方で、内部通報を受けた際の調査手順や秘密保持、通報者保護などを怠ると、企業は漏えいリスクや不当な処分による紛争を招く可能性があります。本記事では、社内通報制度と相談窓口の整備において企業が注意すべきポイントを解説します。
Q&A
Q1:パワハラ防止法で企業はどんな義務を負っているのですか?
通称「パワハラ防止法」(改正労働施策総合推進法)により、企業はパワーハラスメント防止策を講じる義務を負います。具体的には、
- ハラスメント禁止方針の社内周知
- 相談窓口の設置
- 通報内容の調査・被害者保護・加害者への措置
- 再発防止策の策定
などが基本的要件として定められ、一定規模以上の企業は必須となっています。
Q2:内部通報制度とパワハラ相談窓口は同じものですか?
一般的に「内部通報制度(ホットライン)」は、企業内部の不正行為(法令違反、セクハラ、横領等)を通報するためのシステムを指し、パワハラ防止に特化した相談窓口はその一部機能として併設される場合があります。
ただし、企業によっては別々の窓口を設けたり、統合して「コンプライアンス相談窓口」「ハラスメント相談窓口」として一本化するケースもある。いずれも通報者保護や秘密保持が重要ポイントです。
Q3:通報者保護(公益通報者保護法含む)ではどのような保護があるのでしょうか?
公益通報者保護法により、通報者が正当な目的で不正行為を通報した場合、企業は解雇や不利益取扱いを行うことが禁止されています。通報者の身分を守るため、企業は匿名通報を受け付けたり、通報者の情報を最小限の範囲でしか共有しない体制を構築する必要があります。違反すると行政指導や法律上の責任が問われる可能性があります。
Q4:通報内容が誤報や悪意のあるデマだった場合、どうすればいい?
企業はまず通報内容を客観的に調査し、真偽を確認します。悪意ある虚偽通報で企業や他の従業員に損害が発生した場合、懲戒処分や損害賠償請求を検討する可能性もあります。ただし、無闇に「嘘だ」と決め付ける前に、公正な調査手順を踏むことが重要です。
一方、通報者が意図せず勘違いで誤報したケースでは、懲戒するのは不合理と判断されることがあります。
解説
内部通報制度と相談窓口の意義
- コンプライアンス強化
- 従業員が不正やハラスメントに気づいた際、社内ホットラインを利用して早期発見・是正が行われれば、企業の信用失墜や法的責任を回避しやすい。
- 社内で問題が起きても外部に漏れる前に対処でき、社会的スキャンダルや行政処分を回避するメリットが大きい。
- 組織風土の改善
- 透明性の高い通報制度があることで、従業員が不安なく働き、ハラスメントや不正に対して拒否感を持つ組織文化が育まれる。
- 企業は通報者を大切に扱う姿勢を示すことで、従業員のエンゲージメントや働きがいを高められる。
- パワハラ防止法への対応
パワハラ防止法の義務を果たすために、相談窓口の設置と機能強化は不可欠。相談窓口の運用において、内部通報制度と一体化させることで管理コストを削減できる場合も多い。
通報窓口の設計・運用
- 窓口形態
- 社内窓口:企業内に専任部門やコンプライアンス担当者を配置。メリットは対応が迅速なこと、デメリットは通報者が身元バレを恐れ利用しにくい可能性がある。
- 外部委託窓口:弁護士事務所などの第三者機関が通報を受け付ける。メリットは通報者が安心して情報を提供できるが、費用や連絡のやり取りに時間がかかることも。
- 匿名通報の扱い
- 匿名通報を受け付けるか否かは企業の方針次第だが、公益通報者保護法では匿名でも保護対象となる場合がある。
- 匿名通報が増えれば誤報や悪質な通報も混じる可能性があるため、調査手順やフィルタリングを適切に行う仕組みを整備する。
- 調査プロセスと報告
- 通報があったら調査委員会や担当チームが事実確認を行い、必要に応じて関係者ヒアリングや資料収集を実施。
- 調査結果をまとめ、経営陣に報告し、懲戒処分や組織改善などの対応方針を決定する。被害者へのフォローも並行して行う。
- 機密保持と通報者保護
- 通報内容や通報者の個人情報は限定的なメンバーだけが取り扱う。
- 通報者に対する不利益処分を防ぐため、守秘義務や報復禁止を規定し、違反があれば懲戒対象とする。万一、上司からの報復が疑われれば速やかに追加調査・措置を講じる。
パワハラ相談窓口とハラスメント対策
- パワハラ防止規程との連動
- 企業がハラスメント防止規程を策定し、パワハラの具体例や禁止行為、違反時の処分を明文化。相談窓口はその規程に基づき公正な調査を行う。
- 従業員に対して「こんな場合はすぐ通報してほしい」というガイドラインを示し、相談を躊躇しないよう周知する。
- セクハラ・マタハラなど他のハラスメントとの共通窓口
- パワハラだけでなく、セクハラ、マタニティハラスメント(マタハラ)など各種ハラスメントを一括で扱う相談窓口も増加。
- 担当者は基本的なハラスメントの定義や対応策を把握し、迅速かつ公平な対応を心がける。
- 教育・研修
- 管理職向けに、パワハラやセクハラの境界線・事例を学ぶ研修を実施。パワハラ防止法の趣旨や具体的行為を理解させる。
- 従業員向けには、相談窓口の利用方法やハラスメントを目撃した場合の対応などを周知し、通報義務や協力義務を促す。
トラブル想定例
- 通報後に報復人事が行われたケース
- 従業員が上司のパワハラを通報した後、担当業務から外され閑職へ配置転換された。労働審判で報復目的と認定され、企業が不当人事と判断されるケース。
- 対策:企業は通報者を不利益に扱わないルールを徹底し、異動・配置転換の合理的理由が説明できるよう記録を残す。
- 外部窓口への通報を受けて企業が対応を怠った
- 外部委託のホットラインでセクハラ通報があったのに、担当者間の連携ミスで企業が数週間放置。被害者が退職し、損害賠償請求を起こされるケース。
- 対策:外部窓口と企業担当者の連絡ルールを明文化し、報告時期や方法を契約書に定める。
- 誤報による無実の従業員処分がトラブルに
- 匿名通報で「部下にパワハラしている」と言われた上司が、企業の不十分な調査で懲戒処分を下された後、上司が処分無効を主張し訴訟に発展するケース。
- 対策:通報内容を複数の証拠や複数人のヒアリングで検証し、加害者とされる者の弁明の機会を十分に確保する。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、社内通報制度と相談窓口の整備において、以下のようなサポートを行っています。
- 内部通報規程・ハラスメント防止規程の作成
- 企業規模や業種、既存のコンプライアンス体制を分析し、内部通報規程やハラスメント防止規程を法的観点でチェック・改定します。
- 通報者保護や匿名通報への対応、調査フローなどを詳細に規定し、運用マニュアルを整備します。
- 外部窓口の運用支援
- 弁護士が外部通報窓口を請け負い、従業員の通報を受けた段階で客観的かつ専門的に事実確認をサポート。企業へ中立的な報告を行い、トラブルの早期解決に寄与します。
- 守秘義務を順守しつつ、企業のリスクを踏まえたアドバイスや通報者とのやり取りを担当します。
- 調査委員会の指導・代理
- モラハラやセクハラなどの通報があった場合、社内調査委員会の立ち上げから調査手順の確立、ヒアリング・証拠収集方法を指導。
- 必要に応じて外部委員として弁護士が参加し、公正な視点で調査を進めることで、社内での不正やハラスメントを正確に把握し、適切な処分を行います。
- 紛争対応・労働審判・訴訟代理
- 通報者保護を怠ったと主張され不当解雇や賃金カット等で労働審判・訴訟が起きた場合、企業側代理人として弁護士が対応。
- 被害者や加害者の対応を誤って損害賠償を請求された事案でも、早期和解や裁判での防御戦略を構築し、企業のリスクを最小限に抑えます。
まとめ
- 内部通報制度とパワハラ防止法に基づく相談窓口の整備は、企業のコンプライアンス体制強化に不可欠であり、適正な運用がなければ情報漏洩や不当処分による紛争リスクが高まる。
- 通報者の匿名保護や不利益取扱い禁止が守られないと、企業が不当解雇や損害賠償を問われるケースが増加している。
- ハラスメント防止規程を整備し、報告・調査・処分のプロセスを明確に定め、調査を適正に行えばトラブルを早期収束できる可能性が高い。
- 弁護士を活用することで、通報窓口や調査委員会の運営を適正化し、紛争が生じた際にも迅速に対応できる体制を構築可能。企業は法令遵守と信頼性向上を同時に目指せる。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス