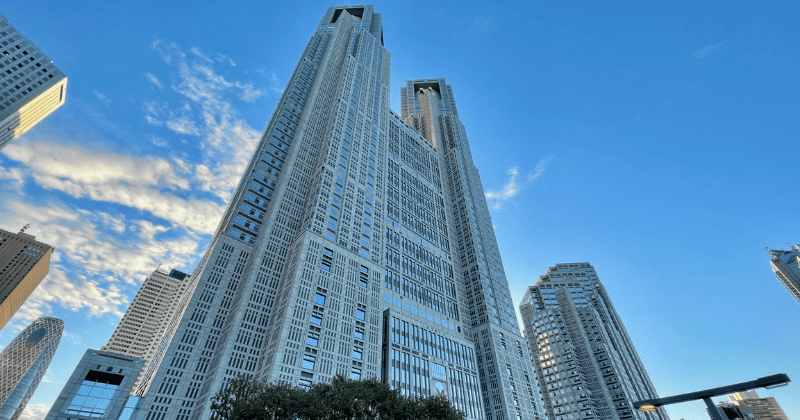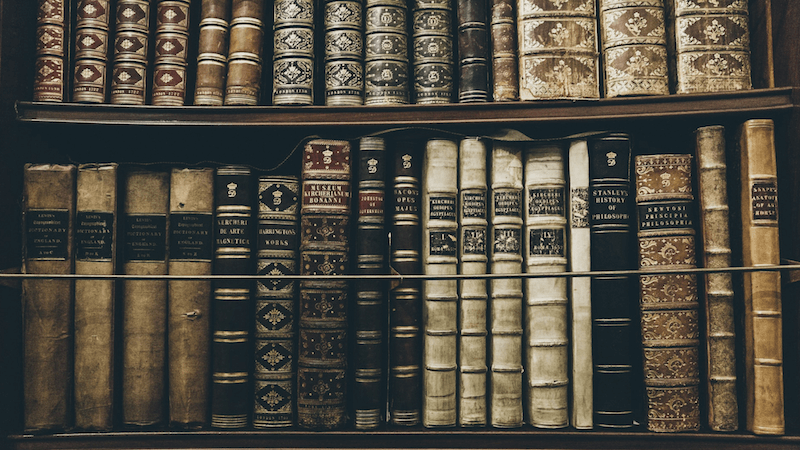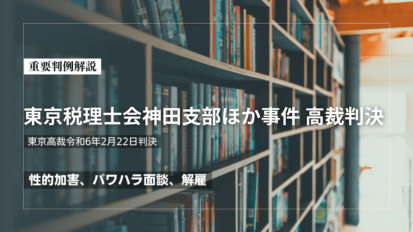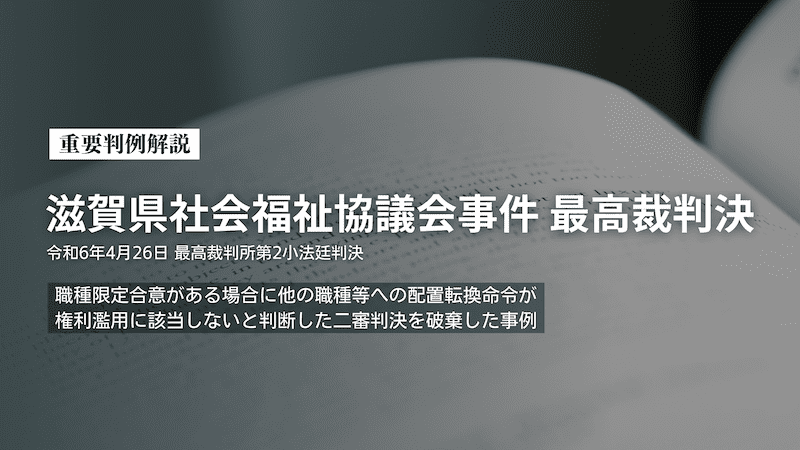コラムの内容を解説した動画は【こちら】
はじめに
2025年4月1日、全国初となる「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(以下、東京都カスハラ防止条例)が施行されます。
近年、顧客や取引先からの悪質なクレームや迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が深刻化しており、特にサービス業や医療・介護など現場の従業員が多い東京では対応が急務となっていました。厚生労働省の調査でも、カスハラ相談が「増加」した企業の割合は23.2%にのぼり、パワハラ(19.6%)等を上回って唯一「減少」を上回ったとの報告があります。こうした背景から東京都は条例を制定し、企業等が組織的にカスハラ対策に取り組むことを求めています。
本記事では、中小企業(サービス業・医療・介護・飲食業等)を中心とした事業者の皆様に向けて、東京都カスハラ防止条例および関連ガイドラインに基づく実務対応策を解説します。条例および東京都のガイドライン・共通マニュアル、厚労省資料等を踏まえ、初期対応のフローから社内ルール整備、再発防止策、具体事例、そして消費者や障害者の権利との関係まで網羅的に取り上げます。現場対応のポイントから法的留意点まで整理しています。
INDEX
- 東京都カスハラ防止条例と指針の概要
- 施行までのスケジュールと背景
- 企業に求められる義務と責任
- カスハラ・クレームの初動対応フロー(現場・上司・組織対応)
- 社内ルール整備(就業規則、マニュアル、通報窓口の整備)
- 社員研修・再発防止策の必要性
- ケーススタディ(具体的事例:企業間取引・サービス利用者・医療・介護・飲食業)
- トラブル拡大防止のコツ(法的視点・記録・警察連携など)
- 消費者・障害者の権利と合理的配慮の関係整理
- 解説動画
東京都カスハラ防止条例と指針の概要
東京都カスハラ防止条例の目的は、カスタマーハラスメントの防止について基本理念を定め、東京都・顧客等・就業者・事業者それぞれの責務を明らかにし、必要な施策を推進することで、働く人の安全・健康や事業者の安定経営、そして顧客等の豊かな消費生活を守り、公正で持続可能な社会の実現に資することにあります。
条例前文では、東京の発展には働く人全員が力を発揮できる環境づくりが必要であり、そのため様々なハラスメントの未然防止が不可欠であると指摘されています。特に顧客等からの著しい迷惑行為であるカスタマーハラスメントは働く人の人格や尊厳を侵害し、就業環境を害し、事業の継続にも悪影響を及ぼすものであり、個々の企業のみならず社会全体で防止に取り組む必要があると述べられています(東京都カスタマー・ハラスメント防止条例)。
条例はカスハラの定義を明確にしています。「カスタマーハラスメント」とは、「顧客等(商品やサービスの提供を受ける者や業務に密接に関係する者)から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」を指します (東京都カスタマー・ハラスメント防止条例)。ここでいう「著しい迷惑行為」とは、典型的には暴行や脅迫などの違法行為、または正当な理由なく著しく過度な要求をすること、暴言その他の不当な言動を意味します (東京都カスタマー・ハラスメント防止条例)。要するに、法に反する行為や社会通念上許容されない無理難題・罵詈雑言といった行為がカスハラに該当します。また条例第四条では「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない。」と規定し、カスハラ行為の禁止を明示しています (東京都カスタマー・ハラスメント防止条例)。この「何人も」には都民か否かを問わずあらゆる人が含まれ、企業間取引における取引先からの行為なども含めてカスハラは行ってはならないとされています。
もっとも、条例にはカスハラ行為そのものに対する罰則規定は設けられていません。懲罰的な規定を設けることについては制定過程で議論されましたが、「罰則に該当しない類似行為は許される」という誤ったメッセージとなりかねない等の懸念から、故意に罰則は設けなかった経緯があります。
しかしだからといってカスハラが許されるわけではなく、行為の内容によっては従来どおり刑法や民法等に基づき処罰や損害賠償請求の対象となり得る点が指針で強調されています。
例えば暴力行為や脅迫行為であれば刑法の傷害罪・脅迫罪等に問われる可能性がありますし、悪質な営業妨害であれば業務妨害罪(刑法233条)や不法行為による損害賠償請求(民法709条)など法的措置が取り得ます。つまり、条例自体に罰則は無くともカスハラ行為は法的に看過されないという位置づけです。
条例はまた、都や事業者等の責務を定めています(詳細は後述)。さらに第11条に基づき、条例の内容を具体化するための「カスタマーハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」が策定されています (カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン) | 計画 | TOKYOはたらくネット)。このガイドラインでは、カスハラの具体的内容、顧客等・就業者・事業者それぞれの責務、東京都の施策、事業者の取組事項、その他カスハラ防止に必要な事項が詳細に示されています。
指針は条例の解説的な役割を果たし、企業が講ずべき対策や判断基準など実践的な助言を提供するものです。また東京都は2025年3月、各業界団体が自らの業界向けマニュアルを作成する際の共通事項やポイントを示す「各団体共通マニュアル」を公表しました (カスハラ防止各団体共通マニュアルを作成|3月|都庁総合ホームページ)。
この共通マニュアルは、業界ごとのカスハラの特徴や望ましい対応策の手引きとなるもので、各企業が実際に社内マニュアルを整備する際の参考資料となります。
ガイドラインと共通マニュアルは、条例の実効性を高める両輪として位置付けられており、事業者にとって具体的な対応策を検討する上で欠かせないものです。
要約すると、東京都カスハラ防止条例は「カスハラをしない・させない」社会を目指す理念法であり、ガイドラインや共通マニュアルを通じて企業が取るべき具体策を示したものです。以下、その具体策や企業への求められる対応について順を追って見ていきます。
施行までのスケジュールと背景
東京都カスハラ防止条例制定の背景には、前述のようにカスハラ問題の深刻化があります。特に第三次産業従事者や公共サービス従事者の多い東京で対策の必要性が高まり、2023年10月頃から東京都は「公労使による『新しい東京』実現会議」等の場で対応策の検討を開始しました。
その後、有識者による検討部会が開催され、2024年7月には条例骨子案の公表とパブリックコメント募集が行われています。
寄せられた意見を踏まえ、条例案が同年9月に都議会に提出され、2024年10月4日に条例が可決・成立しました(公布は令和6年10月11日付、条例第140号 (東京都カスタマー・ハラスメント防止条例))。制定過程では都民や事業者からの意見募集も実施されており、現場の声を取り入れながら内容が練られています。
条例成立後、都は速やかに具体策の検討を進め、2024年12月25日に指針(ガイドライン)が公表されました。指針策定には労働政策審議会等での議論も経ており、現実的で実効的な内容となっています。また先述の共通マニュアル案も2025年2月に公表され、年度内(2025年3月)に確定版が公表されています。条例の施行日は2025年4月1日と定められており、企業はそれまでに必要な社内対応を整備することが望ましい状況です。
このようなスケジュールの中、東京都は条例施行に合わせて企業側の準備を支援すべく、説明会や周知資料の提供、業界団体との連携を進めています。条例には附則で、社会環境の変化等を勘案して必要があれば見直し検討を行う旨も定められており、今後の運用状況によっては更なる制度強化も視野に入れられています。したがって企業としては施行までに体制を整えることはもちろん、施行後も情勢の変化に注視しつつ継続的に対策をアップデートしていくことが重要です。
まとめると、東京都カスハラ防止条例は約1年半にわたる慎重な議論を経て施行の運びとなりました。施行まで残りわずか(執筆時点)ですが、中小企業においても自社の従業員を守りつつ適切にクレーム対応する体制を構築する必要があります。次章以降では、企業に課せられた責務と具体的な初動対応・予防策について解説していきます。
企業に求められる義務と責任
東京都カスハラ防止条例は、事業者(企業)に対して主体的・積極的なカスハラ防止への取組を行う責務を課しています。第九条第1項で「事業者は、基本理念にのっとり、カスタマーハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組む」と明記されており、カスハラ対策は単に従業員任せではなく組織として能動的に行うべきものであるとされています。また同項は「都が実施するカスハラ防止施策に協力するよう努めなければならない」とも規定しており、東京都の施策(ガイドライン周知や支援策等)に企業が協力する姿勢も求められます。
さらに条例第九条第2項では、実際に従業員がカスハラ被害に遭った場合の企業の対応義務が定められています。事業者は自社の業務に関連して就業者(従業員)がカスハラを受けたときは、速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し行為の中止を申し入れる等、必要かつ適切な措置を講ずる努力義務があります。
簡単に言えば、カスハラ発生時には会社として直ちに従業員を守り、加害顧客に対してやめるよう要求することが求められるのです。
例えば暴言を受けている従業員を一人にせず上司が間に入って介入したり、明らかな脅迫に対しては警察に通報することも「必要かつ適切な措置」に含まれるでしょう。
加えて第九条第3項では、逆の立場として自社の従業員が他社の顧客等に対してカスハラ加害者とならないように必要な措置を講ずる努力義務も定められています。
これは企業間取引など自社が「顧客」の立場になる場合を想定した規定です。例えば自社の営業社員が取引先の下請企業に対して暴言や過大な要求をするようなことがないよう、企業は社員教育や内部ルールの整備を行うべきだという趣旨です。万一自社社員が取引先にカスハラを働けば、取引先から自社に対して安全配慮義務違反で損害賠償を請求されたり、下請法違反等で行政処分を受ける可能性もあります。したがって「カスハラをしない」の観点でも社内統制が求められています。
以上のように条例上「努めなければならない」という努力義務の形式ではありますが、企業には(1) カスハラ防止策への主体的取組、(2) 被害発生時の迅速適切な対処、(3) 自社従業員の加害抑止という3つの責務が課せられています。これらを怠れば、職場の安全配慮義務違反として企業が法的責任を問われるリスクもあります。
カスハラ対策は法令上も社会通念上も、もはや企業の当然の義務といえるでしょう。
このほか、条例第十四条では企業が講ずべき具体的な防止措置について定められています。「顧客等からのカスハラを防止するための措置」として、企業はガイドラインに基づき、次のような対策を講ずる努力義務があります。
- 必要な体制の整備(例:社内に相談窓口を設ける、人員配置や権限ルートを決める等)
- カスハラ被害に遭った就業者への配慮(例:心身のケア、勤務環境の調整等)
- カスハラ防止のための手引(社内対応マニュアル)の作成
- その他必要な措置(業種・企業規模に応じ適切と考えられる施策)
そして企業がこの「手引」(マニュアル)を作成した際は、従業員もそれを遵守するよう努めなければならないことも規定されています。これは、せっかく社内ルールを定めても現場で守られなくては意味がないため、社員にも遵守努力義務を課した形です。
以上が条例上の企業の義務と責任ですが、平たく言えば「会社としてルール・体制を整え、従業員を守り、いざという時毅然と対応しなさい」ということです。以下、その具体像を初動対応フローや社内ルール整備の観点から詳しく見ていきます。
カスハラ・クレームの初動対応フロー(現場・上司・組織対応)
カスハラやクレーム対応において発生直後の初動対応は被害拡大を防ぐ上で非常に重要です。現場の従業員が一人で抱え込まず、上司や組織と連携して速やかに適切な対応を取ることが求められます。
東京都の共通マニュアルでも、現場・一次対応から二次対応(上司・組織対応)への切り替え基準や対応手順をあらかじめ定めておくことが推奨されています。ここでは一般的な初動対応フローの例を解説します。
現場での一次対応(従業員による対応)
まず最前線の従業員は、落ち着いて顧客の話に耳を傾けつつも毅然とした態度を崩さないことが肝要です。理不尽な要求や暴言に対して、過度にへりくだったり安易な妥協をしたりすると、かえって相手を増長させてしまう恐れがあります。そのため、謝るべきところは丁寧に謝りつつも、守るべき一線(従業員の人格・安全)は譲らない姿勢が重要です。
例えば電話で高圧的な口調で「お前をクビにできる」などと言われても、事実に反する無理な要求には安易に屈しないよう指針では求めています。現場対応者は事前に社内マニュアルで定められたフレーズや対応例を参考にしながら、可能な範囲で問題の沈静化を図ります。
ただし、暴力や人格否定的な罵倒が始まるなど明確にカスハラに該当する状況になった場合には、一人で背負い込まず早めに次の段階へ移行する判断が必要です。
上司・現場監督者への引継ぎ(二次対応)
従業員の一次対応で解決しない、あるいはそもそも対応困難な悪質クレームである場合、上司や現場責任者が対応を引き継ぐのが望ましいです。
現場監督者が代わって応対することで、顧客に対して「組織として対応している」ことを示し、現場社員をこれ以上孤立させない効果があります。上司は状況に応じて、事実確認や問題点の整理を冷静に行いながら、顧客に対して必要な注意喚起をします。
たとえば「そのような暴言は業務上受けかねます」と毅然と伝える、要求内容が過度であれば「社として対応できる範囲を超えております」ときっぱり断る、といった対応です。
東京都のマニュアル案でも、対面場面で同じ要求が繰り返され一定時間を超過した場合には「警察に相談します」と明確に伝え、それでも聞き入れられなければ退出を求めるという方針例が示されています。このように管理職の立場から組織としてノーと言うことは、現場従業員を守るだけでなく、常識の範囲を超えた要求には応じないという会社の一貫した姿勢を示す意味でも重要です。
組織的な対応・外部機関との連携(三次対応)
上司が出てもなお収まらない場合、あるいは暴力・脅迫など法に触れる重大な事態となっている場合は、組織ぐるみの対応に移行します。
具体的には、警察への通報を躊躇しないことが挙げられます。
東京都の共通マニュアルでも「緊急性や危険性を伴う場合、110番通報をためらわないことが重要」と明記されています。
実際、明白な暴行・脅迫(「殺すぞ」「火をつけるぞ」等)といった発言が出た場合や、客が暴れて物を壊すような行為に及んだ場合は、速やかに警察を呼ぶべきです。警察沙汰は避けたいと躊躇する企業もあるかもしれませんが、従業員の安全確保が最優先であり、被害が深刻化する前に専門機関の力を借りる判断は適切な危機管理です。
また、状況によっては顧客への対応自体を中断・中止する決断も必要です。
たとえば度重なる迷惑行為を理由に「本日の対応はこれ以上いたしかねます。お引き取りください」と宣告し、警備員等の助けを借りて退出いただく、電話であれば警告の上で通話を終了する、といった措置です。
条例第9条2項が定める「行為の中止の申入れ」は、場合によってはサービス提供の中断(取引停止)も含むものと解されます。ホテルの事例では、迷惑行為の激しい宿泊客に対し、最終的に料金返金の上で退館措置をとることも考えられます。
このように企業として「これ以上の対応はできません」と打ち切る判断も、トラブルをそれ以上大きくしないためにはやむを得ない場合があります。
初動対応後の報告・記録とフォロー
現場対応が一段落した後は、ただちに社内で経緯を共有し、記録を残すことが重要です。
誰が・いつ・どこで・何をされたか、顧客は何と言ったか、自社はどう対応したか……可能な限り詳細に事実関係を記録します。「『暴言を吐いた』ではなく『○○という言葉で大声で怒鳴った』というように具体的な言動を記録する」ことが望ましいといえます。録音やメモ書きなど形式は問わず、後から客観的に検証できる証拠を残しておくことが肝要です。
これにより、同じ顧客が後日「そんなひどいことは言っていない」などとクレームをつけてきた際にも記録に基づき反論できますし、今後類似の事例が発生した際の社内共有知見にもなります。作成した記録は上長や関係部署(カスタマーサポート部門や法務・人事など)に速やかに報告・共有し、必要に応じて顧客対応方針の見直しや被害従業員へのフォローに活用します。初動対応フローの中で最後になりますが、この報告・振り返りまで含めて一連の初期対応と捉えることが大切です。
以上が一般的な初動対応の流れとなります。業種や業態によって細部は異なりますが、共通して言えるのは「現場対応者任せにしない」「エスカレーション基準を明確に」「必要なら警察等の外部を含め組織で対応する」という点です。自社の状況に合わせて事前に対応フローを策定し、従業員にも周知しておくことで、いざというときスムーズに動けるようになります。
社内ルール整備(就業規則、マニュアル、通報窓口の整備)
初動対応を適切に行うためには、平時から社内のルール・体制を整備しておくことが不可欠です。東京都条例・指針も、企業に対しカスハラ防止のための社内体制整備を求めています。ここでは、就業規則等の社内規程、対応マニュアル、従業員からの相談窓口といった内規整備のポイントを解説します。
就業規則等への方針明文化
まず基本となるのは、自社として「カスタマーハラスメントには組織的に対処し、働く人を守る」という基本方針を社内外に明示することです。例えば就業規則や服務規程に以下のような条項を設けることが考えられます。
- 顧客からのハラスメント行為への対応指針
従業員が著しい迷惑行為を受けた場合には業務を一時中断して上長へ報告できること、会社として必要措置(注意喚起・警察連絡等)を講じること、等。 - 従業員によるカスハラ禁止
自社の従業員が取引先や顧客に対しハラスメント行為を行った場合の懲戒処分規定。東京都のマニュアル案でも企業間取引のカスハラ対策として「自社従業員がカスハラを行った場合の懲戒規定など対処を明確化しておく」ことを推奨しています。
このように社内規程に方針を落とし込むことで、全社員に周知徹底しやすくなります。対外的にも、自社がカスハラに組織としてNOを突きつける姿勢を示すことにつながります。顧客対応業務のマニュアルや社内ポスター等に「カスタマーハラスメントは会社として許しません」といったメッセージを掲示する企業も出てきています。もちろん現場対応ではお客様への敬意は払いつつも、「事実上許容しない」という企業方針を持つことが従業員の安心に繋がるでしょう。
カスハラ対応マニュアルの策定
次に、実践的な社内マニュアルを整備します。条例第14条も手引(マニュアル)の作成を企業責務として掲げています。東京都は各社が参考にできるよう「各団体共通マニュアル」の雛形(Word版)も提供しています (カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル | 計画 | TOKYOはたらくネット)。これを自社の業態に合わせて修正し、独自の「カスハラ対応マニュアル」として完成させると良いでしょう。
マニュアルには以下のような項目を盛り込みます。
- カスハラの定義と事例
どのような行為が該当しうるか(暴力・暴言・過度な要求など)と具体例。業界でよくある迷惑行為を洗い出し、どこからがカスハラか共通認識を示します。 - 基本方針
「従業員の安全・人格を守るため毅然と対応する」「正当な苦情には真摯に対応する」等の姿勢を明記。 - 初期対応フロー
前章で述べたような現場から上司・警察へのエスカレーション手順や各場面(対面・電話・オンライン)ごとの対応方針。例えば「面談中に同じ要求を3回以上繰り返されたら上長に引き継ぐ」「通話開始○分で収まらなければ一旦折り返し対応に切り替える」等、目安となる基準もあると現場で判断しやすくなります。 - 対応NG事項
やってはいけない対応(過剰な謝罪、違法な要求への安易な迎合、侮辱的対応のし返し等)も明示しておきます。例:「他社は金を払った」などの脅し文句に対して顧客を特別扱いせず過度にへりくだらないことがポイントです。 - 記録・報告方法
インシデント発生時の報告先や、記録に残すべき事項、書式など。例えば「日時・相手・状況・発言内容」をメモまたは所定フォーマットに記録し、終了後直ちに上長へ共有する、といった手順です。 - 被害者支援策
被害を受けた従業員のケア手順(相談窓口案内、産業医・カウンセラーへの繋ぎ方、休養の検討等)。 - 外部機関連絡先
警察(110番や所轄署)、弁護士や外部専門家への相談先など。
このようなマニュアルを全従業員に配布・周知しておくことが重要です。社内マニュアルに相談窓口の連絡先を明記し、イントラネットでも周知する取組を行うことも考えられます。自社でも、新入社員研修や定期研修でマニュアル内容を教育し、誰もが内容を把握している状態を目指しましょう。なおマニュアルは一度作って終わりではなく、運用状況に応じて適宜アップデートすることも大切です(この点は後述の再発防止策で触れます)。
従業員からの相談・通報窓口の設置
カスハラ問題に適切に対処するには、従業員が被害を受けた際に安心して相談できる窓口を設けておく必要があります。指針でも「社内に相談窓口(規模によっては相談担当者)を設置すること」が求められており、これによって会社がカスハラ発生状況を把握できるようにします。
窓口は人事部門やコンプライアンス担当などが担うケースが多いですが、規模に応じて外部の相談ダイヤルを契約する方法もあります。
重要なのは、窓口があるだけでなく実際に社員に利用されることです。
- 窓口の周知徹底
マニュアルや社内掲示板、イントラネット等で窓口の連絡先を明示し、いつでも相談してよい旨を繰り返し案内します。「困ったらここに電話していいんだ」と全員が知っている状態にします。 - 利用しやすい工夫
面談形式だけでなく、電話・メール・匿名報告箱など複数の方法で相談を受け付けるようにします。特に現場社員が店舗から本社に電話しづらい場合もあるため、メールフォーム等があると便利です。24時間対応の外部相談窓口(メンタルヘルス相談を兼ねる等)の導入も検討できます。 - プライバシー保護と不利益取扱い禁止
相談内容や通報者のプライバシーは厳重に守り、相談したことを理由に不利益な扱い(報復・評価への悪影響等)を一切行わないことを社内に周知します。従業員が「報告したらかえって自分の評価が下がるのでは」と不安を抱えないようにする配慮です。相談窓口担当者と人事部門が連携して適切にプライバシー管理する仕組みも重要とされています。
相談窓口に報告があった後の社内手続の流れも決めておきます。例えば、人事やコンプライアンス部門が事実関係を確認し、必要に応じて経営層へ報告、顧客対応部署と連携して再発防止策検討、といった一連のプロセスです。こうした内部手続の整理も指針で求められているところです。
以上、社内ルール整備として「規程による基本方針の明示」「具体的マニュアル策定」「相談窓口の設置」を解説しました。これらを整えることで、従業員は「会社が守ってくれる」という安心感を持ちやすくなり、万一の際にも組織だった対応が可能となります。東京都のガイドラインでも事業者に求められる具体的取組(方針策定、相談窓口、マニュアル、手続整備、被害者ケア、研修等)が詳細に示されており、企業は自社の状況に合わせてこれらを順次実行に移すことが期待されています。
社員研修・再発防止策の必要性
社内ルールを策定しただけでは十分ではありません。 現場でそれを実践できるよう、従業員教育・研修を行うことが不可欠です。また、一度カスハラが発生した後は、適切な事後対応と再発防止策を講じることで同様の被害を繰り返さない努力が求められます。
この章では、研修のポイントと再発防止の取り組みについて説明します。
社員研修の実施と内容
ガイドラインでも、策定した方針・マニュアルや手続を社員に周知徹底するため研修・教育の実施が必要だとされています。特にサービス現場の従業員やその上司(現場監督者)に対して、カスハラ発生時の対処方法や判断基準について理解を深める研修が有効です。
研修コンテンツの例としては、
- カスハラの基礎知識
カスハラとは何か、どんな行為が該当するか(条例上の定義や事例紹介)。「お客様の苦情」と「カスハラ」の違いを明確に認識させます。特に「顧客と従業員は対等の立場であり相互に尊重すべき」という基本理念を再確認します。 - 初期対応のロールプレイ
想定事例を基に役割演習(ロールプレイング)を行います。例えばクレーマー役と店員役に分かれ、マニュアルで決めた台詞や対応を実際に声に出して練習します。現場で咄嗟に適切な言葉が出るよう、繰り返し訓練することが望ましいです。研修では「どの段階で上司を呼ぶか」「どんな表現で注意するか」等のケーススタディも取り入れ、対応スキル向上を図ります。現場監督者向けには、一次対応者をフォローする心構え(決して部下を責めない等)や警察連絡の判断基準なども教育します。 - 苦情対応の基本
正当なクレームに対する傾聴・謝罪・是正措置の取り方も並行して教育します。カスハラを防ぐには、普段のクレーム対応力を高めること(サービス向上)も有効な未然防止策です。顧客の不満がエスカレートしてハラスメント化する前に真摯な対応で鎮静化できれば理想的です。そのためのコミュニケーション研修(クレーム応対研修)も合わせて実施すると良いでしょう。
研修は新入社員時だけでなく、定期的(年1回など)に全社員対象に行うことが望ましいです 。また異動や昇進で新たに顧客対応責任を負う社員には適宜追加研修をします。
研修実施にあたっては、東京都や厚労省が公開している動画・資料を活用したり、必要に応じ外部講師や専門家(弁護士等)を招くのも有効でしょう。ポイントは、全従業員が「自分たちの会社はカスハラにこう対応する」という共通認識とスキルを持つことです。それによって現場判断のブレを防ぎ、組織として一貫した対応が可能になります。
カスハラ発生後の再発防止策
カスハラが発生してしまった場合、そのままにせず事後検証と再発防止策の実施を行います。
具体的には、まず被害に遭った従業員のケアを最優先します。ひどい暴言や威嚇を受けた場合、従業員は深刻な心理的ダメージを負うことがあります。適切な体制整備を怠ると被害が拡大し、企業の安全配慮義務違反につながり得るとも指摘されており、休職や退職に追い込まれるケースも発生するおそれがあります。そうならないよう、上司や人事担当者は被害者と面談して状況を把握し、必要に応じて心身のケア措置を講じます。
例えば精神的ショックが大きければ産業医面談を設定する、有給休暇や特別休暇で数日休ませる、配置転換を検討する、といった対応です。被害社員に「あなたのせいではない」と伝え、決して一人で抱え込まないよう支えます。
また、職場の他の従業員にも、当該社員が安心して働けるようフォローアップを依頼します。メンタルヘルスケアについては専門カウンセラーの手配も検討します。
こうした被害者への配慮措置を整えることは企業の重要な責務であり、適切な対応が取られなかった場合には社員から企業が訴えられるリスクもある(安全配慮義務違反)ことを肝に銘じましょう。
次に、社内でその事案を共有・分析します。
記録や関係者からの聞き取りを基に、「なぜ起きたか」「会社の対応は適切だったか」「今後どう防ぐか」を検討します。
東京都ガイドラインでも、実際の事例を活用して新たな防止策を検討し、マニュアルや研修の見直し・改善に役立てることが重要とされています。
例えば今回のケースでは上司呼び出しが遅れた、と反省点があればエスカレーション基準を時間や回数で明確化する、顧客からの要求パターンに新しいタイプがあればマニュアルにQ&Aを追加する、という具合です。
さらに、経営者から全社員に向けて「今回のようなカスハラには会社として断固対処する。皆さん一人では悩まず必ず相談してほしい」といったトップメッセージを発信することも効果的です。実際に事案が起きた後に経営トップが従業員をねぎらい、再発防止策にコミットする姿勢を示すことで、社員の安心感と会社への信頼が高まります。
また、定期的に職場アンケートを実施し、潜在的なカスハラ被害や不安を把握することも有益です。
従業員が声を上げていないだけで実は日常的に困っているケースが潜んでいるかもしれません。匿名アンケートやヒアリングで実態調査し、必要なら追加対策を講じます。さらに産業医や衛生委員会(労働安全衛生法で義務付けられる組織)とも連携し、従業員の健康確保の視点から助言を仰ぐことも考えられます。
以上、社員研修と再発防止策について述べました。研修による予防と、事後の検証・改善というPDCAサイクルを回すことで、カスハラへの組織対応力は着実に向上します。カスハラはゼロにするのが理想ですが、起きてしまった経験から学びを得て次に活かす姿勢が、企業の持続的な成長と従業員の安心に繋がるでしょう。
ケーススタディ(具体的事例:企業間取引・サービス利用者・医療・介護・飲食業)
ここで、よくあるカスタマーハラスメントの想定事例をご紹介します。業種ごとに典型的なケースと対応のポイントを見てみましょう。
企業間取引のケース
下請企業の社員が元請企業の担当者から執拗に怒鳴られ、「次は契約を切るぞ」などと脅されたケースです。
取引上の力関係を背景に無理難題を押しつけたり、不必要に恫喝する行為は典型的なBtoBのカスハラと言えます。条例でも企業間のカスハラも禁止されており、こうした行為はパワハラと同様に重大視されています。
対応としては、自社の上層部に速やかに報告し、必要に応じて取引先企業の上席と協議することが考えられます。
また場合によっては、独占禁止法上の優越的地位の濫用や下請代金法違反として行政処分や罰則の対象になり得る可能性もあります。
自社社員が被害を受けた場合は、取引先との関係悪化を恐れて泣き寝入りせず、法的措置も視野に入れた毅然とした対応が必要です。一方で、自社が加害者側にならぬよう取引先への接し方を社員に教育しておくことも重要です。
サービス業(小売・宿泊業など)のケース
あるホテルでは、常連の顧客が毎回客室の清掃の粗を探して難癖をつけ、「部屋を無料でアップグレードしろ」「今すぐ自分の目の前で掃除し直せ」などと要求しました。さらには、「俺は東京の不動産会社の社長だ」「お前なんかクビにしてやる」などと大声で威圧し、止めに入った上司の名刺を突き返して破り捨て「土下座しろ」とまで要求してきました。従業員がそれを断ると「今すぐキャンセルするぞ」と息巻きましたが、最終的には宿泊代を支払いました。しかし他の宿泊客とのトラブルに発展しかねない暴言が続いたため、ホテル側は警察に相談の上で料金を返金し退館いただく措置を取りました。
このケースでは、ホテル側は毅然と対応しつつも安全に配慮し、警察の助言を得てトラブル客を退去させることが考えられます。
サービス業では他のお客様への影響も考慮しなければなりません。限度を超える迷惑客に対しては入店禁止・利用お断りを含めた対応もやむを得ません。
サービス業ではこのように周囲への波及も踏まえ、必要なら組織判断で取引自体を打ち切る勇気も持つことが重要です。
飲食業のケース
とある食品スーパーでは、半額シールの貼られた弁当を客が自らの不注意で落としてしまい商品が破損しました。店員が衛生上販売できないと説明すると、その客は「いいから売れ」「代わりに他の商品を半額にしろ」と理不尽な要求を繰り返し、店内で長時間大声を出して騒ぎ続けました。
また、別の飲食店では、店員が他の客対応で手が離せない隙に「遅いんだよ!」と怒鳴り散らし威嚇する顧客もいました。
飲食業では酔客による絡みや土壇場でのクレームも多く、現場スタッフが少人数で対応している時に起きやすい傾向があります。
対応策として、バックヤードから応援スタッフや店長をすぐ呼べる体制を整えておく、深夜帯は二人体制にするといった工夫が考えられます。また、店頭に「他のお客様のご迷惑となる行為はお断りします」と掲示する店舗も増えています。
万一店内で暴れたり他のお客様に危害を及ぼす恐れがある場合は、迷わず警察に通報して対応することが従業員の安全と店内秩序を守るために必要です。
医療機関のケース
調剤薬局での例です。
ある患者が処方箋を持って来局し、他にも待っている患者がいる中で自分が呼ばれるのが遅いことに立腹し、「早くしろ」「何をチンタラやってるんだ」と薬剤師に怒鳴りつけました。さらに薬剤師が薬の効果や服用方法を説明し始めると「そんなことはどうでもいい、さっさとよこせ」などと罵声を浴びせました。
別のケースでは、患者が医師の指示より多い量の薬を出せと要求し、薬剤師ができない理由を丁寧に説明したところ「ふざけるな、殺すぞ」と脅された例もあります。
医療・調剤の現場では、患者や家族が不安や苛立ちから強い口調になること自体は理解できますが、明らかな暴言・脅迫は許されません。
対応策として、薬剤師や受付スタッフだけで抱えず上席の薬局長や医師に連絡してもらう、自衛措置としてカウンター越しに一定距離を保つ・複数スタッフで対応するなどがあります。それでもエスカレートする場合には、他の患者様の安全確保のためにも警察介入を検討すべきでしょう。
近年は病院での暴言暴力に備え警備員を配置する例もあります。医療従事者へのハラスメントは患者の治療にも悪影響を及ぼすため、組織全体で毅然とした態度を示すことが求められます。
介護現場のケース
介護施設や訪問介護の現場でも、利用者本人やその家族からハラスメントを受ける事例が少なくありません。
ある介護施設では利用者の家族がスタッフに向かって「無能だ」「役立たず」と罵倒したり、「もっとちゃんと介護しろ」と怒鳴って脅すケースが想定されます。
また、認知症の高齢利用者が女性介護職員の身体(胸部)に触ろうとするセクシャルハラスメントも想定されます。
介護職員は利用者に寄り添う気持ちが強い分、我慢してしまいやすい傾向がありますが、深刻な人権侵害であり放置すれば職員の士気低下・離職に直結します。
対応として、施設長やケアマネージャーが状況を把握し家族には冷静に注意・説得を行うこと、必要に応じて利用契約の見直し(サービス提供停止も含め)を検討することもあります。
認知症による行動については、職員を二人体制にして対応する、一部男性職員に代わってもらう等の対策が考えられます。また、家族にも介護現場でのマナーや限界を説明し理解を得る努力が必要です。公的機関がまとめた介護現場ハラスメント対策マニュアルなども参考になります (介護現場におけるハラスメント対策 – 厚生労働省)。
介護は利用者の尊厳を守る仕事ですが、同時に働く人の尊厳も守られなければならないという点を関係者全員が認識することが大切です。
以上、いくつかの事例を紹介しました。これらのケーススタディから明らかなように、カスハラは業種を問わず発生し得るものです。
それぞれ状況は異なりますが、共通する教訓として、
- 毅然さと安全確保のバランス
相手の威圧に屈しない姿勢を示しつつ、危険時は直ちに身の安全を守る(退避・警察連絡)。 - 早めのエスカレーション
一人で抱え込まず、適切な段階で上司や第三者を介入させる。特に医療や介護では感情的対立を避けるため別の職員と交代する。 - 記録と証拠の重視
後日のためにやり取りを詳細に記録し、可能なら録音・録画しておく(法律の許す範囲で)。 - 場合によっては取引停止も辞さない
悪質な顧客にはサービス提供をお断りすることも検討(他の善良な顧客や従業員を守るため)。
こうした対応が求められます。
自社の業界特性に応じて想定事例を洗い出し、事前にシミュレーションしておくことが何よりの備えとなります。実際に東京都の共通マニュアルでも業界ごとのケーススタディが盛り込まれています。自社内でも勉強会等で共有し、いざという時に落ち着いて対処できるようにしておきましょう。
トラブル拡大防止のコツ(法的視点・記録・警察連携など)
カスハラ対応において、被害やトラブルをこれ以上拡大させないためのコツ・留意点をまとめます。法的な視点からの備えや、社内外の連携術など、知っておくと役立つポイントです。
記録と証拠の確保
前述したように、詳細な記録を残すことはカスハラ対応の基本です。指針も「可能な限り詳細な内容を記録し、速やかに組織内で報告・共有することが重要」と強調しています。記録は将来の紛争防止に極めて有効なツールです。
例えばクレーマーが後日「店員に侮辱された」など虚偽の主張をした場合でも、当時の録音や記録があれば会社側の正当性を証明できます。また、迷惑行為がエスカレートして警察沙汰や法的措置となった際にも、録音・録画や対応記録は重要な証拠となります。そのため可能な範囲で録音・監視カメラ等の活用も検討しましょう。もちろん録音する際は相手に断りを入れるのが望ましいですが、最近ではコールセンター等で「通話を記録させていただきます」とアナウンスする例も一般化しつつあります。
インターネット上の誹謗中傷についても、投稿内容や日時、投稿者の情報などを正確に記録して証拠保存しておきます。記録した情報は単に証拠としてだけでなく、社内で類似対応時の参考事例として役立ちます。例えば「過去に○○という要求に対してこう対応したところ沈静化した」といったナレッジが蓄積され、マニュアル改善や社員教育にも活かせるでしょう。
警察等との連携
身の危険を感じたら即110番通報——これは繰り返しになりますが最も重要なポイントの一つです。
企業の中には「お客様相手に警察を呼ぶのは…」とためらう向きもあるかもしれません。しかし、刃物沙汰や暴行事件に発展してからでは手遅れですし、従業員を危険にさらすことは決してあってはなりません。東京都の共通マニュアルでも「緊急時はためらわず110番通報することが重要」と明言されています。
また、事前に所轄警察署と意見交換しておき、どういう場合に来てもらえるか相談しておくのも有効です。地域によっては企業向けの防犯講習などでクレーム対応時の警察への伝え方(「暴れていて危険です」等明確に)を教えてくれることもあります。
警察以外でも、例えば悪質クレームが続く場合に弁護士から内容証明郵便で警告状を送付してもらうという方法もあります。これは法的効力はありませんが第三者の目が入ることで相手への心理的圧力となり、行為をやめさせる効果が期待できます。
いずれにせよ、社内だけで解決しようとせず、必要に応じて外部の力を借りることは決して恥ではありません。むしろ組織防衛策として適切であり、従業員にも「何かあれば会社が守るために警察でも弁護士でも使う」という姿勢を示すことが抑止力につながります。
迷惑顧客への措置(出入禁止・契約打ち切り等)
常習的または悪質なカスハラ加害者に対しては、思い切って取引関係の終了を検討することもトラブル拡大防止につながります。
小売店や施設であれば出入禁止措置、会員制サービスであれば会員資格の剥奪、企業間取引であれば契約更新の見送りなどです。
例えば先のホテルの例では当該客に事実上の出入り禁止措置をとっていますし、他社でも店頭で「迷惑行為をされた方のご利用はお断りします」と宣言しているケースがあります。
法律上、正当な理由なく特定の顧客を差別的に扱うことは問題ですが、従業員への著しいハラスメントという正当な理由があればサービス提供の拒否は認められ得ると考えられます。
実務的には、社内で対応可否の判断基準を設け(例:「人格否定の暴言を繰り返した場合は退去要請」等)、それを満たした場合には毅然とお断りする運用をすることが考えられます。この際も記録が重要で、後日クレーマーからのクレーム(二次クレーム)に対して「○月○日○時にこのような迷惑行為があったためお断りしています」と説明できるようにしておきます。
なお、迷惑行為者が悪質クレーマーとして他に広報し始めた場合(SNS等で店名を挙げて中傷するなど)は、次に述べるように企業側も情報発信を検討します。
SNS・ネット上のトラブル対策
最近では、店頭で要求が通らないと見るやSNS等に店や従業員の悪口を書き込むような顧客も見られます。このようなオンライン上のカスハラに対しても組織的対応が必要です。
SNS上での事実無根の誹謗中傷には組織として投稿内容を特定して削除要請を検討したり、自社のホームページや公式SNSで会社の対応方針を公表して正しい情報発信を行うことも考えられます。
具体的には、プラットフォームのガイドラインに基づき違反報告を行い投稿削除を求める、必要なら発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法に基づく手続)を検討する、といった法的対応も視野に入ります。
自社に落ち度が無いのに一方的にネット攻撃されている場合、沈黙していると企業イメージが損なわれる恐れもあるため、速やかに事実を発信し風評被害を食い止めることが大切です。他のお客様や取引先から問い合わせが来る場合には、広報担当を通じて「当社として然るべき対応を行っております」等丁寧に説明します。
いずれにせよ、リアルからネットまで一貫して組織対応することで、カスハラ加害者に付け入る隙を与えないようにすることが拡大防止のポイントです。
会社としての備えと法的リスク管理
最後になりますが、企業はカスハラ防止策を講じない・被害が出ても放置するといったことがないようにしなければなりません。もし怠れば、前述のとおり安全配慮義務違反として被害社員から訴えられるリスクがあります。
実際の裁判でも、企業側がカスハラ発生防止の取り組みや事後対応を十分にしていたか否かが責任判断の重要なポイントになると指摘されています。
また、自社社員が加害者となった場合には被害者側企業から損害賠償請求を受ける恐れもあります。さらに、取引先への過度な要求が優越的地位の濫用等に該当すれば行政処分・刑事罰もあり得ます。
こうした法的リスクを回避するためにも、本記事で述べてきたような社内ルール整備・社員教育・記録保全・適切対処を確実に実践することが重要です。万一トラブルが大きくなってしまった場合には、速やかに顧問弁護士等に相談し、被害者のケアと並行して法的な打ち手を検討しましょう。
以上、トラブル拡大防止の観点から記録、警察・専門家連携、迷惑顧客対策、ネット対応、法的リスク管理などのポイントを解説しました。平時から最悪の事態を想定し準備しておくことで、いざという時に慌てず適切な対応が取れるようになります。
消費者・障害者の権利と合理的配慮の関係整理
カスハラ対策を推進する上で留意すべきは、正当なクレームや顧客の権利まで萎縮させてしまわないことです。条例も「この条例の適用に当たっては、顧客等の権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない」と明記しています (東京都カスタマー・ハラスメント防止条例)。つまり、カスハラを防ぐという目的があるとはいえ、顧客の正当な要求や意見表明まで抑え込んではならないということです。
消費者の正当なクレーム
まず、消費者の正当なクレームについて整理します。
指針では「正当なクレームは業務改善や新商品開発につながるものであり、不当に制限されてはならない」と謳われています。お客様からの苦情・意見・要望は本来、企業にとって貴重なフィードバックであり、謙虚に耳を傾け改善に活かすべきものです。
事実、「お客様は神様」と言われた時代もあり、現在でもカスタマーサクセス(お客様の成功体験を創出する)が企業経営の重要テーマです。したがって、カスハラ対策を理由に正当なクレームまで軽視・黙殺しては本末転倒です。
条例策定時にもその点は十分配慮されており、消費者基本法や消費者契約法など既存の消費者保護法制上、企業には苦情を適切かつ迅速に処理する責務があることが指針に引用されています。
例えば、消費者基本法5条は、事業者は商品・サービスに関する苦情を適切かつ迅速に処理するための体制整備に努めるべきと規定しています。また、消費者契約法は契約時の情報提供義務等を定めています。
要するに、「顧客の苦情対応は企業の責務」と法律で定められているのです。東京都ガイドラインでも、こうした消費者の権利(安全を求める権利、知る権利、意見を反映させる権利等)と企業の責務(情報提供、苦情処理体制整備等)を十分に尊重するよう求めています。
その上で、どんな苦情でも無制限に受け入れるわけではないという線引きがカスハラ規制です。
「正当な理由がない過度な要求」かどうかが分水嶺になります (東京都カスタマー・ハラスメント防止条例)。
例えば、商品に明らかな欠陥があり交換を求めるのは正当ですが、それに便乗して法外な損害賠償を要求するのは「正当な理由のない過度な要求」と言えます。また、店員の小さなミスに対し人格を否定するような暴言を浴びせるのは不当な行為です。
一方、例えば高齢の顧客が説明を何度も聞き返すのは、単に理解したいからであって迷惑行為ではありませんし、障害のある方が通常以上の配慮を求めるのも当然の権利です。そういった正当な要求まで「クレーマーだ」と決めつけないことが大切です。
第5章で触れた社員研修でも、苦情対応とハラスメント対応の切り分けを教える必要があります。従業員が過敏になりすぎて、少し厳しい口調のお客様まで敵視してしまうと健全な顧客対応が損なわれます。あくまで相手の言い分に耳を傾けた上で、その内容・態様が社会的に許容できる範囲か否かを冷静に判断するよう指導しましょう。
障害のある顧客等への合理的配慮
次に障害のある顧客等への合理的配慮についてです。
条例策定時、「障害者への配慮がカスハラ防止と両立するよう留意すべき」との指摘がなされ、指針でも詳細に触れられています。
具体的には、障害者差別解消法第8条第2項が引用されており、
事業者は障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表示があった場合、負担が過重でないときは障害者の権利利益を侵害しないよう必要かつ合理的な配慮をする責務を有する
と規定していることが示されています。
これはつまり、障害のあるお客様から何らかの配慮(バリアフリー対応やコミュニケーション上の補助等)を求められた場合、対応が極端に困難でない限りは合理的な範囲でそれに応じる義務が企業にあるということです。
例えば、聴覚障害のある方には筆談や要点を書いたメモを渡す、視覚障害のある方には口頭で丁寧に説明する、車椅子利用者には段差を避けた経路を案内する、といった配慮です。これらは顧客の正当な権利であり、決して「面倒な要求」ではありません。むしろ企業側が積極的に提供すべきサービスです。したがって従業員には、障害のあるお客様から通常と異なる対応を求められた際でも決してぞんざいに扱わず、誠意を持って対応するよう教育する必要があります。
また、障害特性ゆえに言動が激しくなってしまうケース(例えば認知症の方の暴言など)もありえますが、それはハラスメントの意図とは切り離して対応することが求められます。専門知識を持った職員がフォローに当たり、「障害を理解し適切に援助する」視点で接することが重要です。
まとめ
まとめると、カスハラ対策と消費者・障害者の権利保護は両立させるべきものです。
条例の基本理念(第3条2項)も「顧客等と就業者とが対等の立場において相互に尊重すること」を謳っています (東京都カスタマー・ハラスメント防止条例)。これは顧客だけを神聖視するでもなく、逆に従業員だけを特別扱いするでもなく、お互い人間として尊重し合おうという当たり前の原則です。企業は従業員の人格・安全を守りつつ、顧客の正当な権利にも最大限配慮するという両面を追求する責務があります。そのために、社員研修等で「正当なクレーム歓迎、ハラスメントNo」というスタンスを周知すると良いでしょう。
例えば「お客様の貴重なご意見は大歓迎。ただし暴力や脅しなど行き過ぎた行為はお断りします」といった社内メッセージを共有することです。消費者団体が提唱する消費者の責任という考え方もあり、権利の裏には適切に行使する責任が伴うとされています。指針でも、Consumers Internationalが提唱する消費者の責任(批判的意識を持つこと、主張し行動すること、社会的弱者へ配慮すること 等)に触れ、消費者側にも節度ある行動が求められることを示唆しています。
一方で企業側には「消費者の苦情を適切迅速に処理すること」などの責務が定められていることも再確認されています。要するに双方が歩み寄って初めて健全な関係が成り立つということです。
カスハラ防止条例は決して「企業がクレームを封じ込める権限を得た」ということではありません。顧客の声を真摯に受け止める企業努力はこれまで通り重要であり、その上で明らかに行き過ぎた迷惑行為からは従業員を守りましょう、というバランスを取ったものです。この点を履き違えず、正当な要求には真摯に、悪質な行為には毅然とというメリハリの利いた対応を心がけることが肝心です。社員にもそのことをよく理解させ、カスハラ防止とサービス向上の両立を目指しましょう。
以上、東京都カスタマーハラスメント防止条例と関連指針に基づき、中小企業が押さえておくべき初動対応と予防策を詳述しました。「カスハラから従業員を守る」ことは、単に社員のためだけでなく健全なサービス提供体制を守り抜くことでもあります。従業員が安心して働ける環境があってこそ、結果的に良いサービスがお客様に提供できます。
本記事の内容を参考に、自社のルールや体制を見直し、必要な措置を講じていただければ幸いです。東京都の条例施行はゴールではなくスタートです。今後はこの条例を契機に、社会全体で「顧客と従業員がお互い尊重し合う」風土を醸成していくことが期待されます。
企業としてもその一翼を担い、カスタマーハラスメントの無い公正で持続可能なビジネス環境を実現していきましょう。
解説動画
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス