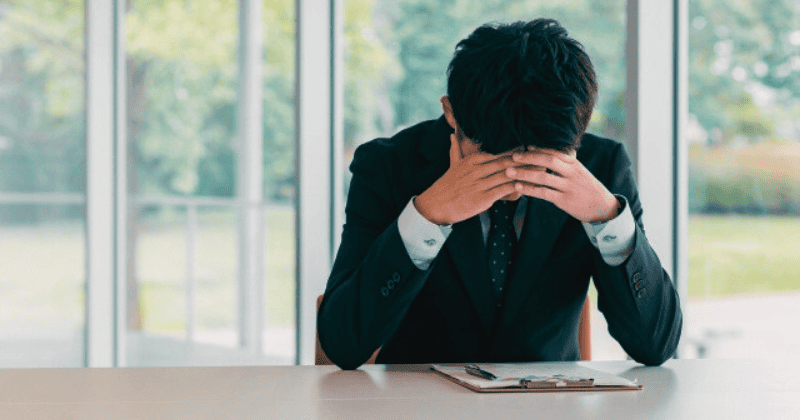はじめに
職場におけるいじめやモラルハラスメント(モラハラ)は、近年深刻な社会問題として認識されています。上司や同僚による暴言・嫌がらせ、無視、過度な指示出しなど、多様な形態で行われるモラルハラスメントは、被害者の心身の健康を著しく損ない、離職や訴訟に発展するリスクを高めます。さらに、企業内部で放置すると、生産性の低下や企業ブランドの毀損につながる重大な問題です。
本記事では、職場いじめ・モラルハラスメントの典型例や法的リスク、企業が導入すべきハラスメント防止策や相談窓口の整備など、具体的な対応策を弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。働きやすい職場環境を守るために、企業が取るべき行動を確認しておきましょう。
Q&A
Q1:職場いじめ・モラルハラスメントとは具体的にどのような行為ですか?
一般的には、特定の従業員に対し、言葉や行動で心理的圧力を加えたり、無視・排除したり、過度な叱責や人格否定を行うなど、相手の尊厳を傷つける行為を指します。上司から部下への一方的なパワハラのみならず、同僚間の仲間外れや陰口、部下から上司への逆ハラスメントも含まれます。
Q2:企業が職場いじめやモラハラを放置すると、どんなリスクがありますか?
被害者がうつ病や適応障害などメンタル不調を発症し、長期休職や離職につながり、企業は安全配慮義務違反として損害賠償責任を負う可能性があります。さらに、労働局や裁判所での紛争に発展すれば、企業イメージが大きく毀損される恐れがあります。
Q3:パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)で企業はどんな義務を負いますか?
2020年6月に施行された通称「パワハラ防止法」により、企業はパワーハラスメント防止措置を講じることが義務付けられました(中小企業は2022年4月から義務化)。具体的には、ハラスメントの社内方針制定や相談窓口の設置、研修の実施などが求められます。職場いじめ・モラハラの防止策を整備し、従業員への周知と適切な相談対応が不可欠です。
Q4:ハラスメント相談があった場合、企業はどう対応すべきでしょうか?
まずは速やかに事実関係を調査し、被害者・加害者・目撃者等からヒアリングを行い、再発防止と被害者の救済措置を講じることが大切です。調査結果に基づき、必要なら加害者に対する懲戒処分を検討し、被害者の配置転換や心身のケアなども検討します。
調査内容や処分内容は適切に記録し、後日トラブルが再燃しないよう運用面でもフォローアップが必要です。
解説
職場いじめ・モラハラスメントの実態と事例
- 言語的ハラスメント
- 上司が部下を常に叱責・否定する、侮辱的な言葉で人格を否定する、過度にプライベートを詮索・攻撃するなど。
- 同僚間でも仲間外れや陰口を繰り返し、ターゲットに精神的苦痛を与えるケースが多い。
- 物理的・身体的ハラスメント
机を叩く、物を投げる、身体接触を用いて威圧するなど。これは暴行や傷害罪に該当する恐れがあり、重大な刑事事件に発展する可能性もある。 - 業務上の優位性を利用したハラスメント
部下に過度な仕事量を与える、逆に仕事を与えないで孤立させる、ミスを執拗に責め立てるなど。パワハラの典型例であり、企業が見逃せば安全配慮義務違反となるリスクが高い。 - 逆ハラスメント・カスタマーハラスメント
部下が上司に対して集団で嫌がらせを行うケースや、顧客からの過剰なクレームで従業員が精神的圧力を受ける「カスハラ」も広義のモラハラに含まれる。
企業が講ずべき防止策
- ハラスメント防止規程の整備
- 就業規則やハラスメント防止規程の中で、職場いじめ・モラハラの定義や禁止行為を明確化し、違反者への懲戒処分を定める。
- パワハラ防止法の要件を満たし、相談窓口や調査手順、被害者保護なども記載しておくとよい。
- 相談窓口の設置・運用
- 被害者が安心して相談できる社内外の窓口を複数用意し、匿名報告や外部委託なども含めて利用しやすい体制を整える。
- 相談を受けた担当者が適切にプライバシーと公平性を保ち、事実調査に移るフローをマニュアル化しておくとスムーズ。
- 研修・啓発活動
- 管理職向けにはパワハラ防止研修、一般従業員向けにはハラスメント全般研修を定期的に実施。具体的な事例や判例を紹介して認識を高める。
- メンタルヘルスとの関連性や、いじめが組織全体に及ぼす悪影響などを分かりやすく解説し、企業文化としてハラスメントを許さない姿勢を示す。
- 再発防止とフォローアップ
- 問題行為が判明し処分を下した後も、加害者と被害者が再び同じ職場で働くなら、定期的なフォローアップや人事異動、配置転換などが必要かを検討する。
- 加害者に対する更生プログラム(コーチング等)の導入や、被害者のメンタルケア・カウンセリングなども検討することが望ましい。
法的リスクと企業責任
- 安全配慮義務違反
- 判例上、企業は従業員が健康被害を被らないよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っており、職場いじめ・モラハラで従業員がメンタル疾患となった場合、企業が損害賠償責任を負う可能性がある。
- 「ハラスメント防止策を講じていない」「相談を受けても放置した」などが認定されると賠償額が高額になるリスクが大きい。
- 損害賠償請求や労働審判
- 被害者が企業や加害者個人を相手取り、不法行為による損害賠償(慰謝料)請求や労働審判を起こすケースが増加。
- 企業が適切に対応していれば責任を軽減できる可能性があるが、放置・黙認があったとされると企業の責任が重くなる。
- 懲戒処分や解雇の無効リスク
- 加害者への処分が手続き不備や周知不足で無効とされる事例もある。就業規則に懲戒事由としてモラハラを明示し、弁明の機会付与など適正手続きを守る必要がある。
- 不公平な処分や差別的な扱いを加害者に行えば、逆にハラスメントとみなされる二次トラブルも起こり得るため、公正な調査と処分が求められる。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、職場いじめ・モラハラスメントへの対策として、以下のサポートを提供しています。
- ハラスメント防止規程の整備
- 就業規則やハラスメント防止規程で、いじめ・モラハラの定義や相談窓口、調査手順、処分基準などを明確化。
- パワハラ防止法の要件を踏まえ、管理職の責務や従業員の通報方法を規定して法的リスクを低減します。
- 研修・啓発プログラム
- 管理職向けパワハラ防止研修や、全従業員へのハラスメント対策セミナーを企画・講師派遣し、具体的な事例や判例を紹介しながら啓発活動をサポートします。
- 学習後の理解度テストやアンケートを実施し、継続的な教育効果を検証できます。
- 相談窓口運用と調査支援
- ハラスメント相談を受ける専用窓口を社内外に設置する際の体制構築や、調査プロセスのマニュアル作成を支援。
- 具体的な事案が発生した場合、事実調査やヒアリングの進め方をアドバイスし、公平・客観的な判断ができるようサポートします。
- 紛争対応・代理人業務
- 被害者から安全配慮義務違反や不法行為の損害賠償を請求された場合、企業側代理人として労働審判・訴訟に対応し、企業の適正対応や加害者の処分の正当性を立証します。
- 万が一のトラブルでも早期解決を図り、企業の被害を最小限に抑えるための戦略を提案します。
まとめ
- 職場いじめ・モラハラスメントは、被害者のメンタル面や企業全体の生産性に大きな悪影響を及ぼし、放置すると安全配慮義務違反として企業が損害賠償責任を問われる恐れが高い。
- パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により、企業はハラスメント防止措置を講じる義務があり、相談窓口や調査フロー、就業規則上の懲戒規定などを明確に整備し、従業員に周知する必要がある。
- 具体的な防止策としては、ハラスメント防止規程の作成、研修・啓発、相談窓口の設置、公正な調査手順の確立が欠かせない。
- 弁護士と連携し、トラブル発生時の調査や懲戒処分の適正手続き、紛争対応の戦略などを確立しておくことで、企業はリスクを大幅に低減し、健全な職場環境を維持できる。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス