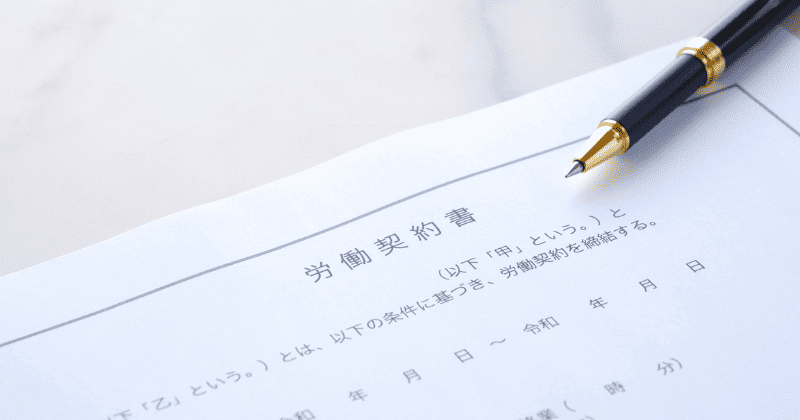はじめに
企業が新卒・中途を問わず人材を募集した際、選考を経て最終的に「採用内定」を出すケースは多いでしょう。採用内定の通知を受けた応募者は、しばしば「いつから本契約となるのか」「内定は確定なのか、取り消されることはあるのか」といった不安や疑問を抱きます。また、企業側も「せっかく内定を出したのに、直前で辞退されるリスクは?」「内定辞退に違約金は請求できないのか?」など、様々な疑問を持つことがあります。
実は、採用内定と労働契約の成立時期については、労働法や裁判例上、一定のルールや解釈が存在しています。たとえば、内定の段階で既に労働契約が成立するとみなされる場合もある一方、企業が一方的に内定を取り消すことが許されるかどうかは厳しく制限されています。また、内定辞退に関連する違約金の問題なども、トラブルになりやすいテーマです。
本記事では、採用内定の法的な位置づけや、内定取消が認められる要件、入社前の承諾書の効力などを総合的に解説します。これから採用活動を進める企業の方、あるいは内定トラブルを防ぎたい人事担当の方は、ぜひ最後までご覧ください。
Q&A
Q1. 採用内定は、すでに労働契約が成立しているのですか?
裁判例上、通常の「採用内定」は解約権留保付の労働契約とみなされると解されています。つまり、内定を出すタイミングで基本的には労働契約が成立しているとみなされますが、入社までの期間中に一定の事由があれば、企業側が解約(内定取消)を行えるという形です。ただし、安易に解約できるわけではなく、厳格な要件が課される場合が多いです。
Q2. 内定取消が許されるのはどんな場合ですか?
一般的には、内定時に示した留保条件を応募者が満たせなかった場合(例:卒業見込みだったのに卒業できなかった、重大な経歴詐称が判明した、など)や、企業の経営破綻などやむを得ない事情が生じた場合とされています。ただし、いずれの場合でも、判例上は解雇に準じる厳格な判断が求められ、容易には取消が認められない傾向があります。
Q3. 内定辞退に違約金を課すことは可能ですか?
労働基準法16条では、労働契約締結時に労働者に違約金を課したり、損害賠償額を予定する契約を結ぶことを原則禁止しています。採用内定の段階でも、すでに労働契約が成立していると解される場合がある以上、内定辞退に違約金を設定することは違法となる可能性が高いでしょう。
Q4. 入社承諾書などの書面を取り交わした場合、その効力はどうなりますか?
入社承諾書は、内定者が「企業からの内定を承諾しました」という意思表示を示すための書面ですが、これだけで一方的に違約金を設定したり、内定者の退職の自由を縛ったりすることは認められません。あくまでも採用内定が正式に決まったことを双方確認する程度の意味合いにとどまります。
Q5. 内定者が複数の企業から内定を得ていて、直前で辞退することは問題ですか?
企業としては困ることが多いですが、法的には労働契約を解除する自由を完全に奪うのは難しく、内定者の入社前辞退を強引に引き留めることは認められにくいです。ただし、就業規則や個別契約で退職(辞退)に関する猶予期間や手続きを定めるなど、一定の調整を行うことは可能です。
解説
「解約権留保付労働契約」とは
採用内定の法的性質について、判例では「企業が採用内定を通知し、応募者がそれを承諾した時点で、留保条件付きの労働契約が成立する」との考え方を示しています。具体的には、「卒業すること」「健康状態に問題がないこと」「経歴や資格が偽りでないこと」などを条件として、入社日までに著しく不適格な事情が判明しない限り、入社を確定するという仕組みです。
これにより、企業は単なる「採用の予約」ではなく、実質的に契約を締結している状態となり、後から内定取消をする場合は、解雇と同程度の正当性が求められるようになります。仮に企業が十分な理由なく内定を取り消した場合、不当解雇として損害賠償を請求される可能性もあります。
内定取消が認められるケース
- 学業要件を満たさない
- 新卒採用で「大学卒業見込み」を前提に内定を出したにもかかわらず、単位不足などで卒業できなかった場合。
- この場合でも、もし企業側が「卒業できなくても問題ない」という合意をしていたならば取消は難しくなります。
- 重大な経歴詐称
- 応募者が学歴・職歴や資格に重大な虚偽を記載していた場合。
- ただし、些細なミスや誤記ではなく、採用の可否に決定的な影響を与えるような重要な詐称である必要があります。
- 健康状態が著しく悪化
入社前に大病を患い、就労が困難となってしまったなど。ただし、合理的配慮を行えば勤務可能なケースでは取消は困難です。 - 企業の経営破綻
企業側の経営が急激に悪化し、事業継続が困難になったなど、やむを得ない場合。ただし、安易に「経営不振」を理由にすると、裁判所で厳しい目が向けられます。
内定辞退と違約金の問題
- 労基法16条の趣旨
労働者が労働契約を辞める自由を不当に制限することは、労働法の大原則に反します。よって、違約金や過度な罰金規定を設けることは無効となる可能性が極めて高いです。 - 実質的に損害が発生した場合
例えば、内定者に高額な研修費を会社が全額負担していた場合など、特別な事情があるとしても、その損害をそのまま労働者に転嫁することは認められにくいです。特別な書面を取り交わしていても、実態によっては無効と判断されることがあります。
入社前の手続きと注意点
- 入社承諾書の取り交わし
内定者が入社意思を正式に確認する意味合いで承諾書を差し入れるのは有効です。ただし、違約金や過剰な不利益条項を盛り込まないように注意しましょう。 - 就業規則や重要事項の事前開示
賃金や労働時間、福利厚生などの重要事項は、入社前にしっかりと説明し、後々のトラブルを防ぎます。 - 連絡・コミュニケーションの徹底
入社までの期間に懸念事項や体調不良などがあれば、早期に確認し対処することで、内定取消や辞退を回避できる場合があります。 - 採用活動における適正プロセス
面接・選考時に法律違反(マタハラ・セクハラ・プライバシー侵害など)があると、その後の内定者との関係に不信感が生まれ、トラブルを誘発しかねません。採用活動全般を適切に行うことが重要です。
弁護士に相談するメリット
内定にまつわるトラブルは、解雇トラブルと並んで労使双方にとって大きなリスクを伴います。弁護士に相談することで、以下のメリットが得られます。
- 内定通知書・入社承諾書の適切な文面作成
法的リスクを最小限に抑えた形で、内定条件や留保事項を明記した書面を作成できます。 - 内定取消の要件や手続きのアドバイス
経営悪化や経歴詐称など特別な事情がある場合、どのような手順や証拠が必要かを具体的に提示してもらえます。 - トラブル発生時の迅速な対応
内定者から「不当取消」「損害賠償請求」などを提起された場合、早い段階で弁護士が関与すれば、訴訟リスクを軽減し適切な和解や解決策を模索しやすくなります。 - 採用プロセス全体の見直し
面接時の質問内容や応募者への説明方法など、採用活動全体を見直し、不必要なリスクを排除することが可能です。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、採用内定に関する規程整備やトラブル対応の実績が多数ございます。必要に応じて就業規則や社内マニュアルの作成・改訂などもサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
- 採用内定は、「解約権留保付労働契約」とみなされるのが通説であり、企業が内定を一方的に取り消すには、解雇に準じる高度な正当性が必要とされます。
- 内定辞退への違約金は、労基法16条により原則として禁止されており、法的に認められる可能性は非常に低いです。
- 入社前の段階であっても、企業と内定者の間には一定の契約関係が生じるため、内定時に提示する書面や説明は慎重に行う必要があります。
- 弁護士に依頼すれば、内定取消の手続きや書式、リスク管理などを含め、適切なアドバイスを得られます。
今後の採用活動を円滑に進めるためにも、企業側は「内定」の段階で既に契約が成立しうることを十分に理解し、トラブルを未然に防ぐ体制を整備しておきましょう。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス