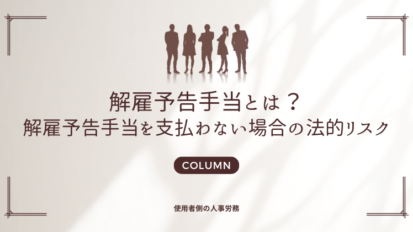はじめに
正社員採用に際して、まずは数カ月間の「試用期間」を設ける会社は多いでしょう。試用期間は、企業側が新入社員の適性や能力、勤怠態度などを見極める期間であり、同時に社員側にとっても職場環境や業務内容が自分に合うかを確認する期間です。
一方で、試用期間をどのように設定し、管理すればよいか具体的なルールを定めていない企業も少なくありません。試用期間中の解雇や延長がトラブルに発展するケース、また適性が合わない社員を本採用拒否した結果、訴訟や労働審判に発展するケースもあります。
そこで本記事では、試用期間の法的性質や設定の仕方、解雇や延長をする際の注意点について解説します。最後には専門家の活用方法やリスク回避策についても言及していますので、ぜひご一読ください。
本稿は、企業法務に強みを持つ弁護士法人長瀬総合法律事務所が執筆しております。新卒採用、中途採用を問わず、試用期間の運用にお悩みの企業様は、ぜひ参考にしてください。
Q&A
Q1. 試用期間は必ず設けなければならないのですか?
法律で義務付けられているわけではありません。ただし、実務上は多くの企業が「本採用前の評価期間」として試用期間を設定しています。適性を見極める目的で導入するのであれば、就業規則や労働契約書にしっかりと明記しましょう。
Q2. 試用期間は最長どのくらい設定できますか?
一般的には1~3カ月程度が多いですが、企業によっては6カ月、あるいは1年とする場合もあります。ただし、長期にわたる試用期間は、後述する解雇リスクや不当労働行為リスクなどで問題が生じやすいため、なるべく必要最小限にとどめるのが望ましいです。
Q3. 試用期間中の解雇は通常より簡単なのでしょうか?
「試用期間だから簡単に解雇できる」という誤解は禁物です。試用期間中であっても、解雇するためには合理的な理由が必要であり、解雇権濫用法理(労働契約法16条)が適用されます。むしろ近年の裁判例では、試用期間中の解雇であっても会社側に厳格な立証を求める傾向が強いので注意が必要です。
Q4. 試用期間を延長する場合に気をつけることは?
試用期間の延長は、就業規則や労働契約書に明確な規定がある場合に限り認められるというのが原則です。また、延長の理由として「もっと適性を見極めたい」「研修が予定より長引いた」などが必要になりますが、あいまいな理由で繰り返し延長すると無効とされるリスクが高まります。延長を行う場合は、期間や理由を従業員に明確に説明し、合意を得ることが重要です。
Q5. 本採用拒否をしたいとき、どのような要件を満たせばいいですか?
実務上は、「試用期間終了時の解雇」と同じ扱いとなるため、解雇権濫用法理に照らして客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。具体的には、就業規則に定める評価基準に従い、勤怠不良や業務遂行能力の著しい不足などを総合的に判断する必要があります。また、本人への面談や指導の記録、成績評価のプロセスを整備しておくことも大切です。
解説
試用期間の法的性質
試用期間は、労働契約上の契約形態そのものを決定づけるものではなく、正社員としての労働契約は結んでいるが、その適格性を見極めるための「解約権留保付労働契約」と解釈されるのが一般的です。つまり、形式上は本採用を前提として雇用契約を締結しつつ、一定期間だけ会社側に解約権(解雇権)を留保している状態といえます。
したがって、試用期間が終われば当然に本採用となるという立て付けであっても、会社側の適性判断によって解約権を行使できる余地が残されているわけです。ただし、先述のように解雇権濫用法理が適用されるため、無制限に解雇できるわけではありません。
試用期間を設定する目的と意義
- 採用ミスマッチの防止
- 書類選考や面接だけでは把握しきれない実務能力や職場適性を確認できる。
- 逆に、従業員側も「思っていた業務内容と違う」「社風が合わない」などを判断できる。
- 組織への早期適応を促す
試用期間中は研修やOJTを重点的に行い、職場ルールや業務内容を集中的に身につける期間とする会社も多い。
試用期間中の解雇が認められる具体例
- 著しい勤怠不良(無断欠勤・遅刻早退を繰り返すなど)
- 業務遂行能力の欠如(求人票や面接で説明していたスキルに明らかに満たない)
- 重大な素行不良(セクハラ、暴言、業務命令違反、犯罪行為など)
ただし、これらの事由が認められる場合でも、いきなり解雇ではなく、注意・指導や改善の機会を与えるなどの手続きを踏まないと、裁判で解雇無効とされるリスクがあります。
試用期間の延長に関する注意点
- 就業規則や労働契約書への明記
「試用期間の延長はできる」「延長できる期間は何カ月まで」など、延長の可能性や要件を定めておく。 - 延長理由の明確化
「研修期間が長引いた」「評価に必要な材料がまだ不足している」など、客観的に説明できる事情を提示し、本人に納得してもらう努力をする。 - 最大延長期間の設定
無制限に延長できるルールを設けると不安定要因が大きいため、最大でも数カ月程度に留めるのが通常。
本採用拒否のリスク管理
- 評価基準の明文化
何をもって「不合格」とするのか、客観的かつ具体的な指標(スキル、勤怠、態度など)を定める。 - 評価手続きの透明性
面談や評価結果を記録し、本人にもフィードバックすることで、後日の紛争を防ぎやすい。 - 指導・改善の機会の付与
たとえば「この部分を改善してほしい」「一定期間内に指摘事項を修正すること」といったステップを踏む。 - 解雇予告手当・予告期間
試用期間中でも解雇にあたるため、労働基準法の解雇予告制度が適用される。
弁護士に相談するメリット
試用期間の運用に際して、思わぬ法的リスクを回避するためには、以下の点で弁護士に相談するのが有益です。
- 就業規則や労働契約書の整備
試用期間に関する条文を適切に整備し、「延長の要件」「本採用拒否の基準」などを明確化しておく。 - 個別ケースの判断サポート
「試用期間中に解雇したいが、どの程度の証拠があれば安全か」「延長を検討しているが、問題にならないか」など、ケースごとのリスクを見極められる。 - トラブル時の迅速な対応
試用期間満了で本採用拒否を通告したら、従業員が「不当解雇」と主張してきた場合など、早期に対処することで紛争を大きくせずに解決できる可能性が高まる。 - 企業ブランディングにも寄与
法的紛争が起きると、企業イメージに悪影響が及ぶこともあります。弁護士の助言を得ながら適正な対応を取ることで、従業員との信頼関係を維持し、企業の評判を守ることにつながります。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、採用・人事・労務管理に関するさまざまな問題をサポートしています。試用期間の制度設計からトラブル対応まで、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
- 試用期間は法的に必須ではありませんが、採用ミスマッチを防ぐ重要な制度として広く活用されています。
- ただし、「試用期間だから解雇が容易」という認識は誤りで、解雇権濫用法理が厳格に適用されます。
- 試用期間の延長や本採用拒否を行う際は、就業規則や労働契約書に明確な定めがあること、合理的理由と手続きが備わっていることが必要です。
- 具体的な対応が分からない場合、弁護士のサポートを受けることでリスクを抑え、スムーズな対応が期待できます。
試用期間を適切に活用することで、企業と従業員のミスマッチを減らし、長期的に安定した雇用関係を築くことができます。そのためには、単に「3カ月設ける」というだけではなく、評価基準の明示や改善指導のステップなどを整理しておくことが大切です。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス