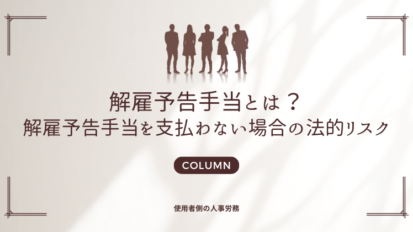はじめに
労働者派遣と請負契約(業務請負)は、企業が外部の人材やサービスを活用する際に使われる代表的な契約形態です。しかし、両者の区別があいまいなまま運用されると、「偽装請負」とみなされ、労働者派遣法や労働基準法などに違反するリスクがあります。
偽装請負は、名目は請負契約なのに実態は派遣契約と変わらない(派遣としての許可を取得していないのに、指揮命令を行っている)ケースを指します。これが明るみに出ると、是正勧告や行政処分、さらには企業イメージの悪化を招く可能性が高いため、企業は契約段階で労働者派遣と請負の違いをしっかり理解し、適正に運用することが求められます。本記事では、その具体的なリスクと対策を弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。
Q&A
Q1:労働者派遣と請負契約の一番の違いは何ですか?
指揮命令権の所在が最大の違いです。労働者派遣では、派遣先企業が派遣労働者に対して直接指揮命令を行います。一方、請負契約では、請負業者(受託側)が独立して業務を遂行し、発注者が労働者に直接指示を出すことはありません。発注者は成果物に対して対価を払うという関係になります。
Q2:偽装請負になると具体的にどんなペナルティがありますか?
偽装請負と認定されると、労働者派遣法違反として、是正指導や改善命令の対象となります。悪質な場合、派遣先企業として最大1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性もあります。また、社会保険や労働保険の手続き、賃金支払いなどについても遡及リスクが発生し、企業負担が大きくなります。
Q3:業務委託契約や下請契約も労働者派遣と混同されることがありますか?
はい、広義でいう「請負契約」には業務委託契約や下請契約も含まれます。要は、受託側が独立した事業者として仕事を引き受け、完成した成果物や提供したサービスに対して対価を受け取る形態です。もし発注者が実質的に労働者の勤務状況を管理し、個別に指示・命令していると、実態は派遣とみなされる可能性があります。
Q4:請負契約で発注していますが、緊急時には発注者が現場で直接指示しても問題ないでしょうか?
一時的な調整や緊急対応ならば一定の柔軟性は許容されるケースもありますが、恒常的に発注者が直接業務指示を行うと、請負の実態が崩れて偽装請負の疑いが高まります。請負の場合は、あくまでも受託業者の管理者が労働者に指示を出すべきであり、発注者は成果物や納期管理に留めるのが本来の形です。
解説
労働者派遣契約の特徴
- 指揮命令関係
- 派遣先企業が、派遣された労働者に対して直接業務上の指示を行い、就業場所や勤務時間、作業方法などを管理します。
- 派遣労働者は派遣元(派遣会社)と雇用契約を結び、給与の支払いや労働保険手続きは派遣元が行いますが、実務の指揮命令は派遣先が担います。
- 期間制限
- 一般派遣の場合、受入れ期間の上限3年ルール(個人単位・事業所単位)があり、延長には労使協定や組合意見聴取などの手続きを踏む必要があります。
- 派遣契約期間の満了後、雇用安定措置(直接雇用のオファーなど)が派遣元・派遣先に求められる場合もあります。
- 派遣元の許可・届出
- 労働者派遣事業を行う場合、厚生労働省の許可が必要となります(特定派遣は廃止済み)。
- 無許可で派遣契約と同様の行為を行うと違法となり、偽装請負と同様のリスクを抱えます。
請負契約の特徴
- 業務完遂の責任
- 請負業者は、発注者から依頼された業務や成果物を独立して完成させる義務を負います。労働者への指示命令は請負業者側が行い、発注者は成果物の検収や納期管理を行うのみが基本形です。
- 成果物やサービスに対する対価
- 請負契約では、完成した成果物やサービスの提供に対して発注者が報酬を支払います。
- 完成責任は請負業者が負うため、瑕疵があれば請負業者の責任で修補や損害賠償が必要となります。
- 資材・設備・労務管理
- 原則として、請負業者が自前の資材や設備、労働者を使い独自に管理します。発注者がこれらを直接管理し、労働者に指示を出すような状態になると「偽装請負」とみなされるリスクが増大します。
偽装請負の典型的ケース
- 発注者が現場リーダーとして労働者を直接管理
- 請負業者の管理者が不在、または名目的にしか存在せず、発注者側がシフト作成や業務指示、休憩時間の管理を行っている。
- このような状態では実態として「派遣」に該当する可能性が高く、許可なく行うと違法派遣となるリスクがあります。
- 労働者が発注者の名札や制服を着用
- 請負業者の従業員が発注者の会社名ロゴ入りのユニフォームを着用していたり、発注者の名刺を使って営業するなど、外部から見て誰が雇用主か分からない状態。
- 見た目の一体感だけでなく、実質的に発注者の社員として業務にあたっていると判断される恐れがある。
- 発注者による人事評価や懲戒
- 請負契約であるにもかかわらず、発注者が人事考課を行い、昇給・降給、懲戒処分の決定をする。
- 請負業者を経由せずに直接労働者の働き方や処分を決めている場合、派遣に該当する可能性が高いといえます。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労働者派遣と請負契約の区別や偽装請負リスク回避のために、以下のサポートを行っています。
- 契約書類のチェック
- 労働者派遣契約書、業務請負契約書、業務委託契約書などの条項を精査し、実態が派遣になっていないか、競業避止や秘密保持が十分かなどをアドバイスします。
- 必要に応じて契約書の修正案を提示し、コンプライアンス体制を強化します。
- 運用上の指導
- 現場での指示命令の実態や、業務プロセスの管理方法をヒアリングし、偽装請負リスクを抽出。
- 労働時間管理やセキュリティ対策などの運用ルールを整備し、派遣先・請負事業者双方が安全に取引できるようにします。
- 労使トラブル・行政対応
- 行政による立ち入り調査や是正指導が入った場合、速やかに企業の立場を整理し、書面回答や改善計画策定を支援します。
- 労働審判や訴訟で偽装請負が主張されたときも、事実関係の精査や証拠整理、適法性の主張立証を担当し、企業リスクを最小限に抑えます。
- 最新法改正・判例情報の提供
- 労働者派遣法や下請法など関連法の改正動向や裁判例を随時共有し、企業が適正な契約形態を選択できるようコンサルティングします。
- 派遣期間制限の運用や雇用安定措置への対応など、派遣法の実務をアップデートし続けるサポートを行います。
まとめ
- 労働者派遣か請負契約かを正しく区別する最も重要なポイントは、指揮命令権が発注者に及ぶかどうか。
- 偽装請負として摘発されると、労働者派遣法違反を問われるだけでなく、社会保険や賃金の支払など遡及的な負担が生じ、企業イメージも大きく損なわれる恐れがある。
- 請負契約では、あくまで請負業者が独立して労働者を管理し、発注者は成果物に対して対価を支払う関係にとどまるのが原則。
- 適正な契約・運用のためには、弁護士と連携し、契約書の整備や現場の指示命令体制の監査を実施することが望ましい。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、偽装請負のリスクや労働者派遣と請負契約の違いについて、具体的な事例や対策方法をYouTubeチャンネルにて解説しています。企業のコンプライアンス強化のために、ぜひ参考にしてみてください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス