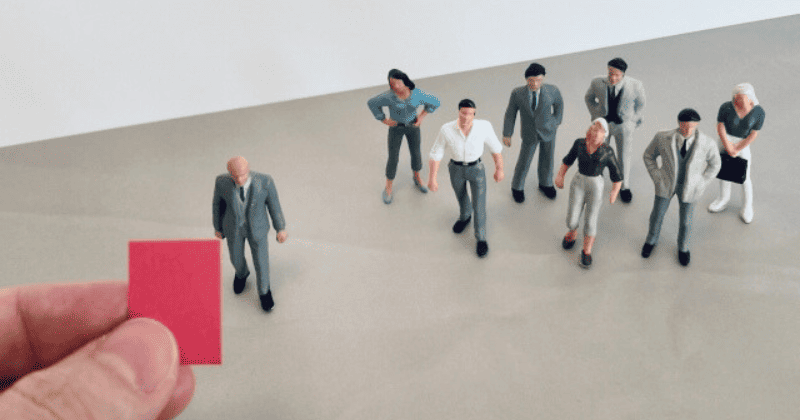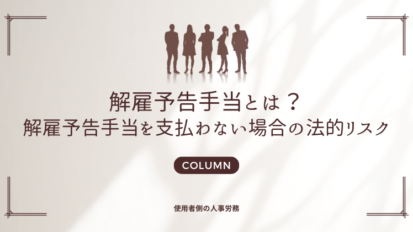はじめに
企業が従業員の秩序を維持し、適正な企業活動を行うためには、就業規則に基づくルールを設定し、従業員に対して違反行為があった場合に懲戒処分を行うことが不可欠です。しかし、懲戒処分は従業員の労働契約に大きく影響を与える行為であり、不当解雇や過度な処分とみなされると、労働審判や裁判で無効とされるリスクがあります。
とりわけ、就業規則の記載があいまいだったり、処分の程度が不相応に重い場合などは裁判所で無効と判断されやすく、企業にとって大きなダメージとなります。本記事では、弁護士法人長瀬総合法律事務所が、就業規則違反に対する懲戒処分を適正に行うためのポイントや留意点を解説します。
Q&A
就業規則に書かれていない事由で従業員を懲戒できますか?
原則として、就業規則や懲戒規程に明示していない事由で懲戒処分を行うのは望ましくありません。裁判例でも、「就業規則等で定めた懲戒事由に該当しない限り、懲戒処分は無効」とされる傾向が強いです。ただし、社会通念上明らかに企業秩序を乱す重大な行為があれば例外的に懲戒が認められる場合もありますが、就業規則に明示することが基本と考えてください。
懲戒解雇と普通解雇は何が違うのですか?
懲戒解雇は、従業員の違反行為や不祥事が非常に重大である場合に適用される、最も重い懲戒処分です。一方、普通解雇は、能力不足や勤務態度不良などを理由とした一般的な解雇手続きで、懲戒ではありません。懲戒解雇は退職金不支給、失業保険の制限など、被処分者に対する影響が大きいため、裁判所はその適法性を極めて厳格に判断します。
始末書や戒告は法的にはどのように扱われますか?
始末書は従業員に反省と改善を促すための書面であり、戒告は「口頭・書面で注意を与える軽い懲戒処分」という位置づけです。法律上の明確な定義があるわけではありませんが、就業規則で処分区分を定める際に、戒告や減給など軽微な処分と降格や懲戒解雇など重い処分を区別して規定します。いずれにせよ、処分の根拠や手続きが不明確だと紛争が生じる可能性があります。
処分を決める際、従業員から意見を聴取する必要がありますか?
はい、処分対象者の言い分を聴取する「弁明の機会」を与えることは、適正手続きの観点から重要です。本人が何も知らされずに一方的に処分された場合、処分の公正性が疑われ、無効となるリスクが高まります。懲戒処分委員会や上司との面談など、適切な場を設けて事情を聴取し、記録を残しておくことが望ましいです。
解説
懲戒処分を行うための基本要件
- 就業規則(懲戒規程)の明確化
- 違反行為の具体的な内容と、それに対応する処分の種類・重さを就業規則や懲戒規程に明示します。
- 「遅刻3回で戒告」など具体的な基準を定めることで、従業員が処分を予測しやすくなり、裁判所での有効性も認められやすくなります。
- 懲戒事由と事実認定の正確性
- 処分の根拠となる事実(違反行為)が客観的に確認できるか、証拠を収集し、従業員本人にも説明できるようにします。
- 曖昧な噂や憶測だけで処分に踏み切るのは危険です。
- 相当性の原則
- 違反行為の重大性に見合った処分を選択する必要があります。たとえば、軽微な遅刻を理由に懲戒解雇するのは過度であり、無効となる可能性が高い。
- 処分を重くする場合は、過去の指導・注意履歴や本人の言い分、会社への悪影響度合いなど総合的に判断します。
- 手続き的適正
- 弁明の機会を付与し、処分内容と理由を明示・書面交付するなど、公平性・透明性を担保する手続きを踏む。
- 処分後の異議申し立て制度や不服申立てルートを設ける企業もあります。
懲戒処分の種類と運用
- 戒告・訓戒・譴責(けんせき)
- 比較的軽い懲戒処分であり、口頭または書面で注意を与える。再発防止を促すのが目的。
- 就業規則で「一定回数の戒告が重なると減給」など、次の処分へのステップを規定することもある。
- 減給
- 賃金を一定額カットする処分。ただし、減給処分の上限(1回あたりの賃金総額の10%以内、総額の1/10を超えないなど)は労働基準法で規制されている。
- 金銭的負担を伴うため、適用時には慎重な判断が必要。
- 出勤停止・停職
- 一定期間、会社への出勤を禁じ、賃金を不支給とする。従業員にとっては収入と就業機会を失うため、重い処分に分類される。
- 期間が長すぎる場合は適切性を疑われるので、就業規則に定める上限と照合して運用する。
- 降格・役職解任
- 管理職を解任したり、職位や給与等級を引き下げたりする処分。本人の労働条件が大きく変わるため、慎重な手続きと明確な根拠が必要。
- 就業規則に降格の具体的事由と手続きを定めておくことが望ましい。
- 懲戒解雇
- 最も重い処分であり、従業員に重大な違法・背信行為があった場合に適用。退職金不支給や失業手当給付制限などの不利益があり、裁判所での判断も厳しい。
- 手続きのミスや事由のあいまいさがあると、解雇無効となるリスクが非常に高い。
懲戒処分の適法性を支える具体的ステップ
- 調査・事実確認
- まずは、対象行為がいつ、どこで、どのように行われたのかを客観的証拠(目撃証言、監視カメラ、メールログなど)で確認します。
- 事実認定に時間がかかる場合は、一時的に自宅待機を命じることもあるが、必要性と期間の相当性に注意します。
- 弁明の機会付与
- 処分対象者を呼び、具体的な疑いの内容を提示し、意見を聴取します。
- メモや録音などで手続き経過を記録し、後々紛争になったときに証拠として活用できるようにします。
- 懲戒委員会や決裁フロー
- 大企業では懲戒委員会を設置し、人事部や法務部など複数部署の意見を集約したうえで処分を決定することが多い。
- 小規模事業者でも、社内決裁フローを明確化し、一人の独断で処分を決めないようにすることが大切です。
- 処分通知と記録
- 処分が決まったら、本人に書面で通知し、違反行為と処分内容、理由を具体的に示します。
- 処分履歴は社内で適切に管理し、同種の事案での処分の一貫性を保てるようにします。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、懲戒処分に関わる以下の課題について、企業をサポートできます。
- 就業規則・懲戒規程の整備
- 適法な懲戒事由の設定、処分種類の区分、手続きフローなどを最新の法令・判例に照らして作成・見直し。
- 条項の文言があいまいであれば具体化を提案し、処分無効のリスクを下げます。
- 懲戒事案発生時の助言・調査サポート
- 従業員の違反行為が発覚した際の事実調査や証拠収集、本人へのヒアリング手順などを具体的に指導。
- どの程度の処分が相当か、過去の判例や企業の慣行を踏まえてアドバイスします。
- 懲戒処分の文書化・通知
- 処分理由書や本人通知書の作成を支援し、法的問題が生じないようにチェック。
- 社内の懲戒委員会にオブザーバーとして参加し、公正な判断をサポートすることも可能です。
- 紛争対応
- 処分後、従業員が不当解雇や処分無効を主張して労働審判・訴訟を起こした場合、企業側代理人として対応。
- 経緯や証拠を整理し、適法性・相当性を立証する戦略を提案します。
まとめ
- 懲戒処分は就業規則違反に対して企業が秩序維持のために行う措置だが、処分の重さや手続きを誤ると、労働審判や裁判で無効とされるリスクが高い。
- 就業規則(懲戒規程)で処分事由と種類を明確化し、事実確認・弁明機会・相当性・手続き的適正をしっかり守ることが重要。
- 最も重い処分である懲戒解雇は、裁判所の審査が非常に厳しいため、事由の重大性や再三の注意履歴などを整えておく必要がある。
- 企業としては、弁護士など専門家の助言を得ながら懲戒規程を整備し、懲戒事案発生時の対応に万全を期すことが望ましい。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、懲戒処分にまつわる具体的な事例紹介や、就業規則の整備方法、不当解雇リスクを回避するポイントなどをYouTubeチャンネルで配信しています。実際の判例も取り上げながらわかりやすく解説していますので、参考にご覧ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス