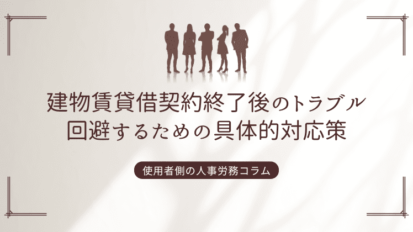はじめに
セクシャルハラスメント(セクハラ)やマタニティハラスメント(マタハラ)は、職場において依然として根深い問題となっています。従業員が被害を受けるだけでなく、企業が社内不祥事として大きく信用を失う事例も少なくありません。さらに、近年の法改正により、事業主にはハラスメント防止策を講じる義務が明確化され、対応を怠れば行政指導や社名公表などのリスクがあります。
本記事では、セクハラ・マタハラの具体的事例や法的責任、そして企業が防止措置として整備すべき体制を詳しく解説します。自社のセクハラ・マタハラ対策を強化したい企業のご担当者は、ぜひ参考にしてください。
Q&A
Q1.セクハラとマタハラの違いは何ですか?
- セクハラ(セクシュアルハラスメント)
性的な言動(発言や行動)によって相手に不快感・苦痛を与え、職場環境を害する行為。上司からの性的関係の強要、性的な冗談やボディタッチなどが典型例。 - マタハラ(マタニティハラスメント)
妊娠・出産、育児休業を取得する労働者に対し、不利益な扱いをする行為。育休を取らせない・復帰後に不当な降格をするなどが代表的。
Q2.セクハラやマタハラを防止する法律は何があるのでしょうか?
- 男女雇用機会均等法
セクハラ防止措置を事業主に義務付け。違反すれば行政指導や社名公表の可能性。 - 育児・介護休業法
マタハラ防止策を定め、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを禁止。 - パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)
ハラスメント全般を防止する措置を義務付け。
Q3.具体的にセクハラやマタハラにはどのような事例がありますか?
- セクハラの事例
性的な発言や下ネタを繰り返す、身体を不必要に触る、デートをしつこく誘う、性的画像を見せるなど。 - マタハラの事例
妊娠を理由に業務から外す、育休取得を阻止する、復職後に意図的に役職を下げる、妊婦を執拗に退職に追い込むなど。
Q4.事業主は具体的にどのような防止措置を講じなければなりませんか?
代表的には下記のような対応が求められます。
- 就業規則へのセクハラ・マタハラ禁止規定を明記。
- 相談窓口の設置(外部窓口を含む場合も)
- 社内啓発・研修を定期的に行い、ハラスメント行為が違法であることを周知。
- 発生時の調査と被害者・加害者対応(被害者保護のための配置転換、加害者への懲戒処分など)
- 再発防止策の実施。
Q5.マタハラは男性にも適用されますか?例えば父親の育休取得を妨げるなど。
はい、男性が育児休業を取得する権利も育児・介護休業法で保障されており、それを理由に不利益取扱いをする行為はマタハラ(パタハラ)と呼ばれ、違法となる場合があります。男女関係なく妊娠・出産・育児に伴うハラスメントは法的保護の対象です。
解説
セクハラの種類
- 対価型セクハラ
- 上司が性的関係を求め、応じなければ昇進・評価を不利にするなど、労働条件に影響を与える形態。
- 裁判例では非常に悪質とみなされ、多額の損害賠償が認定される可能性が高い。
- 環境型セクハラ
性的な言動や行動によって職場環境が不快・苦痛となる形態。性的な冗談、メール、画像の共有などが挙げられる。被害者の能力発揮や意欲を阻害する。
マタハラのタイプ
- 制度利用妨害型
妊娠・出産・育児休業などを申し出た従業員に対し、「仕事に支障が出るから取得するな」「辞めたらどう?」などと圧力をかける。 - 不利益取扱い型
妊娠・育児休業を理由に降格、減給、配置転換などを行う。合理的理由がないのに職務内容を変えて収入を大幅に下げるなど。
ハラスメント防止のための企業対応
- 就業規則・ハラスメント規程の明確化
セクハラ・マタハラがどのような行為に該当するのか、懲戒処分の例、相談窓口、調査手続などを詳細に規定。 - 相談窓口の設置と運営
被害者が安心して相談できるよう社内外窓口を設置し、通報者が不利益を被らないよう配慮する。 - 研修や周知活動
全社員を対象にハラスメント防止研修を行い、具体的事例を説明。管理職向けにはより詳細な責任と対応法を伝える。 - 実態調査と対応
相談が寄せられたら迅速かつ公正な調査を行い、事実認定。加害者への懲戒処分や被害者フォローを適切に行う。
トラブル事例と企業責任
- セクハラ放置による精神疾患
上司の性的言動を放置し、被害者が適応障害やうつ病になった場合、企業が安全配慮義務違反として損害賠償責任を負う可能性。 - マタハラで退職強要
妊娠を理由に「迷惑だから辞めて」「妊婦にできる仕事はない」と追い込み、被害者が退職。後日マタハラ裁判に発展し、企業に高額賠償命令が出るケースも。 - 被害者・加害者対応の失敗
被害者を人事異動で対応したが、加害者は処分せず野放し。会社がパワハラ・セクハラ防止義務を果たしていないとみなされ、被害者が慰謝料を請求。
弁護士に相談するメリット
ハラスメント対応は非常に敏感な問題であり、法的観点と慎重な手続きが必要です。弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。
- ハラスメント規程・就業規則の整備
企業の実態に合わせた明確な禁止行為や懲戒処分、相談窓口の運用方法を策定。 - 相談窓口設計・社内研修支援
外部窓口の導入や社内での相談体制づくり、管理職・従業員研修の内容作成などをサポート。 - 内部調査・第三者委員会の支援
事案発覚時の公正な事実確認、加害者・被害者へのヒアリング手続きなどを指導し、後日の裁判リスクを回避。 - 紛争時の解決
被害者から損害賠償請求を受けた場合や労働審判・訴訟になった際、企業の代理として交渉・裁判対応を行う。
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、セクハラ・マタハラに関する豊富なノウハウを持ち、企業向け研修や相談窓口の構築支援も行っています。
まとめ
- セクハラ(性に関する言動での不快・苦痛)とマタハラ(妊娠・出産・育児休業を理由とする不利益取扱い)は、いずれも違法性が高く、放置すれば企業責任が問われる可能性があります。
- パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)と合わせ、企業は相談体制の整備、調査・懲戒処分、再発防止策などを講じる義務を負っており、怠れば行政指導や社会的信用の低下が避けられません。
- 就業規則でセクハラ・マタハラ禁止規定を定め、具体的事例・相談窓口・懲戒規定を明文化し、全従業員への周知と定期研修を行うことが重要です。
- 弁護士に相談すれば、適正なハラスメント対策制度の構築や紛争対応まで一貫したサポートが受けられ、企業リスクを大幅に減らせます。
ハラスメント対策は企業の社会的責任であり、従業員の安全な職場環境を守るためにも、セクハラ・マタハラを許さない風土を作り、早期対応できる仕組みを整えましょう。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス