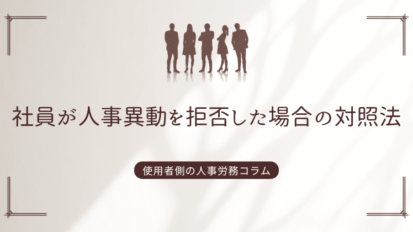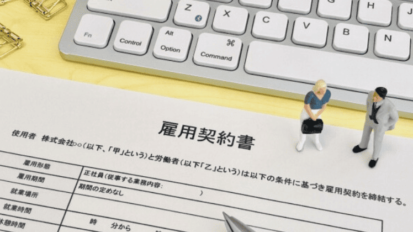はじめに
テレワーク(在宅勤務・リモートワーク)とフレックスタイム制を組み合わせる企業が増えています。コアタイム以外は自由に働けるフレックス制は、通勤時間や業務時間帯を柔軟にできる一方、勤怠管理や生産性評価が複雑化する可能性が高く、適切な運用をしないと未払い残業代の発生やコミュニケーションロスなどの課題に直面します。
本記事では、フレックスタイム制とテレワーク(在宅勤務)の併用で考慮すべき労務管理上の注意点、コアタイムや労働時間の扱い、生産性を維持するポイントなどを解説します。従業員のワークライフバランスを高めつつ、法令順守とトラブル防止を両立させるための指針としてください。
Q&A
Q1. フレックスタイム制と在宅勤務を組み合わせるメリットは何でしょうか?
代表的には、
- 柔軟な働き方
通勤時間の削減とフレキシブルな労働時間の両立で、育児介護や私用とも調整が容易。 - 生産性向上
自分の集中できる時間帯に働けるため、効率が高まりやすい。 - 人材確保・離職防止
通勤負担軽減と時間帯の選択が可能で、多様な人材の就労継続に寄与。
Q2. 企業が気をつけるべきデメリットやリスクはありますか?
主なリスクとして、
- 勤怠管理の複雑化
コアタイム以外の自己裁量時間を正確に把握しないと、未払い残業代のトラブルやサービス残業発生リスクが高まる。 - コミュニケーション不足
在宅かつフレックスで勤務時間帯がバラバラだと、リアルタイムの連絡や意思決定が遅れやすい。 - 評価やマネジメントの難易度
時間管理が大変な分、成果管理や職務分担も曖昧になりがちで、チーム全体の連携が難しい。
Q3. フレックスタイム制を導入する際のコアタイムは必ず設定しなければいけませんか?
法律上コアタイムの設定は義務ではありません。しかし、全員が全くバラバラだとミーティングや連絡調整が困難になるため、一部コアタイムを設ける企業が多いです。コアタイムを廃止するスーパーフレックスの例もありますが、コミュニケーション上の課題に注意が必要です。
Q4. 在宅フレックスの場合、どのように労働時間を把握すればいいでしょうか?
勤怠管理システムで打刻したり、PCログやチャットログの取得など客観的記録を併用することが推奨されます。自己申告だけでは不十分とされ、サービス残業や超過労働が潜在化する可能性が高いため、定期的な上司のモニタリングや「終業報告書」なども有効です。
Q5. フレックスタイム制で深夜残業や法定休日労働が発生した場合の残業代計算はどうなるのですか?
フレックスタイム制であっても、深夜(22時~翌5時)の割増や法定休日(週1日)の割増は通常どおり計算が必要です。フレックスの「清算期間」内での総労働時間を超えた分は時間外割増賃金が発生するため、就業規則や計算ルールを設けましょう。
解説
フレックスタイム制の基本構造
- 清算期間
法令上、最長で1か月。企業は清算期間内の総労働時間を定め、期間終わりに不足・超過分を精算し、残業代計算を行う。 - コアタイムとフレキシブルタイム
コアタイムは従業員全員が在席する時間帯、フレキシブルタイムは各自が自由に始業・終業できる時間帯。 - 申告・承認
労使間で36協定とは別にフレックスタイムに関する協定を締結し、就業規則にも明記する必要がある。
テレワークとの組み合わせ
- 在宅フレックスのメリット
交通費・通勤時間の削減と、時間帯の柔軟性がさらに拡大。育児介護者や遠隔地人材にとって魅力。 - 管理上の注意
自己裁量時間が大きくなるため、業務報告方法やコミュニケーションルールを整えないと進捗管理が難しい。 - コアタイム設定
通信会議やミーティングを行う共通時間帯(例:10時~15時)を設けるとスムーズに情報共有できる。
労働時間管理の具体策
- 勤怠システム
Web打刻やICカード、PC起動ログなどで始業・終業を記録し、残業代計算に活かす。 - アプリ・クラウドツール
スマホやPCで出退勤を登録し、データをリアルタイムで人事部が確認できるようにする。 - 申請・承認フロー
残業や休日出勤は必ず事前申請し、上司が承認しなければ無効とするなど、36協定順守の仕組みを作る。 - 自己申告との整合
労基署ガイドラインに沿って、客観的記録と自己申告を照合し、過少申告を防ぐ。
コミュニケーションと評価の工夫
- 定期オンラインミーティング
コアタイムに週1回や朝夕の短い打ち合わせを設定し、進捗確認や雑談も含めたコミュニケーションを促す。 - ツール活用
チャットやグループウェアで日報やタスク進捗を共有し、可視化することでチーム連携を円滑に。 - 成果主義との整合
在宅フレックスでは従業時間や見える頑張りが少なくなる分、目標管理(MBO)やKPI設定で客観的に評価を行う。 - マネジメント研修
管理職向けに、テレワーク×フレックスの部下をどう指導・評価するか、ラインケアやコミュニケーション手法を学ぶ研修を実施。
弁護士に相談するメリット
フレックスタイム制とテレワークの併用は柔軟性が高い一方、就業規則整備や労務管理が複雑化します。弁護士に相談することで、以下のようなサポートが可能です。
- フレックスタイム協定・就業規則改定
法的要件(清算期間、対象労働者、始業終業時刻の決定方法など)を満たす形で規定を作成。 - 残業代リスク回避
自己裁量時間が増えてもサービス残業とみなされないよう、客観的記録と36協定順守を実現する制度設計。 - 在宅フレックスのセキュリティ対策
情報漏えいリスクを就業規則や誓約書に盛り込み、違反時の懲戒規定をアドバイス。 - 紛争発生時対応
労働者から未払い残業代請求やハラスメント訴訟などが起きた場合の交渉・訴訟対応を企業代理で行う。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、複雑な勤務形態の就業規則整備や労務トラブルの解決に経験があり、企業に合わせた最適な制度導入をご提案します。
まとめ
- フレックスタイム制×テレワークは働き方の柔軟性を大きく高め、生産性や従業員満足度向上につながる一方、労働時間管理やコミュニケーション、評価制度の適切な運用が難しくなるというデメリットも存在します。
- 法的には、フレックスタイム協定(労働基準法)や就業規則の改定で、コアタイムや清算期間、在宅勤務手当などのルールを明示し、残業代計算や長時間労働抑制を徹底する必要があります。
- 在宅フレックスでは客観的な勤怠管理ツールと報告・承認フローの整備、上司と部下のコミュニケーション(面談・チャット等)で生産性と健康を維持する仕組みが重要です。
- 弁護士に相談すれば、フレックス導入時の協定作成から就業規則改定、セキュリティ対策、紛争対応まで一貫したサポートを受けられ、企業リスクを軽減できます。
企業としては、制度の形だけでなく、従業員の実態に合わせた実効性ある運用が重要です。フレックスタイム制とテレワークのシナジーを最大限引き出すために、法令順守と労務管理を徹底しましょう。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス