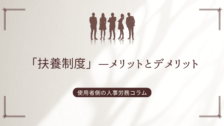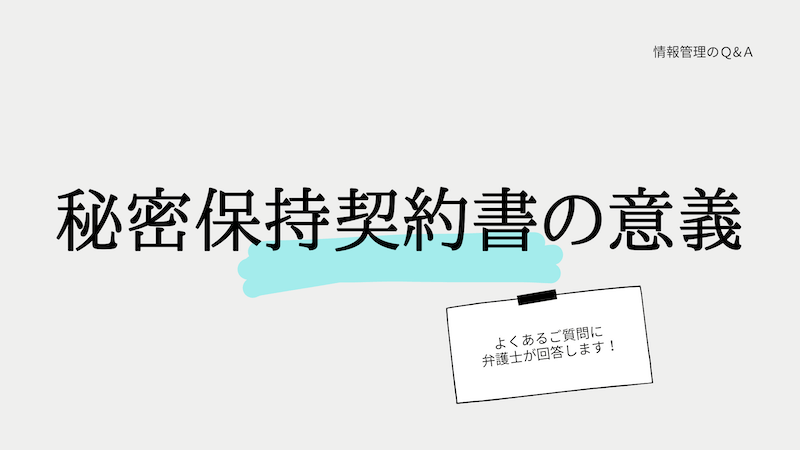はじめに
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用していると、時に誹謗中傷や嫌がらせ投稿、虚偽情報の拡散などに直面することがあります。被害者として放置しておくと、個人や企業の名誉が大きく傷つけられ、長期的なダメージを被るリスクが高いです。こうしたトラブルを解決するための第一歩として、SNS運営会社への通報・削除依頼が挙げられます。
本稿では、主要SNSの通報機能や報告方法を中心に、削除依頼を行う際の具体的な手順や注意点を解説します。投稿が削除されない場合の追加対応策や、弁護士に相談するメリットについても触れますので、SNS上で誹謗中傷被害を受けている方はぜひ参考にしてください。
Q&A
Q1:SNS運営会社に通報や削除依頼を出すと、どれくらいの確率で投稿を削除してもらえるのでしょうか?
SNSごとにガイドラインや審査基準が異なります。明らかな違反(脅迫やヘイトスピーチなど)であれば削除される可能性が高いですが、単なる批判や感想レベルであれば削除に至らない場合が多いです。
Q2:通報や報告は具体的にどうやって行えばよいですか?
各SNSに備わっている「通報機能」や「報告フォーム」を利用します。削除を求める投稿を開いて、「違反報告」「不適切なコンテンツを報告」などのボタンを押すのが一般的な流れです。
Q3:投稿が削除されない場合、ほかにどんな方法がありますか?
SNS運営会社が削除に応じない場合、仮処分や発信者情報開示請求などの法的手段を検討します。弁護士のサポートを得て削除命令を裁判所から出してもらう方法が考えられます。
Q4:誹謗中傷以外に、アカウントをなりすましされた場合はどう対処すれば良いですか?
なりすましアカウントはSNSの規約に違反することが多いため、運営会社へ通報して削除を要請できます。投稿者に損害賠償を求める場合は発信者情報開示請求や法的措置を行うのが一般的です。
Q5:通報すると相手にバレることはありますか?
通常、SNS上の通報は相手に通知されません。ただし、裁判手続きに移行する際には、相手方に自身の情報(または弁護士の情報)や法的手続きを行った事実が伝わることがあります。
解説
SNS運営会社が削除を判断する基準
- ガイドライン違反
- 各SNSが定める「コミュニティガイドライン」や「利用規約」に違反するかどうか
- ヘイトスピーチ、人種差別、脅迫、暴力的コンテンツなどは削除対象になりやすい
- 法律違反の可能性
- 特に犯罪予告や違法行為の助長、著作権侵害、プライバシー侵害などが認められる場合
- 誹謗中傷でも、ただの感想や意見の域を超え、社会的評価を低下させる具体的事実摘示があるかどうか
- 報告内容の具体性
- 通報者がどの部分を問題視しているのか、具体的に説明できているか
- 運営会社が判断しやすい形で情報提供するほど削除対応が期待できる
削除されない場合の追加対応
- 再通報・追加証拠の提示
- 運営会社が「ガイドライン違反なし」と判断したとしても、別の視点や追加のスクリーンショットを示すことで再審査を促す
- 仮処分や発信者情報開示請求
- SNS運営会社が応じない場合、裁判所に対して投稿削除の仮処分を申し立てる
- 加害者を特定し、損害賠償や示談交渉へ進む方法
企業アカウント運用時の注意点
- 社内ルールの整備
SNSポリシーや投稿ガイドラインを策定し、担当者や従業員が誤投稿しないようにする - モニタリング体制
定期的にSNS上での言及やハッシュタグを監視し、早期発見・早期対応を徹底 - 炎上時の初動対応
企業として、誰がどのように謝罪や事実関係を説明するかをマニュアル化しておく
弁護士に相談するメリット
削除依頼が認められやすくなる報告書類の作成
「誹謗中傷や違法投稿に該当する理由」を法的観点で明確に示せば、SNS運営会社も削除判断しやすくなります。弁護士が文書作成を代行することで、通報内容の説得力が増します。
仮処分申立て・発信者情報開示請求のサポート
SNS運営会社が通報に応じない、もしくは削除を拒否した場合、裁判所からの命令で削除を実現する仮処分手続きを検討できます。また、投稿者を特定して損害賠償を求めるための発信者情報開示請求も弁護士が主導するとスムーズに進みます。
企業ブランディングと法的リスク管理
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業のSNS運用ガイドライン策定や炎上対応マニュアルの整備など、リスク管理の総合的サポートを行っています。トラブルの発生を未然に防ぎつつ、万一の際にも迅速な法的対応が可能です。
精神的負担の軽減
誹謗中傷被害は被害者に大きな精神的ストレスを与えます。弁護士に依頼すれば、SNS運営会社や裁判所とのやり取りを代理してもらえ、被害者本人の負担が大幅に軽減されます。
まとめ
- SNS運営会社への通報・削除依頼の基本
- 不適切な投稿を発見 → 通報機能で「ガイドライン違反」を報告
- 運営会社が審査 → 違反と判断されれば削除やアカウント制限
- 削除されない場合は再通報や法的手段へ
- 削除が認められやすいケース
-
- ヘイトスピーチ、脅迫、わいせつ、個人情報漏洩など、明確な規約違反・違法性がある
- 客観的な証拠を提示し、具体的に害が生じていることを示せる
- 削除されない場合の対処策
- 再通報・追加証拠
- 仮処分など裁判手続き
- 弁護士との連携メリット
-
- 文書作成代行で通報の説得力向上
- 削除拒否時の仮処分・発信者情報開示請求など法的支援
- 企業SNSポリシーや炎上対応策の整備
SNS運営会社への通報・削除依頼は、誹謗中傷や不当な投稿による被害を防ぐための初期対応として有効です。しかし、削除に応じてもらえない場合や、投稿者を特定し賠償請求が必要な場合もあり得ます。こうした状況に備え、専門家と連携し、法的手段を視野に入れたトラブル対応を検討することをおすすめします。
長瀬総合の情報管理専門サイト
情報に関するトラブルは、方針決定や手続の選択に複雑かつ高度な専門性が要求されるだけでなく、迅速性が求められます。誹謗中傷対応に傾注する弁護士が、個人・事業者の皆様をサポートし、適切な問題の解決、心理的負担の軽減、事業の発展を支えます。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
当事務所は多数の誹謗中傷の案件を担当しており、 豊富なノウハウと経験をもとに、企業の皆様に対して、継続的な誹謗中傷対策を提供しており、数多くの企業の顧問をしております。
企業の実情に応じて適宜顧問プランを調整することも可能ですので、お気軽にご連絡ください。