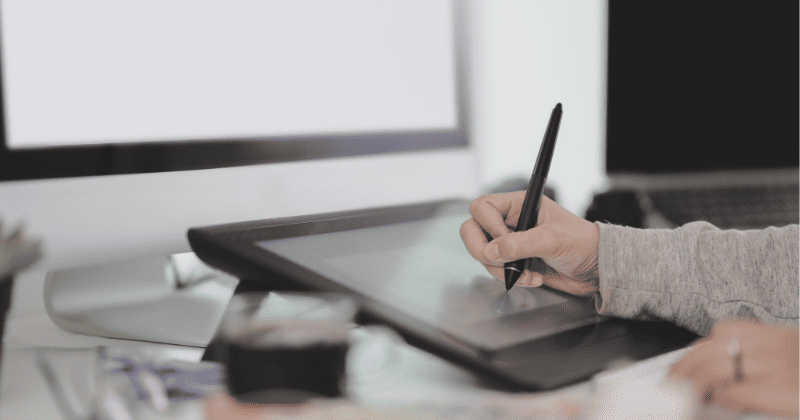はじめに
裁量労働制とは、従業員の労働時間を実際の働いた時間ではなく、あらかじめ定めた時間を「みなし」としてカウントする制度を指します。研究開発や高度専門業務、企業の企画業務などに携わる従業員が自律的に時間を使えるようにする目的で導入されるケースが多いですが、その対象業務や導入手続きは労働基準法で厳しく限定されています。
本記事では、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の違いや導入要件、運用上の注意点などを解説します。制度を誤って導入してしまうと未払い残業代のリスクが高まり、企業に大きな負担がかかる恐れがあります。裁量労働制を検討中の企業の皆さまのご参考となれば幸いです。
Q&A
Q1. 裁量労働制って、残業代が不要になる制度ですか?
裁量労働制では、あらかじめ定めた「みなし時間」を働いたものとみなすため、通常の時間外労働(残業)という概念はなくなります。しかし、深夜労働や休日労働があった場合の割増賃金は別途支払う必要がありますし、制度導入要件を満たしていないと、無効として未払い残業代を請求される恐れがあります。
Q2. 専門業務型と企画業務型の違いは何でしょうか?.
- 専門業務型裁量労働制(労基法38条の3)
- 対象業務が法律や省令で限定列挙されており、研究開発やシステムエンジニア、デザイナーなど専門性の高い業務に適用される。労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出。
- 企画業務型裁量労働制(労基法38条の4)
- 企業の中枢で企画・立案・調査・分析を行う業務などが対象。労使委員会の5分の4以上の多数決による決議を行い、労働基準監督署へ届出。
- 専門業務型と比べて要件がさらに厳しく、対象業務を明確に定義する必要がある。
Q3. 対象外の業務に裁量労働制を適用することはできないのですか?
はい。法律や省令が定める対象業務以外に裁量労働制を適用することはできません。たとえ「裁量が必要」という会社の主張があっても、適法ではない場合は未払い残業代が発生するリスクが非常に高いです。
Q4. どのくらいの「みなし時間」を設定すればいいのでしょうか?
労使協定(専門業務型)や労使委員会決議(企画業務型)で1日のみなし労働時間を定める形が一般的です。例えば「1日8時間」と定めれば、その時間で働いたものと見なされますが、実際の仕事が5時間で終わっても8時間、10時間かかったとしても8時間とカウントします。
Q5. 裁量労働制を導入したら、労働時間管理は不要になるのですか?
いいえ。裁量労働制下でも、健康管理目的などで実際の労働時間を把握する義務があります。また、深夜・休日の割増賃金を算出するためには、どの時間帯に働いたのかを確認しなければなりません。まったくのノーチェックは法律違反のリスクを伴います。
解説
専門業務型裁量労働制(労基法38条の3)
- 対象業務
法令により限定的に列挙されている。例: 新商品開発の研究者、システムエンジニア、新聞・雑誌の記者、プロデザイナー、弁護士等の法律専門家など。 - 導入手続き
労使協定を締結し、その協定に定める事項(対象業務・対象労働者・みなし労働時間等)を労働基準監督署へ届け出る。 - みなし労働時間
1日のみなし労働時間を協定で定める。通常は8時間や7.5時間など。 - 健康管理措置
長時間労働になりがちな業務であることから、面談指導や産業医による健康管理が強く求められる。
企画業務型裁量労働制(労基法38条の4)
- 対象業務
企業の中枢で企画・立案・調査・分析を行う業務で、企業の経営に資する重要な意思決定に関与できるもの。 - 導入手続きの厳しさ
- 専門業務型と異なり、労使協定ではなく「労使委員会」で5分の4以上の賛成により決議する必要がある。
- 決議書を労働基準監督署へ届け出て承認を得る。
- 労使委員会の設置
企画業務型を導入するには、企業内に労使委員会を設けることが義務付けられている。委員は労働者と使用者が同数程度で構成。 - 健康確保措置
専門業務型と同様、健康管理や長時間労働への配慮が必要。毎月一度の健康面談や労働時間の実態調査を実施することが望ましい。
裁量労働制の運用で生じやすいトラブル
- 対象業務外への適用
裁量性の少ない業務に適用していた場合、未払い残業代として請求されるリスク。 - 実質的に上司の指示が細かい
裁量労働と名付けながら、実際には細かい業務指示や残業命令があると、自由裁量がないとみなされ無効化する可能性が高い。 - 健康管理措置の不備
過剰な長時間労働が放置され、メンタル不調や過労死問題に発展すると企業責任が問われる。
実務でのポイント
- 就業規則・労使協定・労使委員会決議の適切な整備
専門業務型と企画業務型で手続きや必要書類が異なるため、混同しないこと。 - 対象業務の具体化
どの部署・職種が裁量労働制を適用されるのか、業務内容を細かく定義し、実態と合致させる。 - モニタリングとフォローアップ
毎月の実働時間や成果をチェックし、過度な長時間労働がないかを把握。健康面のケアも欠かさない。 - 深夜・休日労働の割増賃金
みなし時間には含めず、深夜帯や休日労働に対する割増は別途支給が必要。
弁護士に相談するメリット
裁量労働制の導入や運用は、法律上の要件をクリアしなければ無効や違法とされるリスクがあります。弁護士に相談すると、以下のようなサポートが期待できます。
- 対象業務の適格性評価
現在行っている業務が「専門業務型」「企画業務型」のどちらに該当するか、あるいは該当しないかを法的観点で分析。 - 制度設計・書類作成
労使協定や労使委員会決議など、必要書類の作成・届出をサポートし、行政からの指摘を未然に防ぐ。 - 健康管理体制のアドバイス
長時間労働が懸念される裁量労働制では、面談指導や産業医連携が不可欠。弁護士の視点で、健康管理措置の法的要件を押さえた体制づくりを提案。 - 紛争対応
従業員から「実態は裁量権がない」と主張され、未払い残業代請求を受けた場合に、証拠収集や交渉・裁判対応を一括して任せられる。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、裁量労働制の導入からトラブル解決まで、多角的なサポートを行っています。
まとめ
- 裁量労働制は、従業員が自己裁量で働けるように見なす労働時間制度ですが、対象業務や導入要件が法律で厳格に限定されています。
- 専門業務型と企画業務型があり、導入には労使協定(専門業務型)や労使委員会決議(企画業務型)と監督署への届出が必要です。
- みなし時間を越えて働いたとしても賃金が増えない一方で、深夜労働や休日労働に対する割増賃金は別途支払う義務があります。
- 弁護士に相談すれば、対象業務の適格性や制度設計の合法性チェック、従業員の健康確保措置のアドバイスなどトータルで支援が受けられます。
裁量労働制は労使双方にメリットをもたらす可能性がありますが、要件や運用を誤ると大きなトラブルに発展するリスクがあります。導入を検討する際は、十分に法的要件や運用体制を整備し、従業員の理解を得ながら慎重に進めることが重要です。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス